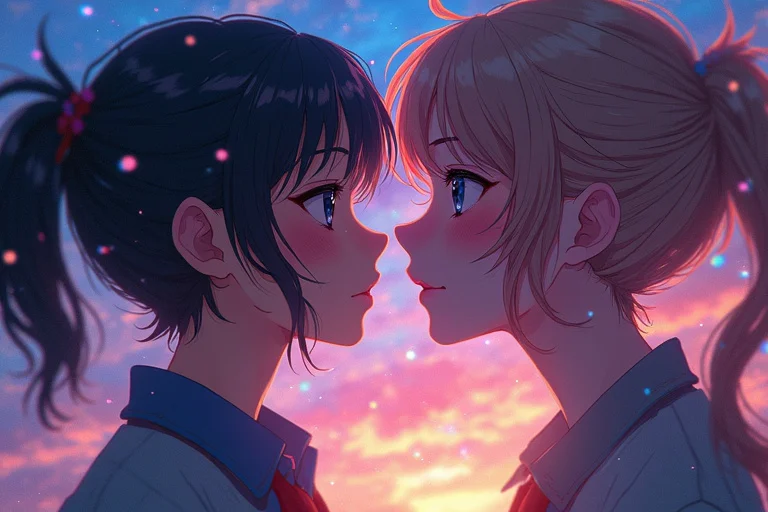第一章 色褪せた街の残響
この世界は、緩やかに死にかけていた。
かつて街の至る所に満ちていた『青春の残響』――路地裏から聞こえるはずの、仲間と交わした秘密の笑い声の幻聴。古本屋の隅に漂う、初めての恋の甘酸っぱい紙の香り。夕暮れの公園に残る、果たされなかった約束の微かな光。それらが日に日に薄れ、世界から色が抜け落ちていくように、人々の表情からも感情が消えつつあった。
僕、レンの体内には、その失われたはずの青春が『砂』として溜まっていた。
感情が揺さぶられるたび、体の中でじゃり、と微かな音が立つ。喜び、悲しみ、怒り。そのどれもが、僕の中に金色の砂粒を降り積もらせた。砂が増えるほど、僕は自身の過去を、まるで昨日のことのように鮮明に思い出すことができた。初めて自転車に乗れた日の、膝に感じた誇らしい痛み。親友と交わした、くだらない誓いの言葉。
だが、その代償は重い。鮮烈な過去は、脆い現在を侵食する。砂が一定量を超えると、今朝食べたものの味や、昨日交わした会話が、するりと指の間からこぼれ落ちるように曖昧になるのだ。だから僕は、心を閉ざした。できるだけ感情を波立たせず、静かに、誰にも触れずに生きる。それが、僕が僕でいるための、唯一の方法だった。
その日、僕は街の中央図書館の、埃っぽい一角にいた。世界のこの奇妙な衰退の原因が、古い文献のどこかに記されているのではないか。そんな淡い期待を抱いて。分厚い革表紙の本をめくっていると、不意に背後から声がした。
「あなたも、探しているの?」
振り返ると、そこに少女が立っていた。窓から差し込む気怠い午後の光を背負い、その輪郭だけがきらきらと輝いて見えた。アリア、と彼女は名乗った。その瞳は、この色褪せた世界には似つかわしくないほど、強い光を宿していた。
「この世界、なんだか寂しいと思わない? 昔はもっと、ドキドキする音や、きらきらした光で満ちていたのに」
彼女の言葉は、僕の心の殻をたやすく貫いた。強い共感が、僕の体内で砂嵐を巻き起こす。じゃり、と今までで一番大きな音が響き、僕は思わず胸を押さえた。幼い頃に見た、夜空を埋め尽くす花火の記憶が、網膜に焼き付く。
「……大丈夫?」
アリアが心配そうに僕の顔を覗き込む。彼女の真っ直ぐな視線に、僕の砂はさらに騒めいた。この出会いが、僕の静かな世界を終わらせる予感がした。そして、それはこの世界の運命をも、大きく揺るがすことになるのだった。
第二章 星屑を辿る旅路
アリアは『星屑の砂時計』の伝説を追いかけていた。世界の中心に鎮座し、人々の青春の輝きを集めて時を刻んでいたという、おとぎ話のような遺物。それが壊れたことで、世界の輝きが失われ始めたのだと彼女は信じていた。
「世界の中心にある『時の神殿』へ行けば、きっと何か分かるはず」
彼女は、ほとんど消えかかった『青春の残響』を頼りに、その場所を探していた。僕は、自分のこの特異な体質と世界の異変を結びつける何かが見つかるかもしれないと思い、彼女の旅に同行することにした。
二人で歩く道は、僕が一人で生きてきた日々とは全く違っていた。アリアは、道端に咲く名もない花に足を止め、その可憐さに声を弾ませた。僕が何気なく見過ごしていた夕焼けのグラデーションを指さし、「今日の空は、燃えるような恋の色だね」と笑った。
彼女の隣にいると、僕の感情は否応なく揺さぶられた。
彼女の笑顔に胸が高鳴るたび、体内の砂がさらさらと増えていく。そのたびに蘇るのは、僕自身の青春の断片。忘れていたはずの友達との他愛ない口論。初めて楽器に触れた時の指先の震え。それらは苦い記憶でさえ、不思議な輝きを放っていた。
僕は、自分の体内に溜まる砂が、もはや単なる呪いではないのかもしれないと感じ始めていた。これは、僕が生きてきた証そのものなのだと。
しかし、旅の途中で立ち寄ったある村で、僕たちは世界の死の現実を目の当たりにする。そこは、完全に色彩を失った「灰色の村」だった。住民たちは、まるで精巧な人形のように無表情で、ただ決められた日課をこなすだけ。笑いも、涙も、怒りさえも、そこには存在しなかった。風の音だけが、空虚に響き渡っていた。
「……どうして」
アリアの肩が、小さく震えていた。彼女の瞳から大粒の涙がこぼれ落ち、灰色の地面に小さな染みを作った。その強い悲しみは、僕の体内の砂を激しく揺さぶり、嵐のように渦を巻かせた。僕は、彼女を、そしてこの世界を、このまま終わらせてはいけないと、強く思った。アリアの涙が、僕に戦う決意を与えたのだ。
第三章 砂の器の真実
長い旅の果てに、僕たちはついに『時の神殿』へとたどり着いた。雲を突き抜けるほど高い山の頂に、その神殿はひっそりと佇んでいた。風化した石柱に囲まれた広間の中央には、しかし、空虚な台座があるだけだった。『星屑の砂時計』の姿はどこにもない。
「そんな……どこにも……」
落胆するアリアの隣で、僕は台座に吸い寄せられるように近づいた。指先が冷たい石に触れた、その瞬間だった。
世界が反転した。
僕の体内の全ての砂が、灼熱のマグマのように沸騰し、共鳴した。激しい眩暈と共に、僕はその場に崩れ落ちる。
意識が遠のく中、僕は見た。いや、思い出したのだ。遥か太古の、この世界が生まれた瞬間の記憶を。
世界は、無数の人々の『青春』の輝きが結晶化して生まれた。しかし、その輝きは永遠ではなかった。輝きを留めておくための器が必要だった。それが『星屑の砂時計』。だが、砂時計は、物理的な物体ではなかった。
僕のような人間が、その『器』だったのだ。
僕の体内の砂は、壊れた砂時計から漏れ出したものではない。僕自身が、この世界の青春の輝きを溜め込むための、生きた砂時計だった。世界の『青春の残響』が薄れていたのは、そのエネルギーが全て、僕という器に吸収され続けていたからだった。世界を救う方法は、ただ一つ。僕が溜め込んだ全ての青春――僕自身の記憶の全てを、この世界に解放すること。
意識が現実へと引き戻される。目の前には、泣きじゃくるアリアの顔があった。
僕は、震える声で彼女に真実を告げた。僕が消えることでしか、世界は救えないのだと。
「嫌だ! そんなの絶対に嫌! あなたのいない世界なんて、色が戻ったって意味がないよ!」
アリアは僕の胸を叩き、叫んだ。彼女の涙が、僕の頬を濡らす。その温かさが、僕の最後の決意を固めさせた。
「アリア」
僕は、できるだけ穏やかな声で彼女の名前を呼んだ。
「君と出会って、僕は初めて、僕の中に溜まる砂を愛おしいと思えた。君と見た夕焼け、君が笑った声、その全てが僕の青春だった。この記憶だけで、僕の人生は、十分すぎるほど輝いていたよ」
僕は静かに微笑み、アリアの手をそっと離した。
第四章 始まりの砂時計
僕は神殿の中央にある台座の上に、ゆっくりと立った。目を閉じ、意識を内なる砂へと集中させる。アリアの嗚咽が聞こえる。ごめん、と心の中で呟き、僕は全身の力を解放した。
黄金の奔流が、僕の体から噴き出した。
それは、僕が生きてきた証である無数の砂粒。一つ一つの粒が、僕の記憶そのものだった。
親友と笑い合った日の光。
初めて嘘をついた日の罪悪感。
アリアと出会った図書館の、古い紙の匂い。
彼女の笑顔。
彼女の名前――。
砂が抜けていくにつれて、僕の記憶が急速に白紙になっていく。僕が誰で、ここがどこで、なぜここにいるのか。目の前で泣いている少女は、誰なのだろう。温かくて、とても大切な存在だった気がするけれど、もう思い出せない。全てが、優しい光の中に溶けて消えていった。
僕から解放された膨大な砂は、神殿の広間で渦を巻き、やがて台座の上で一つの形を取り始めた。それは、星屑を封じ込めたようにきらきらと輝く、壮麗な砂時計だった。
『始まりの砂時計』が静かに反転し、最初の砂粒が落ちた瞬間、世界に奇跡が起きた。
色褪せた世界に、鮮やかな色彩が奔流のように流れ込む。乾いた大地に草花が芽吹き、人々の瞳に感情の光が灯った。街角には再び、懐かしい『青春の残響』が満ち溢れ、子供たちの笑い声が風に乗って響き渡った。世界は、終わりがあるからこそ今が輝く、『青春』という限られた時間を取り戻したのだ。
神殿の床で、僕は静かに目を覚ました。
頭の中は空っぽで、心は生まれたての赤子のように静かだった。
傍らに、一人の少女が座っていた。彼女は、頬に涙の跡を残しながらも、僕を見て美しく微笑んだ。
「はじめまして」
その声は、なぜか僕の胸の奥を、ちくりと切なくさせた。
僕は何も覚えていない。自分が誰なのかも、彼女が誰なのかも。
ただ、神殿の外に広がる、生き生きと輝く世界で、人々が笑い、泣き、恋をしている姿を見て、自然と口元に微かな笑みが浮かんでいた。
僕の青春の終わりは、世界の、新しい青春の始まりだった。
少女――アリアは、僕の隣で、この世界の始まりの物語を、誰にも語ることなく、その胸の奥深くに秘めて、ただ静かに、新しい時が刻まれるのを見守っていた。