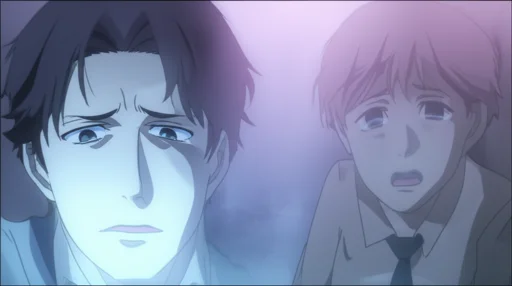第一章 剥がれ落ちる紙片
朝、目覚めるといつも何かが欠けている。名前だったり、昨日の食事だったり、あるいは笑い方だったり。俺、カイの記憶は、砂の城のように夜の間に少しずつ崩れていく。代わりに、シーツの上には乾いた皮膚のように薄い紙片が数枚、散らばっている。文字のない、ただの白い欠片だ。
それを拾い集めて小箱にしまうのが、俺の朝の儀式だった。箱の中には、数えきれないほどの「俺だったもの」が溜まっている。
街はいつも鈍色の霧に覆われていた。人々は俯き加減に歩き、互いの視線を巧みに避けている。路地裏や建物の隅には、澱んだ水たまりのような黒い塊がそこかしこで蠢いていた。『忘却の塊』。誰もがそう呼ぶが、誰もそれに触れようとはしない。一度だけ指先で触れてみたことがある。心の芯まで凍てつくような冷たさと、ぬるりとした粘液の感触。それは、誰かが捨てた後悔や悲しみの残滓そのものだった。
角を曲がった瞬間、鋭い頭痛がこめかみを貫いた。視界が白く点滅し、何か大事なことを、また一つ失った感覚が胸を抉る。
――誰かの名前だ。昨日、話したはずの。
その喪失感と入れ替わるように、目の前の空間がぐにゃりと歪んだ。アスファルトから水が湧き出し、一人の男の幻影が立ち昇る。ずぶ濡れの男が、見えない水面の下から必死に手を伸ばし、声なく助けを求めて喘いでいる。幻影の背後で、ぱりん、と何かが割れる乾いた音がした。幻影は泡となって消え、濡れたアスファルトの染みだけが、誰かの恐怖の痕跡として残された。俺の記憶が剥がれ落ちるたびに起こる、見慣れた、だが決して慣れることのない光景だった。
第二章 共鳴する恐怖
奇妙な変化は、一月ほど前から始まった。俺が生み出す恐怖の幻影に、ある共通したモチーフが紛れ込むようになったのだ。
ある時は、炎に追われる老婆の背後に、ひび割れた姿見が映り込んでいた。またある時は、奈落へ落ちていく少女の足元に、砕けた手鏡の破片が無数にきらめいていた。溺れる男、燃える老婆、落ちる少女。彼らの恐怖はバラバラなはずなのに、必ずどこかに『割れた鏡』が存在する。まるで、俺の失われた記憶が、他人の恐怖を映し出すための、ひび割れたレンズになってしまったかのようだった。
その変化は、街にも伝染した。路地裏の『忘却の塊』たちが、幻影の出現に呼応するように、時折、鏡のように鈍い光を反射し始めたのだ。粘液質の表面が硬化し、鋭利な破片のような様相を呈し始めている。街全体が、一つの悪夢に侵食されていく。
俺は自分の正体を知らなくてはならない。この現象の意味を突き止めなければ。かすかな記憶の糸をたぐり寄せ、街の外れにある一軒の古書店へと足を向けた。「時紡ぎの書庫」。その店の主は、忘れられた記憶を蒐集しているという。
錆びた鈴の音と共に扉を開けると、黴と古い紙の匂いが鼻をついた。カウンターの奥から、無数の皺を刻んだ老婆が静かに顔を上げた。
「おいでなすったね、記憶を失くした子」
老婆――エレナは、全てを見通すような深い瞳で俺を見つめていた。
第三章 無音の栞
エレナは何も聞かなかった。ただ、黙って分厚い革張りの古書をカウンターに置いた。表紙には題名も無く、ただ古びた紋様が刻まれているだけだ。そして、その隣に、一枚の栞をそっと滑らせた。
それは、俺が毎朝シーツの上で見つける紙片に酷似していた。だが、俺のものが脆く乾いているのに対し、それはしなやかで、吸い込まれるような純白をしていた。
「無音の栞さ。文字の無い物語を読み解くためのね」
エレナは言った。「お前の失くしたものが、その本の中にあるかもしれない。だが、物語は時として、読み手に牙を剥くよ」
俺は栞を手に取った。ひんやりとしているが、あの『忘却の塊』のような不快な冷たさではない。静謐で、どこか懐かしい感触だった。言われるがままに、古書の適当なページを開き、その間に『無音の栞』を挟み込む。
瞬間、本のページから黒いインクが滲み出し、人型を成して床に滴り落ちた。それは、物語に登場する騎士の姿をしていた。しかし、その顔は苦悶に歪み、自身の鎧に映る姿を忌々しげに睨みつけている。騎士の幻影は、裏切り者の烙印を押された己の顔を直視できず、城中の鏡という鏡を、その剣で叩き割って回ったという。
ガシャン!と、甲高い破壊音が響き渡る。騎士の幻影の足元に、無数の鏡の破片が飛び散った。まただ。『割れた鏡』。俺自身の恐怖ではないはずなのに、その絶望は、まるで俺自身の心から流れ出たかのように、ひどく生々しかった。
第四章 鏡の向こう側
事態は、俺の想像を遥かに超えて悪化した。騎士の幻影は書庫を飛び出し、街の闇へと溶けていった。そして、路地裏の『忘却の塊』たちを引き寄せ、吸収し始めたのだ。
黒い粘液は騎士の幻影にまとわりつき、鎧となり、剣となった。それはもはや単なる幻影ではない。鏡の破片のように鋭利な身体を持ち、絶望を撒き散らす、実体を持った怪物へと変異していた。怪物が咆哮すると、街中のガラスが共振して砕け散る。人々は恐慌に陥り、その恐怖が新たな『忘却の塊』を生み出し、怪物はさらに力を増していく。悪夢の循環だった。
俺はエレナの元へ駆け戻った。
「どういうことだ! あれは一体何なんだ!」
エレナは窓の外で暴れる怪物を静かに見つめていた。その横顔に恐怖の色はない。
「あれは、お前自身の欠片だよ」
彼女はゆっくりと俺に向き直った。「お前は記憶を失っているんじゃない。記憶を、この世界に『分け与えて』いるんだ」
エレナの言葉は、雷のように俺の脳を撃ち抜いた。『割れた鏡』のモチーフは、他人の恐怖がたまたま作り出したものではない。それは、俺という存在の核を成す、たった一つの巨大な記憶の象徴。俺が記憶を失うたび、その巨大な記憶の断片が、他者の恐怖という形を借りてこの世に漏れ出していたのだ。
「お前が失くした紙片は、記憶の欠片じゃない。お前自身のかけがえのない一部なのさ」
第五章 世界という名の記憶
エレナの手に導かれ、俺は目を閉じた。意識が深く、どこまでも沈んでいく。冷たい水の底へ、あるいは果てしない宇宙の闇へ。やがて、俺は広大な何もない空間に立っていた。そして、目の前には、天を衝くほどに巨大な、ひび割れた一枚の鏡があった。
それを見た瞬間、全てを思い出した。
俺は、カイという名の個人ではなかった。俺は、遥か昔に滅びた世界の、最後の記憶そのものだった。その世界が終焉を迎える瞬間の、ありとあらゆる生命の恐怖、絶望、後悔、悲しみ、その全てを一身に引き受け、次の世界へと持ち越すために生まれた『器』。
この記憶は、あまりにも強大で、あまりにも苦痛に満ちている。だから俺は、俺自身を少しずつ失うことで、その記憶を薄め、この新しい世界に分散させていたのだ。俺から剥がれ落ちる紙片は、その記憶の濾過装置だった。人々が『忘却の塊』を生み出すのは、俺から分け与えられた根源的な恐怖の記憶に、彼ら自身の小さな絶望が触発されるからに他ならない。
そして、あの『割れた鏡』の怪物は、一つに戻ろうとする本能の化身。分散された世界の終焉の記憶が、再びその器の元へと集まろうとする、世界の摂理そのものだった。俺という器が記憶で満たされた時、この世界もまた、終わりを迎える。
第六章 新しい白紙
全てを悟った俺に、選択の余地はなかった。この穏やかな悲劇を終わらせるには、俺が再び、全ての記憶を引き受けるしかない。
俺は怪物の前に立った。もはや恐怖は感じなかった。それは、還るべき場所へと還ろうとしている、迷子のようなものなのだから。俺は静かに両腕を広げた。
「お帰り」
その一言を合図に、怪物を構成していた無数の鏡の破片が、光の粒子となって俺の体へと殺到した。激痛。絶叫。滅びゆく世界の断末魔が、数億の魂の叫びが、俺の内に流れ込んでくる。街が、人々が、エレナの微笑みが、白く、溶けていく。世界がその輪郭を失い、真っ白な光に包まれていった。
やがて、全ての音が消え、俺は完全な無の中に独り立っていた。
どれほどの時間が経っただろうか。その純白の空間に、ぽつりと、小さな緑の芽吹きのようなものが生まれた。新しい生命の息吹。新しい記憶の兆し。それに応えるように、俺の胸から一枚の真新しい『白紙の栞』が、ひらりと剥がれ落ちた。
ああ、また始まるのだ。
俺の意識がゆっくりと薄れていく。名前も、役目も、この途方もない悲しみさえも、遠ざかっていく。
次に目覚めた時、俺は自分が誰なのかも忘れているだろう。
新しい世界で、名もなき青年として目覚める。そして、いつかまた、その世界の『忘れたい記憶』を一身に受け継ぐことになる。全てを忘れることで、全てを始めるために。それが、俺という『器』に与えられた、永遠の物語なのだから。