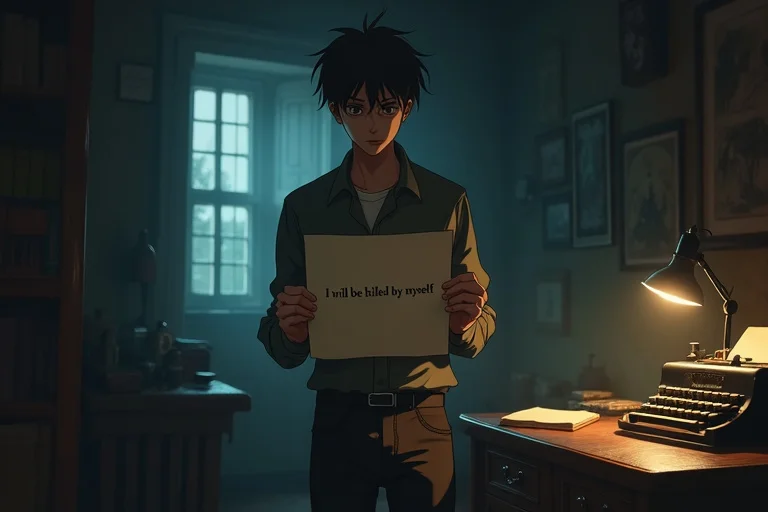第一章 色を失くした朝
朝陽がアトリエの床に長い影を落とす頃、カイトはいつもと同じように、記憶のない絵画の前で目を覚ました。イーゼルに立てかけられた真新しいキャンバス。描かれているのは、紺碧の海を背景に、砂浜で二人の人物が笑い合っている情景だった。砕ける波の飛沫は真珠のように煌めき、空を舞うカモメの翼には風の感触さえ宿っている。それは幸福そのものを切り取ったような、完璧な一枚だった。
だが、カイトの胸を締め付けたのはその完璧さではない。笑い合う二人のうち、片方の人物の顔だけが、まるで底なしの闇で塗りつぶされたかのように、真っ黒だったのだ。
「また、か……」
乾いた唇から、ため息が漏れる。カイトは、自分が見た夢や思考を「絵画」として現実世界に具現化させる特異体質を持っていた。その代償として、描かれた対象に関する記憶は、彼の内側から綺麗に消失する。枕元に増えていく絵は、彼が失った記憶の墓標だった。
ドアをノックする音が響き、幼馴染のミオが顔を覗かせた。「おはよう、カイト。……新しい絵?」彼女はカイトの才能の唯一の理解者であり、彼の失われた記憶の管理人でもあった。
ミオは黒塗りの部分にそっと指を触れようとして、寸前で止める。その瞳に悲しげな色が浮かんだ。「また、『あの人』なのね」
カイトが何も答えられないでいると、窓の外から街のざわめきが聞こえてきた。普段の朝とは違う、不安を含んだ人々の声。二人が窓辺に駆け寄ると、広場に集まった人々が空の一点を見上げ、何かを指さしていた。
彼らの視線の先には、街の象徴である「建国祭の幻影」が浮かんでいた。この世界では、過去の出来事の痕跡が「透明な幻影」としてその場に留まり続ける。建国祭の幻影は、何百年も前に初代国王が民衆に手を振った、祝福に満ちた光景だった。しかし今、その輪郭は陽炎のように揺らめき、まるで古い壁画が風化するように、端から砂になって崩れ落ちていた。
カイトは自分の絵に目を戻した。不自然に塗りつぶされた黒と、世界から消えゆく過去の痕跡。無関係のはずの二つの現象が、彼の心の中で不気味な和音を奏でていた。
第二章 透明な哀歌
痕跡の消滅は、世界中で同時に始まっていた。消えていくのは決まって、人々の心を温めてきた、幸福な記憶の痕跡ばかりだった。愛を誓う恋人たちの囁き、家族で囲んだ食卓の笑い声、戦勝を祝う兵士たちの凱旋パレード。それらがまるで幻だったかのように、空間から、そして人々の記憶から消え去っていく。
「何かが、美しい記憶だけを狙って喰い荒らしているみたい」
ミオの祖母が営む古い図書館で、カイトは低い声で呟いた。高い天井まで続く書架の隙間から差し込む光が、舞い上がる埃をきらきらと照らしている。この図書館には、街で最も古い痕跡の一つ、「始まりの恋人たちの誓い」が、特別な保存空間に安置されていた。
二人がその部屋へ足を踏み入れた、まさにその時だった。
空中に浮かんでいた、若い男女が手を握り合う透明な幻影が、不意に激しく明滅した。まるで燃え尽きる蝋燭の最後の輝きのように。そして、音もなく、光の粒子となって霧散した。
「あ……」
隣にいたミオの祖母が、小さく声を漏らす。彼女は困惑したように眉を寄せ、自分の夫の古い写真に目を落とした。「……あなた。私たち、どうやって出会ったんでしたかしら……? 大切な約束を、したような気もするのだけれど……」
存在が消える、ということはこういうことなのか。カイトは背筋に冷たいものが走るのを感じた。痕跡が消えるだけではない。それに紐づいた人々の記憶、感情、関係性までもが、根こそぎ奪われていくのだ。それは静かな、しかし残酷極まりない世界の破壊だった。
第三章 塗りつぶされた肖像
アトリエに戻ったカイトは、壁一面に掛けられた自らの絵画と向き合っていた。記憶のない傑作の数々。その多くに、あの不気味な黒い塗りつぶしが存在していた。公園のベンチ、夕暮れの教室、雨上がりの路地。様々な風景の中に、必ず寄り添うように存在する、顔のない誰か。
カイトは、失われた記憶の断片を必死で手繰り寄せようとする。だが、そこには虚無が広がるばかりだ。描けば忘れる。その喪失感は、鋭いガラスの破片のように、常に彼の心を苛んでいた。
「あなたの絵は、喪失の記録なんかじゃない」
いつの間にか隣に立っていたミオが、静かな声で言った。
「これは、カイトが何かを、誰かを、必死で守ろうとした証だと思う。忘れてしまうほど、強く想いを込めた……贈り物よ」
その夜、カイトは夢を見た。
見たことのないアトリエ。荒れ果て、埃っぽい。その中央で、年老いた自分がイーゼルに向かっていた。その手には、奇妙な筆が握られていた。持ち手の部分がガラスの砂時計になっており、中の銀色の砂がさらさらと流れ落ちている。
老いたカイトは、その「砂時計の筆」で、美しい風景画の中の、愛おしそうな顔をした少女を、涙を流しながら塗りつぶしていた。一筆ごとに、キャンバスから光が奪われ、筆の砂時計へと吸い込まれていく。夢の中の自分は、絶望と、そして揺るぎない決意に満ちた顔をしていた。
第四章 砂時計の囁き
夢から覚めたカイトは、何かに憑かれたようにアトリエの中を探し始めた。記憶の片隅に引っかかっていた、古い木箱。アトリエの隅で、分厚い埃を被って眠っていたそれをこじ開ける。
中にあったのは、夢で見たものと寸分違わぬ、「砂時計の筆」だった。
カイトが恐る恐るその筆を手に取った瞬間、脳内に奔流のようなイメージが流れ込んできた。色が抜け落ち、すべてが灰色になった未来の世界。活力を失い、虚ろな目で空を見上げる人々。そして、その世界でたった一人、パレットを手に立ち尽くす、年老いた自分の姿。
「見つけたわ!」
息を切らしたミオが、一冊の古文書を抱えて駆け込んできた。彼女の指が示すページには、砂時計の筆の挿絵と共に、こう記されていた。
『記憶を糧とし、時を渡る賢者の筆。描かれし対象の痕跡を現世より消し去り、その光を未来へ運ぶ』
二人の間に、張り詰めた沈黙が落ちる。
痕跡を消していたのは、誰かではない。
未来の世界から来た、カイト自身だった。
「嘘よ……」ミオの声が震える。「じゃあ、カイトが……あなたが、みんなの思い出を……?」
「……わからない」
「私の思い出も、あなたが消したの? あの建国祭で、初めて手を繋いでくれたことも、忘れちゃったの!?」
ミオの瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。彼女との思い出が詰まった痕跡もまた、少しずつ風化し始めていることに、カイトは気づいていた。信じたいのに、信じられない。愛しいはずの幼馴染が、世界を壊す破壊者に見えてしまう。二人の間に、修復不可能な亀裂が入ったように思えた。
第五章 未来からの手紙
カイトは、ミオの悲痛な視線を受け止めながら、再び「砂時計の筆」を強く握りしめた。意識を集中させると、筆を通して、未来の自分からの思念が、静かな手紙のように心に届いた。
未来の世界は、死にかけていた。
過去の輝かしい痕跡が放つ微弱なエネルギーだけが、世界の崩壊をかろうじて食い止める最後の生命線だった。しかし、人々は新たな幸せを紡ぐ力をとうに失い、先人の遺した光を食いつぶして生き永らえるだけの存在に成り下がっていた。そのエネルギーも、今や枯渇寸前だった。
未来のカイトは、何十年もかけて世界を救う方法を探し続けた。そして、ただ一つの、非情な答えに辿り着く。
最も純粋で強力なエネルギーを持つのは、「個人の、最も幸福な記憶から生まれた痕跡」であること。そして、その痕跡の持ち主自身が記憶を完全に手放すことで、エネルギーは純化され、時空を超えて転送できるということ。
塗りつぶされた絵画は、すべてカイトがミオと過ごした、かけがえのない日々の記憶だった。初めて二人で見た海。図書館で居眠りする彼女の寝顔。何気ない会話、共に過ごした時間。それらは、この世界で最も美しく、最も強い光を放つ痕跡だったのだ。未来を救うために、未来の自分は、過去の自分から最も大切な宝物を奪うしかなかった。
「……君との記憶が、未来を救う光になるんだ」
真実を知ったカイトの言葉に、ミオは唇を噛みしめた。しかし、彼女の瞳に宿っていた疑念は、いつしか深い慈愛の色に変わっていた。
第六章 最期のストローク
新しいキャンバスが、イーゼルに立てかけられる。
カイトの脳裏に、これから描くべき最後の絵が、鮮明に浮かび上がっていた。ミオと初めて出会った日。満開の桜並木の下で、風に舞う花びらの中、はにかみながらこちらを見つめる、幼い少女の姿。二人にとっての、すべての始まりの記憶。
彼は「砂時計の筆」を手に取る。
ミオは何も言わず、そのカイトの手に、そっと自分の手を重ねた。温かい感触が伝わる。
「忘れても、私が覚えてる」
涙声だったが、その声は凛としていた。
「私が、あなたの記憶になるから」
カイトは頷き、筆を走らせた。
一筆、また一筆。描くたびに、大切な何かが自分の中から抜け落ちていく。桜の甘い香り。彼女の鈴のような笑い声。初めて触れた、小さな手の温もり。そして、胸の奥で燃え続けていた、愛しいという感情そのものが、ゆっくりと色褪せていく。
やがて、絵は完成した。
桜並木の下に、少女が一人、ただ佇んでいる。
カイトにはもう、その少女が誰なのか分からなかった。どうしてこの絵を描いたのかも、思い出せない。ただ、胸の奥に、ぽっかりと穴が空いたような、温かいような、ひどく切ない感覚だけが残っていた。
第七章 残光のパレット
世界を覆っていた痕跡の風化が、ぴたりと止まった。未来は、救われたのだろう。
カイトのアトリエで、ミオは完成したばかりの絵を、彼の隣で静かに見つめていた。
「綺麗な絵だね」
記憶を失ったカイトが、まるで他人の作品を評するように言った。
「この子、誰だろう。なんだか……すごく、大切な人だった気がするんだ」
その言葉に、ミオは懸命に涙をこらえ、精一杯の笑顔を作った。
「ええ。世界で一番、大切な人よ」
彼女はカイトの手を取り、アトリエの窓を大きく開け放った。外の景色は、一変していた。消えかけていた街の痕跡が、淡く、しかし確かな光を取り戻し、あちこちで再び灯り始めていた。それは、カイトが捧げた幸福な記憶が、未来を救い、そして現在にも再生の光をもたらした証だったのかもしれない。
カイトは、記憶を失ったまっさらな心で、その美しい光景に見入っていた。彼の傍らに置かれたパレットには、まだどんな色も置かれていない。
失われた記憶と引き換えに守られた世界で、二人はこれから、どんな新しい色を紡いでいくのだろう。ミオはカイトの手を強く握りしめた。その温もりだけは、決して失われてはいなかった。