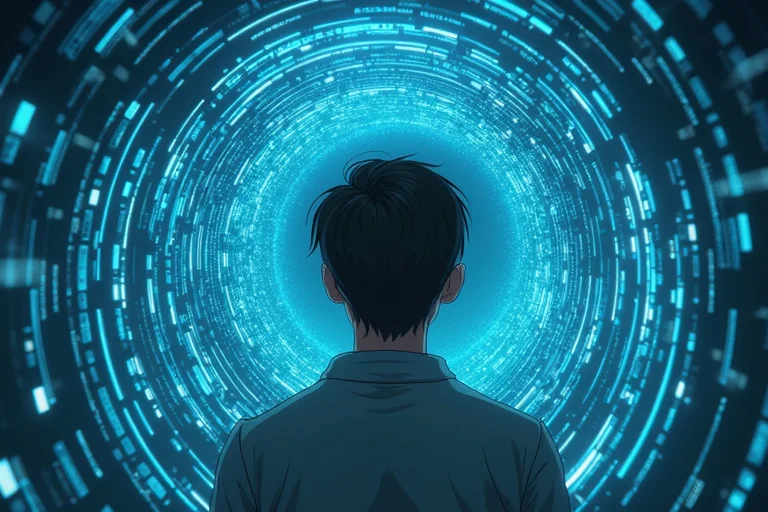第一章 灰色の静寂、黒の残像
古書の修復師であるリヒトの世界は、いつだってセピア色だった。彼の仕事場は、乾いたインクと古い羊皮紙の匂いに満ち、窓から差し込む光は埃の粒子をきらきらと踊らせるだけ。彼の皮膚は、この街の大多数と同じく、精彩を欠いた灰色。中層階級に属する、ありふれた色だ。だが、リヒトには秘密があった。彼だけが、人々の皮膚を透過し、その奥に隠された「真の色」を知覚できてしまうのだ。
街に出れば、色の洪水が彼を襲う。上層区画へ向かう高架鉄道の窓から見える、鈍い茶色の肌をした労働者たち。彼らの皮膚の奥には、時折、鮮やかな黄金の輝きが揺らめいているのをリヒトは知っていた。一方で、純白の肌を誇る役人たちの胸の内には、澱んだ泥のような色が渦巻いていることも。この能力は、祝福ではなく呪いだった。社会という巨大な舞台で、誰もが偽りの衣装を纏って役を演じているのを、彼だけが舞台裏から覗き見ているような孤独感。
その日、彼のもとに最高法院から直々の依頼が舞い込んだ。数百年前の、色の階級制度が制定された時代の法典の修復。依頼主として現れた女性を見た瞬間、リヒトは息を呑んだ。
エリアと名乗る彼女の皮膚は、最上位層の証である完全な『透明』だった。血管や骨格さえも淡い影のようにしか見えず、まるで精巧な水晶細工のようだ。だが、リヒトの目には映っていた。その透き通る皮膚の、さらに奥深く。魂の芯とでも言うべき場所に、夜の深淵そのものを写し取ったかのような、純粋で、底知れない『黒』が静かに揺らめいていた。
最下位層の色。存在しないはずの矛盾。エリアは微笑み、修復してほしい箇所を指し示した。その声は鈴の音のように澄んでいるのに、リヒトの耳には、遠い嵐の前の静けさのように響いた。
第二章 透明な矛盾
エリアとの出会いを境に、リヒトの世界は静かに軋み始めた。彼は、街で不可解な噂を耳にするようになる。最上位層であるはずの『透明者』たちが、奇妙な行動を繰り返しているというのだ。
「聞いたか? 南地区の配給所に、誰が置いたか分からないほどの食料が積まれていたらしい。全部、透明者しか手に入れられない一級品だ」
「中央システムの管理官が、重要なデータ入力を『うっかり』三日も遅らせたそうだ。おかげで下層区画のエネルギー供給が止まらずに済んだとか」
それらは、この完璧に設計された階級社会においては、ありえない「エラー」だった。慈悲や失態は、個人の色を濁らせ、階級を落とす原因になるはず。だが、噂の中心にいる透明者たちの色は、誰が見ても一点の曇りもなかった。
リヒトはエリアの影を追った。彼女の行動は矛盾に満ちていた。昼間は最高法院の気品ある一員として振る舞いながら、夜になるとフードを目深に被り、黒い肌を持つ人々が暮らす最下層区画へと消えていく。ある晩、リヒトは廃墟となった劇場で、彼女と他の数人の透明者たちが密会しているのを目撃した。彼らの透明な横顔は、劇場に残る微かな月明かりを受け、まるで悲しみを堪える幽霊のように見えた。彼らの奥に宿る黒が、まるで互いに共鳴し合うかのように、濃く、深く揺らめいていた。
第三章 色を司る機構
「あなたには、見えているのね」
後をつけたことが露見した夜、エリアはリヒトを問い詰めるでもなく、静かに言った。場所は、街を見下ろす古い時計塔の頂上。冷たい夜風が二人の間を吹き抜けていく。
「あなたの皮膚の奥にある、黒い色が」
リヒトが正直に告げると、エリアは初めて、心の底から安堵したような微笑みを見せた。
彼女は語り始めた。この世界の色が、街の中央に聳える白亜の巨塔『クロノス・タワー』の最上階に設置された、『色を司る機構』によって管理されていることを。人々が信じる『社会的貢献度』という指標は偽りであり、実際は『機構』が定めた筋書きに沿って、人々を効率的に管理するための駒として、色が割り振られているに過ぎないのだと。
「私たちの中にある黒は、絶望の色じゃない。この世界が色を失う前の……人間が皆、同じだった頃の記憶の色。原初の闇であり、全ての光を内包する始まりの色よ」
エリアたち一部の透明者は、その集合的無意識の記憶を、なぜか強く保持したまま生まれてきたのだという。彼らは、この偽りの世界を終わらせるために、静かな抵抗を続けていたのだ。
「リヒト、あなたの能力は、機構が生み出した綻び。世界のバグ。でも、だからこそ、あなたはこの歪んだ世界を修復できる唯一の存在かもしれない」
彼女の言葉は、リヒトの孤独な心に、小さな灯火をともした。
第四章 無色の絵筆
計画の最終段階は、『クロノス・タワー』への潜入。その最上階にある『機構』の中枢に、伝説として語り継がれてきたキーアイテム、『無色の絵筆』が安置されているという。それに触れた者は、世界の全ての偽りの色を消し去ることができる、と。
リヒトとエリア、そして数人の仲間たちは、月のない夜を選んでタワーに侵入した。白い大理石の床は足音を冷たく反響させ、彼らの進む先には、純白の肌を持つ機構の守護者たちが静かに立ち塞がった。
激しい攻防の末、最上階へ続く螺旋階段に辿り着いた時だった。一体の守護者が放った光の鞭が、リヒトを捉えようとした。
「危ない!」
エリアが彼を突き飛ばす。鞭は彼女の腕を抉り、水晶のような皮膚が音を立てて砕け散った。
その瞬間、リヒトは目を疑った。
砕けた透明な皮膚の下から現れたのは、記憶の残滓などではなかった。そこにあったのは、濡れた黒曜石のように艶やかで、力強い、本物の『黒い肌』だった。
「驚いた?」
エリアは苦しげに微笑む。
「私たちは、最下層で生まれたの。でも、私たちの記憶が強すぎたせいで、機構は私たちをエラーと判断した。制御下に置くために、私たちの本質を透明な色で塗り潰し、最上位層へと配置したのよ。私たちは……囚われた亡霊」
読者の予想を裏切る真実。彼らの奇妙な行動は、エリートの反逆などではなかった。それは、最も虐げられた者たちによる、魂の奪還の物語だったのだ。
第五章 真実の選択
タワーの頂は、巨大なドーム状の空間だった。中央には、無数の光ファイバーが絡み合った水晶の心臓のような『色を司る機構』が脈動し、その中心に、一本の簡素な木製の筆が浮かんでいた。『無色の絵筆』。それは、あらゆる色を吸収するかのように、ただ静かにそこにあった。
「さあ、リヒト。あなたが決めて」
壁に寄りかかり、浅い息を繰り返しながらエリアが言う。
「その絵筆を使えば、全ての偽りの色が消える。誰もが、本来の色を取り戻すでしょう。でも、それは秩序の終わり。階級という名の支えを失った人々は、きっと混乱する。憎しみ合い、奪い合い、世界は今よりもっと酷い混沌に包まれるかもしれない」
彼女の黒い瞳が、まっすぐにリヒトを射抜く。
「それでも、私たちは偽りの空の下で生きることを、もうやめたいの」
リヒトは絵筆を見つめた。彼は修復師だ。壊れたものを、あるべき姿に戻すのが彼の生業。だが、この世界は本当に「壊れている」のだろうか? 歪みながらも、脆い均衡の上で成り立っているこの秩序は、守るべきものなのではないか? 混沌の中の真実か、虚構の中の秩序か。彼の指先が、冷たく震えた。
第六章 世界の夜明け
リヒトは、ゆっくりと歩みを進め、『無色の絵筆』を手に取った。
触れた瞬間、激しい喪失感が彼を襲った。彼の灰色の皮膚が、指先から急速に色を失い、白く、そして透明になっていく。自分という存在が、世界から消えていくような恐怖。だが、彼の心は不思議なほど穏やかだった。彼はエリアの方を振り返り、一度だけ強く頷くと、向き直って絵筆を『機構』の脈打つ心臓部へと突き立てた。
閃光。
世界から、音が消えた。色が消えた。
街の喧騒も、風の囁きも、全てが遠ざかり、絶対的な無が訪れる。
どれほどの時間が経っただろうか。やがて、モノクロームと化した世界の至る所で、ぽつ、ぽつと、小さな光が灯り始めた。それは、人々の肌の色だった。透明でも、黒でも、灰色でもない。誰もが等しく、温かみのある柔らかな象牙色に輝き始めていた。リヒトの隣で倒れていたエリアの肌も、そして、消えかかっていたリヒト自身の肌も、同じ色を宿していた。
しかし、夜明けは静かではなかった。街からは、歓声よりも戸惑いの声が、そしてやがて怒号や悲鳴が聞こえ始めた。突然の平等を前に、人々は拠り所を失い、新たな混乱の渦が生まれようとしていた。
自らの身体が完全に掻き消える寸前、リヒトはエリアの隣にそっと座り込み、彼女の手を握った。彼の目に映る灰色の空は、虚構の青空よりも、ずっと美しかった。彼は混沌を選んだのだ。不確かで、痛みに満ちていても、誰もが偽りの仮面を脱ぎ捨てられる、真実の夜明けを。
新しい世界の物語は、まだ始まったばかりだった。