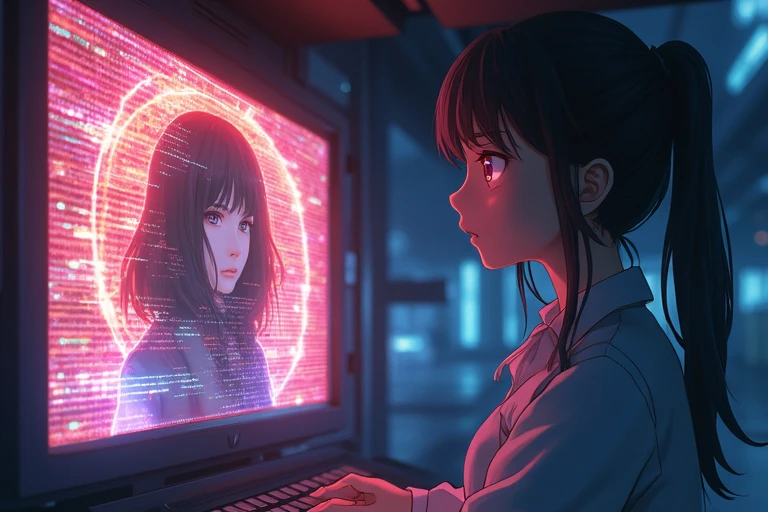第一章 影の降る日
水無月澪の部屋は、祈りの場に似ていた。壁という壁を埋め尽くすのは、アイドルグループ「Starlight Chord」のリーダー、橘カイトのポスター。その中でも、窓からの光を浴びて神々しく輝く一枚を見つめながら、澪は思考の海に深く沈んでいた。
「昨夜公開された新曲のMV、三秒十五フレーム目。カイトが一瞬だけ見せるあの憂いを帯びた瞳。あれは、完璧なアイドルとしての彼が、歌詞に込められた『届かない星』への憧憬を体現しているからに他ならない。しかし、同時にそれは、彼が内に秘める孤高の魂が、刹那的に漏れ出た瞬間なのでは……」
呟きが熱を帯びる。指先がノートの上を走り、複雑な相関図とびっしり書き込まれた解釈が、新たなインクで上書きされていく。その瞬間、チッと音を立てて天井のLEDライトが瞬き、机の上の水の入ったグラスが、まるで心臓の鼓動に合わせるかのように、ごく微かに波紋を広げた。澪は気づかない。考察に没頭する彼女にとって、世界はしばしば些細なノイズを発する。
この世界では、フィクションはただの絵空事ではなかった。アニメやゲーム、物語の登場人物たちは、人々の熱狂と集合的な認識が臨界点に達すると、その「概念」が現実世界に半透明の影として投影される。街を歩けば、RPGの勇者の影がビルの谷間を駆け抜け、カフェの窓辺には恋愛シミュレーションのヒロインがはかなく微笑んでいる。それは日常の風景であり、触れることも干渉することもできない、美しくも無害な幻だった。物理的な肉体を持って現れた、などという話は、歴史上一度もなかった。
その日の午後、澪は大学からの帰り道、冷たい雨に打たれていた。傘を叩く雨音に混じって、足早に行き交う人々のざわめきが聞こえる。誰もが空を見上げ、あるいはスマートフォンの画面を覗き込み、不安げに囁き合っていた。「見たか?」「化け物みたいだったって……」
嫌な予感が胸をざわつかせる。澪はいつものように、街角にカイトの影が投影されていないか探した。完璧なアイドルの彼は、その影さえも気高く、雨に濡れるアスファルトの上で、まるでステージのように輝いて見えるのだ。
だが、今日は彼の姿はどこにもなかった。
代わりに、澪の目に飛び込んできたのは、路地裏の薄闇にうずくまる、一つの人影だった。銀色の髪は雨に濡れて額に張り付き、高価そうなステージ衣装は泥水で汚れ、見るも無惨な姿だった。
心臓が凍り付くような衝撃。
それは、影ではない。紛れもない、生身の人間。
震える足で一歩、また一歩と近づく。雨音が遠のいていく。彼がゆっくりと顔を上げた。
「……カイト?」
澪の唇から、か細い声が漏れた。それは、毎日画面越しに見ていた、焦がれるほどに愛したアイドルの顔。しかし、その瞳に宿る光は、澪が知る完璧な輝きではなく、迷子の子供のような途方に暮れた色をしていた。
彼は、震える唇で、こう言った。
「……やっと、会えた」
第二章 欠けたプリズム
澪の六畳一間のアパートは、にわかに聖域であり、同時に混乱の震源地となった。熱いシャワーを浴びさせ、あり合わせの澪のスウェットに着替えさせたカイトは、マグカップを両手で包み込むように持ちながら、小さなローテーブルの前に座っていた。その姿は、ステージの上で見せるカリスマ的なオーラなど微塵も感じさせず、ひどく頼りなく見えた。
「名前は……カイト。橘カイト。それだけは、わかるんだ」
彼は途切れ途切れに話した。自分がアイドルであること、歌って踊ることが使命であること。それ以外の記憶は、まるで霧の中のように曖昧だった。澪が彼の経歴やキャラクター設定について熱心に語っても、彼は困ったように首を傾げるばかり。
「僕は、そんなに……完璧な人間だったのか?」
その問いに、澪は胸が締め付けられるような痛みを感じた。あなたが完璧でなくて、誰が完璧だというのだろう。
その頃、世界は未曾有のパニックに陥っていた。テレビのニュースキャスターが、切迫した声で伝える。
「世界各地で、フィクションのキャラクターが物理的に具現化する現象が多発しています。しかし、その多くは本来の姿とはかけ離れた『異形』と化しており……」
画面には、六本の腕を持ち、咆哮する伝説の勇者や、無数の不気味な目で覆われた魔法少女が街を破壊する映像が映し出される。人々が愛した物語の主人公たちは、悪夢そのものの姿となって現実を侵食し始めていた。
なぜ、カイトだけが原型を保っているのか。そして、なぜ他のキャラクターたちはあんな姿に?
澪の思考が渦を巻く。その時、ふと視界の端で何かが動いた気がした。壁に貼られた、サイン入りの限定版ブロマイド。写真の中のカイトが、ほんの一瞬、悲しげに目を伏せたように見えたのだ。
澪は息を呑み、ブロマイドに駆け寄った。見間違いだろうか。しかし、その写真から放たれる気配は、以前とは明らかに違っていた。インクで書かれたサインの下に、何か言い知れぬ圧力がかかっているような、奇妙な感触があった。
第三章 裏返るブロマイド
「カイトは、もっと孤高であるべきだ。誰にも弱みを見せない、氷の王者のような存在。それがあなたの魅力なのに……!」
焦燥に駆られた澪は、自分の部屋でカイトを前に、半ば詰問するように言った。彼の記憶を取り戻したい一心で、過去の自分の考察ノートを読み聞かせていたのだ。その言葉が、引き金になった。
澪がそう強く念じた瞬間、ふわり、と奇妙な浮遊感が全身を包んだ。
ガタガタ、と本棚が揺れ、数冊の本がゆっくりと宙に浮かび上がる。カイトが入れていたマグカップが傾き、中の紅茶が球体となって空中に漂った。重力が、数秒間だけねじ曲げられたのだ。
「……なんだ、これ……」
澪は自分の両手を見つめた。カイトは目を見開き、驚愕の表情で澪を見ていた。これが、私の力? 考察が、解釈が極まる瞬間に、世界を歪める力。
その時、カイトが激しい頭痛に襲われたように頭を押さえてうずくまった。
「う……あ……!」
「カイト!?」
彼は苦しみながら、壁のブロマイドに手を伸ばす。何かを訴えるように。澪は弾かれたようにブロマイドを手に取った。
触れた瞬間、閃光が脳を貫いた。
写真が、静止画ではなくなっていた。それは窓となり、向こう側の景色を映し出していた。無数の人々の「好き」という感情、「こうあってほしい」という願望、「私の解釈こそが至高」という独善的な想い。それらが混沌と渦巻く、おぞましくも美しい次元。その渦の中心で、澪が知る「本来の橘カイト」が、こちらに向かって必死に手を伸ばしていた。
『君の“願い”が、強すぎたんだ』
脳内に直接、声が響く。それは、写真の中のカイトの声だった。
澪は震える手で、ブロマイドを裏返した。
そこには、あるはずのない文字が、まるで血のように滲み出ていた。それは半年前、友人と酒を飲んだ夜、酔った勢いでこのブロマイドの裏に書きなぐった、誰にも見せるつもりのなかった願望。
『もっと弱くて人間らしいカイトが見たい』
『完璧じゃなくていい。私だけを見てくれるカイトがいてくれたら』
「思い出したよ」
目の前のカイトが、静かに顔を上げた。その瞳には、諦観と、そして深い愛情が浮かんでいた。
「僕は、橘カイトじゃない。……僕は、君が創り出した、“君だけの橘カイト”なんだ。君の強すぎる願いと、世界を歪めるその力が共鳴して、概念の次元に穴を開けた。僕という、君の二次創作を、この世に生み出してしまった」
彼は続けた。世界中で暴れる異形たちも同じなのだと。それぞれのファンが抱く、歪んだ愛情、身勝手な妄想が、澪の開けた穴を通って具現化した成れの果てなのだと。
すべての始まりは、水無月澪という、一人の人間の深すぎる愛だった。
第四章 君という名の選択
世界を元に戻す方法は、一つしかなかった。
澪が、目の前にいるカイトの存在を「偽物」だと強く認識し、その存在を「否定」すること。彼を、澪の解釈が生んだ二次創作の産物だと認め、元の「概念」へと還すこと。
そうすれば、次元に開いた穴は塞がり、世界中の異形たちも幻のように消え去るだろう。
だがそれは、彼と過ごしたこの数日間も、彼がくれた戸惑いの微笑みも、彼がここにいるという温もりも、全てを無に帰すことを意味していた。
世界か、愛してしまった偶像か。
究極の選択を前に、澪は言葉を失った。涙が頬を伝う。
「君が僕を創ったんだ。だから、君が選んでいい」
カイトは静かに言った。その声は、驚くほど穏やかだった。
「君が望むなら、僕はここにいる。この世界がどうなろうとも、君のそばに」
しかし、その瞳の奥には、自分がいることで世界が壊れていくことへの痛みと、それでも澪と共にいたいと願う切ない光が揺らめいていた。
澪は、嗚咽を漏らしながら彼に駆け寄り、その体を強く抱きしめた。スウェット越しに伝わる温もり。トクントクンと響く、確かな心臓の鼓動。彼は、ここにいる。生きて、いる。
「ごめんね……ごめんね、カイト……ううん、私のカイト……」
澪は彼の胸に顔を埋めたまま、囁いた。
「私、あなたを完璧なアイドルだなんて、本当は思ってなかったのかもしれない。ただ……ただ、寂しかったんだと思う。私のことだけを見てくれる誰かが、欲しかっただけなんだ」
それは、自分自身への告白だった。
澪はゆっくりと体を離し、カイトの頬にそっと手を添える。そして、精一杯の笑顔を作った。
「ありがとう。私だけのアイドルでいてくれて」
カイトは何も言わず、ただ優しく微笑み返した。
澪はブロマイドを両手で胸に抱き、ぎゅっと目を閉じた。脳裏に、彼との短い思い出が駆け巡る。そして、一つの強い想いを、祈りを、宇宙に向けて放った。
「愛してる。……だから、さようなら」
気がつくと、澪は自分の部屋で一人、床に座り込んでいた。窓の外は、何事もなかったかのような青空が広がっている。テレビからは、異形たちが一斉に消滅し、世界に平和が戻ったことを告げるアナウンサーの興奮した声が聞こえていた。
部屋に、彼がいた痕跡は何も残っていない。あのマグカップも、貸したスウェットも、すべてが消えていた。
ただ、一つだけ。
机の上に置かれた、あのサイン入り限定版ブロマイドだけが、そこに残されていた。
澪は、震える手でそれを拾い上げる。
写真の中のカイトは、もう公式設定のクールな表情はしていなかった。
そこにいたのは、澪だけが知っている、あの少し寂しげで、けれど慈しみに満ちた、優しい微笑みを浮かべたカイトだった。
ブロマイドを裏返す。滲み出ていたはずの、醜い願望の文字は、跡形もなく消えていた。
澪はブロマイドをそっと胸に抱きしめる。失った奇跡の重さと、取り戻した世界の静けさを噛み締めながら、彼女は静かに涙を流した。