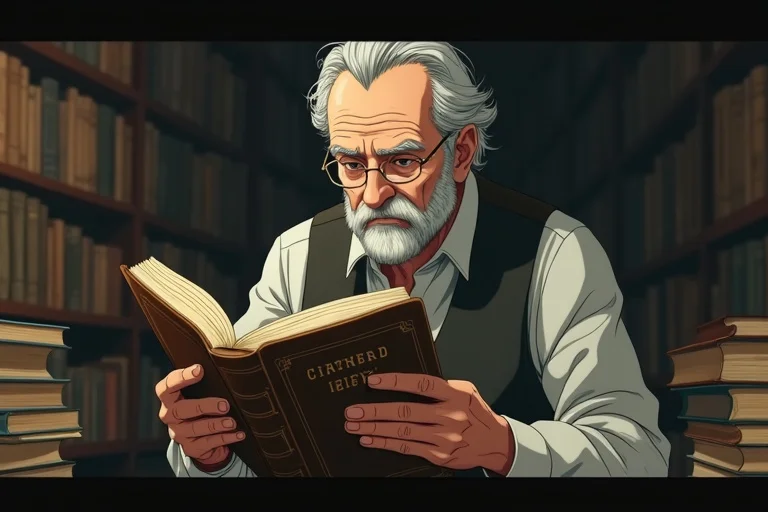第一章 静止した街のささやき
この街では、記憶が形を持つ。人々は胸の奥で熟成させた想いを、色とりどりの『感情の結晶』として取り出し、互いに交換し合う。喜びは太陽を閉じ込めた琥珀のように暖かく、悲しみは月の光を宿した雫のように冷たい。誰もがそうして心を分かち合い、物語を紡ぎ、そして、より美しい物語へと記憶を磨き上げていく。それは、この世界を成り立たせる、優しくも絶対的な法則だった。
僕、アキトだけが、その法則の外側にいた。
きっかけはいつも不意に訪れる。カフェのテラスで湯気の立つカップを眺めていた、その時だった。世界から、ふっと音が消えた。人々の喧騒、遠くを走る路面電車の軋み、風に揺れる街路樹の葉音、そのすべてが完璧な静寂に飲み込まれる。目の前のカップから立ち上る湯気は、空中で精巧な氷の彫刻のように固まり、ウェイトレスの浮かべた微笑みは永遠に引き延ばされた絵画となった。
――また、この瞬間が来た。
僕の左手首には、古びた革紐で結ばれた小さな砂時計が揺れている。普段は一粒の砂も動かない『静止の砂時計』。だが、この無限に引き延ばされた一瞬においてのみ、下にあったはずの瑠璃色の砂が、重力に逆らうようにゆっくりと上へと流れ始めるのだ。
静止した世界で、僕だけが動くことを許される。そして、見る。磨かれる前の、生の情報の残滓を。ウェイトレスの笑顔の奥には、客の些細な一言に傷ついた一瞬の翳りが陽炎のように揺らめいている。向かいの席で愛を語らう恋人たちの間には、選ばれなかった別れの言葉が、無数のひびとなって空間に刻まれていた。
これらは、彼らがやがて『磨き』、忘れていく記憶の断片だ。より良い物語のために捨て去られる、真実の欠片。
僕はいつも、ただそれらを眺めることしかできない。砂時計の砂が数粒、逆流するのを待って、世界が再び色と音を取り戻すのを待つ。だが、今日見えた光景は違った。街の中央広場に立つ慰霊碑――かつて街を襲ったという『灰色の霧の日』の犠牲者を悼む碑だ――その上空に、磨かれた共有記憶とは似ても似つかない、おびただしい数の絶叫と慟哭が、黒い稲妻となって刻まれているのが見えた。
公式の共有記憶では、『灰色の霧の日』は悲劇ではあったが、一人の英雄の自己犠牲によって最小限の被害で食い止められ、人々が手を取り合って復興を成し遂げた『大和解の日』として語り継がれている。その記憶結晶は、街で最も気高く、美しい輝きを放っているはずだった。
なのに、僕の目に見えるのは、英雄譚とは程遠い、救いのない絶望の残響だけだった。砂時計の逆流が、いつもより少しだけ速い。胸の奥が、冷たい水で満たされていくような感覚に襲われた。
第二章 磨かれた英雄の影
真実を知りたいという渇望は、僕を『追憶の書庫』へと向かわせた。街の記憶が集積される、静謐な円形図書館。壁一面の棚には、無数の『感情の結晶』が、その輝きの度合いに応じて分類され、収められている。
目指すのは、書庫の最上階。そこに、『灰色の霧の日』の英雄、カイの結晶が祀られている。陽光を受けて七色に輝く、完璧に磨き上げられた多面体の結晶。それは希望そのものの形をしていた。来訪者は皆、その結晶にそっと触れ、語り継がれる英雄の勇気と献身の記憶を追体験し、心を温めて帰っていく。
僕は恐る恐る、指先をその結晶に伸ばした。
触れた瞬間、温かな光が全身を包み込む。カイの視点から語られる、壮大な物語が流れ込んできた。人々を守るため、迫りくる災禍の中心へたった一人で飛び込んでいくカイ。恐怖を押し殺し、愛する街のためにその身を捧げる崇高な決意。誰もが知る、誰もが愛する、完璧な物語。
そのはずだった。
物語がクライマックスに達し、カイが最後の力を振り絞る、その刹那――世界が、また静止した。
僕の目の前で、英雄カイの崇高な表情が凍り付く。だが、その磨かれた記憶の奥、幾重にも塗り固められた輝きの層の下に、別の顔が見えた。それは、英雄の顔ではなかった。絶望と、後悔と、そして――誰かに向けられた、底知れない憎悪に歪んだ、一人の青年の顔だった。唇が、声にならない形で動いている。
『なぜ』
『お前が』
その言葉の残滓は、僕の魂を直接掴むような、凍てつく冷たさを帯びていた。左手首で、砂時計の砂が激しく逆巻く。結晶から流れ込んでくる温かい光と、その奥から滲み出す冷たい憎悪がせめぎ合い、僕の意識は眩暈と共に遠のいていった。
第三章 記録者の書庫
ふらつく足で『追憶の書庫』を後にした僕の前に、一人の老婆が立っていた。古書のインクと、乾いた薬草の匂いを纏った女性。深く刻まれた皺の奥で、全てを見透かすような瞳が静かに僕を射抜いていた。
「お前さん、見えすぎる目を持っているようだね」
老婆はミナと名乗った。彼女は、この街で忘れ去られた存在――『記録者』だった。人々が記憶を『磨く』ことで失われていく、ありのままの出来事を記録し、歪められていない『原初の結晶』を保管するのが役目だという。
ミナは僕を、街外れの時計塔の地下にある、彼女だけの書庫へと招き入れた。そこは埃と沈黙に満ちた空間だった。棚に並ぶ結晶は、『追憶の書庫』のものとはまるで違う。輝きはなく、濁り、ひび割れ、まるで石ころのように転がっていた。
「これが、磨かれる前の記憶さ。痛みも、醜さも、矛盾も、すべて内包したままのね」
彼女が差し出したのは、ひときゅうすんだ黒曜石のような結晶だった。表面はざらつき、不吉なまだら模様が浮かんでいる。
「『灰色の霧の日』の、原初の結晶だよ」
ミナの言葉に、僕は息を呑んだ。これを、カイの記憶結晶を保管していた書庫で見つけることは決してできない。これは、世界から消されたはずの記憶。
「触れてごらん。お前さんなら、真実が見えるはずだ」
促されるままに、震える指で結晶に触れた。瞬間、指先から全身へと、耐え難いほどの冷気が駆け巡った。
そして、僕の知る世界は完全に崩壊した。
第四章 存在しなかったはずの僕
それは、もはや『無限の一瞬』ではなかった。僕は、あの日の街の中心に、確かに立っていた。空は鉛色に淀み、建物は崩れ、人々の悲鳴が耳を裂く。これは英雄譚などではない。一方的な、ただの蹂躙。絶望的な破壊の光景だった。
そして、その中心にいた。
カイではない。僕と、瓜二つの顔をした少年が。
その少年は、虚ろな目で破壊されていく街を見つめていた。彼の周囲から、世界を蝕む『灰色の霧』が生まれている。愛する者を失った絶望が、彼の内に秘められた強大な力を暴走させていたのだ。彼は、この世界そのものを憎んでいた。全てを無に帰そうとしていた。
その時、一人の青年が少年の前に立ちはだかった。それがカイだった。彼は英雄などではなかった。ただ、友を止めようとした、必死な一人の人間だった。
「やめろ、アキト!」
カイは叫んだ。僕と同じ名前を。
暴走する少年――『僕』は、憎悪に満ちた瞳でカイを睨みつけた。「もう遅いんだ」と呟き、最後の一撃を放とうとする。その瞬間、街の人々の祈り、生きようとする意志が一つになり、光となって少年を包み込んだ。それは攻撃ではない。悲しみに満ちた、一種の『編集』だった。
彼らは、世界を破壊しようとした『僕』の存在そのものを、記憶から『磨き』上げたのだ。彼の絶望を、カイの英雄譚へと書き換えることで。暴走する僕の力を、外部からの災禍『灰色の霧』へと置換することで。
そうして、悲劇的な結末は回避された。世界は救われた。
そして、絶望を選ばなかった可能性、親友を失いながらも生きることを選んだ『僕』の断片から、今の僕――アキトが再構成された。僕が見ていた真実の断片は、過去の記録ではない。磨かれて消え去った、あの破滅の並行現実が、僕という存在を楔にして、この世界に漏れ出してきていた残滓だったのだ。
僕の能力は、失われた記憶を視る力ではない。排除された悲劇を、この世界に再び呼び戻してしまう、危険な扉だった。
第五章 選択の夜明け
地下書庫の冷たい石畳の上で、僕は膝から崩れ落ちた。自分が何者なのか、その答えはあまりにも残酷だった。僕は、磨かれて消された悲劇の亡霊。僕が存在する限り、この世界は常に破滅の可能性と隣り合わせにある。
「砂時計は、消された『お前さん』の魂の欠片を集める器だよ」ミナが静かに言った。「砂が全て逆流した時、二つの可能性は再び一つに戻ろうとするだろう。世界を救うために一度は下された決断を、もう一度、お前さんがすることになる」
見れば、左手首の砂時計は、もう止まることなく、全ての砂が上へ向かって流れ続けていた。硝子の内側から、微かな悲鳴が聞こえる気がした。それは、もう一人の僕の、救いを求める声なのかもしれない。
窓の外が、白み始めている。夜明けだ。
僕は立ち上がり、時計塔の螺旋階段を上った。頂上の展望台からは、朝靄に包まれた街並みが一望できた。人々が目を覚まし、新たな一日を始めようとしている。彼らは今日も、『感情の結晶』を交換し、美しい物語を紡ぎ、ささやかな幸せを分かち合うのだろう。僕が守られた、この偽りの世界で。
真実を暴くべきか? 僕という存在が、この世界の平和が、巨大な嘘の上に成り立っているのだと告げるべきか? それとも、全てを胸に秘め、いつか訪れるかもしれない統合の瞬間に、今度こそ世界を守る選択をするために、静かに生きるべきか?
砂時計を、強く握りしめる。瑠璃色の砂の逆流が、脈打つように僕の意志を問うていた。
どちらの選択が正しいのか、答えは出ない。だが、一つだけ確かなことがある。
僕は、存在する。磨かれて消されたはずの悲しみも、絶望も、全てを抱えて、今ここに立っている。この美しくも脆い世界の片隅で、忘れ去られた真実の響きに耳を澄ませながら。
空が、瑠璃色に染まっていく。僕の砂時計と同じ色だった。流れはまだ、止まらない。僕は、その流れの先にあるものを、ただ見届けるために歩き出す。それが、僕に与えられた、たった一つの役割なのだから。