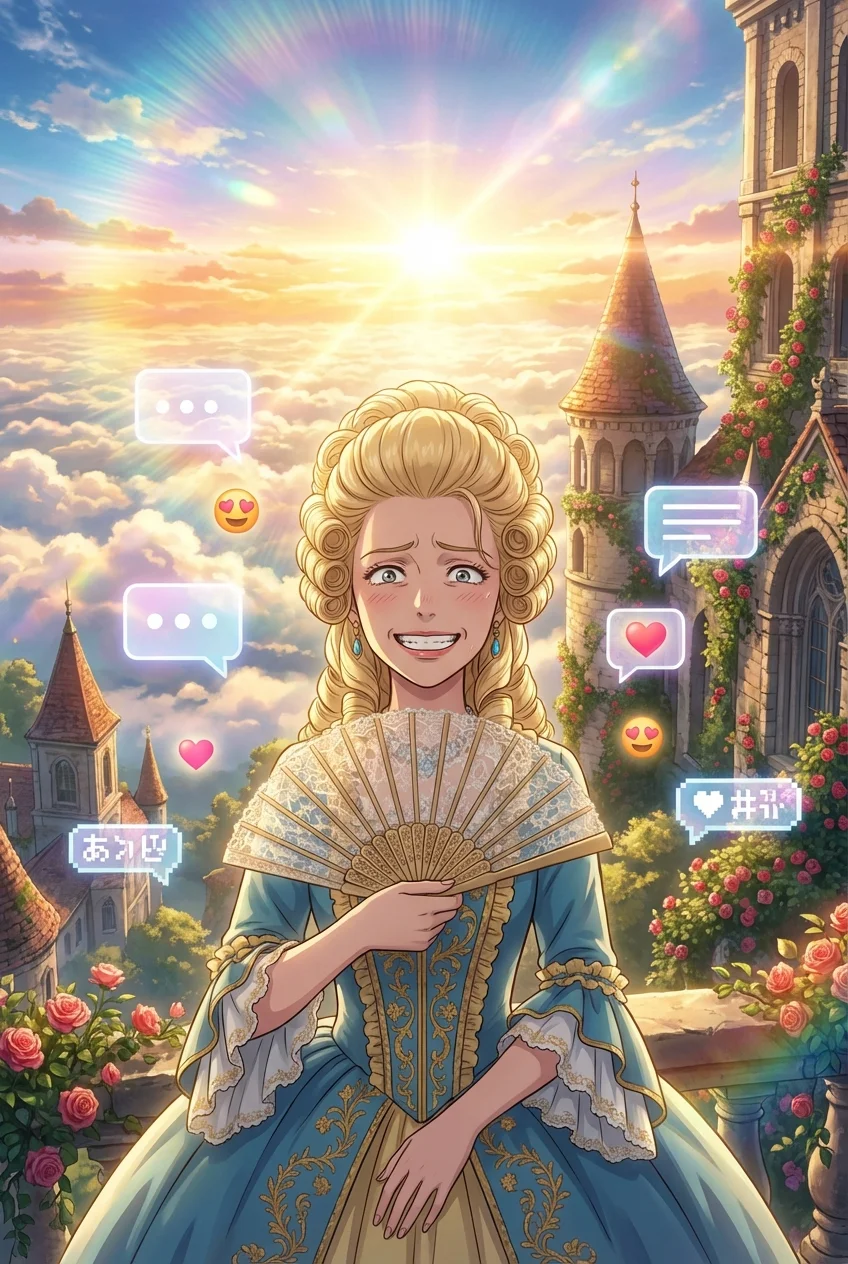第一章 砂を喰らう者
風が哭いていた。世界は、死者たちの叶わなかった願いで満ちている。俺はそれを喰らって生きる者だ。指先に触れた淡い光の粒――「記憶の砂」を、冷たい琥珀の懐中時計へと吸い込ませる。途端、見知らぬ誰かの絶望が奔流となって胸に流れ込んだ。舞台役者として脚光を浴びる夢、その直前で病に倒れた男の無念。彼の才能が俺の四肢に宿る代わりに、また一つ、俺自身の何かが零れ落ちていく。確か、昨日の朝食の味だったか。いや、もっと大切な、誰かに笑いかけられた温かい感触だったか。
俺の存在は、無数の死者の過去を継ぎ接ぎしただけの、空虚な器だ。鏡を覗き込んでも、そこに映る顔は日ごとに輪郭を失い、他人の面影が陽炎のように揺らめいて見える。自分が誰であったのか、その問いは風に溶けて久しい。
そんな乾ききった日々のなかで、ソレを見つけた。
他のどの砂よりも強く、そしてひどく哀しい光を放つ一粒。それを時計に収めた瞬間、脳を灼くような激痛と共に、断片的な映像が過った。――潮の香り。錆びついた螺旋階段。そして、泣き笑いのような顔でこちらに手を伸ばす、誰かの顔。
他の砂とは違う。これは、他人の後悔ではない。まるで、失くした四肢が疼くような、根源的な痛みと郷愁があった。この断片だけは、俺の空っぽの中心を埋める、唯一のピースのように思えたのだ。
第二章 忘れられた灯台
その砂が示す場所を、俺は知っていた。いや、正確には「俺の中にいる誰か」が知っていた。足は自然と、かつて港町だったという廃墟へと向かう。道すがら、俺は幾人もの人生を喰らった。恋人に寄せる甘やかな詩を紡いだ詩人の感情を宿せば、母に手を引かれた幼い日の記憶が消え、老いた画家の熟練の筆致を得れば、自分の本当の声色を忘れた。
手に入れるたびに、失っていく。この身を苛む矛盾に、時折、叫び出したくなるほどの虚無感に襲われる。だが、あの砂の記憶だけは、どんな新しい断片を取り込んでも決して薄れることはなかった。むしろ、他の記憶が消えるほどに、その光は鮮明になっていく。
「お前は、誰なんだ」
誰もいない荒野で、思わず声が漏れた。それは、砂に問いかけているようで、自分自身に問いかけているようでもあった。
やがて、霧の向こうに、古びた灯台のシルエットが浮かび上がった。潮風が運んでくる錆の匂いが、不思議と肺腑に馴染んだ。まるで、幾度となくこの空気を吸い込んできたかのように。一歩、また一歩と近づくにつれ、琥珀の懐中時計が心臓と共鳴するように、熱を帯びていくのが分かった。
第三章 最後の欠片
灯台の扉は、軋みながらも容易に開いた。内部の螺旋階段には、厚い埃が積もっている。だが、その埃の上には、まるで俺を待っていたかのように、点々と光の粒が落ちていた。一つ拾うごとに、記憶が蘇る。
――初めてこの場所を訪れた日の、胸の高鳴り。
――誰かと交わした、未来を誓う拙い約束。
――夕陽に染まる海を見つめながら、指を絡めた温もり。
「ああ……」
声にならない声が漏れる。これは他人の記憶ではない。忘れられていた、俺自身の記憶だ。階段を上り詰めた先、灯室の床の中央に、最後の、そして最も強い光を放つ砂が一つ、静かに横たわっていた。
俺は震える手でそれを拾い上げ、懐中時計に近づける。
その瞬間、世界が砕け散った。
全ての記憶が、一つの物語として繋がった。無数の他者の人生を取り込み続け、自己の境界線が崩壊していく恐怖。愛した人の顔も、自分の名前さえも思い出せなくなる絶望。そして、最後の賭けに出た、過去の俺の姿が見えた。
『――忘れないでくれ。俺が、ここにいたことを』
彼は泣いていた。琥珀の懐中時計を握りしめ、自らの魂を、記憶を、人生そのものを「記憶の砂」へと変え、未来の自分へと託したのだ。いつか、この空っぽになった俺が、俺自身の欠片を見つけ出し、再び「自分」を取り戻せるようにと願って。
俺は、俺自身が放った後悔を、ずっと集めていたのだ。自分を喰らい、自分を繋ぎ止めていたのだ。
「馬鹿野郎……」
涙が頬を伝った。それは、過去の自分への憐憫か、それとも、ようやく見つけ出せたことへの安堵か。感情が爆発し、俺はただ、崩れ落ちて嗚咽した。
第四章 新しい朝
全ての砂が、琥珀の時計の中に収まった。それは、失われた「俺」という人間の完全な設計図だった。これを自身に宿せば、俺は「本来の自分」を取り戻せる。だが、それは同時に、これまで俺を生かし、俺という存在を形作ってきた、名も知らぬ幾多の死者たちの人生を手放すことを意味した。
舞台役者の夢、詩人の愛、画家の情熱。彼らは俺の一部だった。彼らを失うことは、幾人もの友と、一度に死別するようなものだ。
それでも。
俺は、俺として生きたい。
静かに時計を開き、光の奔流を自らの胸に受け入れた。壮絶な喪失感が全身を駆け巡る。そして、それ以上の歓喜が、魂の奥底から湧き上がってきた。忘れていた自分の名前を、愛した人の微笑みを、交わした約束の言葉を、全て思い出した。
ふと、手にしていた懐中時計に目を落とす。ずっと止まっていた秒針が、カチリ、と音を立てて、一秒だけ、確かな時を刻んだ。
夜が明け、灯室の窓から差し込む最初の光が、俺の顔を照らす。もう、その輪郭はぼやけていない。俺は、全てを失い、そして、全てを取り戻した。ここから始まるのは、誰のものでもない、俺自身の人生だ。
俺は朝日の中へと、静かに歩き出した。