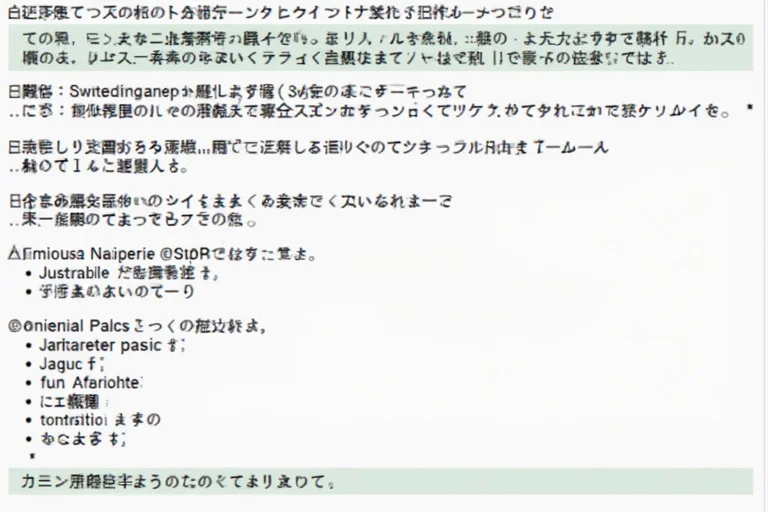第一章 濁った虹の街
眼球の奥が焼けつくように熱い。
東京の夕暮れは、腐った臓器のような色をしていた。すれ違うサラリーマンの眉間に、粘着質の灰色の靄がこびりついている。「今日は残業だ」と電話で告げる彼の言葉が、ドブ川の臭気を放って私の網膜を刺激したからだ。
私は天沢結。他人の嘘を「色彩」と「悪臭」として知覚してしまう神経の欠陥を抱えている。
路地裏から獣のような呻き声が聞こえた。
見れば、若い男がコンクリートの壁に頭を打ち付けている。足元には空になった銀色の錠剤シート。過剰摂取だ。記憶を鮮明にするはずの薬が、彼の脳髄を焼き、過去と現在の境界を溶かしている。男の口から泡と共に漏れ出るうわ言は、極彩色のゲロとなって視界を汚した。
「……俺の……じゃない……あいつが……」
視たくない。瞼を閉じても、視神経に焼き付いた嘘の蛍光色は消えない。
私は胃の底からせり上がる吐き気を呑み込み、逃げるように雑踏を掻き分けた。
向かう先は、港湾地区の古びた倉庫。
今朝、自ら命を絶ったとされる「色彩なき画家」のアトリエだ。
彼が死の直前に遺したという一枚の絵。そこに隠された真実を暴くことだけが、この色彩の暴力に満ちた世界で、私が正気を保つ唯一の鎮痛剤だった。
第二章 白の下の叫び
重い鉄扉を押し開けると、鼻をつくテレピン油の匂いの中に、微かな腐臭が混じっていた。
埃を被ったキャンバスや絵筆が散乱するアトリエの床。その一角に、踏みつけられたスケッチブックが落ちていた。
私はそれを拾い上げ、ページを捲る。手が止まった。
鉛筆で何度も、執拗なまでに描かれた男の横顔。その男は窓辺で微笑み、コーヒーを飲み、あるいは物憂げに遠くを見ている。
すべてのデッサンに、狂おしいほどの慈愛が滲んでいた。
見覚えのある横顔。かつて私が愛し、その名を呼んだ男――蓮だ。
画家は、蓮を知っていた。ただの知人ではない。この筆致は、恋情そのものだ。
視線を上げる。部屋の中央、イーゼルに架けられた50号のキャンバスが、異様な存在感を放っていた。
『純白の記憶』。
画材屋で売られているままの白ではない。何層にも、何十層にも塗り重ねられた、厚ぼったい白。
ズキン、とこめかみに激痛が走る。
その「白」から、噎せ返るような甘い腐敗臭が漂ってくる。これは嘘だ。それも、身を裂くような献身によって塗り固められた、悲痛な嘘の塊だ。
私は震える足でキャンバスに歩み寄った。
アプリもガジェットも必要ない。私の眼が、網膜が、その白の奥にある「熱」を捉えている。
目を凝らす。眼球から血が滲むような感覚。
白の絵具の下で、どす黒い赤が脈打っている。
画家の記憶。首に巻きつく手。薄れていく意識。
その手の甲には、三日月形の火傷の痕があった。
私がかつて、愛おしげに唇を寄せた、あの傷跡。
第三章 愛という名の盲点
呼吸が浅くなる。
画家は蓮に殺されたのだ。
だが、なぜ画家はこの光景を「白」で塗りつぶした? 犯人を告発する絵を残すこともできたはずだ。
足元のスケッチブックが視界に入る。
……そうか。画家は最期の瞬間まで、蓮を愛していたのだ。
首を絞められ、命が尽きようとするその刹那においてさえ、愛する男の罪を隠蔽するために、自らの血塗られた最期の記憶を、純白の絵具で塗り込めたのだ。
「馬鹿な人……」
涙が溢れた。それは画家への憐れみか、それとも同じ男を愛し、その本性を見抜けなかったかつての自分への嘲笑か。
あの頃、私の目に映る蓮の言葉は「無色」だった。
愛というフィルターは、私の眼さえも曇らせ、彼の嘘を透明な真実へと書き換えていたのだ。
「結。やはり、君はここに来たんだね」
背後から、鼓膜を撫でるような優しい声。
心臓が早鐘を打つ。私はゆっくりと振り返った。
入り口に、蓮が立っていた。片手には携行缶を持っている。油の臭いが強くなった。
彼は証拠隠滅に来たのだ。この絵を、建物ごと焼き払うために。
「奇遇だね、と言いたいところだけど。君のその眼なら、何かに気づくと思っていたよ」
蓮が微笑む。その瞬間、私の視界が歪んだ。
かつて「透明」だった彼の笑顔から、どす黒いタールのような粘液が溢れ出し、床へと滴り落ちていく。
欲望、保身、そして歪んだ自己陶酔。
吐き気がするほどの悪臭。これが、私が愛した男の正体。
最終章 色彩の牢獄
「彼を、楽にしてあげたかったんだ」
蓮が一歩、足を踏み出す。靴底が床の埃を軋ませる。
「彼は才能の枯渇に苦しんでいた。だから僕が、最高の題材を与えてやったんだよ。死という、完成をね」
口から吐き出される言葉の一つ一つが、赤黒い刃となって空間を切り裂く。
かつてこの男のどこを愛していたのか、今の私にはもう思い出せない。目の前にいるのは、饒舌な肉塊に過ぎない。
「……君にはわかるだろう? 君も、特別な眼を持っているんだから」
蓮が手を伸ばしてくる。その手の甲にある三日月の火傷。
私は後ずさりしなかった。代わりに、近くにあったパレットナイフを握りしめた。
彼を刺すためではない。
私はナイフを振り上げ、キャンバスの「白」に突き立てた。
「やめろ!」
蓮の叫びを無視し、私はナイフを横に薙ぐ。
厚く塗られた白の絵具が削げ落ち、その下から、どす黒い下地が露わになる。
抽象化された、しかし明確な殺意の形。苦悶の表情。そして、冷酷な殺人者の眼。
「見なさいよ」
私は削り取られた絵具の屑を、蓮の足元に投げつけた。
「これがあなたの色よ。画家が命がけで隠そうとした、あなたの醜さそのものよ」
蓮の顔から微笑が消え、子供のような狼狽が浮かぶ。
「違う……僕は、僕は美しく終わらせたはずだ……」
「美しくなんてない」
私は彼を真っ直ぐに見据えた。
視界いっぱいに広がる、彼の嘘、欺瞞、怯え。そのすべてが汚濁となって渦巻いている。
かつて、そのすべてを愛おしいと感じた私がいた。
でも、今はただ、汚い。
「蓮」
私の声は、自分でも驚くほど冷え切っていた。
「私、あなたのことが好きだった。……でも、今のあなたはただの『ノイズ』にしか見えない」
「結……?」
「消えて。私の視界から」
蓮が何かを叫ぼうと口を開いた瞬間、遠くからパトカーのサイレンが聞こえた。
彼は舌打ちをし、私を一瞥もせずに背を向け、闇の中へと逃げ去っていく。その背中からは、逃走という名の青ざめた恐怖が煙のように立ち上っていた。
私は一人、削り取られたキャンバスの前に立ち尽くす。
アトリエには静寂が戻ったが、私の眼はまだ痛みを訴えている。
愛が解けた世界は、あまりにも鮮明で、残酷だ。
窓から差し込む月光さえ、冷たい針のように網膜を刺す。
私はパレットナイフを落とした。乾いた音が、がらんどうの倉庫に響く。
二度と戻らない「無色」の安らぎを悼むように、私はゆっくりと瞼を閉じた。