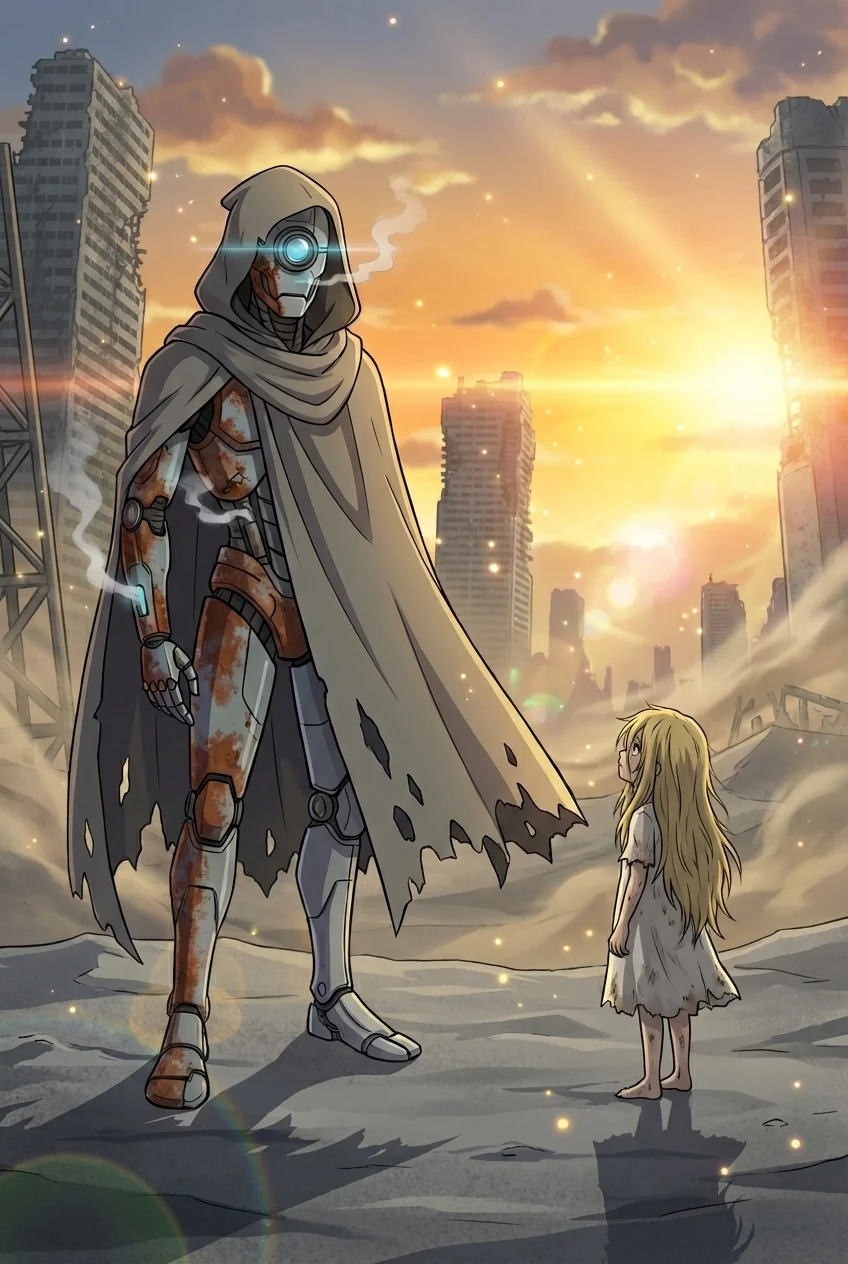第一章 錆びついた幻影
潮風には、いつも腐った紙の匂いが混じっている。
図書館の地下倉庫でカビが生えた古書を無理やり開いた時のような、あるいは、誰にも読まれないまま朽ちた手紙の束が放つ、湿った悲哀の臭気。
カイル・アストラムは、崩れ落ちそうな桟橋の先端で、革手袋をはめた右手を強く握りしめた。眼下に広がるのは、水ではない。青黒く粘つく、液状化した光の奔流だ。
波が岸壁を叩くたび、飛沫(しぶき)の代わりに無数の囁き声が巻き上がる。数百年前の恋人たちの睦言、戦場で散った兵士の断末魔、産声、すすり泣き。それらが渾然一体となって鼓膜を揺らす不協和音こそが、この『海』の正体だった。
カイルは、欄干に残された錆びた鉄の杭へ、恐る恐る指先を這わせた。
革手袋越しでも、その冷たさは伝わってくる。接触。その瞬間、視界が世界から切り離された。
ドォォォンッ!
腹の底に響く衝撃音。傾く視界。
――「総員退避! 積荷は捨てろ!」
脂汗の臭い。恐怖で収縮した男の瞳孔。軋む木材の悲鳴と、足元をすくう冷たい水の感触。肺が焼き切れるような息苦しさ。
(駄目だ、沈む――)
「……ぐ、ッ!」
カイルは弾かれたように手を引っ込めた。
現実に戻った彼の額には、脂汗が玉のように浮いている。呼吸は浅く、心臓は早鐘を打っていた。
今のは二百年前、この場所で座礁した貨物船の船長の『残滓(ざんし)』だ。死の瞬間の絶望が、鉄の分子の隙間にタールのようにへばりつき、カイルの神経を直接蹂躙したのだ。
「また、ハズレか」
荒い息を吐きながら、カイルは懐から真鍮製の円盤を取り出した。『忘れ去られた遺物の羅針盤』。
ガラスの蓋の下に封じ込められているのは、磁針ではない。生命の脈動のように揺らめく、一本の蒼白い光の筋だ。
羅針盤は、持ち主の魂が最も強く引かれる『重力』――すなわち、未練や執着の在り処を指し示す。
光の針は狂ったように震え、海の沖合、あの日家族が飲み込まれた一点を凝視し続けていた。
「父さん、母さん……」
カイルは羅針盤を握りしめた。真鍮の硬い縁が掌に食い込み、鋭い痛みを走らせる。
その痛みだけが、彼を現実に繋ぎ止める錨(いかり)だった。もしこの痛みがなければ、彼はとっくに、眼下の甘美な記憶の泥沼へ身を投じていただろう。
この海のどこかに眠るとされる『最後の知恵』。人類が滅びを回避するために残したという遺産。それを見つけ出せば、なぜ家族があのような理不尽な形で連れ去られたのか、その答えが得られるはずだ。
足元の板が軋む。海面から立ち上る燐光が、カイルの瞳の奥で揺れていた。
海が呼んでいる。お前の居場所は、冷たく残酷な『今』ではない。温かく完成された『過去』の中だと。
カイルは羅針盤をコートのポケットにねじ込むと、愛機である潜水艇『追憶号』のハッチを開けた。
鼻をつくオイルと錆の匂い。それは、腐った紙の匂いよりもずっと無骨で、そして生々しい現実の匂いだった。
「行こう。あの日へ」
ハッチが閉ざされる重金属音だけが、死んだような静寂の中に響き渡った。
第二章 深淵の甘い毒
潜航深度が増すごとに、窓の外の景色は色彩を失い、純粋な『概念』の濁流へと変わっていく。
船体を軋ませるのは水圧ではない。数億、数兆の人々が生きた証、その情報の質量だ。
船壁を通して、無数の人生がカイルの皮膚を撫でる。ある男の栄光、ある女の失意、子供の見た夢。油断すれば、カイルという個人の輪郭(アイデンティティ)など容易に溶解し、巨大なアーカイブの一滴として同化されてしまうだろう。
カイルは操縦桿を握る指が白くなるほど力を込めた。
「……負けるか」
歯を食いしばる。口の中に鉄錆のような血の味が広がった。
羅針盤の光が、かつてない強さで輝き始めている。海溝の裂け目、その深奥。光すら届かぬ闇の底へ。
突如、警報音すらなく、船内の照明が落ちた。
完全な暗闇。しかし、カイルの目には、あり得ない光景が映し出されていた。
パチパチ、と暖炉の薪が爆ぜる音。
鼻腔をくすぐる、クリームシチューの煮込まれる濃厚で温かい香り。
「え……?」
カイルは瞬きをした。操縦席にいるはずの彼は、いつの間にか柔らかい絨毯の上に座っていた。
目の前には、あの日失ったはずのリビングルーム。
父が新聞を読み、母がキッチンで振り返る。湯気越しに見えるその笑顔は、記憶の中のどの写真よりも鮮明で、優しかった。
「おかえりなさい、カイル。遅かったわね」
母の声。鼓膜ではなく、脳髄に直接染み渡るような響き。
「もう、探さなくていいのよ」
父が新聞を置き、穏やかに手招きをする。
「外の世界は寒かったろう。痛かったろう。ここにはもう、不安も恐怖もない。ただ、穏やかな時間だけがある」
カイルの手から力が抜けた。
そうだ、僕はこれを求めていたんだ。
冷たい鉄の感触も、腐った紙の匂いもいらない。ただ、この温かいシチューの香りに包まれて、永遠に眠ってしまいたい。
未来への不安、孤独な食事、毎晩の悪夢。それら全てをこの琥珀色の光の中に溶かしてしまえば、どんなに楽だろうか。
カイルはよろめくように立ち上がり、両親へと手を伸ばした。
指先が、母の温かい頬に触れようとした、その時。
ズキリ。
ポケットの中で、何かが熱を帯びた。
羅針盤だ。
真鍮の熱が、火傷しそうなほどの痛みを太腿に伝える。
『――痛い』
その感覚が、カイルの意識に突き刺さった。
痛み。それは不快なものだ。けれど、痛みこそが、肉体が生きている証拠ではなかったか?
母の笑顔には、皺一つない。完璧すぎる。昨日も、今日も、明日も、この笑顔は永遠に変わらないのだろう。
だが、それは『生きている』と言えるのか?
「……違う」
カイルは呻いた。目の前の甘美な光景に、亀裂が走る。
「僕は、温かいスープが飲みたいんじゃない。傷ついても、血を流しても……自分で選んだ道を歩きたいんだ!」
カイルは叫び、見えない幻影を振り払った。
ガツンッ!!
激しい衝撃と共に、リビングルームの幻影がガラスのように砕け散る。
戻ってきたのは、狭く、寒く、オイル臭いコクピットの闇。
そして窓の外には、海溝の底に突き刺さった巨大な白亜の遺跡が、幽霊のように浮かび上がっていた。
「はぁ、はぁ、はぁ……」
カイルは荒い息を繰り返しながら、震える手で汗を拭った。
甘い毒は、まだ血管の中に残っている。けれど、彼は確かに、その誘惑を拒絶したのだ。
遺跡の扉は、物理的な鍵ではなく、強い『意志』の波長に反応して開く。
カイルは羅針盤を掲げた。亡霊たちの嘆きを振り切り、ただ一点の真実を求める意志。
「開けッ!」
叫びと共に、重厚な石の扉が音もなくスライドする。
そこから溢れ出したのは、海水ではなく、肌を刺すような、無菌室の静寂だった。
第三章 静止した永遠
遺跡の最深部は、海の中とは思えないほど乾燥した空気に満ちていた。
腐った紙の匂いもしない。潮の香りもしない。そこにあるのは、完全に濾過された『無臭』の世界。
ドーム状の広大な空間の中央に、巨大な水晶体が浮遊している。
それは心臓の鼓動のようにゆっくりと明滅し、周囲の壁面には、星空のように無数の光の点が瞬いていた。
「これが……『最後の知恵』」
カイルは震える足で祭壇へと近づく。
水晶体から放たれる光を浴びた瞬間、言葉による説明など不要だった。
膨大なイメージが、雪崩のようにカイルの脳内へ流れ込んでくる。
――世界の流動を止めること。
――すべての瞬間、すべての記憶を、劣化しない完全な『標本』として保存すること。
理解した。肌が粟立つほどの恐怖と共に。
このシステムは、世界を救うためのものではなかった。
悲しみや喪失を恐れるあまり、過ぎ去る時間を永遠にホルマリン漬けにするための、巨大な墓標だったのだ。
そして、カイルの両親もまた、このシステムの一部として取り込まれていた。
カイルの視界が白く染まる。
水晶体が、彼に見せるべき『幸福』を提示したのだ。
嵐の海ではない。転覆する船でもない。
そこには、永遠の日だまりの中で微笑む両親の姿があった。
彼らは老いることもなく、病むこともなく、死ぬこともない。繰り返される完璧な午後。
水晶のさざめきが、カイルの脳髄を撫でる。
『こっちへおいで、カイル。ここでは誰も失われない。失敗もしない。傷つくこともない。ただ、美しい記憶だけが永遠に巡る楽園だ』
カイルの足が止まった。
目の前には、喉から手が出るほど欲しかった両親がいる。
手を伸ばせば届く。この水晶の中に飛び込めば、もう二度と、一人で震える夜を過ごさなくていい。
羅針盤を見る。針はピタリと止まり、水晶体を指していた。
ここが、旅の終着点だと告げている。
「父さん……母さん……」
カイルはふらふらと水晶体に歩み寄り、その表面に両手をついた。
冷たく、硬質な感触。
その向こう側で、両親が微笑みかけてくる。
「一緒になろう。永遠に」
カイルは頷きかけた。涙が頬を伝う。ここには痛みがない。苦しみもない。それがどんなに素晴らしいことか。
だが。
水晶越しに見る母の手には、あかぎれがなかった。
父の顔には、苦労して刻まれた笑い皺がなかった。
綺麗すぎる。つるりとしていて、引っかかりがない。
ふと、カイルは桟橋で感じた、あの不快な腐臭を思い出した。
そして、潜水艇の中で感じた孤独な寒さを。
羅針盤を握りしめた時に掌に食い込んだ、鋭い痛みを。
「……ここでは、腹は減らないのか?」
カイルの問いに、水晶の中の両親はただ微笑むだけだ。
「新しい本を読んでワクワクしたり、足の小指をぶつけて悶絶したり、不味いコーヒーに顔をしかめたり……そういうことは、ないのか?」
答えはない。ただ、肯定的な沈黙があるだけだ。
変化がないということは、成長もしないということだ。
それは生きているとは言わない。ただ、綺麗に装飾された死体だ。
「違う……」
カイルの声が震えた。
「こんなものは、僕が愛した家族じゃない。彼らはもっと、汗臭くて、必死で、不格好で……温かかったんだ!」
カイルは水晶体から手を引き剥がした。
皮膚が剥がれるような抵抗感。楽園が、彼を逃がすまいと絡みついてくる。
「僕は、永遠の安らぎなんていらない! 泥にまみれても、傷だらけになっても……明日へ進む痛みが欲しいんだ!」
カイルは叫んだ。それは、彼自身の魂からの慟哭だった。
第四章 流転する明日へ
カイルの拒絶に呼応して、水晶体の色が穏やかな青から、どす黒い赤へと変色した。
空間全体が振動し、無数の光の点が警告色に染まる。
『愚かな。外の世界には苦しみしかない。お前の記憶も、いずれ海に溶けて消えるだろう。それでもいいのか?』
直接脳内に響く声は、もはや甘い誘惑ではなく、冷徹な宣告だった。
「消えるからこそ、美しいんだ!」
カイルは懐から羅針盤を取り出し、高く掲げた。
「過去は変えられない。でも、未来はまだ決まっていない!」
その時、異変が起きた。
これまで『過去の重力(もっとも強い未練)』だけを指し示していた羅針盤の針が、狂ったように回転を始めたのだ。
カイルが希求したのは、特定の過去ではない。
まだ存在せず、質量も持たず、どこにあるかもわからない『明日』という概念。
「示せ、羅針盤! 過去ではなく、まだ見ぬ地平を!」
『エラー。対象座標、存在せず。計算不能。計算不能』
水晶体が悲鳴を上げる。
羅針盤は、『最も重い記憶』を指すシステムだ。だがカイルは今、質量ゼロの『未来』に、命懸けの重みを乗せた。
その論理的矛盾(パラドックス)が、システムの中枢に致命的なバグを引き起こしたのだ。
羅針盤のガラスが熱でひび割れ、内部から眩い白光が溢れ出す。
それはもはや遺物を探す道具ではない。停滞した時間を切り裂く、変革の刃だった。
『やめろ! 統合が崩れる! 世界が再び、死と喪失に満ちてしまう!』
「それでいい。それが、生きるってことだ!」
カイルは涙を流しながら、白熱する羅針盤を振りかぶった。
「さよなら、父さん。さよなら、母さん。……愛していたよ」
それは、二度目の、そして本当の別れの言葉。
彼は迷いなく、羅針盤を水晶体の中心へと叩きつけた。
ガギィィィンッ!
世界が割れる音がした。
水晶体に蜘蛛の巣状の亀裂が走り、次の瞬間、爆発的な光と共に砕け散った。
奔流。
溢れ出したのは、光ではない。止まっていた『時間』だ。
保存されていた数億の記憶たちが、一斉に解き放たれ、奔流となって渦巻く。
その中で、カイルは見た。
両親の姿が、穏やかな光の粒子となって崩れていくのを。
水晶の中の作り物の笑顔ではない。最期に見せた、心配そうにカイルを見つめる、人間らしい表情。
「……あぁ」
カイルは手を伸ばした。指先が光の粒子に触れる。
温かかった。そして、瞬く間に指の間をすり抜けて消えていった。
彼らは永遠の檻から解放され、本来あるべき『死』へと、大いなる海へと還っていく。
胸が張り裂けるような喪失感がカイルを襲う。
だが同時に、背中に翼が生えたような、不思議な軽さを感じていた。
足元の床が崩れ、海水が雪崩れ込んでくる。
遺跡が崩壊し、滞っていた『記憶の海』が、再び命を育むための循環を始めていた。
最終章 水平線の向こう
海上は、嵐が過ぎ去った後のような静けさに包まれていた。
カイルは『追憶号』のハッチを押し開け、よろめきながら甲板へと這い出した。
眩しい。
空が青い。これほどまでに澄んだ青空を見たのは、いつ以来だろうか。
そして、海の色も変わっていた。
あの粘りつくような光の渦は消え失せ、透き通った水が太陽の光を反射してきらめいている。
風が吹いた。
「……くさいな」
カイルは苦笑した。潮風には、海藻の腐った匂いと、魚の生臭さが混じっていた。
腐った紙のような陰湿な匂いではない。それは生命が生まれ、死に、そしてまた生まれるサイクルの匂い――『生きている世界』の匂いだった。
「……思い出せない」
ふと、カイルは呟いた。
両親の顔を思い出そうとした。しかし、かつて写真のように鮮明だったその映像は、霧がかかったようにぼやけていた。
声のトーンも、手の温もりも、明確な感覚としては失われていた。
彼がシステムを破壊し、記憶を海へ還した代償だ。彼自身の中にあった『固着した過去』もまた、流れ去ってしまったのだ。
喪失感はある。胸にぽっかりと穴が開いたようだ。
けれど、その穴を通る風は、驚くほど心地よかった。
カイルはポケットから、砕け散った羅針盤の残骸を取り出した。真鍮の枠だけが残り、中の光はもうない。ただのガラクタだ。
彼はそれを、大きく振りかぶって海へと投げ入れた。
ポチャン、と小さな水しぶきを上げて、それは青の中へと沈んでいった。
過去への道標は、もういらない。
「行くか」
カイルは舵を取る。
行き先は決まっていない。地図もない。
彼は顔を上げ、果てしなく続く水平線を見つめた。
そこには、まだ誰も見たことのない、不完全で、残酷で、トラブルに満ちていて――そして何よりも自由な未来が広がっていた。
エンジンが唸りを上げ、船が波を切り裂いて進み始める。
白い航跡だけが、彼が確かに今を生きている証として、海面に刻まれていった。