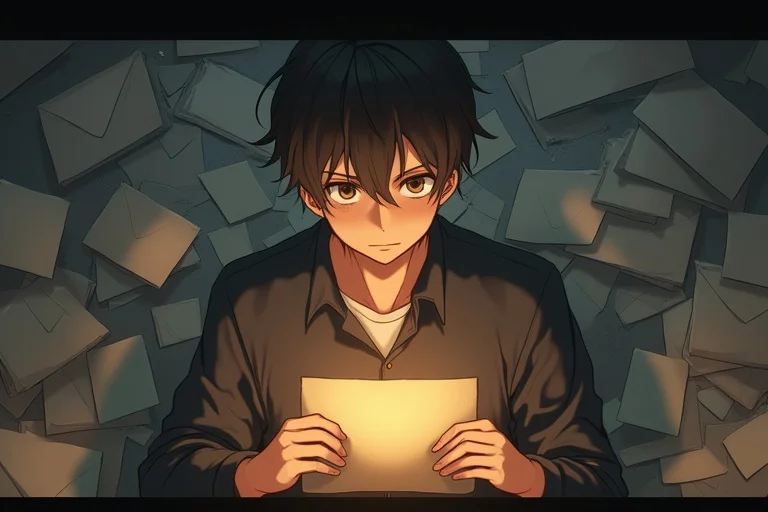第一章 琥珀色の雨
雨は、古い鉄の味がした。
崩れ落ちた天井から、灰色の滴が絶え間なく降り注ぐ。
廃教会の祭壇。
その瓦礫の隙間に、淡い燐光がこびりついている。
イザヤは泥に塗れたブーツを鳴らし、その光の前で足を止めた。
ずぶ濡れのコートが、鉛のように重い。
目の前の光が、チリチリと音を立てて明滅している。
まるで、助けを求める子供の瞳のように。
イザヤは息を殺し、ひび割れた指先を伸ばした。
躊躇いは一瞬。
光に触れた刹那、脳髄を焼き切るような衝撃が走る。
「ぐっ……!」
視界が歪む。
教会の風景が弾け飛び、見知らぬ戦場の悪臭が鼻腔を突き刺した。
(熱い、腹が熱い、誰か――母さん)
他人の絶叫が、濁流となってイザヤの神経を侵食する。
焼けた肉の匂い。硝煙。置き去りにされた絶望。
こみ上げる吐き気を、奥歯を噛み砕くほどの力でねじ伏せる。
同調しろ。
飲み込まれるな。
この痛みは、俺のものじゃない。
イザヤは脂汗を垂らしながら、見えない何かの手を握りしめるように、光を両手で包み込んだ。
皮膚が焦げるような幻痛が走る。
「……聞こえるか」
呻くように、イザヤは喉を震わせた。
「アンナは無事だ。北のシェルターで、お前の帰りを待っている」
嘘ではない。
この教会へ辿り着く道すがら、イザヤはその名を持つ老婆の最期を看取っていた。
数十年越しの伝言。
光が、大きく脈打った。
こびりついた執着が剥がれ落ちる感覚。
琥珀色の粒子がイザヤの指の間から溢れ出し、螺旋を描いて雨空へと昇っていく。
「還れ」
短く告げる。
雨音に混じり、ありがとう、という微かな残響が鼓膜を撫でた。
イザヤはその場に膝をつき、荒い息を吐いた。
胃液が喉までせり上がる。
他人の人生を看取るたび、自分の中身が削げ落ちていくようだ。
震える手で、懐から古びた銀時計を取り出す。
針は「XII」を指したまま、凍りついたように動かない。
ガラスに指を這わせる。
何も思い出せない。
自分が何者で、なぜこの「処理」を続けているのかさえも。
ただ、胸の奥にある空洞だけが、風を切るように鳴いている。
ふと、背筋に冷たい視線を感じた。
入り口のアーチの下。
いつの間にか、少女が立っていた。
透き通るような白いワンピース。
瓦礫の上を裸足で踏みしめ、表情のない顔でイザヤを見つめている。
「……また、君か」
少女は答えない。
ただ、その華奢な指先を、荒野の果て――西の空へと向ける。
まただ。
行く先々で現れる、この亡霊のような幻影。
彼女を見るたび、イザヤの胸は焼け付くように痛む。
愛おしさと、自分の首を絞めたくなるような罪悪感が、同時に喉元へこみ上げるのだ。
「あそこに、何がある」
少女は目を細め、悲しげに微笑んだだけだった。
次の瞬間、彼女の姿は霧のように揺らぎ、雨の中に溶けて消えた。
イザヤは舌打ちをし、泥だらけの身体を起こした。
西へ。
止まった時計を握りしめると、冷たい金属が掌に食い込んだ。
第二章 針の止まった刻
旅路は、緩やかな自殺に似ていた。
西へ向かうほどに、大気中の「濃度」が増していく。
地表を漂う無数の光。
行き場を失った死者たちの嘆きが、足元にまとわりつく。
三日目の夜、イザヤは廃墟のビルの陰でうずくまっていた。
身体が重い。
食事をとっていないのに、空腹を感じない。
喉が渇いているはずなのに、水筒の水を見ると吐き気がする。
「……おかしいな」
自分の手を見る。
傷だらけだが、血の色が薄い気がした。
まるで、生きている実感が希薄になっていくようだ。
傍らで、焚き火が爆ぜた。
炎の向こうに、また彼女が座っている。
膝を抱え、じっとイザヤを見ている。
「なぁ」
イザヤは掠れた声で呼びかけた。
「君は、俺を恨んでいるのか?」
答えはない。
だが、イザヤには分かっていた。
この胸を焦がす罪悪感の正体。
自分はきっと、過去に何か取り返しのつかない過ちを犯したのだ。
この少女に対して。
イザヤは懐中時計を取り出し、焚き火にかざした。
裏蓋に刻まれた奇妙な紋章。
複雑な幾何学模様の中に、微かな窪みがある。
そこへ、道中で拾った青い石――あるレムナントの核だったもの――を嵌め込んでみた。
カチリ。
音がして、裏蓋がスライドする。
現れたのは、小さな羅針盤だった。
針は北を指さず、頑なに「西」のある一点を示して震えている。
「……地図だったのか」
導かれている。
あるいは、招かれている。
イザヤは羅針盤が示す方角と、少女の視線が重なるのを見た。
そこにあるのは、かつて「首都」と呼ばれた爆心地だ。
(行けば、終わるのか?)
恐怖があった。
真実を知ることで、辛うじて保っている自分の輪郭が崩壊してしまうのではないかという恐怖。
だが、留まることは許されない。
イザヤの肉体は、日に日に「人間」としての機能を失いつつあった。
眠りは浅く、心臓の鼓動は不気味なほど遅い。
「行かなくちゃ」
誰にともなく呟き、イザヤは立ち上がった。
少女の幻影が、ふわりと立ち上がり、闇の奥へと手招きする。
その背中は、泣いているように見えた。
第三章 終わりの場所
辿り着いたのは、世界の墓場だった。
ねじ曲がった鉄骨。
地層のように積み重なったコンクリートの山。
かつて首都だった場所は、巨大なクレーターと化している。
その中心部。
羅針盤の針が狂ったように回転し、ピタリと止まった場所。
そこには、太陽を直視したような、強烈な光の渦があった。
レムナントだ。
だが、これまで見てきたものとは桁が違う。
数千、数万の感情が混ざり合ったような濁流ではない。
たった一つの、純粋で、強大な「願い」の塊。
イザヤは足を引きずり、光の淵へ踏み入った。
皮膚が粟立つ。
光の中心に、二つの影が焼き付いている。
過去の残像。
崩落した地下街の天井を支えようとして、潰れていく瓦礫の映像。
「……あ?」
イザヤの口から、間の抜けた声が漏れた。
瓦礫の下敷きになっている男。
血まみれで、腹部を鉄筋に貫かれている男。
それは、自分だった。
今の自分と同じ顔、同じコートを着た「死体」だ。
そして、その傍らで泣き叫んでいるのは、あの少女。
「嘘だ」
イザヤは後ずさる。
足がもつれ、瓦礫に無様に転がった。
「俺は、生きてる。息をしてる。心臓も……」
胸に手を当てる。
ドクン、ドクンと遅い音がする。
だが、目の前の光景は、絶対的な現実として網膜に焼き付いて離れない。
フラッシュバックが、脳天を殴りつけた。
――激痛。鉄の味。
――『イザヤ! 目を開けて!』
――彼女の声。温かい手。
視界が真っ赤に染まる。
崩落の瞬間、俺は彼女を突き飛ばした。
それが最期のはずだった。
なのに、なぜ彼女が泣いている?
なぜ、彼女の身体が透けていく?
記憶の中の少女が、瀕死のイザヤに覆いかぶさる。
彼女の輪郭が光となって崩れ、イザヤの傷口へと流れ込んでいく。
『嫌よ。あなたがいない世界なんて』
『私の時間をあげる。私の全部をあげるから――』
『生きて』
光の奔流。
少女の命そのものが、死にかけたイザヤの細胞を無理やり繋ぎ止め、心臓を再び動かす。
禁忌の蘇生。
「う、うわあああああああああ!」
イザヤは地面をのたうち回った。
胃の中身をすべて吐き出した。
出てきたのは胃液ではなく、どす黒い汚泥のような液体だけだった。
「ふざけるな! やめろ!」
地面を拳で叩きつける。
爪が割れ、血が滲む。
思い出した。全部、思い出した。
自分が生きている理由。
それは、彼女が自らの魂を燃料にして、俺という抜け殻を動かしているからだ。
俺は人間じゃない。
彼女の犠牲の上に成り立つ、醜い継ぎ接ぎの怪物だ。
「なんで……なんでだよ!」
イザヤは泣きわめきながら、光の中に立つ現在の彼女――幻影を見上げた。
彼女はもう、消えかけていた。
この場所へ導いたことで、残った力の全てを使い果たしたのだ。
「俺なんか生かすために、君が消えるなんて……そんなの間違ってる!」
「いいえ」
凛とした声が響いた。
幻影の彼女が、イザヤの目の前に跪く。
その手は、イザヤの泥だらけの頬に触れた。
冷たいはずの幻の手が、焼けるように熱い。
「間違ってない。私が選んだの」
「俺は死ぬべきだったんだ! 君が生きるべきだった!」
「それでも、私はあなたに生きていて欲しかった」
イザヤは首を振った。
拒絶したかった。
こんな理不尽な愛を受け入れたくなかった。
だが、彼女の瞳があまりにも真っ直ぐで、あまりにも綺麗で。
イザヤの喉から、嗚咽が漏れた。
第四章 動き出す未来
「見て」
少女が、イザヤの胸元に転がった懐中時計を指差す。
「あなたの旅は、無意味じゃなかった」
イザヤの脳裏に、これまで解放してきた光たちの顔が浮かぶ。
戦場の兵士。母親。名もなき浮浪児。
イザヤが触れ、痛み分け、空へ還した魂たち。
「あなたは、私だけのものじゃなくなった。あなたが背負った痛みの分だけ、世界は少しだけ軽くなったの」
少女はイザヤの胸、動かない心臓があった場所に手を重ねた。
「これが私の願い。ただ生きるんじゃなく、誰かの光になって」
イザヤの目から、涙が溢れて止まらなかった。
自分を責めることで、彼女の犠牲を「罪」にしていた。
だが、それは彼女の覚悟への冒涜だったのだ。
彼女は、俺に罰を与えたんじゃない。
灯火を託したのだ。
「……分かった」
イザヤは、彼女の透き通る手の上に、自分の手を重ねた。
強く、握り返す。
「背負うよ。君の命も、願いも。この身が朽ち果てるまで、全部抱えていく」
覚悟を口にした瞬間。
止まっていた空気が震えた。
地面に落ちていた懐中時計が、激しく共鳴音を上げる。
錆びついた銀の塗装がボロボロと剥がれ落ち、その下から、朝日のような黄金の輝きが露わになった。
カチリ。チクタク、チクタク。
秒針が動き出す。
過去に縛られていた時間が、未来へ向かって流れ出した音。
「ありがとう、イザヤ」
少女の輪郭が、金色の粒子となって弾けた。
もう、悲しげな幻影ではない。
全てを肯定し、包み込むような光の渦。
「愛してる。ずっと、あなたの中で鼓動し続けるから」
「ああ……俺もだ」
イザヤは立ち上がり、降り注ぐ光の粒子を全身で受け止めた。
光はイザヤの皮膚に吸い込まれ、血液となり、熱となる。
ドクン。
ドクン。
胸の奥で、力強い音が響いた。
それは借り物の命の音ではない。
二つの魂が溶け合い、新たに刻み始めた「生」のリズムだ。
光が消え、風が止んだ。
頭上を覆っていた鉛色の雲が割れ、突き抜けるような青空が覗く。
イザヤは、黄金に輝く懐中時計を拾い上げた。
針は正確に、新たな時刻を刻んでいる。
もう、痛みから目を逸らさない。
空洞だった胸は、確かな熱で満たされている。
彼はコートの埃を払い、前を向いた。
もはや、死に場所を探す亡霊ではない。
記憶を繋ぎ、終わりを始まりへと変える「調律者」。
「行こう」
イザヤは時計を胸ポケットにしまい、ブーツの踵を返した。
その足取りは重くとも、迷いはなかった。
瓦礫の荒野の先に、微かな緑が芽吹いているのが見えた。