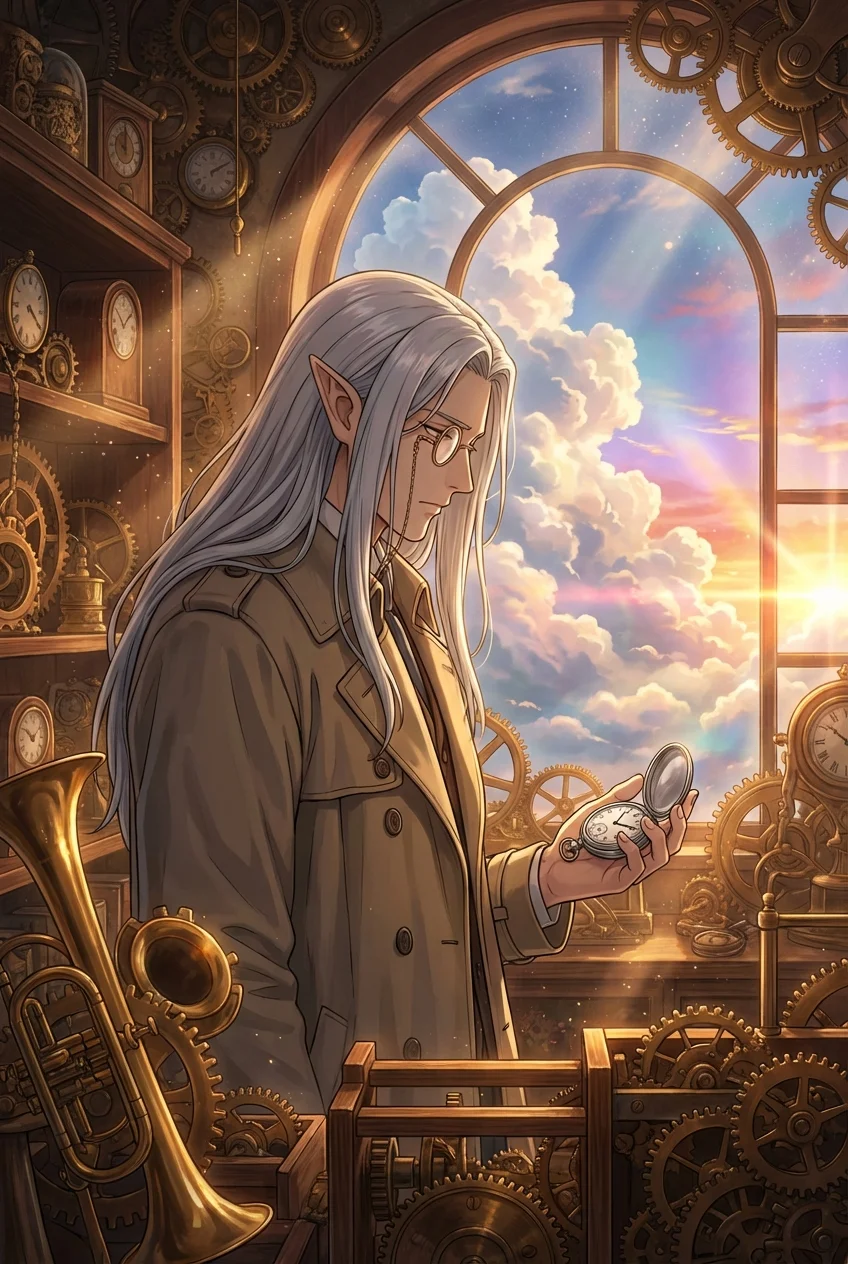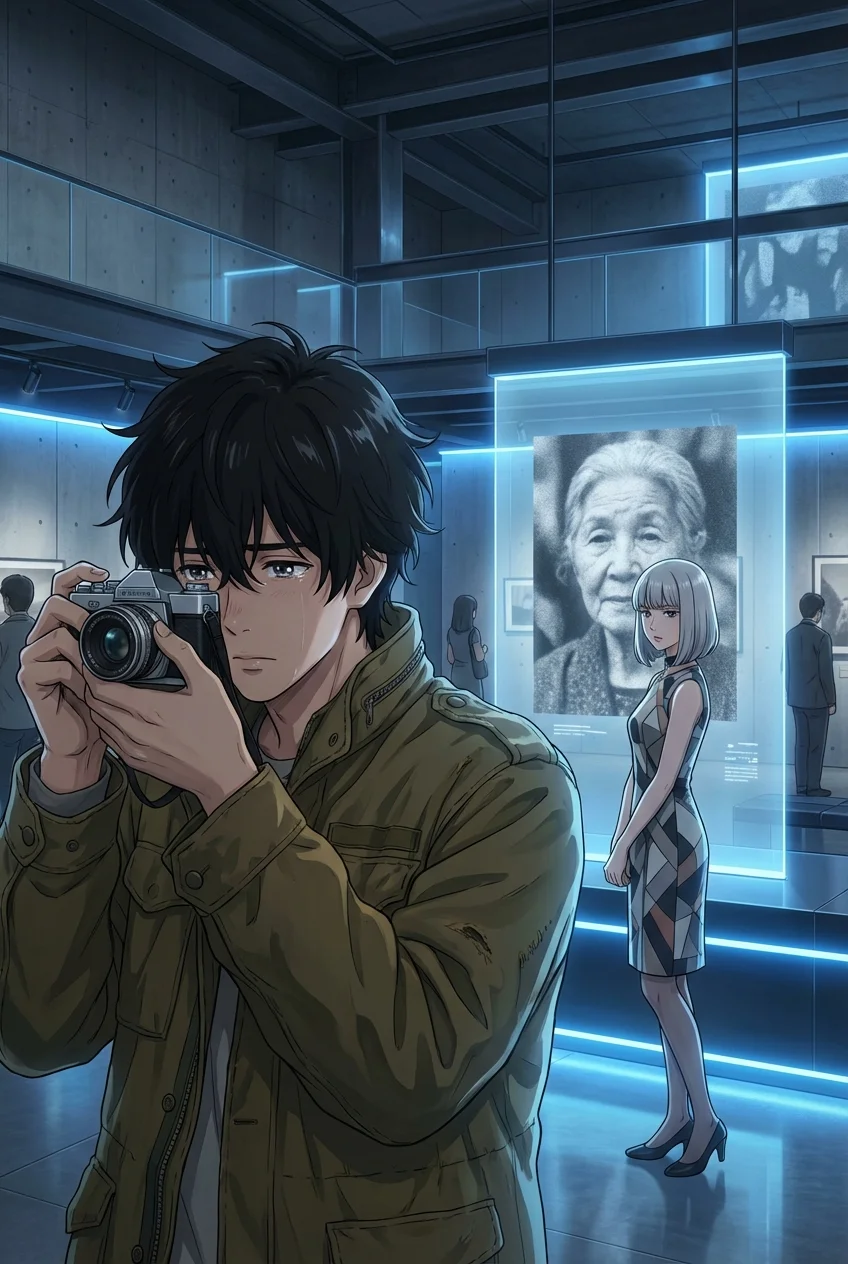第一章 深淵のノイズ
「聞こえるか、カイト。深度一万、予定通りの地獄だ」
ノイズ混じりの通信が、鼓膜をやすりのように削る。
俺は眉間の皺を深くし、コンソールのボリュームを最小まで絞った。
「……ああ。五月蠅いくらいにな」
「相変わらず愛想がねえな。その『耳』、少しは役に立ってるのか?」
「エンジンの第三シリンダー、0.02秒のズレがある。爆発したくなければ回転数を落とせ」
「マジかよ」
通信の向こうで、相棒のバナージが息を呑む気配がした。
俺、カイト・シラナミには、機械の『悲鳴』が聞こえる。
比喩ではない。金属の軋み、回路の過電流、構造上の欠陥。それらが不協和音となって、脳髄に直接響いてくるのだ。
今の俺を包んでいるのは、全長八メートルの有人潜水機『トリトン』。分厚いチタン合金の殻一枚隔てた外側は、一千気圧の水圧が支配するマリアナ海溝の底だ。
だが、俺にとっての地獄は水圧じゃない。
音だ。
潜水母艦からのソナー音、推進器の振動、そして何より――この深海から響いてくる、正体不明の『歌』。
「ターゲットまであと五百メートル。……おい、見ろよアレ」
バナージの上ずった声。
俺はフロントモニターに目を向けた。
暗黒の海。本来なら、マリンスノーだけが舞う死の世界。
だが、そこに『光』があった。
青白い燐光ではない。幾何学的な、あまりにも直線的で鋭利な光のライン。
海底の泥を割り、巨大な構造物がせり出している。
「遺跡……いや、都市か?」
「月面基地開発の連中が血眼になって探してた『オリジン』が、まさか地球の底にあるとはな」
世界は今、月面開発ラッシュに沸いている。
月の裏側で発見された超古代文明の痕跡。そのエネルギー源を巡り、国家と企業が争っている最中だ。
だが、俺たちが雇われた弱小サルベージ会社『アビス・ワークス』が入手した情報は違っていた。
『月にあるのは受信機に過ぎない。送信機は、地球の最深部にある』
馬鹿げた話だ。
だが、目の前の光景は、その馬鹿げた仮説を現実として突きつけていた。
俺の耳に響く不協和音が、かつてないほどの高音で叫び声を上げ始める。
「……来るぞ、バナージ。衝撃に備えろ」
「は? 何が――」
警告と同時に、ソナーが絶叫した。
影が走る。
上空――いや、直上の海水面方向から、三機の黒い機体が急降下してきた。
第二章 略奪者たち
「所属不明機! いや、あのエンブレム……『ルナ・ダイナミクス』か!」
バナージが叫ぶ。
月面開発最大手の私兵部隊。ハイエナどもめ、嗅ぎつけるのが早すぎる。
敵機は流線型の無人ドローンだ。躊躇なく魚雷発射管を開くのが見えた。
「カイト、逃げるぞ! 勝てるわけがねえ!」
「無理だ。後ろに回られた」
ドゥン、と鈍い音が海水を震わせる。
スーパーキャビテーション魚雷。水中の音速を超える殺意の塊。
俺は操縦桿を乱暴に倒した。
『トリトン』のバーニアが悲鳴を上げ、巨体が横滑りする。
数メートル先を、泡の軌跡が切り裂いていった。
「避けただと!?」
「音が聞こえるんだよ。奴らのスクリュー、羽が一枚欠けてる」
俺は目を閉じた。
視覚情報はいらない。必要なのは音だ。
水流の変化、敵機のモーター音の変調、魚雷の信管が作動する微かなクリック音。
オーケストラの指揮者のように、戦場のすべてが『音』として配置される。
「バナージ、デコイ射出! そのままクラッシュダイブだ!」
「死ぬ気か! これ以上潜ったら圧壊深度だぞ!」
「遺跡の『入り口』が開いてる。あそこなら水圧制御が効いてるはずだ!」
「根拠は!?」
「あの中から聞こえる音が、そう『歌って』いる!」
俺はアクセルをベタ踏みした。
警告アラートが赤く点滅し、船体がミシミシと音を立てる。
背後で爆炎が上がった。デコイが身代わりになったのだ。
遺跡の巨大なゲート。
青い光の膜が張られたその場所へ、俺たちは鉄塊ごとのめり込んだ。
衝撃。
そして、静寂。
第三章 偽りの空
目を開けると、そこは空気のある空間だった。
計器類が正常に戻る。外部マイクが拾う音は、風の音。
「……おい、嘘だろ」
バナージの震える声。
俺はキャノピー越しに外を見た。
そこは、広大なドーム状の空間だった。
そして、頭上には。
「月……?」
満月が浮かんでいた。
いや、違う。
俺たちが知っている月よりも、遥かに巨大で、そして表面のクレーター配置が『逆』だ。
「ここは……月の裏側と同じ景色か?」
俺は機体を降りた。
足元の感触は、乾いた砂。レゴリス。
一万メートルの深海に、月面があった。
「カイト、あれを見ろ。中心にある塔だ」
ドームの中央に、黒曜石のような塔が聳え立っている。
俺の耳に響く『歌』の発生源は、間違いなくあそこだ。
俺たちは塔へ向かった。
不思議なことに、ルナ・ダイナミクスの追手は入ってこない。あの光の膜を越えられなかったのか。
塔の内部は、静謐そのものだった。
埃ひとつない廊下。壁面に走る光の脈動。
最深部の広間。
そこに鎮座していたのは、巨大な球体だった。
空中に浮遊し、複雑なホログラムを周囲に投影している。
「これが……オーバーテクノロジーの核心……『セレーネ・コア』」
バナージが夢遊病者のように手を伸ばす。
「触るな!」
俺は叫んだ。
音が変わったのだ。
美しい旋律だった『歌』が、突如として不吉な警告音へと変貌した。
「え?」
バナージの指先が、コンソールに触れる。
瞬間。
ホログラムが展開した。
それは、地球と、その周りを回る月の映像。
だが、映像の中の『月』には、無数の鎖が絡みついていた。
『――拘束シールド、解除』
無機質な合成音声が脳内に直接響く。
「拘束……?」
俺は理解した。
この遺跡は、エネルギープラントでも、兵器工場でもない。
第四章 檻の中の獣
「バナージ、今すぐ離れろ! それはスイッチじゃない、鍵だ!」
「何言ってんだ、カイト。見ろよ、すげえエネルギー数値だ。これを持ち帰れば億万長者……」
ズズズズズ……。
地鳴りが響く。
いや、頭上の『偽りの月』がひび割れていく。
「空が……割れる?」
ドームの天井だと思っていた映像が、ノイズと共に消失した。
その向こうに見えたのは、岩盤ではない。
何もなかった。
ただ、圧倒的な『質量』を感じさせる、漆黒の何か。
俺の『耳』が、かつてない悲鳴を上げた。
それは機械音ではない。
生物の、鼓動だ。
ドクン、ドクン、ドクン。
地球の核(コア)だと思っていた場所から、その音は響いている。
「おい、嘘だろ……」
バナージが腰を抜かす。
ホログラムの表示が変わる。
『Project MOON : Phase Final - Containment Breach (封印決壊)』
「月は……」
俺は乾いた唇を舐めた。
「あの空に浮かんでいる月は、ただの衛星じゃなかった」
俺たちが夜空に見上げていた月。
それは、地球という惑星そのものを封じ込めるための『蓋』だったのだ。
そして、この深海遺跡は、その蓋を内側からロックするためのアンカー。
「俺たちは、開けちまったんだ。パンドラの箱を」
第五章 星の産声
警告音が鳴り止まない。
トリトンの通信機が生きていた。地上のニュース音声が、雑音混じりに飛び込んでくる。
『緊急報道です! 月が……月が崩壊しています!』
『重力異常発生! 潮位が上昇しています!』
俺はトリトンのコクピットに駆け戻った。
「乗れ、バナージ! 脱出するぞ!」
「どこへ!? 月が落ちてくるんだぞ!?」
「月は落ちてこない。剥がれ落ちるだけだ」
俺はエンジンを点火した。
この遺跡全体が、浮上を始めている。
「どこへ行く気だ、カイト!」
「特等席へ。新しい世界の夜明けを見るんだ」
トリトンは遺跡の崩壊と共に、上昇流に乗った。
光の膜が消え、海水が雪崩れ込んでくる。
だが、それよりも早く、俺たちは海面へと射出された。
水面を突き破り、空へ。
そこにあったのは、見慣れた夜空ではなかった。
頭上を覆っていた『月』という名の幻影の殻が、砕け散り、剥がれ落ちていく。
その隙間から覗いていたのは、無数の星々。
そして、今まで月によって隠蔽されていた、巨大な構造物。
地球を取り囲むように配置された、銀色のリング。
「なんだ……あれは……」
「管理システムだ。俺たちは、ずっとあいつらに飼われていたんだよ」
俺の耳に、新しい音が届いた。
それは、地球外からの通信音。
あるいは、ずっと遮断されていた『外の世界』からの呼び声。
「五月蠅くなりそうだ」
俺は呟き、しかし口元を歪めて笑った。
この退屈で閉塞した世界が終わる音なら、悪くない。
砕け散る月の破片が、流星となって海へと降り注ぐ。
その光の中で、俺は初めて、世界を美しいと思った。