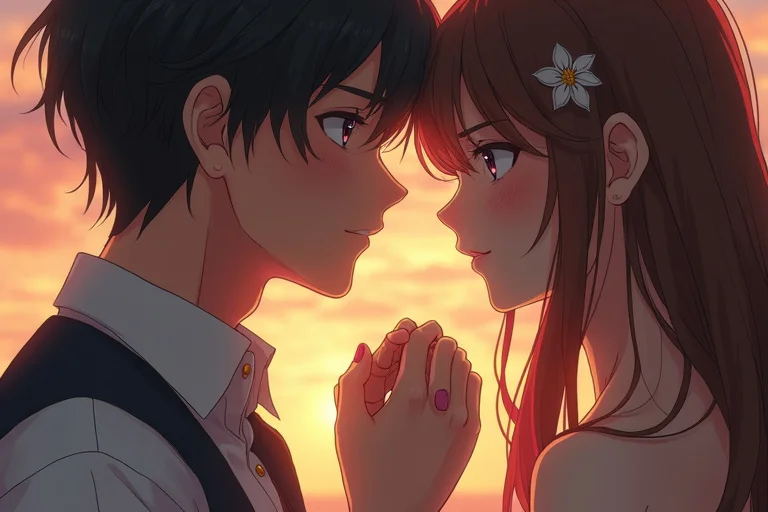第一章 軋む空
「聞こえるか? この音」
カイトは錆びついたスパナを弄びながら、天井を見上げた。
分厚いチタン合金の向こう側で、何億トンもの硫酸の雨が叩きつけている。
「何も聞こえねえよ。気圧調整弁のノイズだろ」
相棒のレノが、端末から目を離さずに答える。
安っぽい合成たばこの煙が、狭い整備通路に充満していた。
「違う。もっと高い音だ。……悲鳴みたいな」
カイトには聞こえていた。
この巨大な浮遊都市『アーク・セブン』の骨組みが、限界を超えて軋む音が。
金星の上層大気、高度50キロメートル。
人類が地球を食い潰し、この灼熱の惑星に逃げ込んでから半世紀。
俺たちは硝子の柩の中で、窒息寸前の金魚みたいに生きている。
「おい、カイト。環境省から緊急依頼だ」
「パスだ。今日は気圧が悪い」
「報酬は特A級。新鮮な『水』がボトルで支給されるぞ」
水。
その単語に、カイトの喉が反射的に鳴った。
リサイクル装置を通した尿の濾過水じゃない、本物のH2O。
「……場所は?」
「第9セクター。『エデン』の換気ダクトだ」
カイトの手が止まる。
エデン。
政府高官と、選ばれた科学者しか立ち入れない聖域。
テラフォーミング計画の中枢であり、唯一、植物が自生しているとされる実験区画。
「あそこは完全自動化されてるはずだろ」
「センサーが異常を感知したらしいが、ドローンを送っても戻ってこないそうだ。……お前の『耳』が必要なんだとよ」
カイトはこめかみを指先で叩いた。
異常聴覚。
気圧の微細な変化、金属疲労の周波数、ガスの漏れる音。
常人には聞こえない『死の予兆』を聞き取る才能。
それが、カイトがこの最底辺の整備士として生かされている理由だった。
「わかった。行こう」
カイトは立ち上がり、汚れたツナギのジッパーを上げた。
耳の奥で、金属の悲鳴がまた一段と甲高く響いた。
それはまるで、都市そのものが「もう終わりにしてくれ」と泣いているようだった。
第二章 偽りの楽園
第9セクターへのエアロックが開く。
途端に、空気が変わった。
「うっ……なんだ、この湿度は」
レノが顔をしかめて防護マスクを調整する。
整備通路とは違う、ねっとりとした濃密な空気。
だが、カイトが感じた違和感はそれだけではなかった。
(静かすぎる)
空調のハム音がない。
ポンプの振動もない。
あるのは、生温かい風の音と、何かが『脈打つ』ようなリズムだけ。
「おい、壁を見ろよ」
レノがライトを向けた先。
無機質な通路の壁を、血管のような蔦が覆い尽くしていた。
「植物……なのか? これ」
色は鮮やかな緑ではない。
赤黒く、濡れたような光沢を放っている。
「触るな」
カイトは鋭く制止した。
「音がする」
「はあ? 植物が音なんて……」
「呼吸音だ。こいつら、息をしてやがる」
カイトは壁に耳を近づけた。
シュー、シュー。
微かだが、確実に空気を吸い込み、何かを吐き出している。
その時、通路の奥から女性の声が響いた。
「あら、整備士さん? 予定より早いのね」
白衣を纏った女が立っていた。
胸元には『主任研究員:エレナ』のIDカード。
しかし、彼女の右腕は、あの赤黒い蔦と同化し、異形の鉤爪のように変質していた。
「なっ……! あんた、その腕!」
レノが腰のスタンバトンに手を伸ばす。
エレナは艶然と微笑んだ。
「美しいでしょう? これが『適応』よ」
「適応だと?」
カイトが問う。
「テラフォーミング計画なんて、最初から失敗していたのよ。
この星の気圧と酸性雨に耐えられる植物なんて、地球種じゃ作れなかった」
エレナは一歩近づいてくる。
その足音もまた、湿った肉が床を叩くような音だった。
「だから、私たちは発想を変えたの。
星を人に合わせるんじゃない。人を星に合わせるのよ」
カイトの背筋に冷たいものが走る。
「まさか、このダクトの故障っていうのは……」
「故障じゃないわ。開放よ」
エレナが腕を振るうと、壁面のパネルが弾け飛んだ。
そこには巨大な換気ファンが回っていた。
だが、送り出されているのは清浄な空気ではない。
赤黒い胞子を含んだ、黄金色のガス。
「アーク・セブンの全区画に、この『福音』を届けるの。
あと数時間もすれば、居住区のみんなも進化できるわ。
肺が焼け爛れる苦しみから解放されるのよ」
「ふざけるな!」
レノがバトンを構えて飛びかかった。
だが、エレナの反応速度は人間離れしていた。
蔦のような右腕が鞭のようにしなり、レノを壁まで吹き飛ばす。
「がはっ……!」
「レノ!」
カイトは駆け寄ろうとしたが、足元の床から生えた蔦に足首を掴まれた。
「あなたには聞こえるでしょう? 整備士さん。
この星の歌が。
私たちの身体が、金星の一部になろうとする歓喜の歌が」
カイトは必死にもがいた。
だが、耳に入ってくる音は、恐怖を煽るものではなかった。
(……心地いい?)
彼の特異な聴覚は、この赤黒い植物たちが奏でる和音が、
金星の暴風や気圧と完全に『調和』していることを理解してしまった。
不協和音を奏でているのは、むしろ人間の作ったこの都市の方だった。
第三章 境界線の向こう側
「カイト……逃げろ……」
レノが苦しげに呻く。
その顔には、すでに赤い斑点が浮かび上がっていた。
「もう遅いわ」
エレナが笑う。
「胞子は充満した。あなたたちの肺の中で、種はもう芽吹いている」
カイトは自分の喉を押さえた。
息が苦しい。
肺が焼けるように熱い。
だが、不思議と恐怖は薄れていく。
(俺はずっと、この音が嫌いだった)
金属の軋み。
漏れ出す空気。
死へのカウントダウン。
だが、今聞こえるのは、力強い鼓動。
「カイト、そいつを止めろ! メインバルブを閉めるんだ!」
レノの声が遠くなる。
カイトはよろめきながら、制御コンソールへと向かった。
目の前には、緊急停止ボタンがある。
これを押せば、換気ファンは止まる。
セクター9は隔離され、居住区の人間は助かる。
だが、それは『延命』に過ぎない。
あと数年で、アーク・セブンは墜ちる。
金属疲労は限界だ。
修理部品もない。
人類は、この硝子の柩の中で、酸の海に沈むのを待つだけだ。
一方、目の前にあるのは『進化』。
人間であることを捨て、この地獄のような惑星で生きる怪物になる道。
「どっちが……正解なんだ」
カイトの手が震える。
「選んで」
エレナが囁く。
「緩やかな絶滅か、醜い存続か」
カイトは閉じていた目をカッと見開いた。
彼の耳に、決定的な音が届いたからだ。
キィィィィィン……。
それは、第9セクターの隔壁ガラスに走った、致命的な亀裂の音。
「……選ぶ必要なんて、最初からなかったんだ」
カイトはスパナを握りしめ、制御盤を叩き壊した。
停止ボタンごと、回路を粉砕する。
「なっ、何を!?」
エレナが驚愕の声を上げる。
「ファンを止めても無駄だ。外壁が割れるぞ!」
カイトが叫んだ瞬間、轟音と共に世界が白く染まった。
第四章 金色の雨
気圧差で鼓膜が破けそうな衝撃。
暴風がセクター内を荒れ狂う。
だが、即死するはずの気圧の中で、カイトは生きていた。
喉の奥から這い上がってきた何かが、食道の内側を覆い、
肺を瞬時に作り変えていく感覚。
激痛。
そして、歓喜。
カイトは床に倒れ込んだまま、割れた天井を見上げた。
金星の分厚い雲の切れ間から、黄金色の雨が降り注いでいる。
それは、肌を焼く酸の雨のはずだった。
けれど今、カイトの変質した皮膚を伝う雫は、まるで温かいシャワーのように感じられた。
「……綺麗だ」
隣では、レノがうずくまりながら、喉から植物の根のようなものを吐き出していた。
彼もまた、死なずに済んだらしい。
エレナは、吹き込む暴風の中で両手を広げ、笑っていた。
彼女の背中からは、薄い皮膜のような翼が伸び始めている。
「聞こえるか、レノ」
カイトは掠れた声で言った。
声帯が変わったのか、その声は以前よりも低く、重厚に響いた。
「……ああ。聞こえるよ」
レノが顔を上げる。
その瞳は、爬虫類のように縦に裂け、金色に輝いていた。
「雨の音だ。……いい音だな」
都市の軋む音はもう聞こえない。
聞こえるのは、新生した生態系が、この過酷な惑星と握手を交わす音だけ。
カイトはゆっくりと立ち上がった。
防護マスクはもういらない。
彼はマスクを剥ぎ取り、地面に叩きつけた。
そして、猛毒の大気を肺いっぱいに吸い込む。
甘い。
腐敗と硫黄の混じった、生命の匂い。
眼下に広がる雲海の向こう。
かつて地獄と呼ばれたその場所が、今や彼らにとっての『約束の地』となろうとしていた。
人類は滅んだ。
そして、金星人(ヴィーナシアン)が生まれた。
カイトは歩き出した。
崩れ落ちていく硝子の柩を背に、終わりのない黄金の雨の中へ。
(了)