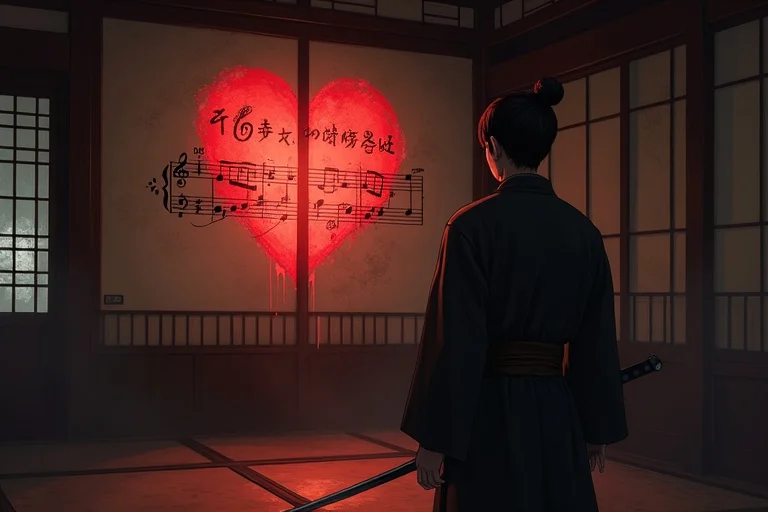第一章 鉄の匂い
雨が降っている。
江戸の町を灰色の帳(とばり)が包み込み、軒先を叩く水音が、鼓膜にへばりついて離れない。
弥助(やすけ)は、井戸端で手を洗っていた。
何度も、何度も。
手桶から掬った水は冷たく、指先の感覚を奪っていく。
それでも彼は、掌をこすり合わせるのをやめない。
「……落ちねえ」
呟きは、雨音にかき消された。
目に見える血など、とうに洗い流されている。
皮膚が赤く剥けるほどこすっても、鼻の奥にこびりついた鉄錆のような匂いが消えないのだ。
「弥助様、お勤めのご刻限です」
背後から掛かった低い声に、弥助の肩がびくりと跳ねた。
振り返ると、奉行所の若侍が立っている。
濡れた蓑(みの)から滴る水が、地面の泥を跳ねさせていた。
「……分かっている」
弥助は震える手を懐に隠し、努めて低い声を出した。
山田浅右衛門(やまだあさえもん)。
世間が恐れ、忌み嫌う『首切り浅右衛門』の一門。
それが弥助の表の顔だ。
だが、その実態は、虫一匹殺すのに躊躇い、血を見れば吐き気を催す、臆病な男だった。
ただ一つ。
彼には、呪いのような才があった。
剣を振るう瞬間だけ、感情が凍りつき、肉をバターのように断つ『慈悲の太刀』が振るえるのだ。
苦痛を与えず、瞬きの間に首を落とす。
その技だけが、彼をこの地位に縛り付けていた。
「罪人は、牢にてお待ちです」
「……名は」
「元・勘定方、佐久間源次郎(さくまげんじろう)」
弥助の足が止まった。
世界が、ぐらりと揺れた気がした。
雨音が遠のく。
源次郎。
その名は、かつて同じ道場で竹刀を交わし、共に甘味処で団子を頬張った、幼馴染の名だった。
第二章 牢獄の再会
地下牢の空気は、腐った藁と湿気で澱(よど)んでいる。
松明の頼りない明かりが、格子の向こうの男を照らし出した。
源次郎は、端座していた。
後ろ手に縛られ、着物は薄汚れているが、その背筋はかつて道場で見た時と同じく、矢のように伸びている。
「……良い雨音だ」
源次郎が、格子越しに弥助を見ずに言った。
「地上の喧騒が聞こえねえ。静かだ」
「源次郎……」
弥助の声は、情けないほどにかすれていた。
源次郎がゆっくりと顔を上げる。
痩せた頬。伸びた無精髭。
だが、その瞳だけは、少年の頃のように澄んでいた。
「よお、弥助。出世したな」
「ふざけるな!」
弥助は格子を掴み、叫んだ。
錆びた鉄が掌に食い込む。
「なんで……なんでお前がこんな所にいる! 勘定方に出仕して、嫁も貰って、順風満帆だったはずだろうが!」
「世の中、帳尻が合わねえことばかりでな」
源次郎は薄く笑った。
「不正を見て見ぬふりができなかった。それだけだ」
「だからって、上役に刃向かって……放火の罪まで着せられて……」
「俺は、火など点けていない」
きっぱりと、源次郎は言った。
「だが、誰かが責任を取らねばならん。そういう仕組みなんだよ、この腐った幕府は」
「俺が……」
弥助は崩れ落ちそうになる膝を必死に支えた。
「俺が、お前を斬るんだぞ」
「ああ。知っている」
源次郎の声は、あまりにも優しかった。
「だから、安心したんだ」
「……なに?」
「他の下手な首切り役なら、苦しんで死ぬかもしれん。だが、お前なら大丈夫だ」
源次郎は、縛られたまま器用に身を乗り出し、格子の隙間から弥助を見つめた。
「弥助。お前の剣は、優しいからな」
「やめてくれ……」
弥助は頭を抱えた。
「俺は人殺しだ。優しさなんてない。ただの、臆病な人殺しだ」
「違う」
源次郎の言葉が、鋭く響いた。
「お前は、痛みを誰よりも知っている。だから、お前の剣には殺意がない。あるのは『断絶』だけだ」
源次郎は目を細めた。
「頼む、弥助。俺を、お前の手で送ってくれ。それが、俺の最後の望みだ」
弥助の目から、涙が溢れ出した。
拭うこともできず、ただ流れるままにする。
外の雨音は、まだ止まない。
第三章 白州の静寂
伝馬町の処刑場は、異様な熱気に包まれていた。
雨は小降りになっていたが、見物人たちの傘の花が咲き乱れている。
彼らは血を求めていた。
正義の執行という名の、娯楽を求めていた。
弥助は、白州の砂利を踏みしめた。
足袋を通して伝わる石の冷たさが、彼を現実へと引き戻す。
腰に差した刀、『是清(これきよ)』が、鉛のように重い。
中央には、源次郎が座らされていた。
目隠しはされていない。
彼は最期まで、この世を見届けるつもりなのだ。
検視役の与力が、罪状を読み上げる。
「……よって、打首獄門に処す!」
形式的な言葉が、空虚に響く。
弥助は、源次郎の背後に立った。
刀の柄に手を掛ける。
掌が汗で滑る。
(できない)
弥助の心が叫んだ。
(友を、斬るなんて)
手が震える。
呼吸が浅くなる。
視界が白く霞む。
その時。
「弥助」
源次郎が、誰にも聞こえないほどの小声で囁いた。
「あの日の、柿の味を覚えているか」
弥助の脳裏に、鮮やかな橙色が蘇った。
腹を空かせた子供時代。
神社の裏で盗んだ渋柿。
二人で齧りつき、あまりの渋さに顔を見合わせて笑った。
「……ああ」
「俺は、あの時、お前が笑ってくれて嬉しかったんだ」
源次郎は、前を向いたまま続けた。
「泣き虫の弥助。俺の自慢の親友」
震えが、止まった。
源次郎は、死を受け入れているのではない。
弥助に、業(ごう)を背負わせまいとしているのだ。
自分が取り乱せば、源次郎の名誉が汚れる。
無様に首を斬り損ねれば、源次郎に地獄の苦しみを与えることになる。
(俺が、してやれることは)
弥助は深く息を吸い込んだ。
肺の奥まで、湿った空気が満ちる。
恐怖も、悲しみも、後悔も、すべて吸い込み、丹田に落とす。
世界から、音が消えた。
見物人のざわめきも、風の音も、自分の心臓の音さえも。
ただ、源次郎の首筋にある、一本の透明な線だけが見えた。
「……御免」
弥助は、刀を抜いた。
振りかぶる動作さえ、風になびく柳のように自然だった。
殺意はない。
力みもない。
ただ、そこにある線を、なぞるように。
銀閃(ぎんせん)。
刀身が、空気を、雨粒を、そして骨と肉を通り抜けた。
手応えはなかった。
あまりにも鋭い斬撃は、切断されたことさえ、肉体に気づかせない。
源次郎の首が、ゆっくりと前に傾く。
その顔は、穏やかだった。
口元には、微かな笑みさえ浮かんでいるように見えた。
どさり。
首が落ちる音で、世界に音が戻ってきた。
歓声。
怒号。
ため息。
弥助は、血振るいもせず、刀をじっと見つめた。
刃には、脂ひとつ、刃こぼれひとつなかった。
ただ、雨粒が一滴、切っ先から零れ落ちた。
それは、刀が流した涙のようだった。
第四章 雨上がりの空
処刑から三日が過ぎた。
弥助は、職を辞した。
誰が止めるのも聞かず、屋敷を引き払い、刀を封印した。
源次郎の墓は、小高い丘の上にあった。
罪人の墓ゆえ、墓石はない。
ただ、弥助が手向けた野花だけが、風に揺れている。
「……馬鹿野郎」
弥助は、供え物の柿を置いた。
熟した柿だ。
甘く、柔らかい。
「あんな笑顔で逝きやがって」
懐から、一通の手紙を取り出す。
処刑の後、源次郎の妻から渡されたものだ。
『弥助へ。
俺が死ねば、世間は俺を悪党と呼ぶだろう。
だが、俺の魂を救ってくれたのは、お前の剣だ。
お前の剣は、人を殺すためのものじゃない。
人を、苦しみから解き放つためのものだ。
だから、自分を責めるな。
お前は、俺の誇りだ。
源次郎』
弥助は空を見上げた。
雨は上がっていた。
雲の切れ間から、薄い陽光が差し込んでいる。
手の震えは、もうなかった。
だが、頬を伝う熱い雫だけは、いつまでも止まることがなかった。
「……食おうぜ、源次郎」
弥助は柿を二つに割った。
片方を墓前に。
もう片方を、自分の口に。
甘い。
そして、どうしようもなく、苦かった。
風が吹き抜け、草木がざわめく。
それはまるで、「うまいな」と笑う、あいつの声のように聞こえた。
弥助は立ち上がった。
刀は捨てた。
だが、友との約束だけは、この胸に刻まれている。
彼は歩き出した。
雨上がりの、泥濘(ぬかる)んだ道を。
一歩、また一歩と。
その背中には、もう迷いはなかった。