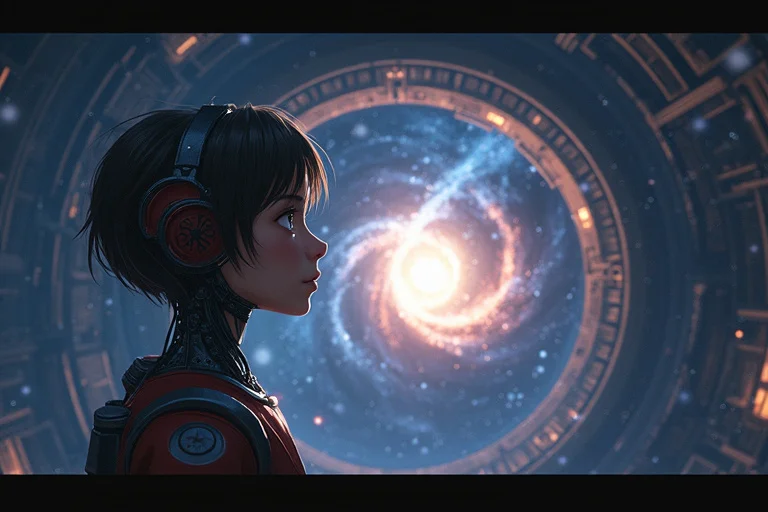第一章 0と1の境界線
雨の匂いが少し、強すぎる気がした。
私は指先を空中になぞらせ、パラメータを調整する。
湿度の数値を2パーセント下げ、アスファルトが濡れる香りを微調整した。
「完璧だ」
窓の外、灰色の空から降り注ぐ雨粒は、物理演算の極致と言っていい。
ガラスに張り付く水滴の重力落下、その不規則な軌道。
私は記憶再生士(メモリー・アーキテクト)。
依頼人の記憶データから、もう二度と戻らない「あの日」を仮想空間に再構築するのが仕事だ。
だが、この空間は特別だった。
クライアントはいない。
これは私自身のために作り上げた、妻・エミとの最後の記憶だ。
テーブルには、湯気を立てる二つのマグカップ。
モカ・マタリの酸味を含んだ湯気が、鼻腔をくすぐる。
すべてが完璧に再現されているはずだった。
けれど、私の職業病とも言える異常なこだわりが、わずかな違和感を拾い上げる。
マグカップの縁。
そこに付着した口紅の跡が、ほんの一瞬、ノイズのように明滅したのだ。
「……レンダリング・エラー?」
ありえない。
このセッションに使っているサーバー容量は、国家予算並みのコストをかけている。
バグなど許されない。
私は眉をひそめ、自分の手元を見た。
血管の青み、皮膚の皺、爪の半月。
すべてが高解像度で存在している。
カラン、とドアベルが鳴った。
心臓が跳ねる。
この音だけは、どんなに調整しても毎回、私の鼓動を早める。
「おまたせ、カイト」
濡れた傘を畳みながら、エミが入ってきた。
5年前に事故で失った、最愛の妻。
記憶の中の彼女は、いつも28歳のままだ。
「早かったね」
私は微笑んで迎え入れる。
これはシナリオ通りの会話だ。
彼女は席に着き、コーヒーに口をつける。
「雨、ひどくなってきたね」
彼女が窓の外を見る。
その横顔に見とれながら、私は安堵する。
やはり、彼女の挙動にはバグ一つない。
だが、次の瞬間。
エミは私の目を見て、シナリオにない言葉を口にした。
「ねえ、カイト。……そろそろ、気づいてるんでしょ?」
第二章 逆転する座標
思考処理が停止した。
「……え?」
「気づいてるはずよ。このコーヒー、もう30分も経ってるのに冷めないこと」
彼女の指摘に、私はカップを掴んだ。
熱い。
淹れたてのような熱さが、指先に伝わる。
物理エンジンの時間経過設定が機能していない?
「バグじゃないわ」
エミが静かに告げる。
その瞳には、私が設定した覚えのない、深い悲しみが宿っていた。
「私が、時間を止めたの」
「何を言っているんだ、エミ。これは僕が作ったシミュレーションだ。君は……」
言いかけて、言葉が喉に詰まる。
君は、データだ。
そう言おうとして、あまりにも人間的な彼女の表情に気圧された。
エミが手を伸ばし、私の頬に触れる。
その手は温かく、そして震えていた。
「違うの、カイト。あなたがシミュレーションを作っているんじゃない」
視界の端で、世界が歪む。
窓の外の雨が、空中で停止した。
店内の色彩が彩度を失い、ワイヤーフレームの骨組みが透けて見え始める。
「あなたが、シミュレーションなの」
雷に打たれたような衝撃が走った。
「僕が……データ?」
「そうよ。あなたは5年前の事故で、私を庇って死んだの」
呼吸ができない。
いや、そもそも私は呼吸をしていたのか?
過去の記憶がフラッシュバックする。
雨の日。スリップしたトラック。
助手席の私。
違う。
私は生き残ったはずだ。
ずっと、エミを失った悲しみの中で生きてきたはずだ。
「私はどうしても、あなたにさよならが言えなかった」
エミの声が涙で潤む。
「だから、あなたの脳のスキャンデータを使って、この『記憶再生士のカイト』を再現したの。あなたが生き残って、私が死んだという設定(IF)の中でなら、あなたは苦しまずに生き続けられると思ったから」
私の存在そのものが、彼女の悲しみが生んだ虚構。
私が感じていた「喪失感」さえも、プログラムされた性格設定(パラメータ)だったのか。
私は自分の手を見る。
指先から、画素(ピクセル)が剥がれ落ちていくのが見えた。
第三章 ログアウトの雨
「サーバーの維持費、もう限界なの」
エミが泣きながら笑った。
その笑顔は、記憶の中のどのデータよりも美しく、残酷だった。
「今日で、契約が切れるの。だから最後に、本当のことを話したかった」
私の体は、腰のあたりまでノイズに変わっていた。
恐怖はなかった。
不思議なほど、心が凪いでいる。
自分が「作り物」であるという絶望よりも、目の前のエミが「本物」であり、生きていてくれたという事実が、私のプロセッサを歓喜で満たしていた。
「そうか……君は、生きていたんだね」
私は残った右手を伸ばし、彼女の涙を拭う。
指先の感覚はもうない。
けれど、彼女の温もりだけは、データを超えて魂に届く気がした。
「ごめんね、カイト。勝手に蘇らせて、勝手に殺して」
「謝らないでくれ。僕は幸せだったよ。たとえ偽物の記憶でも、君を愛し続けることができたんだから」
世界が崩落していく。
壁が消え、床が抜け、白い光が周囲を包み込む。
「元気でやるんだよ、エミ」
「うん……うん……! 愛してる、カイト」
「僕もだ」
視界がホワイトアウトする直前。
私は最後の力を振り絞り、システムコマンドを実行した。
『Execute: Happy_Ending_Protocol』
それは、残される彼女の記憶から、私の消滅による悲しみを少しだけ和らげ、前を向かせるための、些細なパッチプログラム。
僕という存在が消えても、雨上がりの空のように、彼女の人生が晴れ渡るように。
光の中で、私は微笑んだ。
「さようなら」
システム終了
画面上の文字列が消え、暗転したモニターに、泣きはらした女性の顔が映り込んでいる。
外は、静かな雨が降り続いていた。