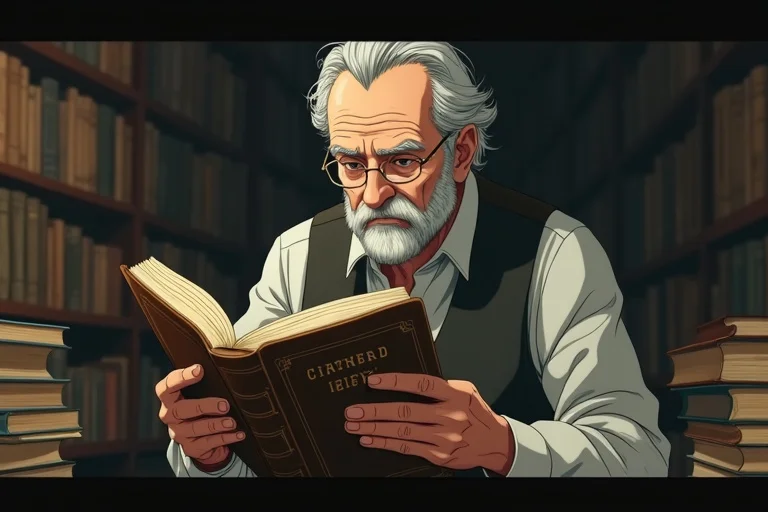第一章 忘却の預かり物
神保町の裏路地に佇む「桐島古書店」の空気は、いつもインクと古い紙の匂いで満ちていた。店主の桐島蒼(きりしまあおい)は、その澱んだ静寂の中で、本の背表紙を指でなぞるのが日課だった。それは外界との間に見えない壁を築き、自らの内に閉じこもるための儀式にも似ていた。
その壁を、予期せぬ客が叩いたのは、冷たい雨がアスファルトを濡らす日の午後だった。ドアベルがちりん、と寂しげな音を立てる。入ってきたのは、上等な紫色の和服を上品に着こなした、白髪の老婦人だった。その佇まいは、この埃っぽい店にはあまりに不似合いだった。
「ごめんくださいまし」
鈴を転がすような、しかしどこか切実さを帯びた声だった。蒼がカウンターから顔を上げると、老婦人は真っ直ぐに彼を見つめていた。その瞳は、深い森の湖のように静かで、底知れない色をしていた。
「ひとつ、預かっていただけないでしょうか」
老婦人は、風呂敷から一冊の本を取り出した。それは市販されている本ではない。革で装丁され、表紙には何も書かれていない、無垢な本だった。蒼が受け取ると、ずしりとした重みと、人の手の温もりがかすかに伝わってきた。
「これを、一ヶ月後の今日、受け取りに参る者がおります。その者にお渡しいただきたいのです」
「……受け取りに来る方のお名前は?」
「それは、お会いになれば分かります」
老婦人は曖昧に微笑むだけだった。そして、最も奇妙な依頼を口にした。
「お願いがございます。決して、この本の中をお読みになりませんよう」
強い意志を込めたその言葉に、蒼は思わず息を呑んだ。老婦人はカウンターに、分厚い封筒を置いた。中には、預かり料としては法外な額の現金が入っているのが透けて見えた。
「必ず、参りますから」
それだけ言うと、老婦人は深々と一礼し、再び雨の街へと姿を消した。後に残されたのは、インクの匂いに混じる微かな白檀の香りと、謎めいた一冊の本、そして蒼の胸に芽生えた、不吉な予感にも似た好奇心だった。その日から、彼の止まっていた時間が、軋みを上げて動き出すことになる。蒼はまだ、その本に自身の過去を縫い付けた針が、深く突き刺さっていることを知らなかった。
第二章 禁じられた頁
約束の一ヶ月が、刻一刻と近づいていた。蒼は店の奥にある金庫に例の本をしまい込み、意識してその存在を忘れるように努めた。だが、忘れようとすればするほど、革装丁の滑らかな感触と、老婦人の「決して読むな」という言葉が、脳裏に焼き付いて離れなかった。
奇妙な出来事が起こり始めたのは、期限を三日後に控えた夜だった。閉店後の店内で本の整理をしていると、不意に店のドアが、とん、とん、と優しくノックされた。こんな時間に誰だろうと覗き窓から外を見るが、雨に濡れた路地には誰の姿もない。風の悪戯かと思ったが、そのノックは翌日も、そのまた翌日も、同じ時間に繰り返された。まるで、見えない誰かが本の返還を待ちわびているかのように。
蒼の心は、日に日に不安と焦燥に蝕まれていった。そして、約束の日の前夜。深夜の静寂の中、またしてもドアをノックする音が響く。蒼は意を決してドアを開けたが、やはりそこには誰もいなかった。冷たい夜風が、彼の頬を撫でていく。その瞬間、何かがぷつりと切れた。
蒼は憑かれたように金庫へと向かい、あの本を取り出した。指先が微かに震える。禁忌を破る背徳感と、抗いがたい引力。彼はゆっくりと、革の表紙を開いた。
そこに現れたのは、インクで綴られた美しい手書きの文字だった。
『勿忘草(わすれなぐさ)の約束』
そう題された物語は、ある兄妹の、あまりにもありふれた、そしてかけがえのない日々の記憶から始まっていた。兄の視点で語られる物語。公園のブランコ、妹の好きだった苺味のキャンディ、雨上がりの虹。その一つ一つの描写が、蒼の心の奥底にしまい込んでいた風景と、不思議なほど重なった。
読み進めるうちに、蒼の呼吸は浅くなる。物語の中の兄は、幼い妹を守れなかった罪悪感に苛まれていた。妹が、青いワンピースを着ていたこと。兄が、目を離したほんの一瞬の隙に、彼女が道路に飛び出してしまったこと。響き渡るブレーキ音と、人々の悲鳴。
「やめろ……」
蒼の口から、かすれた声が漏れた。それは、彼が十数年間、夢に見続けてきた光景そのものだった。妹の千尋(ちひろ)を失った、あの夏の日の記憶。千尋が好きだった勿忘草の花、蒼が事故の直前に口ずさんでいたテレビアニメの主題歌。物語は、まるで蒼自身の魂を覗き込み、その記憶を正確に書き写したかのようだった。
なぜ。誰が。どうして。
物語の結びには、こう書かれていた。
「僕は今日も、君のいない世界で息をする。君を忘れないことが、僕にできる唯一の償いだから」
それは、蒼が胸の内で繰り返してきた独白そのものだった。彼は本を閉じることもできず、ただ愕然と文字の羅列を見つめていた。これは単なる物語ではない。これは、蒼の罪と後悔そのものを封じ込めた、呪いにも似た手紙だった。外では、いつの間にか止んでいた雨が、再び窓を叩き始めていた。
第三章 優しい嘘の在り処
翌朝、蒼は店を開ける気になれず、手の中の本を握りしめていた。約束の受け取り人が現れるはずの日。しかし、彼が対峙すべきは、もはや見知らぬ客ではなかった。この本の作者、彼の魂の最も柔らかな部分を抉り出した、正体不明の「誰か」だ。
手がかりは、本に挟まれていた一枚の写真の切れ端だけだった。古い公園の隅に立つ、小さな女の子の足元。履き古した赤い靴が写っている。蒼は、その写真に見覚えがあった。千尋が大切にしていた靴だ。
蒼は、記憶の糸を必死に手繰った。近所の写真館、両親のアルバム。だが、手掛かりは見つからない。途方に暮れかけたその時、ふと脳裏に浮かんだのは、店の常連である高林という老人の顔だった。穏やかな物腰で、時折、蒼の顔色の悪さを気遣ってくれる、優しい人。彼は以前、町の古い歴史について語る中で、近所の写真館の変遷に詳しいと話していた。
藁にもすがる思いで、蒼は高林の家を訪ねた。高林は驚いた顔をしたが、すぐに蒼を招き入れた。蒼が震える手で本と写真を見せると、高林の表情が、悲しみとも憐れみともつかない複雑な色に翳った。
「……やはり、読んでしまわれたのですね」
その声に、蒼は心臓を鷲掴みにされたような衝撃を受けた。
「あなたが……? なぜ、僕の過去を……」
「落ち着いて聞いてください、桐島さん」
高林は静かに語り始めた。彼は元精神科医であり、今は退職して静かに暮らしていること。そして、十数年前のあの日、彼は偶然、事故の現場を通りがかったのだと。
「あなたの記憶は、少しだけ、真実と違っています」
高林の言葉に、蒼は混乱した。何を言っているんだ。あの光景は、脳に焼き付いて離れないのに。
「確かに、あなたは千尋ちゃんの手を離してしまった。しかし、それはあなたのせいではない。あの日、千尋ちゃんは、以前から患っていた心臓の病で、突然発作を起こして倒れたのです。あなたの目の前で」
「……嘘だ。千尋は、病気なんかじゃ……」
「ご両親は、あなたに余計な負い目を背負わせたくなくて、そのことを隠しておられた。あなたが『自分のせいだ』と深く思い込んでしまったから……。事故は、倒れた千尋ちゃんに、脇見運転の車が突っ込んできたのが原因です。あなたは、彼女を庇おうと、必死にその小さな体を抱きしめていた。私はこの目で、それを見ていたのです」
偽りの記憶。蒼の世界が、音を立てて崩れていく。自分が信じ続けた罪悪感は、自分自身が作り出した幻だったというのか。あまりの衝撃に、言葉が出なかった。
「あの本は、私が書きました」と高林は続けた。「あなたのカウンセリング記録や、ご両親から伺ったお話を元に、あなたの視点から。あなたがいつか、その苦しみから解放される日が来ることを願って。老婦人は、私の妻です。あなたにきっかけを与えるための、協力者でした」
では、本を受け取りに来るはずだった人物とは?
「それは、『過去の呪縛から解放された、新しいあなた自身』のことですよ、桐島さん。あなたが真実を受け入れ、自分を許すことができたなら、その本は役目を終える。あなたが、それを受け取るべきなのです」
蒼の頬を、熱い涙が伝った。それは十数年間、流すことのできなかった涙だった。罪悪感ではなく、ただ純粋な悲しみと、そして、目の前の老人への感謝の念が入り混じった、温かい涙だった。
第四章 勿忘草の約束
すべてが、優しい嘘で塗り固められた真実だった。蒼が抱えていた罪悪感という重い鎧は、高林の言葉によって、脆くも崩れ去った。彼は、自分が妹を守れなかった無力な兄ではなく、最後まで妹を守ろうとした、ただの少年だったのだ。
数日後、蒼は千尋の墓前に立っていた。手には、一輪の勿忘草。
今までは「ごめんね」としか言えなかった。だが、今日は違った。
「千尋、会いたかったよ」
初めて口にできた素直な言葉は、風に乗り、青い空へと溶けていった。心が、ふわりと軽くなるのを感じた。
桐島古書店には、再びいつもの静寂が戻った。だが、その空気はもはや澱んではいない。窓から差し込む光が、埃をきらきらと輝かせ、どこか温かく感じられた。蒼は、カウンターの奥で、新しい万年筆を手にしていた。目の前には、真っ白な原稿用紙が置かれている。
高林が紡いでくれたのは、蒼の「偽りの記憶」の物語だった。今度は、蒼自身が「本当の記憶」を紡ぐ番だ。忘れていた千尋の笑顔、交わしたくだらない会話、二人で見た夕焼け。それらを一つ一つ丁寧に拾い上げ、言葉にしていく。それは、失われた時間を取り戻し、未来へと歩き出すための、彼自身の儀式だった。
ペンが、さらさらと紙の上を滑る。インクの匂いが、心地良い。
彼は、物語の冒頭にこう記した。
僕の記憶は、優しい嘘でできていた。
その一文は、罪からの解放宣言であり、新たな人生の始まりを告げる産声でもあった。本の外には、柔らかな日差しに満ちた世界が広がっている。蒼は、もう壁の内側に閉じこもる必要はない。彼はこれから、物語を紡ぐことで、世界と、そして誰かの心と繋がっていくのだろう。手元に残された革装丁の本は、今や呪いの象徴ではなく、彼の人生の道標を示す、温かい栞となっていた。