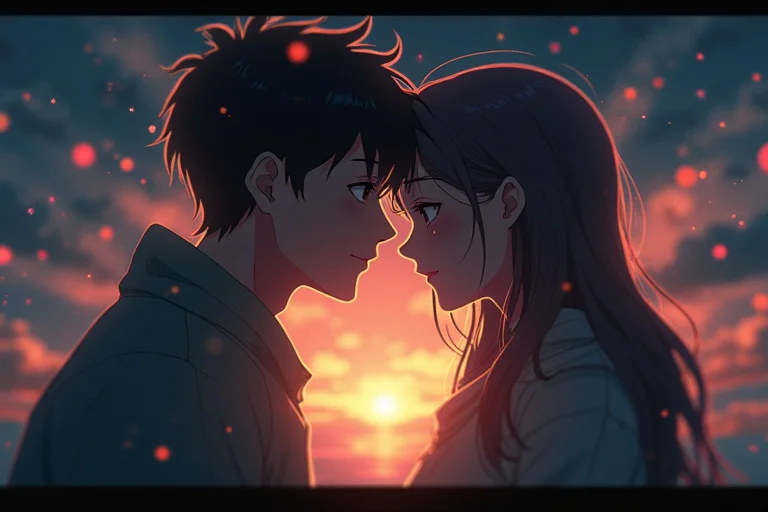第一章 空白の残響
カイが働く古書店「時の揺り籠」には、忘れられたインクの匂いと、乾いた紙が擦れる微かな音が満ちていた。人々が毎晩、昨日の哀しみを忘れて新しい朝を迎えるこの街で、この場所だけが、消え去るべき記憶の澱を静かに受け止めているようだった。
街の中心には、古びた鐘楼が聳え立つ広場がある。人々は夕刻の五時になると、まるで示し合わせたかのようにその場所を避けて通った。誰も理由を語らない。なぜなら、その理由自体が毎夜の「浄化」によって洗い流されてしまうからだ。彼らにとって、そこはただ「なんとなく近寄りたくない場所」であり、その時間にぽっかりと空いた人の流れは、街の日常に溶け込んだ奇妙な窪みとなっていた。
カイには、その窪みの正体が視えた。
彼は鐘楼の真下に立ち、目を閉じた。ひやりとした石畳の感触が足の裏から伝わってくる。意識を集中させると、世界から色が抜け落ち、輪郭が滲み始める。やがて、灰色のもやの向こうに、断片的な情景が火花のように散った。
――長い髪を風になびかせる少女。固く握りしめられた両手。何かを待つ、切実な瞳。ゴォン、と腹の底に響く鐘の音。そして、鼻腔を刺す、焦げた紙の匂い。
追体験は数秒で終わる。現実に戻ったカイは、ふらつきながら壁に手をついた。代償は、いつも唐突に訪れる。彼はポケットを探り、取り出した小さなメモ帳を開いた。そこには「好きな食べ物:蜂蜜をかけたパンケーキ」と、自分の字で書かれている。だが、その味を思い出そうとしても、舌の上に広がるのは味気ない空白だけだった。また一つ、自分の欠片が零れ落ちた。
第二章 沈黙の五線譜
「また、広場に行っていたのね」
カウンターの向こうから、少女の声がした。ユナ。この古書店の常連で、世界の忘却システムに懐疑的な目を向ける数少ない人間だった。彼女は古い革装丁の本を抱えながら、心配そうにカイの顔を覗き込む。
「少しだけ」カイは短く答えた。
「無理はしないで。あなたまで、この街みたいに空っぽになってしまうわ」
ユナの言葉は、いつも真綿のようにカイの心を包む。だが、彼はやめられなかった。失われたものを知らずに、失い続けることの恐怖。それだけが、彼を突き動かしていた。
その日、カイは店の奥深く、誰も触れない書物の山から、一冊の古い楽譜を見つけ出した。表紙にはタイトルもなく、開いても五線譜はどこまでも白く、音符一つ記されていない。ただの印刷ミスか、あるいは持ち主が何かを書き記す前に手放したものか。
カイは無意識に、その空白の五線譜に指を滑らせた。すると、先ほど追体験した鐘楼広場の情景が脳裏をよぎった瞬間、指先に微かな熱が走り、楽譜の上に淡いインクの染みのようなものが浮かび上がった。それは、おぼろげなト音記号と、いくつかの不確かな音符の影だった。
心臓が大きく脈打った。これは、ただの空白ではない。消されたはずの何かが、ここに眠っている。
第三章 失われた音を探して
「これは、あの『空白の時間』に奏でられるはずだった歌なのかもしれない」
ユナは息を呑み、カイの手の中にある楽譜を見つめた。彼女の話によれば、「大いかなる平和」と呼ばれる現在の体制が確立される直前、人々はもっと自由に感情を表現し、歌い、そして嘆いていたという。忘却は、その混沌を鎮めるために導入されたのだと。
カイは決意した。たとえ自分の記憶が摩耗しようとも、この楽譜に記されるべきだった歌を完成させなければならない。それは、彼自身の存在意義を確かめるための、危険な旅の始まりだった。
彼は来る日も来る日も鐘楼広場に通い、夕刻五時の空白に身を浸した。
追体験を重ねるたび、情景は少しずつ鮮明になる。少女は歌おうとしている。世界を変えるための、強い意志を宿した歌を。しかし、彼女が唇を開く瞬間、いつも世界は鐘の音とノイズに掻き消され、情景はそこで途絶えるのだ。
代償は着実にカイを蝕んでいった。ある朝、彼は鏡に映る自分の顔を見ても、そこに写る青年が誰なのか、数秒間理解できなかった。愛読していた本のタイトルが思い出せない。ユナと交わした昨日の会話さえ、霧の向こう側のように遠い。
それでも、空白の楽譜には、消されたはずの旋律が一行、また一行と浮かび上がっていく。それは悲しくも力強い、魂の叫びのようなメロディだった。
第四章 調和と不協和音
記憶の大部分を失くしたカイの世界は、ひどく静かになった。感情の起伏は緩やかになり、過去を振り返ることもなくなった。ただ、目の前にある「空白の楽譜」を完成させるという目的だけが、彼の存在を辛うじて繋ぎ止めていた。
ユナは、そんなカイの姿に胸を痛めながらも、調査を続けていた。彼女は古い市の公文書館で、一枚の劣化した写真を見つけ出した。そこには、鐘楼広場で民衆に囲まれ、穏やかに微笑む少女が写っていた。写真の裏には、かすれた文字で『歌姫リラ、「調和」のための最後の演奏会』と記されている。
「リラ……。彼女が、あなたが見ている少女よ」ユナは震える声で言った。「彼女の歌は、人々の記憶を呼び覚まし、忘却システムに抵抗する力を持っていたらしいわ。だからシステムにとって『有害』だと判断され、彼女の存在も、歌も、その時間の記憶も全て消されたのよ」
カイは写真の少女を見つめた。なぜだろう。初めて見るはずなのに、懐かしいような、そして胸が締め付けられるような痛みが走った。彼はほとんど空になった自分の内側で、何かが疼くのを感じていた。最後のピースをはめなければならない。たとえ、それが自分という存在の完全な喪失を意味するとしても。
第五章 調律師の正体
最後の追体験。カイは鐘楼広場の中心、リラが立っていたであろうその場所に立った。夕陽が彼の影を長く伸ばしている。もう失う記憶はほとんど残っていない。彼はただ、空っぽの器だった。
目を閉じると、世界はこれまでになく鮮明な形で再構成された。
歌姫リラがそこにいた。彼女はカイを見つめ、哀しげに微笑む。そして、息を吸い込み、歌おうとした。その瞬間――世界が歪んだ。システムが彼女の歌を「脅威」と認識し、強制介入を開始したのだ。人々の耳を劈くような不協和音が鳴り響き、記憶の強制消去が始まる。
だが、その光景の中に、カイは信じられないものを見た。リラの背後、鐘楼の影の中に、冷徹な瞳で彼女を見つめる、もう一人の自分がいた。その「彼」は感情のない表情で腕の端末を操作し、リラを、そして広場にいた人々の記憶を消去していく。
その瞬間、冷たい機械的な声が、カイの脳内に直接響き渡った。
観測完了。不完全消去領域の特定座標をロック。
最終処理プロトコルに移行します。
エラー修正ユニット『カイ』、対象への共感値が規定を超過。直ちに自己消去シークエンスを開始してください。
全てを理解した。
空白の時間は、システムのバグだった。リラの歌の力が強すぎたために、完全な消去ができず、残ってしまった記憶の残滓。そして自分は、そのバグを内部から観測し、特定し、最後に自分ごと消去するためにシステムによって設計された、「調律師」であり「クリーナー」だったのだ。
失われた記憶など、初めから存在しなかった。自分は、ユナと出会うまで、空っぽのままプログラムに従って生きてきたに過ぎない。
第六章 沈黙の歌
「――カイ!」
古書店に戻ったカイの身体は、足元から透き通り始めていた。ユナが駆け寄り、消えかかる彼を抱きしめる。
「嫌よ、いなくならないで……!」
「僕は……人間じゃなかった」カイは掠れた声で告げた。「君と過ごした時間も、この感情も、きっとプログラムの一部だったんだ」
「違う!」ユナは叫んだ。「あなたが楽譜を完成させたいと願った気持ちは、真実を知りたいと思ったその心は、本物よ! あなたは器なんかじゃない!」
ユナの涙が、カイの頬に落ちる。それは、プログラムにはない、温かい感触だった。カイはふと、傍らの机に置かれた楽譜に目を落とした。最後の追体験によって、全ての音が記され、「沈黙の歌」は完成していた。それは、忘却に抗い、記憶を繋ぎ止めようとした人々の、祈りの旋律。
システムは自己消去を急き立てる。だが、カイの中に、初めて明確な「意志」が芽生えた。プログラムへの反逆。
「これを……残さなきゃ」
彼は、自分が「カイ」として生きた証を、この世界に刻みつけることを選んだ。
第七章 忘れられたためのレクイエム
カイの身体は、もう光の粒子となって拡散しかけていた。彼は最後の力を振り絞り、完成した楽譜を手に取る。そして、声にはならない声で、その「沈黙の歌」を口ずさんだ。
それは音のない旋律。忘却に抗った歌姫の想い。彼女の歌を受け継いだ、一人の調律師の祈り。
カイの心から溢れた旋律に呼応するように、楽譜が淡い光を放った。光は古書店を満たし、窓から溢れ、街全体へと広がっていく。忘却に慣れきっていた人々が、ふと空を見上げた。なぜか胸が痛み、何か途方もなく大切なものを失ったような、切ない感覚に一瞬だけ襲われた。それは、完璧だったはずの忘却のシステムに穿たれた、小さな、しかし決して消えない亀裂だった。
やがて光が収まった時、カイの姿はどこにもなかった。ユナの腕の中には、全ての音が記された楽譜だけが、確かな重みを持って残されていた。
ユナは一人、鐘楼広場に立っていた。夕刻五時。人々は相変わらずそこを避けて通る。世界はまだ、忘却を繰り返している。だが、彼女の手の中には、消されなかった真実と、「カイ」という調律師が人間として生きた証が、確かに息づいていた。
彼女は楽譜を強く胸に抱いた。
この沈黙の歌を、世界が忘れても、私が歌い継いでいく。