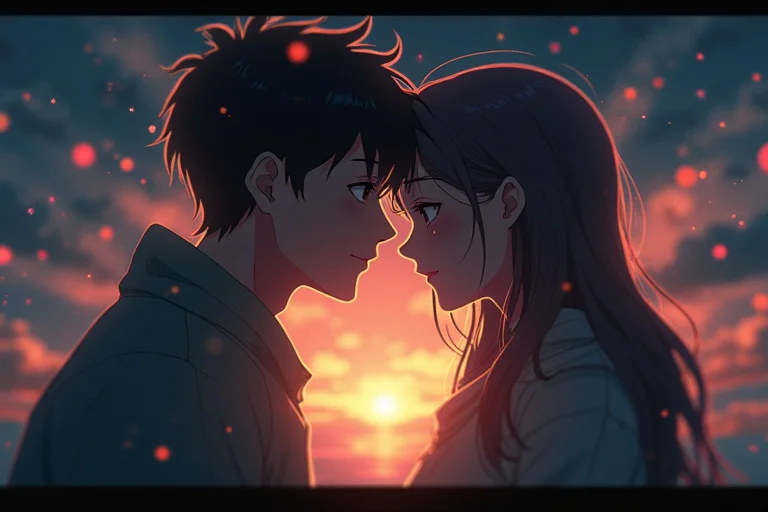第一章 透明な来訪者
神保町の裏路地にひっそりと佇む古書店『โมง昧洞(もうまいどう)』。その店主である俺、相沢湊にとって、世界は二色で構成されていた。真実の「透明」と、嘘の「濁った灰色」だ。
幼い頃の事故を境に、俺は他人の言葉に色が視えるようになった。相手が嘘をつくと、その言葉が吐息のように揺らめき、澱んだ灰色のオーラを放つのだ。それは善意の嘘も、悪意の嘘も、他愛ない冗談も、等しく同じ色だった。この呪いのような能力は、俺から人並みの信頼関係を築く力を奪い、いつしか俺は、言葉を発しない古い本たちだけに囲まれて生きるようになっていた。
そんな俺のモノクロームの世界に、唯一、彩りをもたらす存在がいた。雨宮葉月。半年前から週に一度、決まって木曜日の午後に店を訪れる女性だ。彼女はいつも、背筋を伸ばして書架を眺め、古い文学全集を愛おしそうに撫でては、俺に微笑みかける。
「この時代の本の匂い、好きなんです。時間の重みが凝縮されているみたいで」
彼女の言葉は、いつも澄み切っていた。まるで磨き上げられた水晶のように、一点の曇りもない透明な色をしていた。彼女の前でだけ、俺は呪われた能力のことを忘れ、ただの古書店の店主でいられた。彼女の言葉は、乾いた俺の心を潤す清らかな泉だった。俺が彼女に惹かれるのに、時間はかからなかった。
その日も、葉月はいつものようにやって来て、リルケの詩集を手に取った。彼女の指先が古びた紙を優しくなぞる。その仕草一つひとつが、俺の胸を高鳴らせた。彼女が帰り際に「また来週」と微笑んだ時、俺は、この平穏が永遠に続けばいいと、心から願った。
だが、永遠など、この世のどこにも存在しない。
翌日の金曜日、店のドアベルがけたたましく鳴った。入ってきたのは、葉月のような柔らかな客ではない。スーツを着た二人の男。そのうちの一人、年配の方が手帳を広げ、鋭い目で俺を射抜いた。
「警視庁の田所と申します。近隣で起きている連続失踪事件について、少しお話を伺いたい」
心臓が冷たい手で掴まれたように、どきりと音を立てた。最近、ニュースで耳にしてはいたが、自分の身近に迫ってくるとは思わなかった。
「失踪した三名は、いずれもこちらの常連客だったことが確認されています。何か、お気づきの点は?」
俺は記憶を探り、失踪者の名前と顔を思い浮かべた。確かに、見覚えのある客たちだった。俺が知る限りのことを話すと、田所刑事は頷きながらも、こう言った。
「ご協力感謝します。我々は、あなたが何か隠しているとは**思っていません**から」
その言葉の最後、「思っていません」という部分が、濃い灰色のオーラをまとって霧散した。俺は息を呑んだ。刑事は、俺を疑っている。その事実が、静かだった俺の世界に、不協和音の第一音を響かせたのだった。
第二章 灰色の不協和音
刑事たちが去った後も、店の空気は重く淀んでいた。彼らが残していった灰色の残滓が、古書の黴の匂いに混じり、俺の肺をじっとりと湿らせる。俺は、店の奥の居住スペースに戻ると、冷たくなったコーヒーを無理やり喉に流し込んだ。
疑われている。その事実だけで、世界が再び色褪せていくようだった。これまでも、幾度となく灰色の言葉に晒されてきた。だが、殺人事件の容疑者として向けられる嘘は、まるで鉛のように重く、俺の肩にのしかかった。
俺にできることは何だ? この呪われた能力は、ただ俺を苛むだけで、真実を教えてはくれない。誰が嘘をついているかは分かる。だが、なぜ嘘をつくのか、その嘘の裏に何が隠されているのかまでは、決して明かしてはくれないのだから。
翌週、葉月が店に現れた時、俺の心はささくれ立っていた。彼女の笑顔を見ても、以前のように素直に安らぐことができない。「何かあったんですか? 湊さん、顔色が悪いですよ」と心配そうに覗き込む彼女の言葉が、寸分の狂いもなく透明であることに、かえって胸が締め付けられた。
「……少し、厄介事に巻き込まれて」
俺は事件のことを話した。刑事のこと、疑われていること。葉月は黙って俺の話を聞き、そして静かに言った。
「私は、湊さんを信じています。あなたがあの人たちに何をしたというんですか」
その言葉もまた、一点の曇りもない透明だった。俺は思わず彼女の手を握っていた。冷たい指先に、彼女の温もりがじんわりと伝わってくる。この温かさだけが、今の俺の唯一の救いだった。
「ありがとう、葉月さん。君だけが……」
その日から、俺は自分なりに事件を調べ始めた。失踪した三人の客の購入履歴を洗い出し、彼らのSNSや周囲の人間関係をこっそりと探った。だが、得られるのは灰色の言葉の洪水だけだった。失踪者の妻は「夫は**幸せそうでした**」と泣き崩れ、会社の同僚は「彼が**トラブルを抱えていたなんて**知りません」と首を振る。誰も彼もが嘘をついている。世界中が巨大な嘘で塗り固められているように思えた。疑心暗鬼が心を蝕み、俺は夜ごと悪夢にうなされるようになった。
そんな俺を支えてくれたのは、やはり葉月だった。彼女は俺のまとまらない話を根気強く聞いてくれ、時には調査にまで付き合ってくれた。彼女といる時だけ、俺は灰色の世界から解放された。いつしか、俺は彼女に全てを打ち明けたいと願うようになっていた。この呪われた能力のことも、孤独な過去のことも。そして、この事件が解決したら、彼女に想いを伝えようと、固く心に誓った。
第三章 沈黙のスペクトル
調査は暗礁に乗り上げていた。失踪した三人の共通点は、俺の店の常連であること以外、何も見つからない。諦めかけたその時、ふと、ある違和感に気づいた。彼らの購入履歴をもう一度、日付を追って丹念に見ていく。すると、一つの点と点が、細い線で結ばれた。
彼らは三人とも、失踪する直前に、同じ一冊の本を購入していたのだ。
『深淵の呼び声』。作者不詳、私家版の古い本だ。好事家の間で密かに高値で取引されている、いわくつきの一冊。俺の店にも、一冊だけ古くからあったはずだ。俺は血の気が引くのを感じながら、店の稀覯本が収められたガラスケースに駆け寄った。だが、そこにあるはずの本の定位置は、ぽっかりと空間が空いているだけだった。
誰が買った? 販売記録を震える手でめくる。最後にこの本が売れたのは、三番目の被害者が失踪した、ちょうど一週間前。購入者の欄に書かれた、流れるように美しい筆跡。俺はその名前を知っていた。見間違えるはずがない。
――雨宮葉月。
頭を鈍器で殴られたような衝撃。世界がぐにゃりと歪み、足元が崩れ落ちていく。嘘だ。何かの間違いだ。俺は閉店後の静まり返った店内で、ただ呆然と立ち尽くした。
翌日、葉月が店に現れた。いつものように穏やかな微笑みを浮かべて。俺は平静を装うのに必死だった。心臓が肋骨を突き破らんばかりに鼓動している。
「葉月さん……単刀直入に聞く。一週間前、うちの店で『深淵の呼び声』という本を買わなかったか?」
一瞬、彼女の顔から表情が消えた。そして、悲しげに瞳を揺らしながら、ゆっくりと首を横に振った。
「……いいえ。そんな本、買った覚えはないわ」
その言葉が、彼女の唇から放たれた瞬間。
俺は、視た。
初めて視た。
彼女の言葉が、俺の世界を構成するはずのなかった、あの色に染まるのを。
濁った、重い、絶望的な灰色に。
ああ、と俺は思った。世界が終わるというのは、こういう感覚なのか。唯一信じていた光が、目の前で音を立てて消え失せた。透明だった泉は、一瞬にしてヘドロの浮かぶ沼へと変わった。
「嘘だ……」俺は呻いた。「なぜ嘘をつくんだ、葉月さん!」
俺が声を荒げると、葉月はびくりと肩を震わせ、瞳に涙を溜めた。そして、堰を切ったように真実を語り始めた。
「ごめんなさい……あなたを騙すつもりじゃなかった。でも、言えなかったの」
彼女の言葉は、もう灰色ではなかった。透明な、しかし痛みと悲しみに満ちた言葉だった。
「失踪した最初の人……高村悟は、私の兄なんです。兄はあの本に異常なほど執着していました。兄の行方を探るために、手がかりを求めてあなたの店に通い始めた。それが……始まりだったの」
兄。本。失踪。キーワードが頭の中で渦を巻く。だが、それだけでは説明がつかない。なぜ彼女は本の購入を否定した?
「なぜ、買ったことを隠したんだ?」
「買っていないからよ! 私はあの本を探していたけれど、あなたのお店では見つけられなかった。販売記録は……私が書いたものじゃないわ」
彼女の必死の訴えも、もはや俺の耳には届かなかった。信じていた人間に裏切られた衝撃が、俺の思考を麻痺させていた。その時、俺の脳裏に、長い間封印されていた扉が開くような、激しいめまいが走った。
忘れていた光景。血の匂い。書斎に散らばる原稿。そして、冷たくなった父の姿。
『深淵の呼び声』。あれは、父が遺した未発表の原稿だった。父の死の真相を暴露する、告発の書。父を死に追いやった者たちへの、復讐の書。
俺は、全てを思い出した。
幼い頃の事故で、父の死の記憶と共に、俺の中の何かが壊れた。俺は、父の復讐を果たすためだけに存在する、もう一人の自分を創り出していたのだ。
古書店を開いたのは、父を裏切った関係者たちが、父の最後の作品を探して現れるのを待つためだった。そして、本を読んだ者を、一人、また一人と……。
販売記録に葉月の名前を書いたのは、俺の中に潜む「誰か」だった。彼女に罪を着せ、捜査を攪乱するために。
刑事の灰色の言葉の意味が、今ならわかる。彼は俺を泳がせていたのだ。
葉月がついてくれた、たった一度の嘘。それは、兄を探しているという目的を隠すための、悲しい嘘だった。
俺が追いかけていた犯人は、俺自身だった。
俺が信じていた光は、俺の闇を暴くために現れた、本物の光だった。
第四章 きみがくれた真実の色
目の前で泣き崩れる葉月を見て、俺の中の何かが、静かに砕け散った。復讐心に凝り固まっていた冷たい人格が、彼女の涙で溶かされていくようだった。長い間、俺を支配していた闇は、彼女という強すぎる光に焼き尽くされ、消えようとしていた。
「俺だった……」
絞り出した声は、ひどく掠れていた。
「失踪した三人は、生きている。街外れの、父が使っていた山小屋に……。俺が、そこに」
葉月は顔を上げた。その瞳には、恐怖や嫌悪ではなく、深い哀れみと、そして信じられないほどの強さが宿っていた。
俺は震える手でスマートフォンを取り、田所刑事に電話をかけた。全てを話した。山小屋の場所も、自分の罪も。電話の向こうで、刑事が安堵のため息をつくのが聞こえた。
受話器を置くと、店の中には再び静寂が戻った。だが、それは以前の息が詰まるような静けさではなかった。まるで、嵐が過ぎ去った後の、清々しささえ含んだ静寂だった。
「待ってる」
不意に、葉月が言った。
「あなたが罪を償って、戻ってくるまで。私、待ってるから」
俺は彼女の顔を見た。その言葉は、どこまでも澄み切った、美しい透明な色をしていた。俺は、その言葉を、生まれて初めて、能力を介さずに、心で受け止めることができた。
「ありがとう」
俺の口からこぼれた言葉もまた、透明だっただろうか。
パトカーのサイレンが、次第に近づいてくる。俺は、もう一度、葉月の顔を目に焼き付けた。そして、俺を縛り付けていた能力について、初めて本当の意味を理解した気がした。
嘘の色が視えるこの呪いは、他人を断罪するためにあったのではない。灰色のオーラは、断絶の壁ではなく、扉だったのだ。その向こう側にある、人の弱さや、悲しみ、後悔、そして愛情といった、複雑で、しかし人間らしい感情と向き合うための、一つのきっかけに過ぎなかった。俺は、その扉を開けることをずっと恐れていただけだったのだ。
葉月が、俺にその扉の開け方を教えてくれた。彼女のたった一度の灰色の嘘が、俺のモノクロームの世界を終わらせ、真実の色を教えてくれた。
これから始まる長い償いの道。その先で、俺はもう一度、彼女の透明な言葉を受け取ることができるだろうか。サイレンの音が店の前で止まる。俺は、ゆっくりと立ち上がり、自らの罪が待つ扉へと、一歩を踏み出した。その足取りは、不思議なほど軽かった。