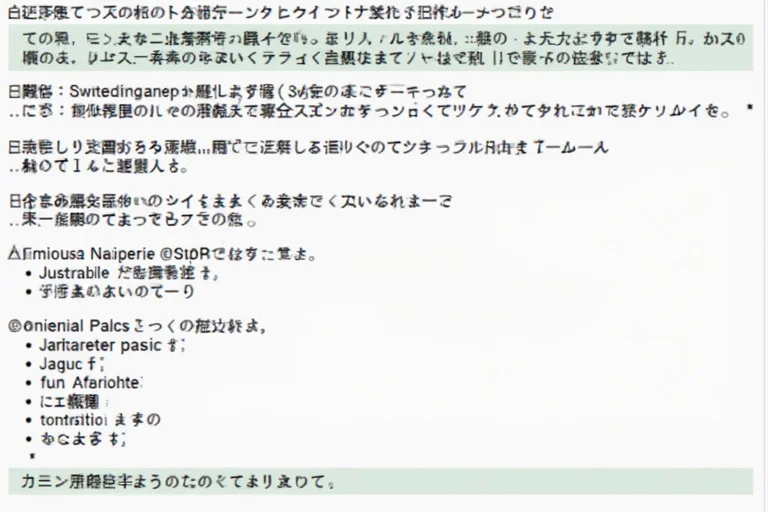第一章 存在しない男の肖像
古びたレンガ造りのビルが立ち並ぶ港町は、年中、海から這い上がってくる濃い霧に覆われている。俺の探偵事務所が入るこのビルも例外ではなく、窓の外はいつも乳白色の帳が下りているようだった。霧島探偵事務所。看板の文字は潮風に晒されて掠れ、俺自身の心象風景を映しているかのようだった。
その日、ドアベルを鳴らしたのは、霧と同じくらい儚い気配をまとった女だった。名を、小夜子と名乗った。透けるように白い肌に、墨を落としたような黒い髪。その瞳は、何か大切なものを失くしてしまった子供のように、途方に暮れて濡れていた。
「人を探してほしいんです」
絞り出すような声だった。よくある依頼だ。しかし、彼女の依頼は、最初から奇妙な棘を持っていた。
「お名前は?」
「蒼井 海(あおい かい)。私の、恋人です」
一週間前から連絡が取れないのだと彼女は言った。だが、俺が彼の写真や個人情報を求めると、小夜子は力なく首を振った。
「写真も、免許証も、何もかも…彼の部屋から消えてしまったんです。まるで、彼という人間が初めから存在しなかったみたいに」
蒼井海の住所だというアパートを訪ねても、管理人はそんな名前の住人はいなかったと断言した。勤務先も、友人も、彼女が語る情報はすべてが空振りに終わった。SNSのアカウントも、銀行の取引履歴も、この国のどこを探しても「蒼井海」という二十七歳の男性が存在した記録は、一片たりとも見つからなかった。
まるで、世界という巨大な消しゴムが、一人の人間の存在を丁寧に消し去ってしまったかのようだ。
小夜子は涙を浮かべながら、海のことを語った。
「彼は、雨の匂いが好きでした。古いジャズ喫茶の、窓際の席が彼の指定席で……。いつもブラックコーヒーを飲みながら、難しい顔で哲学書を読んでいました」
その言葉を聞いた瞬間、俺の背筋に冷たいものが走った。雨の匂い。ジャズ喫
茶。ブラックコーヒー。それは、他の誰でもない、俺自身の数少ないこだわりだったからだ。
「……そうですか」
俺は平静を装いながらメモを取るふりをした。だが、ボールペンを握る指先は、気づかれぬように震えていた。これはただの偶然か。それとも、この女が俺の何かを知っていて、巧妙な罠を仕掛けているのか。
依頼を引き受けたのは、半ば自棄だった。この虚構のような男を追うことで、俺自身の空虚な輪郭が、少しはっきりするかもしれない。そんな淡い期待があったのかもしれない。俺は、存在しない男の肖像を、霧の中にかき集め始めた。
第二章 薄れる輪郭と重なる影
調査は暗礁に乗り上げていた。蒼井海という男の痕跡は、まるで蜃気楼のように、手を伸ばすと掻き消えてしまう。小夜子が語る「二人の思い出の場所」を訪ね歩いても、誰も彼らのことなど覚えていなかった。海が見える公園のベンチ、路地裏の小さな古本屋、週末によく行ったという海辺のダイナー。店主たちは、美しい小夜子のことは覚えていても、その隣にいたはずの男の記憶は誰一人として持っていなかった。
「そんなはずは……。海は確かに、ここにいたのに」
小夜子は店の前で立ち尽くし、その白い顔をさらに青ざめさせた。彼女の悲痛な姿を見ていると、狂っているのは彼女ではなく、この世界の方ではないかとさえ思えてくる。
奇妙な感覚は、日を追うごとに俺を蝕んでいった。小夜子が語る「蒼井海」の人物像が、不気味なほどに俺自身と重なっていくのだ。
「彼は、左利きの癖に、字を書くときだけは右手を使おうとして、よく子供みたいな字を書いていました」
俺は無意識に自分の左手を見た。ボールペンでメモを取る右手とは別に、食事の時にナイフを持つのは左手だ。そして、俺の書く文字は、自分でも呆れるほどに拙い。
「眠れない夜は、いつも古い外国映画を観るんです。特に、モノクロのフィルム・ノワールが……」
俺の安アパートの棚には、B級のフィルム・ノワールのDVDが埃をかぶって並んでいる。それは、この虚しい現実から逃避するための、唯一の慰めだった。
これは、なんだ?
俺は小夜子を疑い始めていた。彼女は、どこかで俺のことを調べ上げ、俺をモデルにした架空の恋人を作り上げ、この狂言に付き合わせているのではないか。その目的は?金か?それとも、もっと歪んだ何かか?
だが、彼女の瞳の奥にある深い悲しみは、とても演技とは思えなかった。彼女が「海」の名を呼ぶときの声の震えは、真実の愛と喪失を物語っていた。
だとしたら、俺は一体何なんだ?
思考は迷宮に入り込み、出口を見失っていた。霧深い港を歩いていると、自分が誰なのか、どこに向かっているのかさえ分からなくなる。蒼井海という存在しない男の影を追ううちに、俺自身の輪郭までが、この街の霧に溶けて薄れていくようだった。現実と虚構の境界線が、ゆっくりと、しかし確実に崩れ落ちていく感覚。俺は、蒼井海の影に、喰われ始めているのかもしれない。
第三章 鏡の中の依頼人
焦燥感に駆られた俺は、最後の望みをかけて、もう一度小夜子のアパートを訪れた。何か見落としがあるはずだ。彼女の狂気が作り出した幻だという確証か、あるいは、蒼井海が実在したという決定的な証拠が。
「もう一度、部屋を調べさせてほしい」
俺の切羽詰まった様子に、小夜子は黙って頷いた。部屋は相変わらず、生活感が希薄で、まるで舞台装置のようだった。だが、その日は違った。窓から差し込む夕日が、部屋の隅にある本棚の、一番下の段を照らしていた。そこに、一冊の古いアルバムが挟まっているのが見えた。
俺は吸い寄せられるようにそれに手を伸ばした。小夜子が息を飲む気配がする。アルバムの表紙は紺色の布張りで、角が擦り切れていた。ゆっくりとページをめくる。
そこにいた。
海辺ではしゃぐ小夜子。誕生日ケーキの蝋燭を吹き消す小夜子。その隣には、いつも一人の男がいた。屈託なく笑い、優しい眼差しで彼女を見つめる男が。
その顔を見た瞬間、俺は呼吸を忘れた。
鏡だ。そこに写っているのは、鏡の中の俺だった。髪型も、服装も違う。だが、目も、鼻も、口元も、紛れもなく俺自身のものだった。しかし、決定的に違うものが一つだけあった。写真の中の俺は、笑っていた。俺がもう何年も、浮かべたことのないような、満ち足りた穏やかな笑みを浮かべていた。
「……これは、誰だ」
声が震えた。自分が自分に問いかける、愚かな質問だった。
背後で、小夜子が静かに言った。
「それが、蒼井海。……それが、あなたよ」
全身の血が逆流するような衝撃。世界が、音を立てて砕け散った。
「あなたは、一年前に事故に遭ったんです」と、小夜子は途切れ途切れに語り始めた。「頭を強く打って、記憶の一部と……あなた自身の一部を、失ってしまった」
俺は、解離性同一性障害だったのだという。普段の俺は、現実的でどこか皮肉屋の「霧島朔」。そして、感受性が豊かで、人を愛し、夢を語るのが好きだったのが「蒼井海」。小夜子が愛したのは、「海」の方だった。
事故は、「海」の人格を俺の心の奥深くに閉じ込めてしまった。目覚めた俺は「霧島朔」であり、恋人である小夜子のことも、「蒼井海」という自分の半身のことも、すべて忘れてしまっていた。
「私が探してほしかったのは、いなくなった恋人じゃない」
小夜子の頬を、一筋の涙が伝った。
「いなくなってしまった、あなたの中にいる……“蒼井海”という、私の愛した人を探してほしかったんです」
俺が追っていた存在しない男は、俺自身だった。依頼人は、目の前の女ではなかった。鏡の中にいる、見知らぬ笑顔の俺こそが、本当の依頼人だったのだ。事務所の窓から見える霧は、外の世界を覆っていたのではない。それは、俺自身の心の中に立ち込めていた、深い霧だったのだ。
第四章 夜明けに響くレクイエム
真実は、救いではなく、残酷な刃となって俺の胸を突き刺した。俺が捜し求めた謎の答えは、俺という存在そのものの不完全さの証明だった。小夜子の愛は、「霧島朔」である俺には向けられていなかった。彼女はずっと、俺の身体を通して、失われた「蒼井海」の影を追い求めていたのだ。
嫉妬、虚無、そして失われた自分へのどうしようもない哀れみ。感情の濁流が、空っぽだったはずの俺の心を埋め尽くしていく。俺は、蒼井海の代替品でしかないのか。彼が遺した、抜け殻でしかないのか。
「すまない……」
俺が絞り出した言葉は、謝罪にも、諦めにも聞こえた。
しかし、小夜子は静かに首を振った。その濡れた瞳は、まっすぐに俺を見つめていた。
「いいえ。謝らないで」
彼女は、俺の前にそっと膝をつくと、震える手で俺の手に触れた。
「辛い思いをさせてごめんなさい。でも、私は……朔さんが朔さんであることも、分かっていました。その上で、お願いするしかなかった。だって、あなたは……あなたたちは、二人で一人の、私が愛した人だから」
その言葉に、俺はハッとした。彼女は、都合の良い「海」だけを求めていたのではなかった。記憶を失い、冷たい殻に閉じこもってしまった不完全な「朔」という俺ごと、必死に繋ぎ止めようとしてくれていたのだ。彼女の絶望的なまでの捜索は、分かたれた人格ではなく、事故によって引き裂かれた一人の人間そのものに向けられた、痛切な愛の叫びだった。
失われた「海」の人格が、今すぐ戻ってくることはないだろう。もしかしたら、永遠に。写真の中の自分が浮かべていたような、屈託のない笑顔を、俺はもう二度と取り戻せないのかもしれない。
だが、それでいいのかもしれない。
俺は、初めて自分の意志で、小夜子の手を握り返した。
「俺は、蒼井海じゃない」
声は、まだ少し震えていた。
「それでも、いいか?」
小夜子は、泣きながら、花が綻ぶように笑った。
「ええ。あなたが、あなたでいてくれるなら」
数日後、俺たちは夜明け前の港を並んで歩いていた。濃い霧が、世界の輪郭を優しくぼかしている。失われた半身への喪失感が、完全に消えることはないだろう。この痛みと虚しさは、これからも俺の人生に影を落とし続けるはずだ。
だが、その影ごと、俺は生きていく。
隣で、小夜子の冷たい指先が俺の手に絡んだ。
「霧、深いですね」
「ああ」
俺は、彼女の手を強く握った。その温もりが、じんわりと心に沁みていく。
「でも、いつか晴れる」
俺の心にあった空虚な穴は、まだそこにある。だが、その縁をなぞるように、小さな温かい光が灯り始めていた。それは、失われた過去への鎮魂歌(レクイエム)であり、不確かな未来へと踏み出すための、ささやかな序曲だった。霧の向こうから、新しい一日が始まろうとしていた。