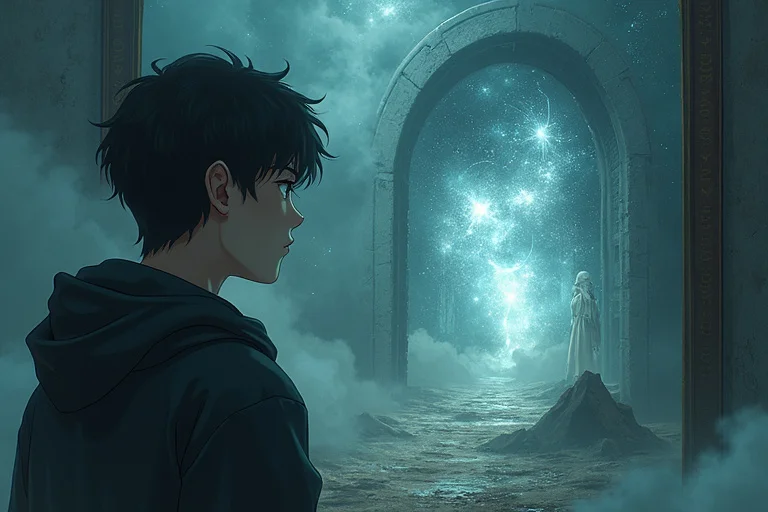第一章 密やかなる肉じゃがの味
水島朔(みずしま さく)の日常は、インクの匂いと紙の質感、そして無数の文字が放つ、密やかな「味」で構成されていた。校正者である彼にとって、文字は単なる記号ではない。ひらがなは淡い甘みを、漢字は複雑な苦味や渋みを、句読点はぴりりとした刺激を、舌の上ではなく、脳の奥深くで感じさせる。共感覚。そう診断されたのは、物心ついた頃だった。誰にも理解されぬその感覚は、朔を世界から切り離し、三十を過ぎた今も、彼は静かな孤島に一人で住んでいるような男だった。
その日、郵便受けに差し込まれていた一通の無地の封筒が、彼の静寂を乱暴に引き裂いた。差出人の名はない。切り貼りされた活字が、白い便箋の上で無機質に並んでいた。
『お前の秘密を、味わっている』
その文字列を目で追った瞬間、朔の口内に、爆発的な懐かしさが広がった。それは、ありふれた味ではない。醤油の香ばしさと味醂の優しい甘み、ほろりと崩れるじゃがいも、そして後から追いかけてくる生姜の爽やかな刺激。十五年前に死んだはずの、母が作った肉じゃがの味だった。
朔は便箋を取り落とした。心臓が氷の塊に握り潰されたように痛む。母の肉じゃが。それは、朔にとって世界の中心であり、絶対的な安息の味だった。母が死んで以来、どんな高級店の肉じゃがも、どんなにレシピを忠実に再現しても、決して朔の感覚を満足させることはなかった。あの味は、母と共に永遠に失われたはずだった。
誰だ。誰がこれを?
母の味を知っている人間は、この世に自分しかいない。共感覚のことは、ごく一部の医療関係者以外には話していない。そもそも、文字から特定の個人の料理の味を再現するなど、可能なのだろうか。
朔は震える手で便箋を拾い上げた。切り貼りされた活字は、まるで嘲笑うかのように、そこに存在している。「秘密」という言葉が、鉛のように重くのしかかる。彼には、誰にも言えない秘密があった。母が交通事故で亡くなったあの日、家を飛び出す母に、彼は酷い言葉を投げつけた。些細な喧嘩。子供じみた反抗。それが、母との最後の会話になった。その後悔は、十五年間、朔の心を蝕み続けていた。
恐怖と混乱の中、朔は確信する。これは単なる悪戯ではない。差出人は、朔の最も深い場所を知り、そして、死んだ母の魂そのものを弄んでいるのだと。口の中に残る肉じゃがの甘い後味は、今や不気味な毒のように、彼の全身を侵食し始めていた。
第二章 焦げ付いた卵焼きの嘘
最初の脅迫状から一週間。朔は眠れない夜を過ごしていた。警察に相談したが、「悪質な悪戯だろう」と真剣に取り合ってはもらえなかった。共感覚の話をすれば、精神的な問題だと一蹴されるのが目に見えていた。
仕事に身が入らず、ゲラ刷りの文字の味が、すべて砂のようにざらついて感じられた。孤独が濃霧のように部屋を満たし、壁の染みさえもが監視の目のように思える。彼は古いアルバムを開き、母の写真を眺めた。優しく微笑む母。その笑顔を見るたびに、胸が締め付けられる。
そんなある日、二通目の封筒が届いた。今度も無地の封筒に、切り貼りされた活字。
『あの日の嘘も、味わい深い』
その文字を読んだ朔の脳を、新たな味が貫いた。ほんのりとした甘さ、だしの豊かな香り、そして絶妙な火加減でつけられた、香ばしい焦げ目の風味。母が作る、少しだけ甘い卵焼きの味だった。朔が風邪を引いた日、運動会のお弁当、何でもない日の朝食。その味は、いつも彼のそばにあった。
だが、「あの日の嘘」という一文が、朔を過去の暗闇へと引きずり込んだ。母が亡くなった事故の日。母との喧嘩の原因は、朔がついた些細な嘘だった。友人と遊ぶ約束を隠していたこと。その嘘に気づいた母は、悲しそうな顔で朔を諭した。反発した朔は、「お母さんなんて大嫌いだ」と叫んで部屋に閉じこもった。それが、母が家を飛び出す引き金になった。
その嘘を知っているのは、自分と母だけのはずだ。差出人は、神か、悪魔か。あるいは、母の亡霊が、十五年の時を経て息子を罰しにきたとでもいうのだろうか。
朔は、自分の過去を徹底的に洗い直し始めた。母の日記、残された手紙、すべてを読み返した。しかし、手掛かりは何一つ見つからない。差出人は、朔の記憶そのものを覗き込んでいるかのようだ。疑心暗鬼が心を蝕み、窓の外を歩く人影にさえ怯えるようになった。自分がおかしくなってしまったのではないか。この味覚は、罪悪感が生み出した幻覚なのではないか。彼の内面世界は、静かに崩壊へと向かっていた。愛と安らぎの象徴だった母の味が、今や彼を苛む呪いとなっていた。
第三章 涙の味と真実のレシピ
三通目の手紙は、葉書だった。活字ではなく、震えるような、見慣れない手書きの文字で、一文だけが記されていた。
『最後の晩餐を、用意した』
そして、裏には古いレストランの地図が描かれていた。そこは、幼い頃、母と二人でよく訪れた、丘の上のレストランだった。今はもう廃墟となっているはずの場所だ。
これは、罠だ。行けば、何が待ち受けているか分からない。だが、行かなければ、この悪夢は永遠に終わらない。朔は、ポケットに小さな護身用のカッターナイフを忍ばせ、震える足で丘へと向かった。
夕暮れの光が、蔦の絡まる廃墟を物悲しく照らしていた。埃っぽい空気の中、ぎしぎしと音を立てる床を踏みしめ、奥へ進む。指定されたテーブルの上には、蝋燭の灯りが一つ揺らめいていた。人影はない。ただ、一冊の使い古されたレシピノートが、ぽつんと置かれているだけだった。
それは、紛れもなく母のノートだった。表紙に書かれた「水島家の味」という文字。ページをめくると、肉じゃが、卵焼き、懐かしい料理の数々が、母の丸みを帯びた文字で記されている。朔は、その一文字一文字から、母の温もりを感じた。
しかし、最後のページだけが異質だった。そこには、葉書と同じ、震えるような見知らぬ筆跡で、こう書かれていた。
「朔へ。この味を、覚えていますか?」
その文字列を目で追った瞬間、朔は経験したことのない味覚に襲われた。
それは、料理の味ではなかった。ただひたすらに、苦くて、塩辛い。喉の奥が締め付けられ、息が詰まる。これは……涙の味だ。とめどなく溢れ、頬を伝い、唇に落ちる、絶望と悲しみの凝縮された味。
「……その味はね、あの子が十五年間、一人で流し続けた涙の味よ」
背後から、静かな声がした。振り返ると、そこに立っていたのは、母の唯一の親友だった、倉田千尋だった。彼女の目もまた、赤く腫れていた。
千尋は、静かに、そしてゆっくりと、すべての真実を語り始めた。
朔の母、美咲は、事故で死んだのではなかった。夫、つまり朔の父親からの長年にわたる暴力に耐えかね、千尋の助けを借りてすべてを偽装し、失踪したのだと。交通事故は、父から逃れるための、命懸けの芝居だった。
「脅迫状は、美咲と私で考えたの。ごめんなさい、怖がらせて。でも、それしか方法が思いつかなかった」
手紙は、脅迫状ではなかった。母から息子への、最後のメッセージだったのだ。
『お前の秘密(=父の暴力という家庭の秘密)を、味わっている(=私もずっと苦しんできた)』
『あの日の嘘(=母が死んだという、世界が信じている嘘)も、味わい深い(=その嘘を背負うのは、本当に苦しい)』
美咲はずっと遠くの街で、息を潜めるように生きていた。朔に会いたくても、父の監視の目があり、会えなかった。そして今、彼女は重い病を患い、余命いくばくもないのだという。最後に一目、息子に会いたい。そして、自分の本当の人生を、本当の「味」を伝えたかった。
「肉じゃがも、卵焼きも、あなたを愛していた幸せな記憶の味。でもね、美咲の人生は、それだけじゃなかった。この涙の味が……彼女の人生そのものだったの」
朔は、その場に崩れ落ちた。母は、生きていた。そして、想像を絶する苦しみの中にいた。自分を孤独にしたと思っていた共感覚は、母からの痛切なメッセージを受け取るための、唯一の架け橋だったのだ。彼の内面世界が、ガラガラと音を立てて崩れ落ち、そして、全く新しい形で再構築されていく。涙の塩辛い味が、彼の罪悪感を、孤独を、ゆっくりと洗い流していくようだった。
第四章 未来のレシピ
千尋に導かれ、朔は海辺の小さなホスピスを訪れた。窓から差し込む柔らかな光の中、ベッドに横たわる母は、アルバムで見た頃の面影を残しながらも、ひどく痩せていた。
「朔……」
か細い声で、母は息子の名を呼んだ。十五年ぶりの再会。朔は言葉を見つけられず、ただ母の手を握った。骨張った、冷たい手。しかし、その手から伝わる温もりは、あの頃と何も変わらなかった。
「ごめんなさい……あなたを一人にして。ずっと、嘘をついていて……ごめんなさい」
母の目から、一筋の涙がこぼれた。その涙は、もうあの塩辛い味ではなかった。朔には、それが分かった。
「ううん……」朔は、ようやく声を絞り出した。「僕の方こそ、ごめん。あの日のこと、ずっと……」
母は、静かに首を振った。「いいの。あなたは、何も悪くない。私の、宝物よ」
二人は、失われた十五年を埋めるように、静かに語り合った。父の暴力のこと。逃亡生活の孤独。それでも、遠くから息子の成長を見守ることだけが、唯一の希望だったこと。朔は、母の人生のすべてを受け止めた。彼の心を長年縛り付けていた「母の死」という呪いは、この瞬間、完全に解き放たれた。
数週間後、母は静かに息を引き取った。朔は、涙を流さなかった。母の人生の味を、すべて受け取った今、悲しみだけではない、温かな感情が胸を満たしていたからだ。
葬儀を終えた朔は、自分のアパートに戻り、母のレシピノートを開いた。そして、新しいページに、万年筆でゆっくりと文字を書き始めた。
『水島朔の、新しいレシピ』
その文字を、彼はそっと味わった。
すると、どうだろう。口の中に広がったのは、今まで感じたことのない、穏やかで、澄み切った、温かい味だった。それは、夜明けの光のような、春の若葉のような、希望に満ちた味。
「許し」と「未来」の味だと、朔は思った。
彼の共感覚は、もはや孤独の象徴ではなかった。それは、母が命を懸けて遺してくれた、愛の絆そのものだった。朔はノートを閉じ、窓を開けた。流れ込んできた風が、新しい世界の匂いを運んでくる。彼はもう一人ではない。母の記憶と、数多の「味」と共に、これからを生きていく。彼の舌の上で、いや、心の中で、未来のレシピが、静かに、そして確かな味わいを奏で始めていた。