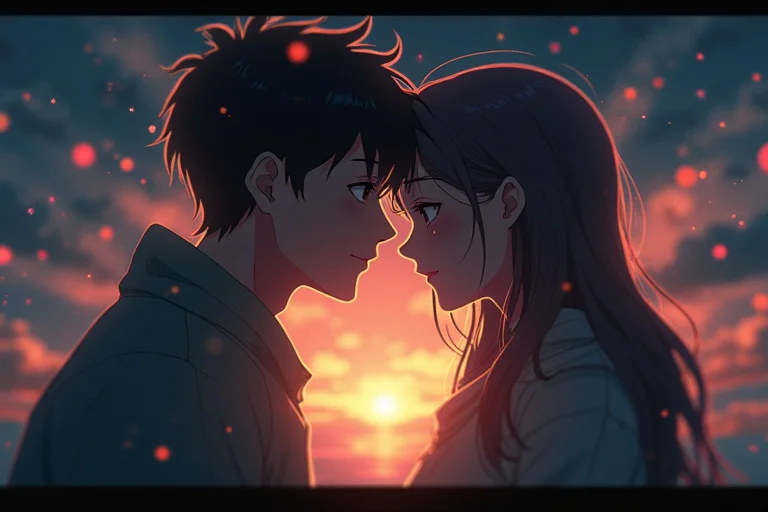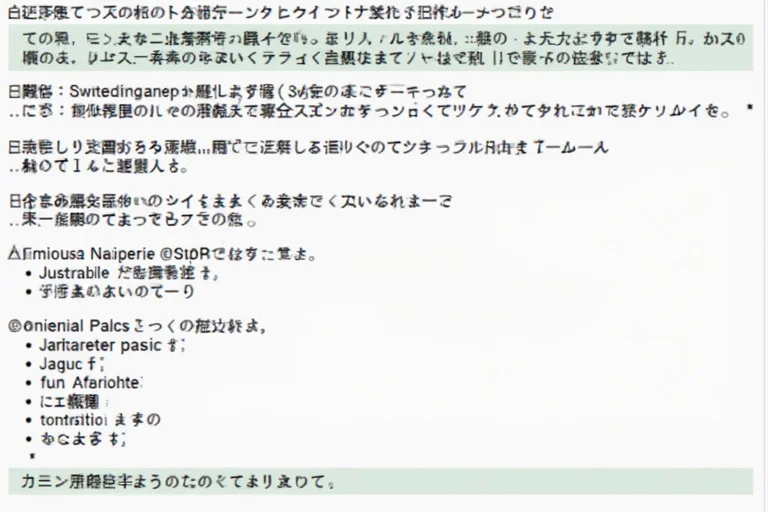第一章 静寂の縮尺模型
倉田湊の指先は、神のそれに似ている、と誰かが言った。ピンセットで1ミリに満たないドアノブを掴み、寸分の狂いなく接着する。息を止め、世界のすべてをこの150分の1の空間に凝縮させる。彼の職業は「再現師」。事件現場をミニチュアで完璧に再現し、警察の捜査資料として納品する仕事だ。現実の惨劇を、硝子のケースに封じ込める静かな儀式。それが湊の日常だった。
今、彼が手掛けているのは、世田谷区で起きた資産家殺人事件の現場だ。血痕の飛び散り方、倒れた椅子の角度、床に散らばるガラス片。湊は写真と資料だけを頼りに、悲鳴さえも聞こえてきそうな生々しい瞬間を、冷たい樹脂と塗料で再構築していく。完璧主義者の彼にとって、この仕事は天職だった。過去の、あの火災の記憶から逃れるための、唯一の聖域でもあった。
深夜、アトリエの静寂を破ったのは、スマートフォンの微かな通知音だった。制作は最終段階に入り、湊はソファで仮眠をとっていた。目を覚まし、ぼんやりとした頭でアトリエの照明をつける。ガラスケースに収められた書斎のミニチュアが、スポットライトに照らされて浮かび上がった。被害者が倒れていた絨毯の上に、何かが見えた。
湊は眉をひそめ、ケースに顔を近づける。そこにあったのは、彼が配置した覚えのない、小さな、小さな黒い羽根だった。まるで、死んだ資産家の魂を運びに来たカラスが落としていったかのような、不吉な存在感。長さはわずか5ミリほど。しかし、完璧に構築された彼の世界において、それは許されざる異物だった。
「……なんだ、これは」
徹夜続きで幻覚でも見ているのか。指で弾き飛ばそうとガラスケースの蓋に手をかけた瞬間、彼は動きを止めた。これはただのゴミや埃ではない。明確な形を持った、羽根だ。湊は自身の記憶を何度も遡るが、こんなものを配置した工程はどこにも存在しなかった。気味が悪い、とだけ思い、彼はその羽根をピンセットで摘み出して捨てた。そして、その夜は妙な胸騒ぎを覚えながら眠りについた。
翌朝、いつものようにニュースを流しながらコーヒーを淹れていると、アナウンサーの冷静な声が湊の耳を突き刺した。
『昨日未明、世田谷の資産家殺人事件の第二の犯行とみられる事件が発生しました。被害者は資産家の元秘書で、自宅マンションで……』
湊はマグカップを持ったまま、画面に釘付けになった。そして、次の言葉に、全身の血が凍るのを感じた。
『……現場には、カラスの羽根とみられる黒い羽根が一枚、残されていました。警察は、犯人が残したメッセージの可能性も視野に……』
湊は、昨夜捨てたはずの、あの小さな羽根の感触を思い出していた。偶然か? いや、偶然にしては出来すぎている。まさか。自分の作ったミニチュアが、これから起こる出来事を、予兆しているというのか? 荒唐無稽な考えを振り払おうとしても、アトリエに鎮座する硝子の箱が、まるで不気味な神託の祭壇のように思えてならなかった。
第二章 滲み出す赤色
「ミニチュアが未来を予言する、ですか」
担当の遠藤刑事は、湊の話を心底呆れたという顔で聞いていた。無理もない。湊自身、自分が何を言っているのか分からなかった。しかし、あの黒い羽根の一致は、彼の合理的な精神を根底から揺さぶるには十分だった。
「疲れているんですよ、倉田さん。あなたの作る模型は芸術品だ。それだけ集中しているんだから、幻覚の一つや二つ……」
「幻覚じゃない!」
思わず声を荒らげた湊に、遠藤は少し驚いたように目を瞬かせた。湊はそれ以上何も言えず、唇を噛んだ。信じてもらえるはずがない。自分ですら、まだ信じられないのだから。
その数日後、新たな依頼が舞い込んだ。今度は連続殺人とは別の、若い女性の失踪事件だった。手がかりが少なく、捜査は難航しているという。湊は依頼を受け、彼女が最後に目撃された自室の再現に取り掛かった。依頼を受けたのは、自分の能力を確かめたいという、恐ろしい好奇心からだった。
壁紙の模様、ベッドに残されたシワ、化粧台に並ぶコスメの配置。湊はいつものように、神経質なまでの精度で部屋を再現していく。だが、今回はただの作業ではなかった。彼は祈るような気持ちで、ミニチュアのどこかに現れるであろう「異変」を待ち構えていた。
三日目の夜だった。作業を終え、アトリエのデスクでうたた寝から目覚めた湊は、ふとミニチュアの部屋に違和感を覚えた。ベッド脇の、白い壁紙。そこに、ごく小さな、しかし見間違えようのない赤いシミが滲み出していた。まるで、壁の内部から血が染み出してきたかのように。
心臓が大きく跳ねた。湊は震える手でスマートフォンを掴み、遠藤に電話をかけた。
「遠藤刑事、失踪した女性の部屋だ! ベッドの横の壁を調べてくれ! 何かあるはずだ!」
「倉田さん、夜中に何を……」
「頼む! 信じられないのは分かっている! でも、もしこれが本当なら、彼女は……手遅れになるかもしれない!」
湊の常軌を逸した必死さに何かを感じたのか、遠藤は「……分かった」とだけ答えた。
翌日、遠藤からかかってきた電話の声は、憔悴しきっていた。
「……あんたの言った通りだった。壁の中から、彼女が見つかった。……どうして、分かったんだ」
その言葉で、湊の疑念は確信に変わった。これは呪いか、あるいは天啓か。いずれにせよ、自分だけが未来の惨劇を覗き見ることができる。罪悪感と、奇妙な使命感が彼の胸を締め付けた。もう、ただの再現師ではいられない。この指先は、悲劇をなぞるだけではなく、未然に防ぐためにあるのかもしれない。湊は、硝子の向こう側に見える予兆と、たった一人で対峙することを決意した。
第三章 割れた鏡像
連続殺人事件は三件目に至り、世間を震撼させていた。犯人は「カラス」と呼ばれ、その劇場型の犯行はメディアを賑わせていた。湊は警察から提供される膨大な資料に目を通し、犯人像をあぶり出そうと躍起になっていた。被害者三名には、表向きの接点は見当たらない。年齢も職業もバラバラだ。
湊は、三つの事件現場のミニチュアをアトリエに並べ、睨みつけるように観察を続けた。しかし、新たな予兆は一向に現れなかった。犯人の次の手がかりが掴めない。焦りが募る。まるで、犯人が湊の能力に気づき、嘲笑っているかのようだ。
「なぜ、何も見えない……」
苛立ちに任せて、湊は過去の資料を床にぶちまけた。散らばった書類の中に、一枚の古い新聞記事が紛れ込んでいるのに気づいた。それは、彼が「再現師」になるきっかけとなった、忌まわしい記憶の断片。十年前に彼が設計した商業ビルで起きた、火災事故の記事だった。安全管理の不備が指摘され、多くの死傷者を出した大惨事。彼はあの事故で、炎の中に消えていく一人の少女を、ただ見ていることしかできなかった。
その記事に印刷された、犠牲者の名前のリスト。湊は、何気なくその名前を目で追った。そして、息を呑んだ。一人、また一人と、指で名前をなぞるたびに、全身の血の気が引いていく。
連続殺人事件の第一の被害者、資産家。彼は、ビルの建設に関わったデベロッパーの役員だった。
第二の被害者、元秘書。彼女は、安全基準の報告書を改竄した疑いのある議員の秘書だった。
そして第三の被害者。彼は、消防設備の点検を怠った管理会社の社員だった。
全員、あの火災事故の関係者だ。
点と点が繋がり、恐ろしい線を描き出す。これは、復讐だ。あの事故で人生を狂わされた誰かによる、計画的な復讐殺人。では、なぜ自分のミニチュアに予兆が現れたのか。それは、自分がこの事件の「当事者」だからではないのか。設計者として、事故の責任の一端を担うべき存在。心を閉ざし、ミニチュアの世界に逃げ込んだ、罪人。
だとしたら、犯人の最後のターゲットは――。
湊は、自分の全身が冷たい汗で濡れるのを感じた。震える視線を、アトリエの隅に向けた。そこには、数年前に趣味で作った、このアトリエ自身のミニチュアが置かれていた。ガラスケースの中で、小さな机に向かう「湊自身」の人形が、精巧に再現されている。
その、人形の背後に。
いつの間にか、一体の黒い影のような人形が、音もなく立っていた。
ゾッとするほどの悪寒が背筋を駆け上った、その瞬間。背後で、アトリエの重い扉が、軋みながらゆっくりと開く音がした。
第四章 不完全な救済
振り向いた湊の目に映ったのは、痩せた青年の姿だった。フードを目深にかぶり、その顔には深い絶望と憎しみが刻まれている。その顔に、湊は見覚えがあった。火災事故の犠牲になった少女の、兄。確か名前は、健太。
「……やっぱり、あなただったか」
湊の声は、自分でも驚くほど静かだった。
「あなたは、妹を見殺しにした。あのビルを設計したあなたが、安全なはずの避難経路を、炎の回廊に変えたんだ」
健太の手には、カッターナイフが鈍く光っていた。その瞳は、復讐の炎で揺らめいている。
「僕だけが、生き残った。あの日から、僕の時間は止まったままだ。責任を負うべき人間たちが、のうのうと生きているのが許せなかった」
健太が、一歩、また一歩と距離を詰めてくる。湊は後ずさり、ミニチュアが並ぶ作業台に背中をぶつけた。硝子のケースがガシャンと音を立てて揺れる。その瞬間、湊の脳裏に、ミニチュアの中の光景がフラッシュバックした。床に倒れる自分の人形。飛び散る赤い塗料。それは予兆。だが、もう逃げることはできない。
健太がナイフを振り上げた。湊は目を閉じる代わりに、彼の目を見据えた。ミニチュア作りで培われた、コンマ数ミリのズレも見逃さない観察眼。それが、健太の肩の微かな動き、筋肉の収縮を捉えていた。
「右だ」
湊は身体をひねり、刃先が頬を掠めるのを感じながら、健太の腕を掴んだ。もつれ合うようにして、二人は床に倒れ込む。
「殺せばいい!」湊は叫んだ。「僕を殺して、君の復讐が終わるなら! でも、君の妹さんは戻らない! 君の心の穴は、決して埋まらない!」
馬乗りになった健太の動きが、一瞬だけ止まった。
「僕もずっと、逃げてきたんだ」湊は続けた。「あの日から。君と同じように、僕の時間も止まっていた。ミニチュアの世界に閉じこもって、過去を完璧に再現することしかできなかった。君の痛みは、僕の罪だ。僕が一生、背負っていく」
湊の告白は、懺悔だった。初めて、彼は自分の過去と、その罪と向き合っていた。健太の瞳から、憎しみの炎が揺らぎ、代わりに涙の膜が張るのが見えた。彼が握りしめたナイフから、力が抜けていく。
その時だった。アトリエの扉が勢いよく開け放たれ、遠藤刑事が雪崩れ込んできた。健太は抵抗することなく、静かに取り押さえられた。
事件は解決した。だが、湊の世界は元には戻らなかった。
彼は「再現師」の仕事を辞めた。アトリエはがらんどうになり、あの精巧なミニチュアたちはすべて処分された。ただ一つ、窓際に残されたものを除いて。
それは、火災が起きる前の、あの商業ビルのミニチュアだった。未完成で、壁も塗装されていない、不完全な模型。
その中には、三体の人形が置かれていた。笑顔で兄の手を引く少女。その隣で、少し照れくさそうに笑う健太。そして、少し離れた場所で、未来への希望に満ちた顔で設計図を広げる、若い頃の湊。
あり得たかもしれない、「もしも」の世界。
湊の指先は、もう未来の惨劇を予兆しない。彼は硝子のケースの中から、現実の世界へと歩み出したのだ。過去を完璧に再現することは、もうやめた。不完全なままでいい。傷だらけの指先で、彼はこれから、温もりのある不確かな未来を、少しずつ組み立てていくのだろう。窓から差し込む夕日が、小さな人形たちを、優しく照らしていた。