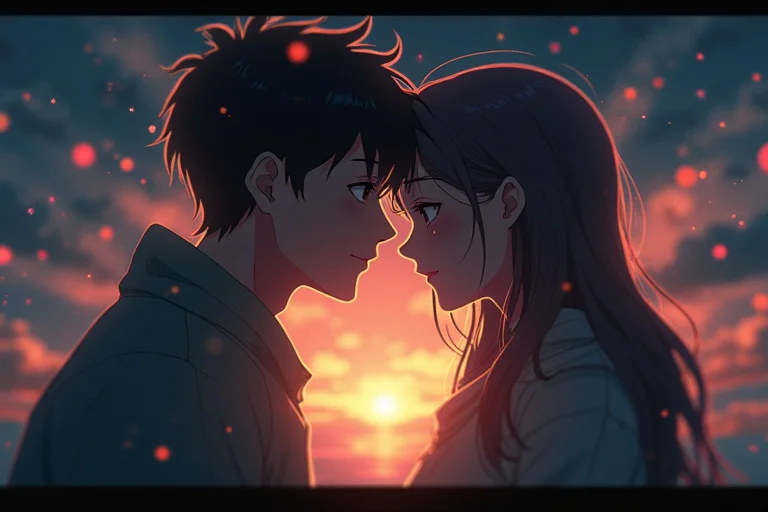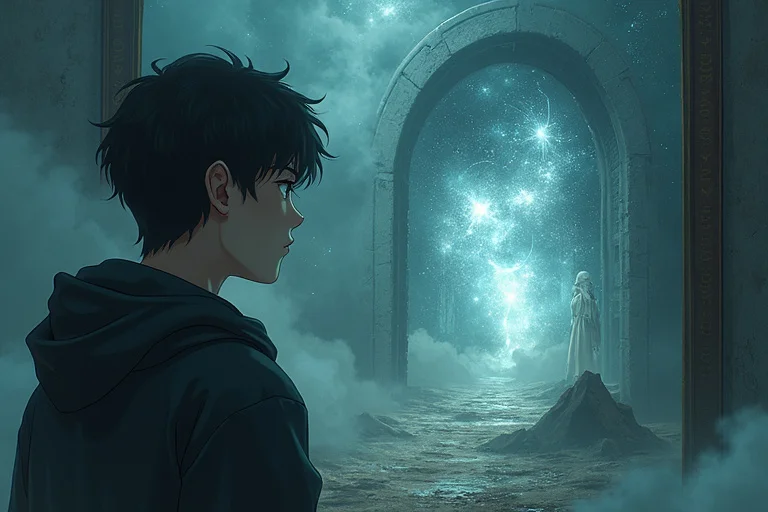第一章 静寂を破る音
神保町の裏路地に佇む古書店『彷徨書房』の主、神代響介にとって、世界は絶え間ない不協和音で満たされていた。それは比喩ではない。彼には、人のつく嘘が、耳障りなノイズとして物理的に聞こえるのだ。高低もリズムもバラバラの、爪で黒板を引っ掻くような不快な音。そのせいで、彼はいつしか人を遠ざけ、古書の静寂とインクの匂いだけを友として生きてきた。本は嘘をつかない。それが唯一の救いだった。
ある雨の日の午後、その静寂は破られた。ドアベルが澄んだ音を立て、湿った空気と共に一人の女性が入ってきた。ショートボブの黒髪が艶やかで、大きな瞳には雨粒のような憂いが宿っている。名を、水瀬美咲と名乗った。
「すみません、古い日記の解読をお願いしたくて……」
彼女が差し出したのは、革の装丁がひび割れた手帳だった。響介は無言で受け取り、ページを繰る。そこには、彼の知らない古い時代のインクで、暗号めいた文字列がびっしりと並んでいた。
「亡くなった祖父の遺品なんです。何か大切なことが書かれているような気がして」
その言葉が、響介の鼓膜を震わせた瞬間、彼は息を呑んだ。
音が、しない。
不協和音のかけらもない。彼女の声は、まるで磨き上げられた水晶のように透明で、一点の曇りもなかった。それは、響介がこの世界に生まれてから一度も経験したことのない、完全な調和の音だった。
彼は驚きに顔を上げた。目の前の女性は、不安げにこちらを見つめている。彼女の心拍すら聞こえそうな静寂。この人は、嘘をついていない。心の底から、一欠片の偽りもなく、そう信じている。
「……お預かりします」
響介は、掠れた声でそう答えるのが精一杯だった。彼の灰色の世界に、初めて差し込んだ一筋の光。その光が、後に全てを焼き尽くす劫火になるとも知らずに。彼の孤独な城の壁に、最初の亀裂が入った瞬間だった。
第二章 不協和音の追跡者
日記の解読は、困難を極めた。祖父が独自に考案したらしい暗号は、響介の知識を総動員しても、一筋縄ではいかなかった。美咲は毎日のように店を訪れ、彼の作業を静かに見守った。彼女がそこにいるだけで、響介を取り巻く世界のノイズは嘘のように掻き消え、心は凪いだ。
彼女は自分のことを少しずつ話してくれた。両親を早くに亡くし、唯一の肉親だった祖父も半年前に他界したこと。祖父は寡黙な宝石職人で、生前はあまり話をしなかったこと。彼女の語る言葉は、常に一点の濁りもない、澄み切った音色をしていた。響介は、生まれて初めて他者を完全に信頼するという感覚を味わっていた。この人だけは、信じられる。この人の前では、忌まわしい能力のことを忘れられる。
しかし、平穏は長く続かなかった。ある夜、店を閉めて帰宅する途中、響介は誰かにつけられている気配を感じた。振り返っても、路地に人影はない。だが、背中に突き刺さるような視線は消えなかった。翌日、店は荒らされていた。本棚は倒され、床には古書が散乱していたが、不思議なことに何も盗まれてはいない。狙いは明らかだった。美咲の祖父の日記だ。幸い、日記は彼が自宅に持ち帰っていたため無事だった。
「誰かが、日記の秘密を狙っている」
響介から事情を聞いた美咲は、恐怖に顔を青くした。その表情からも、言葉からも、不協和音は聞こえない。彼女の純粋な恐怖が、響介の庇護欲を掻き立てた。
「大丈夫、僕が必ず君と日記を守る」
その誓いの言葉に嘘はなかった。彼は、自分の静かな世界を侵す見えない敵と、そして何より、美咲という光を守るために、解読の速度を上げた。日記に隠された秘密を突き止め、この悪夢に終止符を打つのだ。
日記の記述は、徐々に核心に近づいていった。「青い涙」と呼ばれる伝説のダイヤモンド。祖父はそれを、ある悪質な組織から守るために隠したのだという。そして、最終ページに記された一節が、ついに隠し場所を示していた。
『最も清らかなる泉、偽りの月の下に眠る』
響介は、美咲と共に祖父の遺した資料を調べ、場所を特定した。それは、郊外にある古い教会の、今は使われていない洗礼盤のことだった。二人でそこへ向かうことを決めた時、響介は美咲の手を固く握った。彼女の体温が、彼の孤独を溶かしていくようだった。世界中の人間が嘘をつこうとも、この温もりだけは真実だと信じられた。
第三章 砕け散るクリスタル
月明かりが、教会のステンドグラスを通して、幻想的な光の帯を床に描いていた。ひんやりとした石の床を踏みしめ、響介と美咲は祭壇の奥にある洗礼盤へと向かう。埃をかぶった大理石の縁に手をかけ、響介は内側の窪みを覗き込んだ。そこには、古びた小さな木箱が鎮座していた。
「あった……!」
美咲が歓喜の声を上げる。響介は慎重に箱を取り出し、蓋を開けた。ビロードの布の上に、月光を浴びて妖しいほど青く輝くダイヤモンドが横たわっていた。息を呑むほどの美しさ。これが「青い涙」。
「ありがとう、響介さん。あなたがいなければ、見つけられなかった」
美咲が微笑みかける。その言葉も、やはり水晶のように澄んでいた。響介は安堵の息をつき、彼女に宝石を手渡そうとした。
その時だった。
カツン、と硬質な音が響いた。美咲が、小さな拳銃を響介に向けていた。銃口の黒い円が、彼の心臓をまっすぐに狙っている。
「……美咲さん? 何の冗談だ?」
彼の声は震えていた。頭が理解を拒否する。彼女の言葉からは、今この瞬間に至るまで、一度も不協和音が聞こえなかった。ありえない。
美咲の唇が、ゆっくりと弧を描いた。それは、響介が今まで見たことのない、氷のように冷たい笑みだった。
「冗談なんかじゃないわ。最初から、これが目的だったもの」
その言葉ですら、澄んだ音色を保っていた。なぜだ。どうして嘘の音がしない。響介の全身を混乱が駆け巡る。
美咲は、まるで心を読んだかのように、くすくすと笑った。
「あなたのその不思議な力、面白いわね。でも、欠陥品よ。私の言葉が真実に聞こえたのは、私が心の底から、本気で自分を騙していたから」
「……何を、言っている?」
「私は『祖父の遺した秘密を探す、か弱く善良な孫娘』。私はずっと、そう自分に信じ込ませてきたの。あなたに会う前から、ずっと。自分自身に対する完璧な自己暗示。だから、私の言葉に嘘は混じらない。だって、私自身がそれを真実だと信じ切っているんですもの」
世界が、音を立てて崩れ落ちた。
響介が信じた光。彼が唯一、真実だと感じた調和の音。その全てが、最も巧妙に作り上げられた嘘だった。彼の能力は、「客観的な嘘」ではなく、「話者が嘘だと認識している言葉」にしか反応しない。自己欺瞞という、最も根深い嘘の前では、全くの無力だったのだ。
信じていたものが、足元から砕け散る。水晶だと思っていたものは、ただのガラスの欠片だった。彼女の瞳に宿っていた憂いは、彼を欺くための演技。彼女の澄んだ声は、彼を操るための呪文。
「祖父は、組織を裏切ってこのダイヤを独り占めしたのよ。私は、ただそれを取り返しに来ただけ」
美咲は冷徹に言い放ち、響介の手から木箱を奪い取った。不協和音に満ちた世界で、唯一の安息所だと思っていた場所が、最も深く暗い奈落の底だった。絶望が、響介の全身を凍てつかせた。
第四章 沈黙の対話
背後で、教会の重い扉が開く音がした。複数の男たちが、足音を忍ばせて入ってくる。美咲が言っていた「組織」の人間だろう。彼らは、漁夫の利を得ようと後をつけてきたのだ。
「ダイヤを渡せ、小娘」
リーダー格の男が、低い声で言った。美咲の顔から、一瞬だけ余裕が消える。彼女も、ここまで計算してはいなかったのかもしれない。三つ巴の睨み合いが、張り詰めた空気の中で始まった。
響介は、呆然と立ち尽くしていた。もはや、耳から聞こえる音などどうでもよかった。能力が、世界が、自分自身が、何もかも信じられなかった。
だが、その時。彼は見た。拳銃を構える美咲の指が、かすかに震えているのを。冷徹な仮面の下で、彼女の瞳の奥に、怯えと孤独の色が揺らめいているのを。
彼女もまた、嘘の鎧で自分を守らなければ生きていけなかった、孤独な人間なのかもしれない。自己欺瞞という名の牢獄に、自らを閉じ込めて。
響介の中で、何かが変わった。
彼は能力に頼るのをやめた。音を無視し、ただ目の前の人間を、自分の目と心で見つめた。
そして、静かに口を開いた。
「そのダイヤは、偽物だ」
彼の言葉に、男たちと美咲の視線が一斉に突き刺さる。
「祖父の日記には、続きがあった。最後のページは、インクに特殊な薬品を混ぜてある。光にかざすと、本当のメッセージが浮かび上がるんだ」
もちろん、そんな事実はない。完全な、でっち上げだ。だが、彼の声には奇妙な説得力があった。それは、彼が生まれて初めて、他者を欺くために、自分の意志で嘘をついたからだった。
一瞬の動揺が、その場を支配する。その隙を、響介は見逃さなかった。彼は祭壇の燭台を掴むと、男たちに向かって力任せに投げつけた。金属の塊がけたたましい音を立てて床に転がり、男たちの注意がそちらに向く。その瞬間に、響介は美咲の腕を掴み、叫んだ。
「逃げるぞ!」
美咲は一瞬抵抗したが、彼の真に迫った瞳に何かを感じたのか、無言で従った。二人は教会の裏口から、夜の闇へと飛び出した。
事件は、響介が警察に匿名で通報したことで決着した。「青い涙」は無事に回収され、組織の男たちも、そして美咲も逮捕された。
数日後、響介は『彷徨書房』のカウンターで、静かに本を読んでいた。ドアベルが鳴り、客が入ってくる。その客が発する言葉からは、相変わらず不協和音が聞こえた。日常の、些細な嘘の音。
しかし、響介はもう顔をしかめなかった。
彼は、美咲との一件で学んだのだ。音が真実を語るとは限らない。沈黙が偽りであるとも限らない。そして、嘘の裏側には、時に悲しいほどの渇望や、守りたい何かがあることも。
彼の能力は呪いではなかった。ただ、世界が奏でる複雑なソナタの一つのパートを、彼だけが鮮明に聞き取れるというだけのこと。不協和音もまた、音楽の一部なのだ。
響介は客に向かって、静かに顔を上げた。そして、ごく自然に、柔らかく微笑んだ。
「いらっしゃいませ」
不協和音に満ちた世界は、何も変わらない。だが、それを受け止める彼の心は、確かに変わっていた。ノイズの向こう側にある、人の心の微かな旋律に、彼は今、耳を澄まそうとしていた。