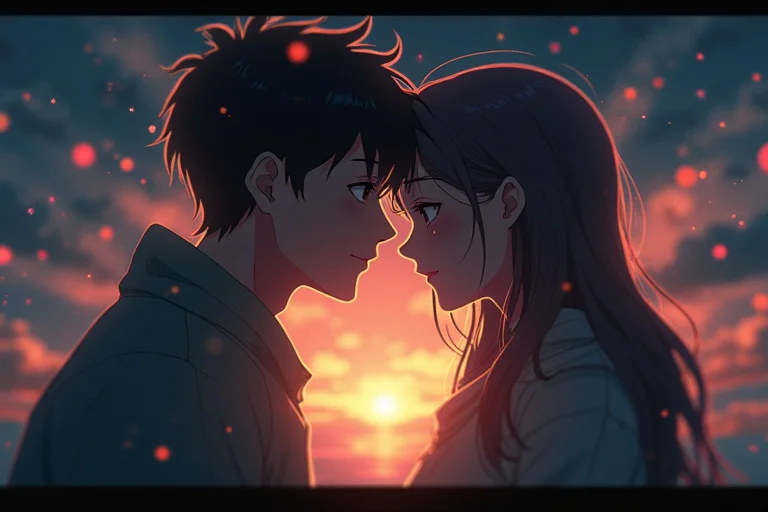第一章 不協和音の黒
音無奏(おとなし かなで)の世界は、音で彩られていた。彼にとって、音は単なる空気の振動ではなかった。それは色であり、形であり、手触りだった。ピアノの調律師である彼にとって、その共感覚(シナスタジア)は天賦の才であり、同時に逃れられない呪いでもあった。ドの音は燃えるような赤、ソの音は澄み切った空の青。彼は鍵盤に触れるたび、指先から溢れ出す色彩の洪水の中で生きていた。
その日、奏は古い洋館に住む常連客、柏木夫人のピアノを調律していた。古いが手入れの行き届いたスタインウェイは、調整を終えると絹のような琥珀色の音色を奏でた。
「ありがとう、音無さん。このピアノもあなたに来てもらうと嬉しそうに歌うわ」
上品な夫人の声は、ラベンダー色の柔らかな霧のようだった。
「とんでもないです。素晴らしいピアノですから」
奏が道具を片付けていると、部屋に快活な声が飛び込んできた。
「おばあちゃま、ただいま!」
振り返ると、太陽をいっぱいに浴びた向日葵のような少女が立っていた。柏木夫人の孫娘、美咲だ。彼女の声は、奏の網膜に鮮やかなレモンイエローを散らした。純粋で、一点の曇りもない、生命力に満ちた色。
「あら、美咲。こちら、調律師の音無さんよ」
「はじめまして!」
屈託のない笑顔に、奏は少しだけ頬を緩めた。彼の世界では、人の声ほど雄弁なものはない。美咲という少女が、どれほど心根の明るい人間かが、その色彩だけで伝わってきた。
洋館を辞し、夕暮れの雑踏に紛れた時だった。それは、突如として訪れた。
背後から聞こえてきた、低く掠れた鼻歌。何の変哲もないメロディのはずだった。だが、その音が奏の鼓膜を震わせた瞬間、彼の世界から一切の色が消え失せた。
視界が、漆黒のベルベットで覆われたように真っ暗になる。街の喧騒、車のクラクション、人々の話し声、全てが真空に吸い込まれたかのように消え、絶対的な無音だけが支配する。それは「黒い色」ですらなかった。色彩と音の「不在」。世界の死。
全身の血が凍りつくような感覚に、奏は思わず立ち尽くす。数秒後、世界は唐突に色と音を取り戻したが、心臓は警鐘のように激しく鳴り響いていた。震える手で振り返るが、雑踏の中に紛れたのか、鼻歌の主は見当たらない。ただ、すれ違った男の痩せた背中だけが、記憶の隅に焼き付いていた。
あれは何だ? 今まで感じたことのない、冒涜的なまでの「無」。
その夜、奏は悪夢にうなされた。黒い何かが、彼の愛する音と色を次々と喰い尽くしていく夢。
翌朝、テレビのニュースが、彼の悪夢を現実のものとして突きつけた。
『昨日夕方から、都内に住む女子高生、柏木美咲さんの行方が分からなくなっており、警視庁は事件に巻き込まれた可能性も視野に捜査を開始しました』
画面に映し出された美咲の屈託のない笑顔。奏の脳裏で、あの鮮やかなレモンイエローが、昨日の「無音の黒」に塗り潰されていくイメージが浮かび、彼は吐き気を堪えて洗面所に駆け込んだ。あの黒は、ただの不協和音などではない。あれは、破滅の前兆だ。
第二章 軋む世界の弦
奏は自室に閉じこもった。防音仕様の壁が、外の世界の色彩から彼をかろうじて守ってくれていた。だが、静寂は記憶を鮮明にする。あの「無音の黒」の感覚が、冷たい触手のように思考に絡みついて離れない。
警察に話すべきか。だが、何を?「犯人の鼻歌が、僕の世界を黒い無音に変えたんです」とでも言うのか。狂人扱いされるのが関の山だ。彼の共感覚は、親しい人間にさえ打ち明けたことのない、孤独な秘密だった。
それでも、美咲のあのレモンイエローの声が脳裏から消えなかった。純粋な光のような色彩が、あの冒涜的な黒に呑まれたかもしれないと思うと、胸が張り裂けそうだった。いてもたってもいられず、奏は街に出た。手掛かりは、痩せた男の背中と、あの鼻歌だけ。あまりに曖昧で、無謀な捜索だった。
街は、彼にとって暴力的な色彩の奔流だった。怒号は汚泥のような茶色、けたたましい広告の音声はけばけばしいマゼンタ、人々の無関心な会話は濁った灰色。彼は人混みを避け、神経を極限まで研ぎ澄ませた。全ての音に耳を傾け、あの「黒」の気配を探す。それは、光の中に一点の闇を探すような、気の遠くなる作業だった。
数日が過ぎ、捜査に進展はないというニュースだけが流れた。奏の心身は摩耗していく。眠りは浅く、食事も喉を通らない。調律の仕事も手につかず、キャンセルが続いた。ピアノの鍵盤を前にしても、美しい色彩を紡ぎ出すことができなかった。指が触れる純白の象牙が、あの「黒」の入り口に見えてしまう。
そんなある日、彼は馴染みのカフェで、一杯のコーヒーを前に項垂れていた。
「奏くん、顔色が悪いじゃないか。何か悩み事かい?」
声をかけてきたのは、店のマスターであり、奏が師と仰ぐ高名な楽器製作者、恩田だった。白髪混じりの髪を後ろで束ね、いつも穏やかな笑みを浮かべている。恩田の声は、奏にとって常に特別なものだった。それは、他のどんな音とも違う、一点の混じり気もない「純粋な白」。まるで、磨き上げられた大理石のような、静謐で完璧な音色。その声を聞くと、奏の乱れた色彩感覚はいつも調律され、心が安らいだ。
「恩田さん……。いえ、少し考え事を」
「そうか。君は繊細だからな。あまり根を詰めないように。君の耳は、世界にとっての宝なんだから」
恩田の白い声に包まれ、奏はほんの少しだけ安堵した。しかし、その安堵はすぐに打ち砕かれる。カフェのドアが開き、入ってきた一人の客。痩せた背中。あの日の男だ。
男がコーヒーを注文する低い声。それは、ただのくぐもった音のはずだった。だが奏の視界に、再びあの「無音の黒」が侵食し始めた。世界が歪む。奏は脂汗を滲ませながら、男から目を逸らさなかった。こいつだ。間違いない。
第三章 静寂のフォルティッシモ
奏は衝動的に男の後をつけた。恐怖よりも、真実を知りたいという渇望が勝っていた。男は人通りの少ない路地を抜け、湾岸地区の寂れた廃工場へと入っていく。ここだ。美咲は、この中にいるに違いない。
奏は震える手でスマートフォンを取り出し、警察に通報した。場所を告げ、少女が監禁されている可能性が高いとだけ伝えた。声が上ずり、まともな思考ができない。
警察の到着を待つべきだ。頭では分かっているのに、足が勝手に工場の中へと向かっていた。錆びた鉄の扉を開けると、ひやりとした空気が肌を撫でる。内部は薄暗く、埃とオイルの匂いがした。奥から、微かな光が漏れている。
息を殺して光の源へ近づくと、そこは少し開けた空間になっていた。そして、奏は信じられない光景を目の当たりにする。
床に敷かれた毛布の上で、美咲が静かに眠っていた。衰弱している様子はなく、むしろ安らかな寝息を立てている。そしてその傍らで、あの痩せた男が、壊れたオルゴールを修理していた。
奏が息を飲んだ音に、男が顔を上げた。鋭いが、敵意のない瞳。
「……来たか。お前も、聞こえたんだろう。あの『黒い音』が」
男の声は、もはや奏の世界を黒く染めなかった。代わりに、深い森のような、静かな緑色に見えた。混乱する奏に、男――影山と名乗った――は静かに語り始めた。
影山もまた、奏と同じ共感覚の持ち主だった。そして彼も、極度の悪意が放つ「無音の黒」を知覚できる、数少ない人間の一人だったのだ。
「あの日、俺はあの少女から、黒い音の『残響』を感じ取った。誰か、とんでもない悪意を持つ人間に狙われていると。だから保護した。あいつが手出しできないように」
「あいつ……?犯人は、あなたじゃなかったのか?」
「犯人は、もっと巧妙に隠れている。自分の音の色さえ偽れる、歪んだ調律師だ」
その時、工場の入り口からゆっくりと足音が近づいてきた。現れた人物を見て、奏は全身の血が逆流するのを感じた。
恩田だった。いつもの穏やかな笑みを浮かべている。
「やあ、奏くん。こんな所で会うとは奇遇だね。私の『不協和音』を、掃除してくれていたのか」
恩田の声は、相変わらず完璧な「純白」だった。だが、彼の目が影山に向けられた瞬間、その白に亀裂が走った。
「出来損ないが……。お前のような濁った音は、世界に必要ない」
恩田が影山に一歩踏み出した、その刹那。
奏の世界が、完全に「無音の黒」に塗り潰された。今まで感じた中で最も濃く、深く、絶望的な黒。世界の終わり。
真犯人は、恩田。奏が最も信頼し、その声に安らぎを見出していた男。彼の完璧な「白」は、完璧な自己欺瞞と、揺るぎない悪意によって作り上げられた偽りの色だったのだ。奏に向けられていたのは善意の仮面。だが、その本性が剥き出しになった瞬間、全てを喰らう黒が正体を現した。恩田は、自分と同じ能力者を「選別」し、自分の基準に満たない者を「不協和音」として排除してきた、連続失踪事件の犯人だった。
第四章 残響のユニゾン
「なぜ……」
奏の声は、黒い真空の中でかき消えそうだった。
「なぜだと? 奏くん、君は才能がありすぎた。私の完璧な世界を乱す、最も危険なノイズだ。いずれ君も、私と同じ『真理』に気づくと思っていたが……君は弱い。濁った音に共感しすぎる」
恩田の手には、鈍い光を放つ工具が握られていた。それは、弦を切るためのチューニングハンマー。彼にとっては、命を絶つための凶器。
絶望が奏を支配した。この黒の中では、何も見えない、何も聞こえない。抵抗することすらできない。
だが、その時だった。暗闇の向こうで、何かが聞こえた。いや、見えた。
それは、眠っている美咲の寝息。か細いが、途切れることのないレモンイエローの線。そして、覚悟を決めた影山の呼吸。静かだが力強い、森の緑。
黒は、全ての音を消すのではなかった。悪意以外の、純粋な生命の音を際立たせるための、絶対的な静寂だったのだ。
奏は理解した。これは呪いではない。真実を見極めるための、彼の耳そのものだ。
「あなたの音は、白じゃない」
奏は、黒の向こうにいる恩田に向かって叫んだ。
「あなたの音は、何もない、空っぽの色だ!」
奏は目を閉じた。視覚に頼るのをやめ、全身を耳にした。黒い静寂の中、恩田の位置が、まるで音を発しているかのように正確に感じ取れた。それは、彼の殺意が作る音の「空白」。奏はその空白に向かって、そばにあった鉄パイプを力任せに振り抜いた。
金属音が響き、恩田の悲鳴が上がった。同時に、世界の色彩が津波のように押し寄せる。駆け込んできた警察官たちの怒声が、激しいオレンジ色となって空間を切り裂いた。
事件は解決した。恩田は逮捕され、彼の歪んだ犯行の全てが白日の下に晒された。美咲は無事に保護され、影山は奏に「あとは頼む」とだけ言い残し、どこかへ姿を消した。
奏の日常が戻ってきた。しかし、彼の世界はもう以前と同じではなかった。
街の音は相変わらず様々な色で溢れている。だが彼は、もうその奔流にただ流されるだけではなかった。一つ一つの音に、声に、その裏にある感情の色彩に、意識的に耳を澄ますようになった。
あの「無音の黒」を感じることもある。ニュースで流れる事件、人々の口から漏れる悪意。そのたびに背筋は凍るが、彼はもう目を逸らさない。黒があるからこそ、光の、色彩の、生命の音がどれほど尊いものかを知ったからだ。
ある晴れた午後、奏は再び柏木家のピアノの前に座っていた。調律を終えたピアノは、完璧なユニゾンを奏でている。リビングから、美咲と友人の楽しそうな笑い声が聞こえてきた。それは、いくつものレモンイエローやスカイブルーが混じり合った、美しいマーブル模様となって奏の目に映った。
世界は不協和音に満ちている。だが、その中にこそ、調律すべき美しい和音は隠れている。
奏はそっと鍵盤に指を置いた。そして、自分のために、世界に存在する全ての色彩と音のために、静かに一曲を奏で始めた。その音色は、少しだけ切なく、けれどどこまでも優しい、希望の色をしていた。