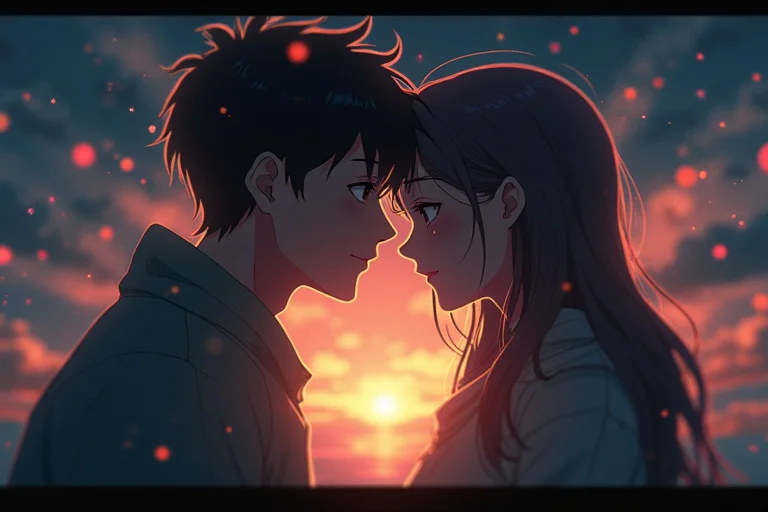第一章 硝子色の残像
雨がアスファルトを叩く音は、ひび割れたガラスのようだ、とカイは思った。街灯の光が濡れた路面に滲み、世界全体が涙でぼやけているように見える。彼の視界の端で、またそれが始まった。ノイズ混じりの、色褪せた幻影。
カフェの窓際で、一人の女性が笑っていた。彼女の髪が揺れ、カップを持つ指先が白く浮かび上がる。声は聞こえない。まるで、分厚い水の壁を隔てて遠い昔の映画を観ているかのようだ。彼女の名前はリナ。三週間前に、この街から忽然と姿を消した女性。カイが今追っている「消失者」だ。
幻影――「残響」とカイは呼んでいた――が消えると、決まって鋭い頭痛が彼のこめかみを抉る。そして、何かが抜け落ちる。今朝、自分がトーストに何を塗ったのか。昨日、どんな本を読んだのか。ささやかな記憶が、砂の城のように静かに崩れていく。これが、他人の「消失した記憶の残響」を視る能力の代償だった。
この世界では、人は人生の節目に自らの肉体の一部――爪や髪、あるいは一滴の血――を「記録石」として中央管理局に奉納する。それは存在の証であり、社会との契約だ。奉納を怠った者は、誰からも認識されなくなり、やがて世界から完全に消滅する。
だが、最近奇妙な事件が多発していた。奉納されたはずの記録石が、保管庫の中で空っぽの抜け殻のように発見されるのだ。内部から、まるで卵が孵るように砕かれている。そして、その記録石の持ち主は、リナのように、例外なく社会から消失していた。
カイはコートの襟を立て、雨の中に一歩踏み出した。リナの残響が遺した微かな温もりを追いかけるように。失われた彼女の記憶の代わりに、また一つ、自分の記憶が雨に溶けていった。
第二章 空洞の囁き
記録石の修復師であるマシロ老人の工房は、古い樟脳と磨かれた鉱石の匂いがした。壁一面の棚には、様々な色と形をした記録石が、持ち主の人生を秘めて静かに眠っている。
「また来たのか、カイ。お前の顔を見るたびに、また一つ記憶を失くしたのではないかと心配になる」
マシロは分厚いレンズの眼鏡の奥から、カイの顔を覗き込んだ。
カイは黙って、新聞の切り抜きをテーブルに置いた。空洞化した記録石事件の特集記事だ。
「何か分かることはありませんか」
マシロは深くため息をつき、手元にあった空洞の記録石の欠片を指先でなぞった。「奇妙だ。実に奇妙だ。記録石は持ち主の魂の器。外からの衝撃には強いが、内側からの力には驚くほど脆い。これらの石は、まるで……持ち主自身の未来が、その石の中に記録されるのを拒絶しているかのようだ」
未来を、拒絶する。
その言葉が、カイの胸に小さな棘のように突き刺さった。
「カイ、お前が追っているものが何なのかは知らん。だが、どうしても真実に近づきたいのなら、一つだけ方法があるやもしれん」
マシロは工房の奥から、黒いベルベットに包まれた小さな箱を持ってきた。中には、曇った水晶のようなレンズが収められている。
「『無名石のルーペ』。他人の記録石の欠片を通して、その持ち主のあり得たかもしれない未来の可能性を垣間見せるという曰く付きの遺物だ。だが、気をつけろ。あれは覗き込んだ者の記憶を燃料にする。お前のような人間が使えば、どうなるか……」
マシロの警告は、雨音にかき消された。カイの心は、すでに禁断の道具に囚われていた。
第三章 無名石のルーペ
裏路地の情報屋から手に入れた「無名石のルーペ」は、触れると氷のように冷たかった。カイは自室に戻り、リナの部屋からこっそり持ち出した、彼女の記録石の小さな欠片をテーブルに置いた。震える手でルーペをかざす。
瞬間、世界が歪んだ。
脳を直接掴まれ、記憶という名の粘土をこね回されるような激しい感覚。子供の頃に見た空の色、初めて読んだ本の題名、亡き母の温もりが、次々と溶けて流れ出していく。絶叫を堪え、カイはレンズの奥に映る光景に意識を集中させた。
そこには、リナがいた。純白のドレスを身に纏い、知らない男と腕を組んで微笑んでいる。幸せに満ちた結婚式の光景。だが、その光景はすぐに陽炎のように揺らめき、次の瞬間には燃え盛る炎に包まれていた。崩れ落ちる教会。絶叫するリナ。そして、どこからか囁き声が聞こえた。
『これでお前は自由だ』
ビジョンはそこで途切れ、カイは椅子から崩れ落ちた。失われた記憶の空白を埋めるように、激しい虚無感が彼を襲う。自由? 何から? あの悲劇的な未来からリナを解放したとでも言うのか。一体、誰が。
第四章 重なる影
リナがよく通っていたという、市立図書館の古い閲覧室。カビ臭い紙の匂いが立ち込めるその場所で、カイはこれまでで最も強烈な残響に襲われた。
目の前に、リナが立っている。誰かと激しく口論しているようだ。相手の男の顔は、いつものように激しいノイズで判別できない。だが、その手に握られているものを見て、カイは息を呑んだ。
『無名石のルーペ』だ。
男が口を開く。その声は、ノイズの向こう側からでもはっきりと聞こえた。
「君の未来は、私が消してあげる。悲劇が確定した未来など、存在しない方がいい。その方が、君は幸せになれるんだ」
その声。
それは、他ならぬカイ自身の声だった。
全身の血が凍りつく。まさか。自分がリナを? 混乱する頭で、カイは震える手でコートの内ポケットを探った。自身の「奉納許可証」。そこに記された記録石の識別番号を、彼は図書館の端末に憑かれたように打ち込んだ。網膜に焼き付いた自分の声が、耳鳴りのように頭の中で反響している。検索ボタンを押す指が、鉛のように重かった。
第五章 未来からの侵略者
画面に表示された検索結果は、無慈悲な宣告だった。
対象記録石: カイ・アズマ
状態: 内部破損。空洞化を確認
膝が笑い、床に手をついた。視界が明滅する。自分が、自分自身の記録石を破壊していた? いや、違う。記憶がない。そんなことをした覚えはない。では、誰が。
脳裏に、マシロ老人の言葉が蘇る。『未来を拒絶するように』。
そして、無名石のルーペが見せたビジョン。『これでお前は自由だ』。
犯人は、現在の自分ではない。
犯人は――未来の自分だ。
未来のカイが、過去に干渉している。リナとの間に起こる、何か決定的な悲劇を回避するために。その悲劇の起点となる、彼女の記録石を破壊した。そして、おそらくは、その事件に関わる自分自身の記録石も。
カイが今まで見ていた「残響」は、リナの消失した記憶などではなかったのだ。あれは、未来のカイによって破壊され、行き場をなくした「未来の断片」。リナとの幸せな結婚という可能性。そして、それが炎に包まれるという悲劇の可能性。未来の自分は、その両方の可能性を根こそぎ奪い去ることで、リナを救おうとしたのだ。
そして、現在のカイは、記憶を失う能力を持つ駒として、この時間軸に置き去りにされた。真実を知らないまま、永遠に犯人を追い続けるように。
第六章 最後の残響
全てを悟ったカイの前に、最後の残響が、まるで舞台の幕が上がるかのように現れた。それは、これまでで最も鮮明なビジョンだった。
薄暗い記録石の保管庫。そこに立つ、年老いた自分。顔には深い皺が刻まれ、その目にはカイが知らない、計り知れないほどの哀しみが湛えられている。未来のカイは、涙を流しながら、若い自分の――今、ここにいるカイの――記録石を、その手に持った特殊な器具で内側から破壊していた。
『これでいいんだ』
未来の自分の声が、脳内に直接響き渡る。それは囁きであり、祈りにも似ていた。
『君は何も知らなくていい。ただ、僕が忘れてしまった温もりを、失われた未来の断片を追い続けてくれればいい。それが、僕が払える唯一の贖罪なのだから』
贖罪。一体、どんな未来が彼らを待っていたというのか。
その答えを知ることは、もうない。
カイは、自分の指先が透け始めていることに気づいた。社会との繋がりが、最後の糸が、ぷつりと切れたのだ。足元から世界が崩れていく感覚。彼はふらつきながら窓辺に寄りかかり、空を見上げた。いつの間にか、雨は上がっていた。雲の切れ間から、弱々しい光が差し込んでいる。
薄れゆく意識の最後に、一つの記憶が星のように瞬いた。
カフェの窓際で、楽しそうに笑うリナの顔。
それが、未来の自分が守りたかったものなのか。それとも、自分がこれから永遠に追い求め続ける幻なのか。もはや、カイには判別できなかった。ただ、その笑顔は、失われた全ての記憶を補って余りあるほど、温かかった。