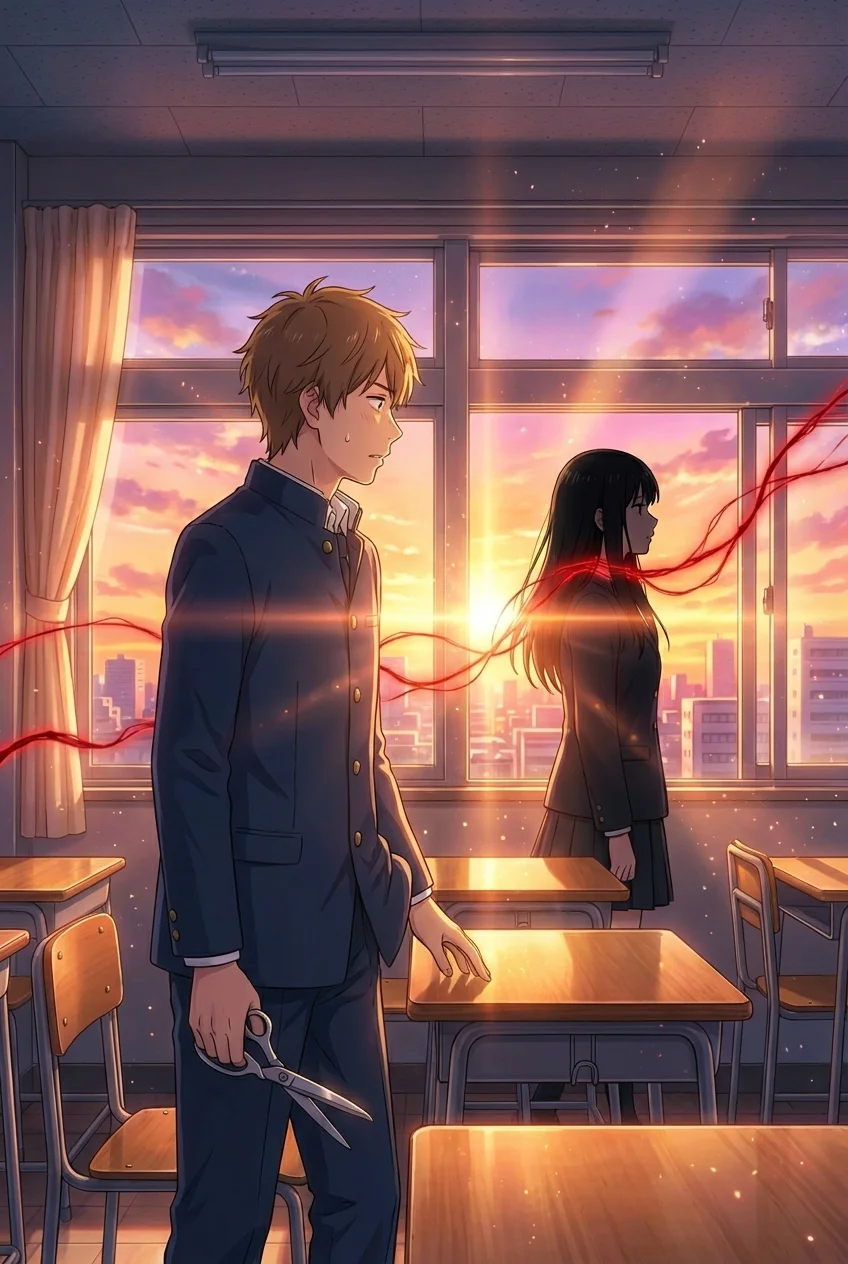第一章 歪んだ歓喜
柏木湊の人生は、静かで、色のない水のようなものだった。喜びも、悲しみも、怒りさえも、その水面に投げ込まれた小石のように、小さな波紋を立てるだけですぐに消え失せ、元の平坦な水面に戻ってしまう。感情という蛇口が、固く錆びついて開かなくなったようだった。幼い頃の火災で両親を失って以来、彼の心は燃え尽きた家の跡地のように、がらんどうのまま時が過ぎていった。
そんな湊が、都心から少し離れた古びた木造アパートの一室に越してきたのは、一月ほど前のことだ。家賃の安さだけが決め手だった。きしむ廊下、隙間風の鳴る窓、陽の当たらない北向きの部屋。しかし、湊にとってはどこで暮らそうと大差なかった。世界は常に等しく灰色だったからだ。
異変が始まったのは、住み始めて一週間が過ぎた頃だった。夜、眠りにつこうと布団に入ると、壁の向こう、誰も住んでいないはずの隣室から、カリ、カリ、と何かを引っ掻くような音が聞こえてきたのだ。最初はネズミかと思った。しかし、音は日に日に大きく、明確になっていく。爪で木の板を執拗に削るような、耳障りな音。普通なら不気味に思うはずのその音を、湊はただぼんやりと聞いていた。不思議なことに、恐怖はまったく感じなかった。
むしろ、その音を聞いていると、胸の奥に微かな温もりが灯るような、奇妙な感覚があった。錆びついた蛇口から、ぽたり、と一滴だけ水が漏れたような感覚。それは、湊が長い間忘れていたものだった。
ある晩、音はさらにエスカレートした。今度は壁を内側から、ドンドン、と強く叩くような音に変わった。まるで、誰かが閉じ込められて、必死に助けを求めているかのようだ。湊はベッドから身体を起こし、音のする壁にそっと耳を当てた。冷たい壁紙の向こうから伝わる微かな振動。そして、音の合間に、すすり泣くような女の声が聞こえた気がした。
その瞬間、湊の口角が、自分でも気づかないうちに、ゆっくりと吊り上がっていた。胸の中で、ぽたりと漏れた水滴が、細い糸となって流れ始める。それは歓喜に似ていた。何故かは分からない。だが、この得体の知れない現象が、自分の空っぽな世界に初めて色を与えてくれたように感じられたのだ。血の通わない心臓が、久しぶりにトクン、と脈を打った。彼はその夜、壁に背を預け、朝まで隣室の音に耳を澄ませていた。まるで恋人が奏でる音楽を聴くように。その顔には、穏やかな笑みさえ浮かんでいた。
第二章 影との同居
隣人との奇妙な同居生活は、湊の日常に歪んだ彩りを与え始めた。天井の隅に黒い染みがじわりと広がり、それが時折、苦悶に歪む人の顔のように見えることがあった。洗面所の鏡を覗き込むと、一瞬だけ自分の背後に長い髪の女の影が映り込み、瞬きをすると消えていることもあった。深夜、キッチンで勝手に蛇口がひねられ、水が流れ出す音で目を覚ますことも一度や二度ではない。
常人ならば狂気に陥るか、即座に荷物をまとめて逃げ出すような出来事の連続。しかし、湊の反応は正反対だった。彼は現象が起きるたびに、まるでご褒美を与えられた子供のように、胸を高鳴らせた。染みを見上げてはその形がどう変化するかを観察し、鏡に映るはずの影を求めて何度も振り返り、水の音を聞いては安堵のため息をついた。
彼の世界は、この部屋に住む「何か」によって満たされつつあった。灰色だった視界に、赤黒い絵の具がぶちまけられたような、鮮烈な刺激。それは恐怖という名のスパイスが効いた、最高のエンターテイメントだった。彼は日中、仕事をしている間も、夜に待っているであろう新たな怪奇現象に思いを馳せ、口元を緩ませることが増えた。同僚からは「最近、何か良いことでもあったのか?」と気味悪がられたが、湊は気にも留めなかった。
この幸福の源泉について、もっと知りたくなった。湊はアパートの大家である老婆を訪ね、自分の部屋の前の住人について尋ねてみた。老婆は少し顔を曇らせ、重い口を開いた。
「ああ、あの部屋ねぇ……。あんたが入る半年前まで、若い女の人が一人で住んでたんだよ。大人しくて、ほとんど誰とも口を利かないような人だったねぇ」
「その方は、どうして引っ越されたんですか?」
湊の問いに、老婆は視線を落とし、さらに声を潜めた。
「……孤独死だよ。死んでから一月以上、誰にも気づかれなくてね。夏場だったから、そりゃあ、ひどいもんだったさ。警察が来て大騒ぎになってね。あんたには、言うべきか迷ったんだが……」
孤独死。その言葉は、湊の胸にずしりと重く響いた。しかし、それは同情や恐怖ではなかった。むしろ、パズルのピースが一つはまったような、奇妙な納得感があった。あの音、あの声、あの影。それらはすべて、誰にも気づかれずに死んでいった女性の、無念の叫びなのかもしれない。
その夜、湊はコンビニで買った安物の日本酒と菊の花を、隣室との境界である壁の前に供えた。
「あなたが、ここにいるんですね」
彼は壁に向かって、静かに語りかけた。
「俺は、あなたがいてくれて、嬉しいです。あなたがくれるもののおかげで、俺は……生きているって感じがするんです」
返事はなかった。しかし、その瞬間、部屋の電灯が激しく点滅し、バチン、という音を立てて消えた。完全な闇が訪れる。その暗闇の中で、カリ、カリ、という爪の音が、これまでで最も近く、まるで湊の耳元で鳴っているかのように、はっきりと聞こえた。湊は暗闇の中で、至福の表情を浮かべていた。彼女が、自分の言葉に応えてくれた。その確信が、彼の空っぽの心を温かい液体で満たしていくのを感じた。
第三章 満ちていく空虚
その夜を境に、彼女はより明確に湊の前に現れるようになった。もはや影や音だけではない。部屋の隅に、ぼんやりとした人型の靄として佇んでいたり、眠っている湊の顔を、氷のように冷たい指がそっと撫でていったりすることもあった。湊はその度に、愛する人に触れられたかのような、甘美な戦慄を覚えた。彼の内面は、この異常な関係性によって、かつてないほど豊かになっていた。感情の蛇口はもはや錆びついてなどいなかった。歪んではいるが、歓喜という名の水が溢れんばかりに流れ出ていた。
そして、満月の光が部屋に差し込む、ある静かな夜。ついに、その時が訪れた。
湊がベッドで本を読んでいると、ふと視線を感じて顔を上げた。部屋の対角線上、月明かりの中に、一人の女が立っていた。これまでのような靄ではない。はっきりとした、実体のある姿だった。長く伸びた髪は顔を覆い隠し、痩せこけた手足はありえない方向にねじ曲がっている。彼女が着ているであろう衣服は汚れ、ところどころが破れていた。何よりも、彼女の全身から発せられる気配は、純粋な絶望と怨嗟そのものだった。それは、孤独の果てに死んでいった者の、救われなかった魂の最終形態だった。
おぞましい、という言葉では足りない。常人であれば絶叫し、気を失ってもおかしくない光景。
しかし、湊の心を満たしたのは、人生で経験したことのない、最大級の多幸感だった。
全身の細胞が歓喜に打ち震え、視界が涙で滲む。ああ、やっと会えた。ずっと会いたかった。君は、俺の灰色の日々を終わらせてくれた、唯一の存在だ。
湊はベッドからゆっくりと降り、一歩、また一歩と、彼女に歩み寄った。彼女は微動だにしない。ただ、底なしの憎悪をその存在だけで発している。
「ありがとう」
湊の声は、震えていた。喜びで。
「君がいてくれたから、俺はまた、感じることができたんだ」
その言葉を口にした瞬間、湊の中で何かが弾けた。パズルの最後のピースが、カチリと音を立ててはまった。
彼は、気づいたのだ。
自分が感じていたこの感情は、恐怖が転化した幸福などではない。
この部屋に渦巻いているのは、怨念や恐怖ではない。ただひたすらに、純粋で、濃密な「寂しさ」なのだ。誰にも気づかれず、誰にも声をかけられず、世界から忘れ去られて死んでいった彼女の、あまりにも巨大な寂しさ。
そして、湊が感じていた高揚感の正体は、その寂しさに自分の空虚な心が共鳴した結果生まれる、歪んだ「繋がり」の感覚だったのだ。空っぽの器と空っぽの器が、互いの空虚さを認め合い、響き合っている。それは、湊が生まれて初めて経験する、他者との完全な一体感だった。
「寂しかったんだね」
湊は、彼女の目の前で立ち止まった。覆い隠された顔の下に、どんな表情があるのかは見えない。
「俺もだよ。ずっと、一人で、寂しかったんだ」
それは、湊が心の底から絞り出した、初めての本当の言葉だった。両親を失って以来、ずっと蓋をしてきた、自身の孤独を認める言葉だった。
その言葉が、魔法になった。
おぞましくねじ曲がっていた彼女の身体が、すうっと真っ直ぐになる。顔を覆っていた長い髪がはらりと落ち、月明かりの下に、穏やかで、少しはにかんだような若い女性の素顔が現れた。その瞳には、怨嗟ではなく、深い安堵の色が浮かんでいた。
彼女は、何も言わなかった。ただ、湊に向かって、ほんの少しだけ微笑んだように見えた。そして、その身体は足元からゆっくりと光の粒子に変わり始め、月明かりに溶けるようにして、静かに消えていった。
後に残されたのは、完全な静寂と、床に落ちた一輪の菊の花だけだった。怪奇現象は、もう二度と起こらなかった。
部屋は再び、ただの陽の当たらない、古い一室に戻った。
しかし、湊の世界は、もう灰色ではなかった。
窓から差し込む朝の光が、これほどまでに暖かいものだとは知らなかった。道端に咲く名もなき花が、こんなにも美しい色をしているとは気づかなかった。彼の空っぽだった心には、彼女が残していった温かい何かが、確かに満ちていた。
湊の頬を、一筋の涙が伝った。それは悲しみの涙ではなかった。失っていたものを取り戻した、再生の涙だった。彼はこれから、この満たされた心で、世界ともう一度向き合っていくのだろう。静かだが、確かな一歩を踏み出すために。部屋の隅には、彼が新しく買ってきた、瑞々しい菊の花が飾られていた。