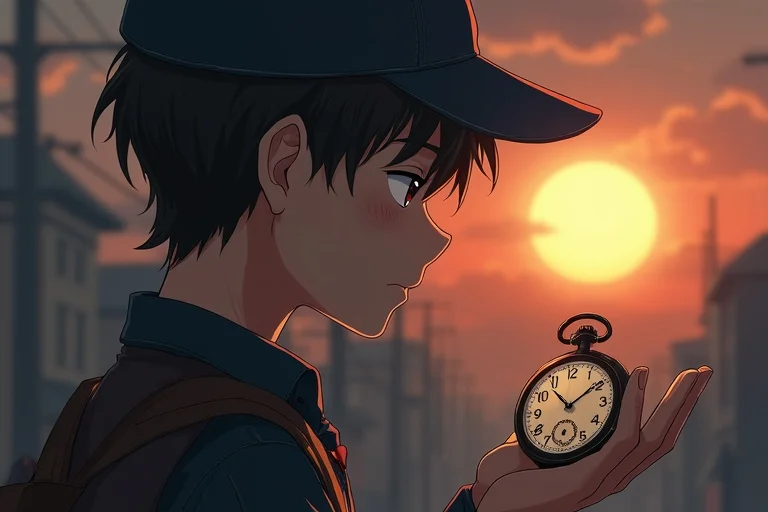第一章 血錆色のレクイエム
空は、熟しすぎた柘榴のように、どす黒い深紅色をしていた。
大戦が始まってから十年、空はずっとこの色だ。人々はもう、かつてそこにあった青を思い出せない。カイは塹壕の泥濘に膝をつき、息を殺しながら鼻腔を震わせた。硝煙と腐臭が渦巻く戦場にあって、彼だけが嗅ぎ取れる香りがある。それは、失われゆく命が最後に放つ、「後悔」という名の芳香だった。
すぐ側で倒れた若い兵士。彼の身体からは、焦げたパンと、故郷のシチューのかすかな香りが立ち上っていた。もっと母の手料理が食べたかった、という無念の香り。カイはその香りを吸い込み、胸の奥深くに刻みつける。これが彼の役目であり、呪いだった。香りの強さと種類で、死者の未練の深さがわかる。錆びた鉄と甘い野花の香りは、伝えられなかった愛の言葉。湿った土とインクの香りは、果たせなかった約束のしるし。
深紅の空が一定の濃度に達すると、世界は過去の幻影に苛まれる。塹壕の向こうに、百年前の騎兵が突撃し、音もなく崩れ落ちる。空には、さらに古い時代の翼竜の影がよぎる。人々は幻覚に慣れ、あるいは狂い、それでもなお争いをやめなかった。
カイは背嚢から一本のペンを取り出した。戦場の廃墟で拾った、透明なガラス製の羽根ペン。それは決して朽ちることがなく、指でなぞると、遠い過去の戦場の叫びや銃声が微かに共鳴する不思議な品だった。彼は古びた手帳を開き、インクをつけ、今しがた嗅ぎ取ったばかりの香りの記憶を書き留めていく。
『――兵士、十七歳。焦げたパンと母のシチューの香り。空腹のまま逝く』
ガラスのペンで記された文字は、血のように赤く、空の色を映していた。それは、この狂った世界でカイが唯一正気を保つための、鎮魂の儀式だった。
第二章 透明な静寂
異変は、夜明けと共に訪れた。
カイが塹壕で仮眠から目覚めた時、世界はありえないほどの静寂に包まれていた。砲声も、怒声も、呻き声も、何も聞こえない。恐る恐る顔を上げ、彼は息を呑んだ。
空が、無色だった。
それは青ではない。白でも、灰色でもない。まるで巨大な水晶のドームに覆われたかのように、どこまでも澄み渡り、向こう側の宇宙の深淵さえ透けて見えそうな、絶対的な「透明」。歴史のどの記録にもない、異常な空。
そして、もう一つ。昨日まで戦場に満ちていた、あの甘く切ない後悔の香りが、一片たりともしなくなっていた。まるで鼻が壊れてしまったかのように、カイが感じ取るのは泥と鉄の無機質な匂いだけだった。
敵も味方も、武器を置いたまま呆然と空を見上げていた。やがて、誰からともなく塹壕を出て、互いに歩み寄る。しかし、そこには憎しみの応酬も、和解の抱擁もなかった。ただ、誰もが穏やかで、どこか虚ろな表情を浮かべているだけ。戦争は終わったのだ。そう、誰もが直感した。だが、その終わり方があまりに不気味だった。歓声も涙もなく、まるで長年演じてきた舞台の幕が、突然何の合図もなく下ろされたかのような、白々しい静けさだけが広がっていた。
第三章 硝子(ガラス)の囁き
数週間が過ぎた。世界から争いは消え、人々は穏やかな日々を取り戻した。街角では人々が微笑み合い、穏やかな会話を交わしている。しかし、カイはその光景に言いようのない違和感を覚えていた。
カフェのテラスで、若い男女が愛を囁き合っている。
「愛しているわ」
「僕もだよ」
その言葉はひどく軽く、彼らの瞳にはかつてカイが後悔の香りの中に感じたような、魂を焦がすほどの熱がなかった。公園で遊ぶ子供たちの笑い声も、まるで録音された音のように、感情の起伏を感じさせない。喜びも、悲しみも、怒りも、すべてが水で薄められたように希薄になっていた。
カイは住処にしている廃教会の片隅で、あのガラスの羽根ペンを握りしめた。ひんやりとした硝子の感触が、指先に過去の戦場の微かな振動を伝える。――ザッ、ザッ、という行軍の音。遠い爆発音。それは、この感情のない世界に残された、唯一の情念の残滓のようだった。
彼は手帳にペンを走らせる。
『この静けさは何だ? なぜ誰も、心から笑ったり泣いたりしない?』
インク壺から吸い上げた黒インクで書いたはずの文字は、紙の上で力なく滲み、まるで燃え尽きた灰のような淡い灰色に変わっていた。その色褪せた文字は、この世界の住人たちの心を映しているかのようだった。
第四章 色を失くした人々
ある夜、カイは悪夢にうなされた。無数の後悔の香りが彼に殺到し、その重みに押し潰される夢だ。叫びながら飛び起きると、枕元のガラスの羽根ペンが、淡い燐光を放っていた。
彼は震える手でペンを手に取る。すると、ペンの輝きが増し、手の中の手帳の文字がひとりでに蠢き、形を変え始めた。灰色の文字が組み合わさり、新たな文章を紡ぎ出していく。それは、この世界の真実を告げる、無機質な囁きだった。
『永劫の争いに星々は嘆き、人の魂魄より負の情を吸い上げり』
『憎悪、嫉妬、悲嘆、後悔。争いの源泉は宇宙の塵と消えん』
『されど、魂の彩りは表裏一体。濃き闇を失いし光は、その輝きを失う』
カイは悟った。無色の空は、平和の訪れなどではなかった。何者か――神か、宇宙の法則か――が、人類の戦争を終わらせるために、その根源である「負の感情」を強制的に奪い去ったのだ。だが、その代償はあまりにも大きかった。憎しみや悲しみを失った人類は、同時に、愛や喜びといった、魂を震わせる強い「正の感情」をも失ってしまったのだ。
濃い影があってこそ、光は強く輝く。感情の振れ幅こそが、人間を人間たらしめていた。人々は争わない人形になった。穏やかで、空虚で、色のない世界。これがおそらく、前代未聞の破滅の、静かなる始まりだった。
第五章 かすかな残香
絶望がカイの心を支配した。自分だけが、この世界の巨大な「喪失」に気づいている。なぜだ。戦場で誰よりも強く、人の感情の極致である「後悔」の香りを嗅ぎ続けてきたからだろうか。彼の嗅覚は、いつしか感情そのものの香りを捉える、特異な感覚へと変質していたのかもしれない。
この空虚な世界で、自分だけが正常な異常者として生きていくのか。カイが手の中のペンを握り潰さんばかりに力を込めた、その時だった。
ふわり、と。
ごく微かな、しかし確かに存在する香りが、光るペンから立ち上った。
それは、彼が今まで嗅いだことのない香りだった。焦げ付くような後悔の香りではない。温かく、清らかで、胸の奥をそっと撫でるような優しい香り。それは、嵐の後の陽だまりの匂いにも似ていた。守るべきものを抱きしめた時の、慈しみの香り。初めて愛を告げられた瞬間の、はちきれるような歓喜の香り。
ガラスの羽根ペン。それは、世界から排出された膨大な感情のエネルギーの奔流の中で、その一部――失われたはずのポジティブな感情の残滓を、奇跡的にその身に吸い寄せていたのだ。
カイの頬を、一筋の涙が伝った。この色を失くした世界で、彼が流した最初の涙だった。
第六章 ただ一人のためのアリア
カイは立ち上がった。彼の目には、もう迷いはなかった。
この穏やかで、争いのない世界は、偽りの楽園だ。人間が人間らしさを失って手に入れた平和に、何の意味があるというのか。
彼は旅に出ることを決意した。失われた感情を取り戻すために。たとえ、それが世界中の誰からも理解されない、孤独な旅路になるとしても。
彼は小さな背嚢に、手帳とインク、そしてわずかな食料を詰めた。最後に、胸のポケットに、あのガラスの羽根ペンをそっと収める。ペンは彼の心臓の鼓動に呼応するように、かすかな温もりと、希望の香りを放っていた。
カイは廃教会の扉を開け、無色の空の下へと踏み出した。
どこへ向かうべきなのか、まだわからない。けれど、このガラスのペンが放つかすかな香りが、きっと彼を導いてくれるだろう。
それは、世界が忘れてしまった“人間らしさ”という名の、アリアの旋律。
風が吹き、カイの髪を揺らす。彼の鼻腔は、確かに捉えていた。地平線の彼方から流れてくる、愛と喜びの、忘れられた香りの痕跡を。
ただ一人、感情の残香を追って。カイの、果てしない旅が始まった。