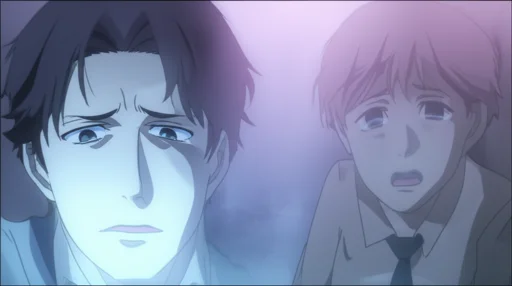第一章 影紡ぎと薄れる輪郭
街は、緩やかにその色彩を失いつつあった。石畳の継ぎ目は滲み、建物の輪郭は午後の陽炎のように揺らめく。人々は互いの顔を確かめるように見つめ合い、やがて視線を落として足早に去っていく。誰かの存在が、その記憶ごとこの世界から薄れていくことに、誰もが気づき始めていた。
俺、カイは、そんな世界で「影紡ぎ」と呼ばれていた。
他人の記憶が欠落した部分、その「空白」に触れると、俺の指先から黒い靄が立ち上る。それはやがて形を成し、持ち主が最も恐れるものの姿をとって実体化する。俺は、その「影」を読み解くことで、失われた記憶の断片を拾い集め、生業としていた。
「弟が……リオが、消えかけているんです」
カフェの隅、窓の外で揺らめく街路樹の葉さえも半透明に見える席で、エリアと名乗る女性は震える声で言った。彼女の瞳には、俺の能力への僅かな恐怖と、それを上回る必死の祈りが浮かんでいた。
彼女の家を訪れると、部屋の隅のベッドに少年が横たわっていた。リオと呼ばれたその少年は、まるで薄いガラス細工のようだった。シーツの色がその体を透かし、呼吸の音さえもほとんど聞こえない。存在そのものが、世界との接続を断ち切ろうとしているかのようだった。
俺は頷き、少年のこめかみにそっと指を触れた。
冷たい。まるで生命の熱が失われた硝子玉に触れているようだ。彼の意識の奥深く、ぽっかりと空いた記憶の空白に精神を沈めていく。そこは、何の感触もない、ただ虚無が広がるだけの場所だった。
俺の指先から、黒いインクが水に落ちるように影が滲み出した。それは床に広がり、ゆらりと立ち上る。影は特定の形を取らず、ただただ冷たく、音を吸い込むような静寂そのものとして部屋を満たしていく。それは「無音」の恐怖。弟が最も恐れていたのは、世界から音が消え、誰の声も届かなくなる孤独だった。
影がリオの細い足首に絡みつこうとした瞬間、エリアが悲鳴を上げた。俺は舌打ちし、自らの意識を引き戻す。影は未練がましげに揺らめくと、霧散して消えた。
「今のが……」
「ああ。あいつの記憶の空白だ。そして、恐怖そのものだ」
俺は立ち上がり、窓の外に目をやった。街はさらに曖昧さを増している。この現象は加速している。世界は、最も基本的な音――人間の呼吸の音――を失い始めている。だから人々は互いの存在を忘れ、その輪郭を失っていくのだ。
「どうすれば……リオは元に戻るのでしょうか?」エリアが縋るように俺の腕を掴む。その手のひらの温かさだけが、この曖昧な世界で唯一確かなもののように感じられた。
俺は答えられなかった。なぜなら、この世界の歪みの中心に、自分自身の、決して開けてはならない記憶の箱があることを、まだ知らなかったからだ。
第二章 錆びついた追憶の旋律
リオの影を紡いでから数日、俺は街の異変が、ある特定の音の欠落に起因するという確信を深めていた。それは、人が眠りに落ちる瞬間の、穏やかで規則正しい呼吸音。その周波数帯が、まるでごっそりと世界から抜き取られたように消え失せている。
自分の過去を探ろうとしても、靄がかかったように何も思い出せない。幼い頃の記憶は、ところどころが虫食いのようになっていた。その空白に触れるのが怖くて、俺はいつも目を逸らしてきた。
そんな時だった。埃っぽい骨董品店に並ぶガラクタの中で、一つの小さな木箱が俺の目を引いたのは。錆びついた真鍮のゼンマイがついた、壊れたオルゴール。なぜか酷く懐かしい気がして、無意識にそれを手に取っていた。店主は「もう音は出ないよ」と笑ったが、俺は構わずに銀貨を数枚渡し、それを持ち帰った。
再びエリアの家を訪れると、リオの状態はさらに悪化していた。彼の指先はほとんど見えず、声を発しても、まるで風の囁きのようにしか聞こえない。エリアは泣き崩れる寸前だった。
俺は衝動的に、懐から取り出したオルゴールのゼンマイを巻いた。ぎ、ぎ、と軋む音がするだけで、鳴る気配はない。だが、諦めきれずにもう一度、力を込めて回す。
カ……ン。
金属が弾けるような、途切れ途霊の音が一つだけ響いた。その瞬間、信じられないことが起こる。ベッドに横たわるリオの輪郭が、一瞬だけ、くっきりと鮮明になったのだ。まるで、失われた世界のパズルのピースが、その音によって一瞬だけ埋められたかのように。
「……今の音」エリアが顔を上げた。「昔、お母さんが歌ってくれた子守唄の……最初の音……」
しかし、奇跡は続かなかった。リオはすぐに元の曖昧な姿に戻り、そして、俺の手の中にあるオルゴールが、ほんの少しだけ透明になっていることに気づいた。このオルゴールは、自らの存在を削って、失われた音を奏でているのだ。
俺は愕然とした。この錆びついた旋律は、世界から失われつつある音そのものだった。そして、エリアの言葉が引き金となり、俺の頭の奥で、固く閉ざされていた扉が、軋みを立てて開き始めるのを感じていた。
第三章 静寂の誕生
俺は自分の部屋に戻り、震える手でオルゴールを握りしめた。エリアの言葉、リオの姿、そしてこのオルゴールの音。全てが俺自身の失われた記憶へと繋がっている。もう逃げることはできない。
俺は目を閉じ、生まれて初めて、自分自身の「記憶の空白」に指を触れた。
それは、底なしの沼に落ちていくような感覚だった。他人の空白に触れるのとはわけが違う。引きずり込まれる。意識が溶けていく。だが、俺は必死に抗い、その中心を目指した。
次の瞬間、俺の部屋の空気が凍りついた。
俺の指先から生まれた影は、これまで紡いできたどんなものよりも巨大で、濃密で、そして絶望的に静かだった。それはゆっくりと人型を成していく。それは、俺自身の姿をしていた。ただし、顔には目も鼻も、そして何より「口」がなかった。ただ、虚無を映すのっぺらぼうの顔が、静かに俺を見つめている。
その影がゆっくりと一歩踏み出すと、影が触れた床が音もなく透明に変わり、存在が希薄になっていく。本棚が、机が、壁が、まるで水彩画のように滲んでいく。
世界が、終わる。
恐怖に竦む俺の目の前で、影はテーブルの上のオルゴールに手を伸ばした。影の指がオルゴールに触れた瞬間、激しい光と共に、忘却の底に沈んでいた記憶が洪水のように俺の脳内になだれ込んだ。
――薄暗い部屋。ベッドに横たわる、小さな妹。
喘ぐように、苦しそうに繰り返される、か細い呼吸。
俺は幼い手で、必死に妹の手を握っていた。
医者は首を横に振った。両親は泣き崩れていた。
やがて、その苦しげな呼吸が、ふっと途切れた。
静寂。
永遠に続くかのような、残酷な静寂。
その静寂が、幼い俺には耐えられなかった。妹の最後の音が消えた世界が、許せなかった。
『こんな音、世界からなくなってしまえばいい』
そう願ったのだ。心の底から。妹の死を象徴する「呼吸の停止」という事実を、この世界そのものから消し去ってしまいたい、と。
その瞬間、俺の能力は生まれた。俺の願いは、世界の法則を歪めた。俺が忘却した「妹の最後の呼吸音」の周波数帯が、この世界から欠落し始めたのだ。俺が他人の記憶の空白から影を紡ぐたび、その行為は俺自身の空白を世界に再投影し、音の欠落を加速させていた。
俺が呼び出す「最も恐ろしい影」は、他人のものではなかった。いつだって、俺自身が忘れ去った、あの日、あの瞬間の「静寂の誕生」が、形を変えて現れていたに過ぎなかったのだ。
第四章 世界が終わるためのフーガ
全てを思い出した。俺が、この世界の静寂の始まりだった。俺の悲しみが、この世界を終わらせようとしていた。
俺の姿をした影は、部屋の中心で静かに佇んでいる。それはもはや俺の制御下にはなく、俺の深層意識が生み出した「忘却」そのものとして、世界を白紙に戻そうとしていた。窓の外は、すでに真っ白な霧に覆われ、街の音は完全に消え失せていた。エリアの声も、リオの存在も、もう感じられない。
絶望と、そして奇妙な安堵が俺を包んだ。これで、終わるのだ。俺が始めた物語を、俺自身が終わらせるのだ。
俺はゆっくりと立ち上がり、自らの影に向かって歩き出した。手には、ほとんど透明になったオルゴールを握りしめている。
一歩、また一歩と近づく。影は、まるで帰りを待っていたかのように、静かに両腕を広げた。その腕の中に、全ての終わりと、そして始まりの静寂があることを俺は理解していた。
「……ごめん」
誰にともなく呟いた言葉は、音になる前に霧散した。
俺は、自らの影に抱きしめられるように、その中心へと身を委ねた。冷たい虚無が全身を包み込み、俺の輪郭が世界と溶け合っていく。意識が薄れる最後の瞬間、俺は確かに聞いた。ずっと昔に失われたはずの、妹の穏やかな寝息の音を。そして、それに重なるように、オルゴールの最後のひとひらの旋律が、心の中で優しく響いた。
世界から、最後の音が消えた。
色彩も、形も、記憶も、喜びも、悲しみも、全てが等しく溶け合った、完全な静寂と忘却。
ただ、どこまでも広がる真っ白な曖昧さの中で、かつてオルゴールがあった場所が、一瞬だけ、星屑のように微かな光を放ち、そして静かに消えていった。