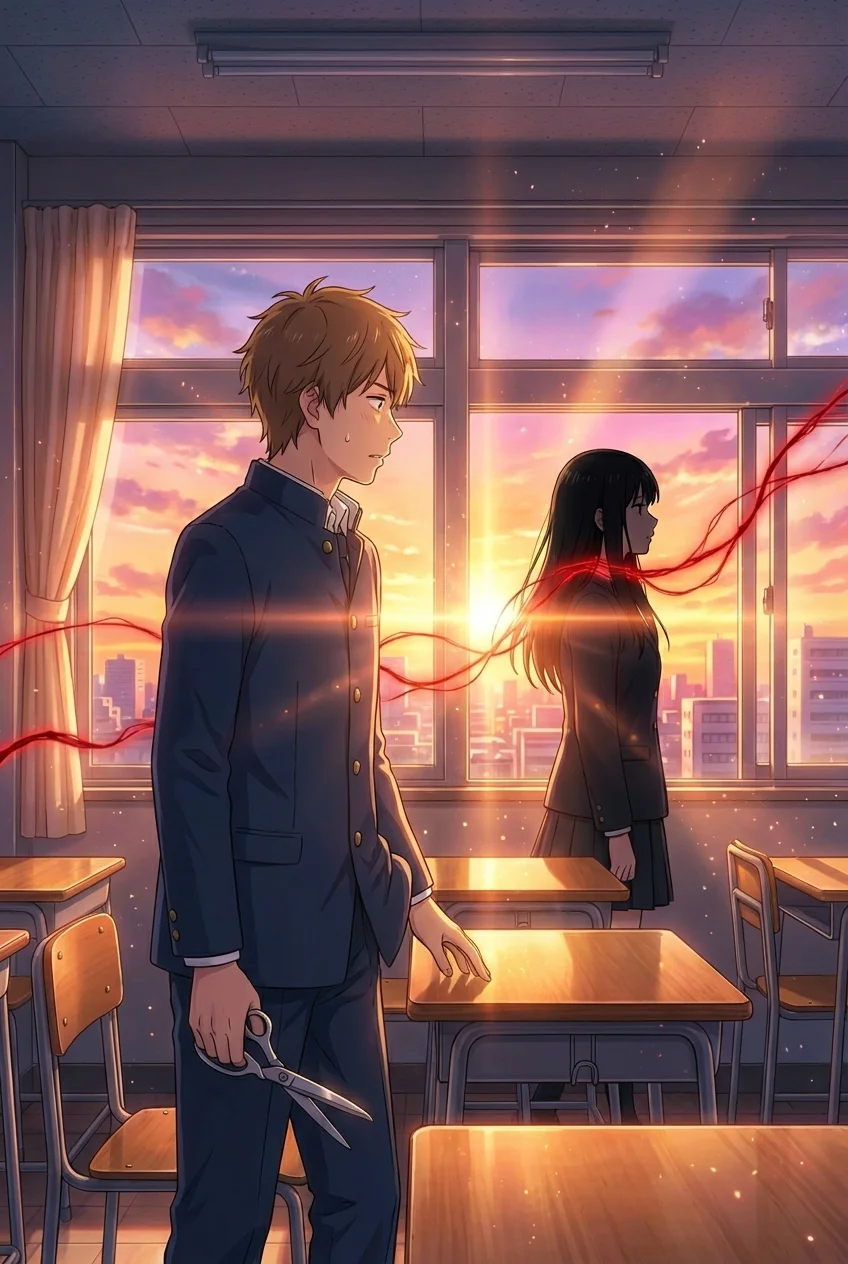第一章 歪んだ世界のノイズ
俺、湊(ミナト)の世界は、常に不協和音で満ちている。車の走行音は金属を引き裂く悲鳴となり、人々の話し声はガラスを掻きむしるノイズと化す。幼い頃の事故が俺の聴覚を歪ませて以来、世界は耐え難い騒音の集合体だった。
静寂を求め、俺は常に耳を塞ぐ。だが、完全に音を遮断することはできない。なぜなら、俺の脳には、この世界のどんな物理的な壁も突き抜けてくる、たった一つの『純粋な音』が届くからだ。
それは、人の心が生む『魂の絶叫』。死や破滅を目前にした人間が放つ、極限の恐怖。その純粋な音だけが、歪んだノイズの海の中で、唯一意味を持つ旋律として俺の脳内に直接響くのだ。絶叫は常に誰かの終焉を告げ、その持ち主の絶望を俺の精神に叩きつける。だから俺は、人との間に透明な壁を築き、孤独という名の静寂に逃げ込んできた。
そんな俺にも、たった一人だけ、世界のノイズを忘れさせてくれる存在がいた。親友の陽(ハル)だ。彼の屈託のない笑顔と、太陽のような声だけは、不思議と歪まずに俺の耳に届いた。
「ミナト、またそれ着けてるのか」
公園のベンチで、陽が俺の耳を指さす。そこには、父親が遺した耳栓のような形の『奇妙なイヤホン』が収まっていた。これだけが、外界のノイズをかろうじて耐えられるレベルまで減衰させてくれる、俺の生命線だった。
「まあな」
「最近さ、変なんだ。妙に静かな場所にいると、誰かの囁き声が聞こえる気がするんだよ。気のせいかな」
陽の何気ない一言に、俺の心臓が微かに軋んだ。気のせいだ、と俺は笑ってごまかしたが、その言葉はイヤホンを通り抜け、脳の奥に小さな棘のように突き刺さった。
第二章 未来からの絶叫
その夜、眠りについていた俺を叩き起こしたのは、過去に聞いたどの絶叫よりも長く、深く、そして鮮明な『魂の絶叫』だった。
それは嵐のように俺の精神を蹂躙し、焼き鏝を押し付けられたような激痛が頭蓋の内側を駆け巡った。
『ミナト……!』
絶叫は、俺の名前を呼んでいた。
全身の血が凍りつく。この声を知っている。毎日、俺の隣で笑っている、世界で唯一の、太陽の声。陽だ。
絶望、裏切り、拭い去れない後悔、そして自己の存在が溶解していく恐怖。奔流となって流れ込んでくる感情に、俺はベッドの上で蹲り、息を殺した。これは未来の陽の絶叫だ。彼は、破滅する。
俺は震える手でイヤホンを耳の奥深くまでねじ込んだ。陽を救わなければ。その一心で意識を集中させると、イヤホンは絶叫を増幅し、脳内に断片的なビジョンを投影し始めた。涙に濡れる陽の顔。複雑な機械に囲まれた、薄暗い研究室。そして、足元から砂のように崩れ落ちていく陽の身体。
これは呪いだ。俺の能力も、このイヤホンも、全てが呪われている。俺は父親が遺した書斎に駆け込み、埃をかぶった日記帳を夢中でめくった。そこには、震えるような文字でこう記されていた。
『このイヤホンは世界を『調律』するためのものだ。世界はあまりにうるさすぎる。静寂こそが救済だが、真の静寂は、最も恐ろしい絶叫を伴う』
第三章 呪いの調律
父親の日記とイヤホンが示すビジョンを頼りに、俺は世界の法則の根源を探った。人々が抱く秘密や罪悪感が『微細な音波』となり、世界に充満していること。そして、その音波が後悔によって増幅されると、人の存在そのものを消滅させてしまうこと。俺は、陽が絶叫の主となる理由を突き止めなければならなかった。
答えは、あまりにも残酷な形で俺の目の前に現れた。イヤホンが投影したビジョンの最後に映し出されたのは、血に濡れたアスファルトと、幼い頃の俺、そしてその隣で泣き叫ぶ、小さな陽の姿だった。
俺は陽のアパートに駆け込み、ドアを叩き続けた。
「お前だったのか」
現れた陽の顔は青ざめていた。
「俺の事故…お前が関係しているのか!?」
感情が爆発する。陽の肩を掴む手に、自分でも驚くほどの力が籠もっていた。
「ごめん…ごめん、ミナト…」
陽は崩れ落ち、嗚咽を漏らした。あの日、俺を驚かせようとした悪戯が、暴走してきた車に俺を突き飛ばす結果になったのだと。彼が長年抱え続けてきた罪悪感という名の『秘密の音』が、ついに彼自身の存在を喰らい尽くそうとしていた。
彼の後悔が、俺の呪われた聴覚を生んだ。そしてその聴覚が、今、彼の破滅を俺に告げている。なんと歪んだ円環だろうか。
第四章 沈黙の交響曲
陽を救う方法は、一つしかなかった。彼の罪悪感の根源である俺が、世界の全ての苦痛と後悔を引き受けること。イヤホンが導く先にある、全ての絶叫の源――『原初の絶叫』を、俺自身の魂で封印するのだ。
「お前のせいじゃない」
俺は泣きじゃくる陽の頭に、そっと手を置いた。
「俺が選んだんだ。静かな世界で、お前は生きてくれ」
俺はイヤホンを最大出力に設定した。瞬間、世界の全ての音が消え、意識は光の速さで深淵へと引きずり込まれていく。
そこに在ったのは、形なき、しかし確固たる意志を持つ『叫び』そのものだった。人類が初めて「無音」を恐れ、己の存在を証明するために放った、孤独と後悔の最初の産声。それが凝縮し、世界に呪いを振りまいていた。
『――来い』
俺は、その『原初の絶叫』に向かって両腕を広げた。俺の存在が粒子となって分解していく感覚。陽の記憶から、湊という親友がいた事実が、写真のインクが滲むように消えていく。
さようなら、陽。
世界から俺という音が消えた瞬間、完全な、それでいて鼓膜を圧迫するような『耳を覆いたくなるような沈黙』が訪れた。
第五章 静寂に響くエコー
数日後、陽は日常を生きていた。時折、理由のわからない喪失感が胸を締め付けるが、それが何なのかは思い出せない。ただ、世界が以前より少しだけ静かになった気がしていた。
ある夜、自室で本を読んでいると、陽はふと顔を上げた。
静寂の向こう側から、ごく微かに、しかし確かに、誰かの声が聞こえる。それは恐怖に満ちた絶叫ではなかった。どこか懐かしく、何かを守ろうとする強い意志を感じさせる、澄んだ音色だった。
その瞬間、陽の脳裏に、忘れ去られたはずの誰かの幻影が閃いた。
静かに微笑みながら、こちらを見ている。その唇が、音を発することなくゆっくりと動いた。
『助けて』
陽は、総毛立った。世界は静寂を手に入れたのではない。ただ、絶叫の交響曲の指揮者が、交代しただけなのだ。
そして陽は悟る。自分の耳に届き始めたこの新たな音が、自分にしか聞こえない、新たな物語の序曲であることを。空っぽになったはずの胸の中心で、忘れられた絆の残響が、確かに震えていた。