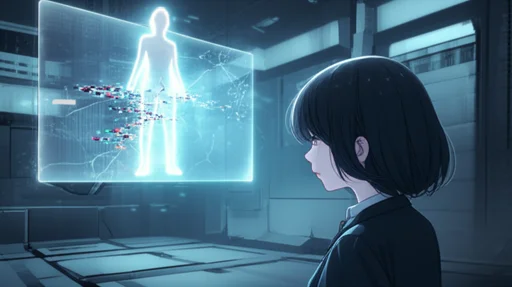第一章 死体は笑う
雨の匂い。
そして、鉄が鼻腔を突き刺すような、濃厚な血の臭気。
薄暗い書斎の空気が、澱んでいる。
重厚なオーク材の机に突っ伏している男。心理学の権威、エルンスト・フェルトマン博士。
その後頭部は、熟れすぎた柘榴のように砕けていた。
「……おい、レオン。どうだ?」
背後から、警部のしわがれた声。
俺は濡れたコートの襟を立てたまま、死体の傍らに屈み込む。
冷え切った博士の指先から転がり落ちた万年筆――モンブランのマイスターシュテュック。
俺は息を止め、その黒い軸に触れた。
刹那。
指先から脳髄へ、熱した鉛を流し込まれたような衝撃が走る。
視界が白く弾けた。
「ぐ、ッ……」
喉の奥から、意図しない音が漏れる。
胃袋が裏返るような吐き気ではない。
口角が、勝手に吊り上がるのだ。
頬が引きつる。
目尻が下がる。
止められない。
「おい、何がおかしいんだ?」
警部の不審げな声。
俺は震える手で顔を覆い、強引に表情筋を押し戻した。
「……違う」
「何がだ?」
「恐怖じゃない。痛みでも、後悔でもない」
俺は万年筆を握りしめる。
そこに焼き付いていたのは、頭蓋を砕かれる瞬間の記憶。
「『歓喜』だ」
俺の言葉に、警部が息を呑む気配がした。
「殺される瞬間、この男は……人生で最も甘美な夢を見ていた。恍惚の中で死んでいったんだ」
ありえない。
密室の惨殺死体だぞ?
だが、俺の指に残る熱は嘘をつかない。
そして、その圧倒的な幸福感の底に、泥のように沈殿している『何か』。
ドクン。
胸ポケットで、鼓動が跳ねた。
いや、心臓ではない。
懐中時計だ。
ガラスが割れ、針の止まった俺の時計が、熱を帯びて脈打ち始めたのだ。
この死体から感じる気配。
それは、俺が失ったはずの記憶の断片と、酷似していた。
第二章 空白の境界
「レオン、お前……手が」
警部の声が震えている。
俺は自分の右手を見た。
指の輪郭が曖昧に滲んでいる。
透けた皮膚の向こうに、書斎の壁紙の模様が見えた。
『同調(シンクロ)過多』。
死者の感情を取り込みすぎた代償。
俺という存在が、世界という枠組みから剥がれ落ち始めている。
「構うな」
「構うなだと? 消えかかってるんだぞ!」
俺は警部を無視し、机の上に散らばる原稿へ手を伸ばした。
博士が最期まで推敲していた論文だ。
タイトルは――『空白の境界に関する考察』。
抽象的な活字の羅列。
だが、紙面に指を滑らせた瞬間、インクに込められた執念が流れ込んでくる。
(足りない……あと一つ、楔(くさび)が必要だ……)
焦燥。
そして、狂気じみた献身。
視界がぐにゃりと歪む。
書斎の風景がセピア色に染まり、重力が消失する。
俺は直感した。
この机の引き出しの中に、全ての「答え」がある。
引き出しの把手に手を掛ける。
指先が激しく拒絶反応を起こした。
触れるな。
本能が警鐘を鳴らす。
これを開ければ、俺はもう「ここ」には戻れない。
ただの傍観者から、当事者へと引きずり込まれる。
「レオン! やめろ、顔色が土気色だ!」
警部が俺の肩を掴もうとする。
だがその手は、霞を掴むように俺の身体をすり抜けた。
「……ッ」
警部が悲鳴を上げて後ずさる。
もう後戻りはできない。
俺の魂には穴が開いている。
幼い頃の記憶がない。両親の顔も、愛された実感もない。
その空虚な穴を埋められるなら、肉体が消滅することなど、些細な代償だ。
俺は乾いた唇を舐め、震える指で引き出しをこじ開けた。
そこには、古びた封筒が一通。
宛名はない。
俺は覚悟を決め、その封筒を鷲掴みにした。
瞬間。
俺の世界が、音を立てて崩壊した。
第三章 止まった時計の鼓動
文字ではない。
言葉ですらない。
映像が、五感をジャックする。
『……オン、レオン』
温かい。
大きな手が、俺の小さな手を包み込んでいる。
見上げると、逆光の中で微笑む青年。
兄さん?
そうだ、俺には兄がいた。
俺の髪をくしゃくしゃに撫でる、不器用で優しい手。
場面が飛ぶ。
食卓。
柔らかなシチューの湯気。
母の笑い声。父の低い咳払い。
だが、その光景はノイズ交じりのテレビ画面のように明滅している。
『この子の能力は強すぎる』
父の深刻な声。
『世界が、レオンの存在を維持できない』
世界が俺を削り取っていく。
俺をこの世に繋ぎ止めるには、強烈な「重石」が必要だった。
ザァッ!
ノイズが走る。
父と母の姿が、光の粒子となって崩れていく。
死んだのではない。
自らの命を、俺という存在を固定するための「概念」へと変換したのだ。
残されたのは、幼い俺と、兄。
『僕がやるよ』
兄が、俺の壊れた懐中時計を握りしめている。
その背中が、今のフェルトマン博士の背中と重なった。
そうか。
博士なんて人間は最初からいなかった。
兄が、姿を変えて俺を見守っていたのだ。
俺の心の穴を埋める、最後のピースになるために。
映像が切り替わる。
今日の午後。この書斎。
背後に立つ影。
兄は振り向かない。
凶器が振り下ろされる風切り音。
その瞬間、兄の顔に浮かんだのは、満面の笑みだった。
痛みの予感よりも速く、安堵が彼を満たす。
これで完成する。
自分の死という衝撃(インパクト)をもって、弟に「真実」を叩き込む。
命を賭して、弟の孤独な記憶に「愛」という色を塗る。
頭蓋が砕ける音。
それは、兄にとって、俺を抱きしめる音と同じだった。
あふれ出す歓喜。
狂っている。
けれど、なんと温かく、透明な愛なのか。
俺の目から、熱い雫がこぼれ落ちた。
だが、それを拭う指の感触は、もうなかった。
第四章 透明なハッピーエンド
「……おい、レオン? どこへ行った?」
警部がキョロキョロと部屋を見回している。
俺は、彼の目の前に立っているのに。
「ここだ、警部」
声を出す。
だが、空気は震えない。
俺の声はもう、物理的な音波を持たないのだ。
自分の手を見る。
そこには何もなかった。
ただ、空間が陽炎のように揺らぎ、塵がキラキラと舞っているだけ。
俺は「視る」だけの存在になった。
世界の一部、あるいは空気そのものに。
恐怖はなかった。
胸の奥にずっと空いていた冷たい風穴が、今はどうしようもなく熱いもので満たされている。
父の厳しさ。
母の温もり。
そして、命を捨てて俺を完成させた、兄の愚直な愛。
チク、タク。
音がした。
幻聴ではない。
俺の意識の中で、止まっていた懐中時計の針が、十数年ぶりに時を刻み始めたのだ。
肉体を失うことで、俺の時間はようやく動き出した。
「うッ……?」
不意に、警部が身震いをして自分の二の腕をさすった。
「なんだ? 急に寒気が……」
警部は不思議そうに、俺が立っている「空間」を見つめる。
見えてはいない。
だが、感じてくれている。
俺はそっと、警部の肩に手を置いた――つもりになった。
「ありがとう、警部。元気で」
警部はハッとしたように顔を上げ、周囲を見渡した。
しかし、そこには誰もいない。
彼は首を傾げ、静まり返った書斎を後にした。
俺は一人、部屋に残る。
もう孤独ではなかった。
窓の外、雨はいつの間にか上がっている。
雲の切れ間から差し込む夕陽が、俺という透明な存在を貫き、床に黄金色の光だまりを作っていた。