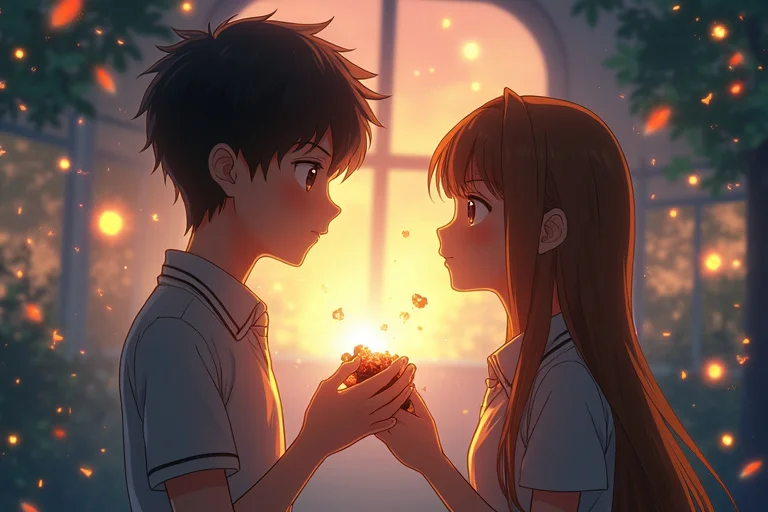第一章 灰色の教室、極彩色の絶望
喉の奥に、べとりと張り付くような甘ったるい匂いがした。
砂糖と鉄錆を混ぜて、強火で焦がしたような悪臭だ。
僕は口元をハンカチで覆いながら、隣の席を見る。
匂いの源泉は、そこにある。
ミナだ。
彼女は答案用紙に覆いかぶさるようにして、鉛筆を走らせている。
カリ、カリ、ガリッ。
芯が紙を削る音が、異常なほど教室に響く。
彼女の背中からは、陽炎のような赤色が立ち昇っていた。
皮膚が焼け爛れるのではないかと思うほどの、灼熱の赤。
『情熱』の色だ。
ミナの鉛筆を握る右手が小刻みに震えている。
指先は血流を失い、死人のように白い。
彼女は今、自分の魂を燃料にくべて、数学の難問という壁を焼き払おうとしている。
見ていられない、と誰もが顔を背ける。
けれど僕だけは、その光景から目を離せない。
恐怖も、同情もない。
ただ、背筋が寒いだけだ。
これほどの激しい感情の奔流を目の当たりにしても、僕の心臓は少しも脈拍を変えない。
それがどうしようもなく、寒い。
バキンッ。
乾いた音がして、鉛筆の芯が折れた。
同時に、立ち昇っていた赤色がフッと消える。
あとには、ドブ川のような薄汚れた灰色だけが残った。
「……できた」
ミナが顔を上げる。
焦点が合っていない。
瞳孔が開いたその目は、深海の魚のように暗く、光を失っている。
「ねえ、時雨くん」
掠れた声。
「私、なにがしたかったんだっけ」
彼女は笑おうとして、頬を引きつらせた。
『情熱』を燃やし尽くした廃人の顔だ。
僕は反射的に、口角を持ち上げる。
眼輪筋を緩め、眉尻を下げる。
鏡の前で何千回も練習した、「親身な友人」の表情だ。
「頑張りすぎだよ、ミナ。少し休もう」
彼女の肩に手を置く。
シャツ越しに伝わる体温は、氷のように冷たい。
教室を見渡す。
吐き気がするほどの極彩色が、視界を埋め尽くしている。
テストの点数に一喜一憂する、弾けるような黄色。
将来への不安に蝕まれる、重苦しい群青色。
他者を蹴落とそうとする、粘着質な紫。
誰も彼もが、感情という絵の具を垂れ流し、空気を汚染している。
世界はこんなにも騒がしく、鮮やかだというのに。
窓ガラスに映る僕だけが、切り抜かれたように透明だった。
肉体はある。
けれど、僕を縁取る色はどこにもない。
喜怒哀楽、そのどれもが僕の中を素通りしていく。
「時雨、顔色が悪いぞ」
不意に声をかけられ、僕は作った笑顔のまま振り返る。
幼馴染のケントだ。
彼の周りには、新緑のような穏やかな若草色が漂っている。
「ちょっと、匂いに酔っただけさ」
「またか。お前は感覚が鋭すぎるんだよ」
ケントが苦笑して、僕の背中を叩く。
その掌から流れ込む「優しさ」の色が、僕の皮膚を滑り落ちていく。
受け止められない。
彼が心配してくれればくれるほど、僕は自分の空虚さを突きつけられる。
僕は化け物だ。
人の心が形として見えるのに、自分だけがその形を持たない。
ただ周囲の色を反射し、人間らしく振る舞うだけの、精巧なガラス細工。
その時だった。
キィィィィィン――!
鼓膜を直接針で刺されたような、鋭利な耳鳴りが走った。
「うっ、なんだ!?」
ケントが耳を塞いで蹲る。
教室中の生徒が悲鳴を上げ、ガラス窓がビリビリと共振した。
僕は窓の外へ視線を走らせる。
学園の中央、時計台。
その最上階にあるはずの『廻色(かいしょく)の砂時計』。
人々の感情を循環させる巨大な装置。
いつもなら透明な砂がサラサラと流れているガラスケースの中が、異常な色に染まっていた。
黒だ。
あらゆる絵の具を混ぜ合わせ、煮詰めたような、ドロリとした黒。
違う。
あれは色じゃない。
色の死骸だ。
ドクン、と。
動くはずのない僕の心臓が、早鐘を打った。
恐怖ではない。
あの黒い虚無に、僕の中の空洞が共鳴しているのだ。
日常が、音を立てて崩れ去ろうとしていた。
第二章 空白の英雄、アオイ
「うわああああっ!」
獣の咆哮のような叫び声が、廊下を震わせた。
僕は教室を飛び出す。
本能が警鐘を鳴らしていた。
あの「黒」が、溢れ出している。
廊下は地獄絵図だった。
壁が砕け、粉塵が舞う中、一人の男子生徒が暴れている。
彼の全身から噴き出しているのは、本来なら『剛力』を示す黄金色のオーラだ。
だが今は、その光に黒い染みが混じり、腐った果実のように明滅している。
「痛い、痛い、熱い!」
彼は自分の喉を掻きむしりながら、手当たり次第にロッカーを殴り飛ばしていた。
感情が制御できない。
色が彼を内側から食い破ろうとしている。
「離れろ! 近づくな!」
教師たちの怒号が飛ぶ。
だが、誰も彼に触れられない。
触れた瞬間に、暴走した感情の濁流に飲み込まれるからだ。
僕は、迷わず彼へと歩き出した。
「時雨!?」
背後でケントの制止する声が聞こえる。
構わない。
僕には聞こえているのだ。
暴れる生徒の心から発せられる、助けてくれという悲痛なノイズが。
彼が僕に気づく。
血走った目が僕を捉え、丸太のような腕が振り下ろされた。
死ぬかもしれない。
そう思考するより早く、僕は一歩踏み込んでいた。
恐怖はない。
だって僕には、失うべき「色」がないのだから。
ドォォォン!
衝撃が走る。
僕は彼の拳を、正面から受け止めていた。
いや、正確には違う。
彼の拳が触れた瞬間、僕の体はスポンジのように彼のオーラを吸い込んだ。
(……ああ、やっぱり)
僕の体の中を、熱した鉛のようなエネルギーが通り抜けていく。
普通の人間なら発狂するほどの憎悪と苦痛。
だが、空っぽの僕にとっては、ただの「通り過ぎる風」に過ぎない。
「が、ぁ……?」
生徒の動きが止まる。
彼の体から毒々しい色が抜け、僕の背中から霧散していく。
濾過(ろか)。
無色透明な僕の魂が、汚れた色を洗い流したのだ。
彼は糸が切れたように崩れ落ちた。
荒い息を吐きながらも、その顔には安堵の色が浮かんでいる。
「……君は、便利だね」
頭上から、冷ややかな声が降ってきた。
温度のない、氷のような声。
見上げると、砕けた天井の梁の上に、人影があった。
青白い肌。
色素の薄い髪。
そして、僕と同じ、何も映さない『無色』の瞳。
「アオイ……」
かつて学園から姿を消した天才。
そして、この異常事態を引き起こした張本人。
彼は重力を無視した動きで、音もなく僕の前に降り立った。
彼からは、何の匂いもしない。
生命感というものが欠落している。
「どういうつもりだ。あの黒い砂は、君がやったのか」
僕が問うと、アオイは薄く笑った。
その笑顔もまた、僕と同じように筋肉を動かしただけの作り物だった。
「救済だよ、時雨」
「救済?」
「感情なんてものは、人を傷つけ、すり減らすだけの呪いだ。見ただろう? あの生徒の苦しみを」
アオイが一歩近づく。
肌が粟立つような圧迫感。
彼もまた、僕と同じ虚無を抱えている。
だが、その深さは僕の比ではない。
「僕はね、他人の色がうるさくて仕方がないんだ。混ざり合い、濁り、腐っていく色を見るたびに、吐き気がする」
彼はポケットから小さな瓶を取り出した。
中には、あの時計台と同じ、どす黒い液体が入っている。
「だから、すべてを消すことにした。世界を無色に戻せば、もう誰も傷つかない。静寂だけが残る美しい世界になる」
「そんなの、死んでいるのと同じだ!」
「生きながら腐るよりは、ずっとマシさ」
アオイの姿が、陽炎のように揺らぎ始めた。
「時計台で待っているよ。砂時計が完全に黒く染まるまで、あと十分。君ならわかるはずだ。この『無』の心地よさが」
言い捨てて、彼は消えた。
後には、再び騒がしさを取り戻した廊下と、立ち尽くす僕だけが残された。
僕は自分の手を見る。
無色透明な掌。
アオイの言う通りかもしれない。
感情なんてなければ、ミナがあんなに苦しむこともなかった。
僕が嘘の笑顔を作る必要もなかった。
けれど。
僕の掌には、さっき助けた生徒の体温が、微かに残っていた。
第三章 無色の受容
時計台への螺旋階段を駆け上がる。
肺が焼けつくように熱い。
足が鉛のように重い。
窓の外は、すでに異界と化していた。
空は紫色の雲に覆われ、地面からは灰色の霧が湧き出している。
世界から「鮮やかさ」が失われつつあった。
「はっ、はっ、はっ……」
最上階の大扉を蹴破る。
そこには、終焉の光景が広がっていた。
巨大な『廻色の砂時計』。
そのガラスの中で、黒い泥が奔流となって滴り落ちている。
もう下半分は完全に黒に染まっていた。
その前に、アオイが立っていた。
指揮者のように両手を広げ、崩壊の時を待っている。
「来たか。でも、もう遅い」
アオイは振り返りもしない。
「あと一滴で、臨界点を超える。世界中の色がリセットされ、僕たちの望む静寂が訪れる」
「僕の望みじゃない!」
僕は叫び、彼に向かって走る。
アオイが指を弾く。
ドンッ! と見えない壁に弾き飛ばされ、僕は床に叩きつけられた。
「なぜ拒む? 君は空っぽだ。誰とも混ざり合えない孤独を知っているはずだ」
アオイが振り返る。
その瞳の奥に、初めて『色』が見えた。
深い、深海のような孤独の藍色。
彼もまた、泣いていたのだ。
誰かの色に触れるたび、自分が何者でもないことを突きつけられる痛みに。
「ああ、知ってるよ。自分が幽霊みたいで、寂しくて、惨めで……」
僕は痛む体を起こす。
「でも、空っぽだからこそ、できることがある!」
ミナの情熱の赤。
ケントの優しさの緑。
暴走した生徒の、生きようとする金色の輝き。
それらが僕の中を通り過ぎる時、確かに僕は「熱」を感じていた。
「僕は色を持たない。だからこそ、誰かの色を濁らせずに受け止められる。光を分けるプリズムになれるんだ!」
「プリズムだと……?」
「君はノイズとして世界を拒絶した。僕は、そのノイズごとかき抱く!」
僕はアオイではなく、砂時計に向かって飛んだ。
黒い泥が詰まったガラス面に、両手を叩きつける。
「やめろ! 君の自我が崩壊するぞ!」
アオイの叫びは聞こえない。
僕の魂の蓋を、全開にする。
来い。
全部、僕の中を通っていけ。
ズドンッ!!
学園中から吸い上げられた感情の濁流が、僕の体に流れ込んできた。
熱い、痛い、苦しい、悲しい、嬉しい、愛しい。
何千、何万という他人の人生が、僕の血管を駆け巡る。
脳が焼き切れそうだ。
自分が溶けて消えてしまいそうだ。
けれど、僕は歯を食いしばる。
拒絶するな。
飲み込め。
このドブのような黒い色は、誰かの切実な思いの成れの果てだ。
(通れ……ッ!)
僕の体が、強烈な光を放った。
赤でも青でもない。
すべての色が重なり合い、極限まで純化された『透明な光』。
「馬鹿な……黒を、光に変えたのか?」
アオイが目を見開いて後ずさる。
僕というフィルターを通すことで、淀んだ感情が濾過されていく。
黒い泥が、さらさらと美しいダイヤモンドダストのような砂に変わり、砂時計の中を逆流し始めた。
光が溢れる。
時計台の鐘が、高らかに鳴り響いた。
ゴォォォォ……ン。
それは終わりの鐘ではない。
世界が再び、呼吸を始めた音だった。
光の中で、僕は見た。
アオイの体にまとわりついていた孤独の藍色が、僕の光に触れ、柔らかな空色へと溶けていくのを。
「……そうか」
アオイが膝をつく。
その表情は、憑き物が落ちたように穏やかだった。
「拒絶するのではなく、透き通らせればよかったのか」
彼の頬を、一筋の涙が伝う。
その涙は、夕焼けのような茜色に輝いていた。
光が収束する。
窓の外には、雨上がりのような突き抜けた青空が広がっていた。
僕は床に大の字に倒れ込み、荒い息を吐く。
生きてる。
手を見る。
やはり、僕の手には何の色もついていない。
相変わらずの、無色透明。
けれど、胸の奥には、じんわりとした温かさが残っていた。
たくさんの色が通り過ぎていった、確かな熱の余韻。
「……君の勝ちだ、時雨」
アオイが力なく笑う。
「勝ち負けじゃないよ。ただ、君の色も綺麗だったって伝えたかっただけさ」
僕は体を起こし、彼に手を差し伸べた。
アオイが躊躇いながら、その手を握り返す。
彼の手は温かかった。
世界は色に溢れている。
時に濁り、傷つけ合い、目を覆いたくなるような色も生まれるだろう。
でも、僕はもう目を背けない。
この透明な心で、世界のすべてを愛していける。
僕だけが、無色透明だ。
そして、それでいいのだと、今は心からそう思える。