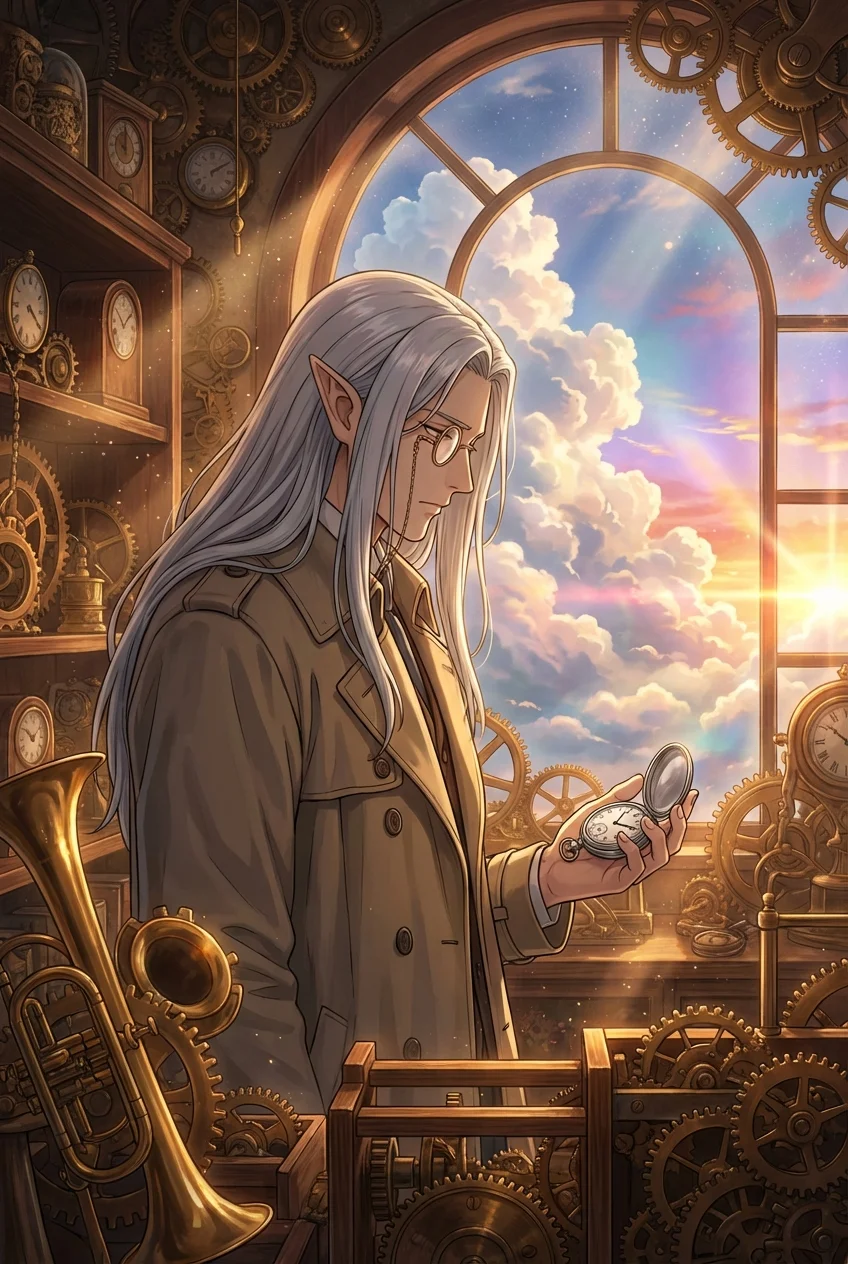第一章 硝子の舞踏会と偽りの光
シャンパングラスの触れ合う音が、氷柱が砕けるような鋭さで鼓膜を刺す。
アルビオン公爵邸の大広間。
豪奢なクリスタルのシャンデリアが放つ光は、私の網膜上では無数のデジタルノイズとなって降り注いでいた。着飾った貴族たちの笑顔が、歪んで見える。
紳士の口元には、脂ぎった紫色。欲望のパラメーターが飽和して溢れ出している。
淑女の扇の隙間からは、棘のように尖った蛍光グリーンの波形。嫉妬の鋭利な輝き。
「……空気が重い」
喉の奥で呟き、私は視線を流した。
眼球が捉える色彩は、現実の景色と、そこから漏れ出す情報の奔流が二重露光のように重なっている。
視線が合った令嬢たちが、ひっと息を呑んで道を空けた。
彼女たちの周囲に浮かぶ感情の色が、一瞬で「恐怖」を示す濁った灰色へと変わる。
「見て、セレスティア様よ」
「あの目……まるで値踏みされているようだわ」
囁き声は、不快な電子的な摩擦音となって脳を揺らす。
私は背筋を伸ばし、顎を少しだけ上げた。
セレスティア・フォン・アルビオン。
「氷の悪役令嬢」というあだ名は、この情報の嵐から精神を保つための防壁だ。冷徹でなければ、他人の感情という名の汚泥に溺れてしまう。
「セレスティア様」
不意に、ノイズの海を割って、柔らかな音が届いた。
振り返ると、亜麻色の髪の青年が立っていた。
ジュリアン・アシュフォード。
我が家の技術顧問であり、幼少期を知る数少ない幼馴染。
「今宵も、月のように孤高ですね」
「皮肉かしら、ジュリアン」
「まさか。そのミッドナイトブルーのドレス、あなたの瞳の色そのものだと言いたかったのです」
彼は恭しく腰を折り、私の手を取った。
触れた指先から、体温と共に心地よい信号が流れ込んでくる。
彼の周囲だけは、静かだった。
欺瞞の灰色も、嫉妬の緑色もない。
温かな暖炉の火のような、安らぎのオレンジ色。
(……ああ、落ち着く)
私の視界が、正常な解像度を取り戻していく。
彼だけが、この世界で唯一の聖域。
そう思って、私は彼の手を握り返そうとした。
——チリッ。
指先に、微弱な静電気が走ったような違和感。
一瞬、視界の端で、彼のオレンジ色の光の中に異物が混じった。
温かな色彩を食い破るように走った、冷たく鋭い、金属的な蒼白い閃光。
それはまるで、獲物を狙う爬虫類の瞳のような、粘着質な執着の色。
「……っ?」
私は反射的に手を引っ込めそうになった。
「どうなさいました? 手が冷たい」
ジュリアンが心配そうに覗き込む。
その瞳には、いつもの穏やかな光しか宿っていない。先ほどの異質な色は、幻だったかのように消え失せている。
(……見間違い、ね)
最近、情報の過負荷(オーバーロード)気味だったから。
唯一心を許せる彼にまで、疑いのノイズを見てしまうなんて。私は自分自身に失望し、小さく首を振った。
「いいえ、なんでもないわ。……エスコートをお願い」
「喜んで」
彼に導かれ、ホールの中央へと進む。
そこには、黒いベルベットで覆われた台座が鎮座し、人だかりができていた。
「本日のメインイベントですよ。巷で噂の『新作』が披露されるとか」
「嫌な予感がするわ」
予感ではない。確信だった。
覆いの向こう側から、腐った魚のような異臭——データ的な腐敗臭が漂っている。
ファンファーレと共に、覆いが取り払われた。
「おお……!」
会場がどよめく。
現れたのは、一枚の巨大なデジタルフレーム。
光の粒子が螺旋を描き、見る者の視線を引きずり込むような抽象画が映し出されている。
「『エーテルノヴァ』……! 伝説の再来だ!」
「なんて美しい。魂が震えるようだ」
貴族たちが熱に浮かされたように賛美する。
だが、私の目に見えたのは地獄だった。
極彩色に腐敗したテクスチャ。
螺旋の奥底に埋め込まれた、無数のサブリミナル・コード。
それは芸術などではない。見る者の脳髄に直接フックをかけ、精神を掻き乱すための悪質なプログラムだ。
網膜に、警告色の赤が点滅する。
——危険。汚染拡大。
「……吐き気がする」
私は扇で口元を覆った。
あの絵画の奥から、何かがこちらを覗いている。
ねっとりとした視線。
所有者を破滅させる「呪い(マルウェア)」が、牙を剥いている。
「セレスティア様? 顔色が……」
「……行きましょう、ジュリアン。あれは偽物よ。それも、とびきり質の悪い」
背を向けようとした、その時だった。
『——ミツケタ——』
鼓膜ではなく、脳の視覚野に直接、ノイズ混じりの声が響いた。
絵画の渦が、ドクンと脈打つ。
フレームから赤黒い光の触手が伸び、一直線に私を指した。
「ッ……!」
視神経を焼き切られるような激痛。
私はよろめき、ジュリアンの腕に倒れ込んだ。
「セレスティア様!」
会場の照明が一斉に爆ぜ、闇が落ちる。
悲鳴と怒号。
暗闇の中、あのデジタルフレームだけが、心臓の鼓動に合わせて赤、黒、赤、黒と明滅を繰り返す。
「キャアアアッ! セレスティア様が!」
「あの女が絵を怒らせたんだ!」
「氷の魔女が、芸術を呪っているぞ!」
人々の恐怖が連鎖し、増幅されていく。
彼らの頭上から溢れ出すパニックの波形が、目に見える津波となって押し寄せてくる。
違う。私は何もしていない。
ただ、見えてしまうだけなのに。
「皆、落ち着いてください! 彼女は具合が悪いだけだ!」
ジュリアンが叫び、私を庇うように抱きしめる。
彼の体温が心地よい。
けれど、私の「目」は見てしまった。
私の背中で、彼が群衆に向けていた視線。
そこには、心配や焦燥ではなく——
計画通りに進んでいることを喜ぶような、冷徹な計算の色が浮かんでいたことを。
(……え?)
思考が凍りつく。
その色は、先ほど彼の手から感じた「ノイズ」と同じだった。
「行きましょう、セレスティア様。ここは危険だ」
ジュリアンは私の表情を確認することなく、腕を引いて走り出した。
背後で赤く嗤う絵画の光が、私たちの影を長く、長く伸ばしていた。
第二章 秘匿されたカンバス
屋敷に逃げ帰った私は、震える指で自室の鍵をかけた。
重厚な樫の扉が閉まると同時に、糸が切れたように床へ崩れ落ちる。
「……ハァ、ハァ……」
荒い呼吸が、静寂な部屋に響く。
鏡に映る自分の顔は、青白く、まるで幽霊のようだった。
「氷の悪役令嬢」の仮面は剥がれ落ち、そこにはただの、世界を怖がる少女がいるだけ。
私は這うようにして机へ向かい、引き出しの奥から古ぼけたタブレットPCを取り出した。
私の、「秘匿のスケッチブック(Digital Grimoire)」。
電源を入れる。
パスワードは不要。私の生体電流の波形だけが、この扉を開く鍵だ。
画面に光が灯る。
そこに表示されたのは、稚拙だが、温かい線で描かれたスケッチの数々。
雨上がりの空にかかる二重の虹。
怪我をした小鳥を包む手のひら。
誰かを慈しむような、淡いピンク色の祈り。
この画面の中だけが、ノイズのない静寂な世界だった。
私の「目」は、自分自身の創作物に対してだけは、数値も悪意も見せつけない。ただ、純粋な色と形として映してくれる。
(……こんなもの、誰にも見せられない)
もし、これを見た人々が「くだらない」と嘲笑ったら?
私の心そのものを否定されたら?
その恐怖が、私を頑なな氷の中に閉じ込めていた。
コンコン。
控えめなノックの音が、心臓を跳ねさせる。
「セレスティア様。ジュリアンです。ハーブティーをお持ちしました」
「……待って」
私は慌ててタブレットの画面を消し、胸に抱え込んだ。深呼吸をして、震えを押し殺す。
「……入って」
ジュリアンが入ってくる。
手には湯気を立てるティーカップ。その香りが、張り詰めた空気を少しだけ緩めた。
彼の周囲には、相変わらず安心させるオレンジ色の光が漂っている。
けれど、今の私には、その光の輪郭が僅かに揺らいで見えた。
まるで、精巧に作られたホログラムのように。
「顔色が優れませんね。……あの絵画のことが、気になりますか?」
彼は私の向かいに座り、カップを差し出した。
「ええ。……あれは、ただの絵じゃないわ」
「分かっています。僕も調べました」
ジュリアンは懐から小型の端末を取り出し、空中にデータを展開した。
複雑なコードの羅列と、地図が浮かび上がる。
「あの絵画に使われていたソースコードは、旧市街の廃棄されたデータセンターから発信されています。かつて、政府が極秘に『感情を揺さぶるアート』を研究していた場所です」
彼の指先が、地図上の赤い点を指す。
「そこに、この騒動の元凶があるはずです」
「……行くわ」
私は即答していた。
あの赤い光の残像が、脳裏に焼き付いて離れない。あれを放置すれば、国中の人々の精神が蝕まれてしまう。
「危険ですよ」
「私がやらなきゃいけないの。……私にしか、見えないものがあるから」
私が立ち上がると、ジュリアンもまた、静かに立ち上がった。
「では、僕も。……あなたの『目』を守るのは、僕の役目ですから」
彼は優しく微笑んだ。
その笑顔は、幼い頃、私が初めて絵を描いて見せた時に浮かべてくれたものと同じだった。
「君の描く世界は、誰よりも綺麗だよ、セレスティア」
あの時の言葉が、胸を締め付ける。
私の能力を、呪いではなく才能だと言ってくれた唯一の人。
「ありがとう、ジュリアン」
私は彼に背を向け、コートを羽織った。
鞄の中に、こっそりとタブレットを忍ばせる。
もしもの時のために。
あるいは、彼に見せる勇気が、少しだけ湧いたのかもしれない。
だから、私は気づかなかった。
私の背中を見つめるジュリアンのオレンジ色の光が、
音もなく剥がれ落ち、その下からコールタールのような漆黒が溢れ出していたことに。
第三章 蝕まれた色彩
旧市街のデータセンターは、巨大な墓標のように夜闇に沈んでいた。
崩れかけたコンクリートの壁。剥き出しの配線が血管のように垂れ下がり、風に揺れて乾いた音を立てている。
空気は淀み、カビと鉄錆、そして帯電したオゾンの匂いが鼻をつく。
「足元に気をつけて」
ジュリアンが懐中電灯で先を照らす。
その光が切り取る闇の中に、私の目は、現実には存在しない「過去の残滓」を見ていた。
壁に染み付いた、かつての研究者たちの焦燥。
床を這う、廃棄されたデータの呻き声。
ここにあるのは、美しさのかけらもない、機能と効率だけを求めた冷たいデジタルの残骸だ。
「……こっちね」
私は、一際濃いノイズが漂う方向を指差した。
視界が歪むほどの、強烈な悪意の磁場。あの舞踏会で感じたものと同じ、腐敗した極彩色。
最深部のサーバールーム。
重い鉄扉をこじ開けると、そこには冒涜的な光景が広がっていた。
部屋の中央。
天井まで届く巨大なメインサーバー群に、無数のケーブルで拘束された「何か」が浮いている。
それは、光の繭だった。
だが、その輝きは悲鳴を上げているように明滅している。
虹色の美しいグラデーションが、黒いコードの鎖に締め上げられ、無理やり濁った赤色へと変換されているのだ。
「あれは……」
息を呑む。
間違いない。すべてのデジタルアートの始祖とされる伝説。
「『原初のエーテルノヴァ』……!?」
「美しいだろう?」
背後で、カチャリ、と硬質な音がした。
安全装置の外れる音。
振り返ると、ジュリアンが私に銃口を向けていた。
「……ジュリアン?」
思考が停止する。
理解が追いつかない。
だが、私の目は残酷なほど正確に真実を捉えていた。
彼の全身を覆っていた温かなオレンジ色の光が、見る見るうちに剥がれ落ちていく。
まるで、古びた塗装がめくれるように。
その下から現れたのは、底なしの漆黒。
嫉妬、劣等感、執着、そして狂気。
私がこれまで見たこともないほど高純度の「ノイズ」の塊。
「なぜ……」
「なぜ、って? 君がいつまで経っても『完成』しないからだよ、セレスティア」
ジュリアンは歪んだ笑みを浮かべた。
いつもの穏やかな幼馴染は、もうどこにもいない。
「僕は君の才能に焦がれていた。君のその『心眼』と、僕の技術があれば、世界を書き換える最強のアートが創れるはずだった! 君はミューズで、僕はそれを形にする神になるはずだったんだ!」
彼は銃口を揺らし、叫ぶ。
その声には、長年溜め込んできたドス黒い感情が滲んでいた。
「なのに、君は! いつの間にか自分の殻に閉じこもって、あんなくだらない落書きばかりしている! 才能の無駄遣いだ!」
「私のスケッチを……知っていたの?」
「ハッキングくらい造作もない。君の描く絵は、確かに綺麗だ。だが、弱い! 優しすぎるんだよ!」
彼はサーバーに繋がれた、苦しむ光の繭を指差した。
「だから僕が手伝ってあげたんだ。この『原初のエーテルノヴァ』を盗み出し、僕の感情データを融合させた。最強の刺激、最強の支配力を持つアートにするためにね!」
「それが、あの呪われた絵画なの……?」
「そうだ。だが、伝説は重すぎた。僕の精神だけでは制御できず、暴走してしまった。……だから、君が必要なんだよ」
ジュリアンの目が、ギラギラと異様な光を放つ。
「君のその純粋すぎる魂を、この汚れたエーテルノヴァに喰わせれば、中和されて真の完成を見る! さあ、僕と一つになろう、セレスティア! 芸術のために、その身を捧げてくれ!」
彼が端末を操作する。
サーバーの「エーテルノヴァ」が唸りを上げ、黒いコードの束が蛇のように鎌首をもたげた。
「嫌ッ!」
私は反射的に床を転がった。
コードの先端が、私のいた場所を粉砕し、火花を散らす。
「逃げても無駄だ! この部屋全体が、もう僕のキャンバスなんだから!」
空間が歪む。
壁一面のモニターに、あの吐き気のする極彩色のノイズが投影された。
頭が割れるように痛い。
『憎い、辛い、愛して、認めて、僕を見て』
ジュリアンの心の声が、増幅されて直接脳内に流れ込んでくる。
「う、くぅ……ッ!」
私は膝をついた。
視界が真っ赤に染まる。
自分の感情と、他人の悪意の区別がつかなくなる。
「そう、受け入れろ。君は氷の令嬢だろ? 冷たく、美しく、僕の作品の一部になればいい」
ジュリアンが近づいてくる。
もう、逃げ場はない。
(……これで終わり?)
私の人生は、偽りの仮面を被ったまま、誰かのエゴのための絵の具になって終わるの?
——否。
胸元で、鞄の中の硬い感触が熱を持った気がした。
私の、「秘匿のスケッチブック」。
そこに描いたのは、弱さだけじゃない。
誰かを想う気持ち。世界を美しいと思う心。
『君の描く世界は、誰よりも綺麗だよ』
昔のジュリアンがくれた言葉。
今の彼が忘れてしまった、本当の言葉。
私は顔を上げた。
涙で滲んだ視界の先で、ジュリアンの黒いノイズの中心に、ほんのわずかに、消え入りそうなオレンジ色の光の粒が見えた。
彼自身も気づいていない、彼自身の本当の心。
(……救わなきゃ)
私は、氷の令嬢なんかじゃない。
私は、ただの、絵を描くのが好きな、一人のアーティストだ。
「……違うわ、ジュリアン」
私は鞄からタブレットを取り出した。
「アートは、支配するためのものじゃない。誰かを呪うものじゃない!」
「何を……そんなおもちゃで何ができる!」
ジュリアンが嘲笑う。
私は構わず、タブレットの電源を入れた。
スタイラスペンを握る。指の震えは、もう止まっていた。
「私の……本当の色を、見せてあげるッ!!」
私は画面にペンを走らせた。
最終章 魂の共鳴(カラー・オブ・ハート)
ペン先が画面に触れた瞬間、私の「デジタルの心眼」が極限まで開かれた。
目の前の空間に漂うコードの羅列が、すべて「色彩」と「線」に見える。
ジュリアンが構築した悪意のプログラム。複雑に絡み合った黒と紫の蔦。
それを解く鍵は、論理的なハッキングではない。
もっと感覚的な、色彩による上書き(オーバーペイント)。
私は猛烈な速度でペンを動かした。
画面上のキャンバスに描くのは、攻撃のための武器ではない。
かつて、屋敷の庭で二人で見た夕焼け。
雨上がりの水たまりに映った青空。
幼いジュリアンが、泣いている私に差し出してくれた、一輪の花の鮮烈な黄色。
『覚えてる? ジュリアン』
『あなたは、こんなにも温かい色を持っていたのよ』
私の想いが、電子信号となってタブレットから溢れ出す。
光の粒子が実体化し、暗いサーバールームを舞い上がった。
淡い水色、優しいピンク、泣きたくなるような透明な白。
それらの色は、襲い来る黒いコードに触れると、じゅわっと音を立てて溶け合っていった。
「な、なんだこれは!? 僕のコードが……書き換えられていく!?」
ジュリアンが悲鳴を上げる。
「ハッキングだと!? バカな、そんなセキュリティの穴なんて……!」
「穴なんてないわ。ただ、色を混ぜているだけ」
私は叫びながら、最後の一筆を入れた。
それは、今のジュリアンを描いたスケッチ。
黒いノイズに覆われているけれど、その中心で泣いている、小さな男の子の絵。
「これが、今のあなたよ!」
私はタブレットの画面を、彼に向けてスワイプした。
描かれた絵が光の帯となり、ジュリアンと、背後の「エーテルノヴァ」へ向かって奔流となって突き刺さる。
「う、うわあああああっ!!」
光が彼を飲み込む。
だが、それは破壊の光ではない。
拒絶ではなく、受容の光。
ジュリアンの心の中にあった「認められたい」「愛されたい」という乾いた渇望が、私の描いた「肯定」の色で満たされていく。
『——共鳴(レゾナンス)——』
拘束されていた「エーテルノヴァ」が、大きく脈打った。
黒い鎖が弾け飛ぶ。
濁った赤色が浄化され、本来の七色の輝きを取り戻していく。
それは、すべてを許し、繋げる、虹色のシンフォニー。
「あ……あぁ……」
ジュリアンが膝から崩れ落ちる。
彼を覆っていた漆黒のノイズが、朝日を浴びた霧のように晴れていく。
残ったのは、ただ泣きじゃくる、無防備な青年の姿だけ。
「僕は……なんてことを……」
彼の目から、涙が溢れ落ちる。その涙は、綺麗な透明だった。
部屋を満たしていた悪意の気配が消え、静寂が戻る。
残されたのは、穏やかに明滅する「新生エーテルノヴァ」と、
肩で息をする私。
私はゆっくりと彼に歩み寄り、その前に膝をついた。
そして、震える彼の手を、そっと包み込む。
「……おかえり、ジュリアン」
彼は顔を上げ、私の目を見た。
そこにはもう、狂気はない。あるのは、深い悔恨と、私への憧憬。
「セレスティア……君の絵は……やっぱり、誰よりも美しいよ」
彼は子供のように泣いた。
私はその背中を撫でながら、自分の頬も濡れていることに気づいた。
数ヶ月後。
王立美術館のメインホールは、かつてないほどの熱気と静寂に包まれていた。
矛盾するようだが、訪れた人々は皆、息を呑んで一枚の作品に見入っているのだ。
ホールの壁一面を使った、巨大なデジタルフレスコ画。
そこには、虹色の光の中で、無数の感情の欠片が手を取り合い、螺旋を描いて昇っていく様子が描かれている。
悲しみも、喜びも、怒りも、安らぎも。
全ての色が調和し、一つの大きな「命」を形作っていた。
タイトルは、『魂の夜明け(Dawn of Soul)』。
作者名は、セレスティア・フォン・アルビオン。
私は、回廊の影からその光景を眺めていた。
もう、氷のような色のドレスは着ていない。
今日は、柔らかな春の陽射しのような、ペールイエローのドレスを纏っている。
「セレスティア様」
背後から声をかけられ、振り返る。
そこには、看守に付き添われたジュリアンの姿があった。
罪を償うための収監が決まり、最後のお別れを許されたのだ。
手には手錠がかけられているが、その顔色は憑き物が落ちたように晴れやかだ。
「……見事です。僕が夢見た『最高のアート』が、ここに完成している」
「いいえ。これは『私たち』の作品よ」
私は微笑んだ。
彼が盗み出した「エーテルノヴァ」の素体がなければ、そして彼が私を極限まで追い詰めなければ、私は自分の殻を破ることはできなかった。
「……待っていてくれますか。僕が、その絵に見合う人間になって戻ってくるまで」
「ええ、もちろん」
私は彼に近づき、そっと囁いた。
「次はキャンバスの上で勝負よ。……ライバルとしてね」
ジュリアンは驚いたように目を見開き、そして深く、嬉しそうに頷いた。
「望むところです」
彼が連行されていく。
その背中は小さくなったけれど、以前よりもずっと力強く見えた。
彼の周囲には、小さな、けれど確かな希望の種のような光が灯っていた。
私は再び、自分の作品に向き直る。
視界には相変わらず、ホールに溢れる人々の感情が色となって映っている。
濁った色も、鋭い色もある。
けれど、もう怖くはない。それら全てが、世界を彩る絵の具なのだと知ったから。
私はポケットからタブレットを取り出し、新しいページを開いた。
そこには、無限に広がる真っ白なキャンバス。
さあ、次はどんな色を描こうか。
この世界は、まだ見ぬ美しい色で溢れているのだから。