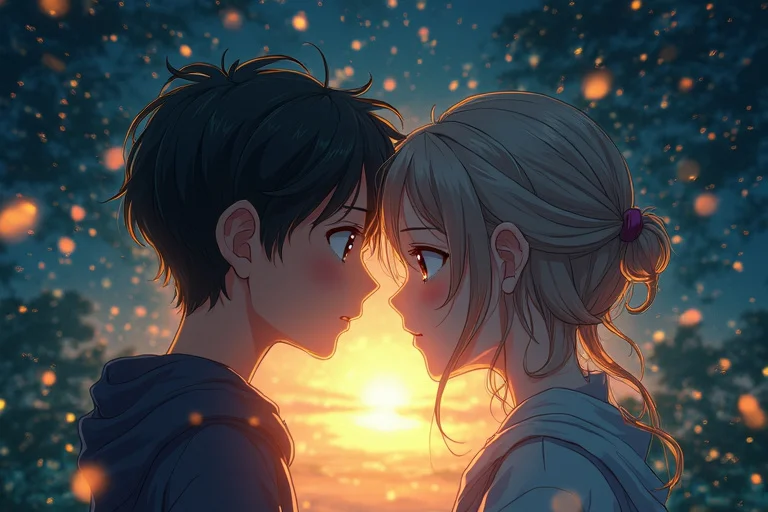第一章 灰色の雨、凍る心臓
アスファルトを叩く雨音が、ノイズのように鼓膜を擦る。
湿った路地裏。
足元にすがりついてくる少女の手は、泥と油で汚れていた。
「お願い……これを、買って」
震える手が差し出したのは、小指ほどのガラス瓶。
中には粘度のある金色の液体が揺らめいている。
『記憶』だ。
それも、かなり純度の高い幸福の記憶。
俺は無感動にそれを見下ろした。
視界の隅を行き交う人々は、俺の目にはすべて鉛筆で塗りつぶしたような『灰色』に映る。
感情を担保に金を借り、返済不能に陥った成れの果て。
「『初めて舞台で主役を演じた日』か」
瓶を受け取ると、指先から微かな熱が伝わってくる。
高揚感。スポットライトの眩しさ。
他人の人生のハイライト。
だが、俺の胸にはさざ波ひとつ立たない。
「質は悪くない」
「じゃあ!」
「だが、うるさい」
俺は懐から札束を抜き出すと、無造作に彼女の顔へ放った。
バサリ、と紙幣が散らばり、泥水に濡れていく。
「え……」
「金はやる。だから俺の視界から消えろ。その悲痛な鳴き声が耳障りだ」
少女は一瞬呆然とし、慌てて泥だらけの札を掻き集めると、脱兎のごとく走り去った。
俺は一つ息を吐き、煙草を取り出す。
火をつける。
煙が雨に溶けていく。
俺の名はレン。
人の記憶を『光』として視るブローカー。
だが、俺自身の中身は空洞だ。
喜びも悲しみも、遠い国の天気予報のように現実感がない。
ふと、左手首を見る。
古びた真鍮の腕時計。
文字盤には『12』の数字しかなく、秒針も分針も存在しない。
『心から心が動いた瞬間にだけ、針が進む』
そんな出鱈目な伝説付きの骨董品。
無論、俺が拾ってから一度たりとも、針が現れたことなどない。
俺には動かすための燃料――心が欠落しているのだから。
ジャケットのポケットに手を入れた時だ。
指先に硬質な紙の感触が触れた。
いつの間に。
記憶の瓶ではない。封筒だ。
取り出し、封を切る。
中には一枚の便箋。
『レン君へ。
あなたの失くしたものを預かっています。
0年0組の教室で待ってる』
差出人の名は『マシロ』。
記憶にない名前だ。
文字の筆跡にも見覚えはない。
なのに。
ドクリ。
肋骨の内側で、奇妙な音がした。
不整脈か。
いや、違う。
これは『痛み』だ。
忘れていた感覚が、錆びついた神経を無理やりこじ開けるように走り抜けた。
俺は吸いかけの煙草を水たまりに捨てた。
傘もささず、灰色の影たちが蠢く大通りを駆け出す。
理由はわからない。
ただ、その名前を見た瞬間、世界の色が少しだけ変わった気がした。
第二章 止まった時計の庭
学園の屋上へと続く階段は、埃と錆の匂いが充満していた。
最上段。
南京錠で固く閉ざされているはずの鉄扉が、わずかに開いている。
隙間から漏れ出す光が、網膜を焼くほどに鮮烈だった。
重い扉を押し開ける。
そこは、屋上ではなかった。
壁も天井もない、無限に広がる茜色の空。
床の代わりには水面のような鏡張りの地面が広がり、雲の流れを映し出している。
その中心に、ぽつんと置かれた学校机と椅子。
「遅いよ、レン」
机に座り、足をぶらつかせていた少女が振り返る。
透き通るような銀髪が、風もないのになびいていた。
大きな瞳は、夕焼けの色を吸い込んで琥珀色に輝いている。
彼女の周囲だけ、空気が震えるほどに色彩が濃い。
「……ここが、0年0組か」
俺は警戒心を露わに、ゆっくりと近づく。
「マシロ、と言ったな。俺の何を盗んだ」
「ひどい言い草」
マシロは机から飛び降りると、軽やかなステップで俺の目の前に立った。
甘いバニラの香りが鼻腔をくすぐる。
「盗んでなんかないよ。あなたが勝手に置いていったんじゃない」
彼女は悪戯っぽく笑い、俺の胸元に指先を這わせた。
心臓の上。
シャツ越しに、彼女の体温が伝わってくる。
「ずっと待ってたんだから。秒針のない時計が、また動き出すのを」
「何の話だ」
俺が彼女の手首を掴もうとすると、マシロはふわりと身をかわした。
まるで蝶だ。
捕まえようとすれば逃げ、離れれば近づいてくる。
「ねえ、レン。覚えてる? 私の好きな色」
「知るか」
「白だよ。何にでもなれる色」
彼女はくるりと回り、スカートを翻す。
「レンの好きな色は?」
「……灰色だ。静かでいい」
「嘘つき」
マシロが急に真顔になり、俺の顔を覗き込んだ。
距離が近い。
長いまつ毛の一本一本まで数えられそうだ。
「本当は、誰よりも鮮やかな世界を欲しがってた癖に」
彼女の指先が、俺の頬に触れた。
その瞬間。
カチリ。
静寂な空間に、硬質な音が響いた。
俺は弾かれたように左手首を見る。
あり得ない。
文字盤の空白だった場所に、細い『秒針』が出現していた。
それが今、確かに一目盛り分、進んだのだ。
「……な」
全身に粟が立つ。
恐怖ではない。
もっと根源的な、魂が震えるような感覚。
「どうして」
俺の声が上擦る。
「お前に触れると、時計が動く」
マシロは悲しげに、けれど慈愛に満ちた瞳で微笑んだ。
「やっと、一秒動いたね」
彼女は俺の手を取り、自分の頬に押し当てた。
「もっと感じて、レン。この痛みも、熱も。全部、あなたが捨てたものなんだから」
俺の手のひらが、彼女の肌の熱を吸い上げていく。
その熱が血管を遡り、心臓へと流れ込む。
痛い。
苦しい。
でも、離したくない。
「お前は、一体……」
問いかけようとした時、マシロの姿がノイズのように揺らいだ。
まるで、接触不良の映像のように。
「あ……」
彼女が小さく呻き、胸を押さえる。
その指の隙間から、光の粒子がこぼれ落ちていた。
第三章 肋骨の檻
「マシロ!」
俺は咄嗟に彼女の肩を抱いた。
実体が希薄になっている。
肉体というより、光の集合体に触れているような頼りない感触。
「時間が、ないみたい」
マシロは苦しげに息を吐く。
周囲の茜色の空に、亀裂が走り始めていた。
ギギギ、と嫌な音が空間を歪ませる。
『銀行』の回収部隊――世界の修正力が、この異空間を嗅ぎつけたのだ。
「レン、聞いて」
彼女は俺の腕の中で、必死に言葉を紡ぐ。
「私は人間じゃない。あなたが過去に『契約』して切り離した、心の欠片」
脳裏に、強烈な閃光が走った。
フラッシュバック。
燃え盛る炎。
誰かの悲鳴。
血まみれで倒れている少女――それは、今のマシロと同じ顔をしていた。
『助けてくれ! 俺のすべてをやるから、彼女を!』
幼い俺の絶叫。
闇の中から現れた、顔のない影。
『ならば対価を。その絶望と、愛する機能のすべてを頂こう』
そうだ。
あの日、俺は彼女を死なせないために、自分を殺した。
感情を、痛みを、愛を切り離し、空っぽの器になることで、奇跡を願った。
切り離された俺の『心』は、死にゆく彼女の魂と混ざり合い、この空間で『マシロ』として再構成されたのだ。
「思い出し……たか」
俺は愕然と呟く。
目の前の少女は、俺の初恋であり、俺の半身だった。
「レン、私を食べて」
マシロが、自身の胸から眩い光の球体を取り出した。
それは、かつて俺が失った感情のすべて。
「私を取り込めば、あなたは完全な人間に戻れる。失った色彩も、感情も、すべて取り戻せるわ」
「そうしたら、お前はどうなる」
「元に戻るだけ。あなたの心臓の中で、静かに溶けていくの」
彼女は屈託なく笑った。
その笑顔が、鋭利な刃物となって俺の胸を抉る。
痛い。
ああ、これが『痛み』か。
俺はずっと、この痛みを忘れるために、世界を灰色に塗りつぶしていたのか。
空間の亀裂が広がり、そこから無数の黒い手が伸びてくる。
灰色の侵食が始まった。
机が、床が、色を失い、石のように固まっていく。
「早く! 銀行が来る!」
マシロが光の球体を俺の口元へ押し付ける。
「嫌だ」
俺はその手を払いのけた。
光の球が床に転がり、チリチリと音を立てる。
「レン!?」
「俺は感情なんていらない。完全になんてなりたくない!」
俺は彼女の肩を掴み、強く引き寄せた。
温かい。
脈打っている。
これが、ただのパーツなものか。
「お前が消えるくらいなら、俺は一生、欠落したままでいい!」
「でも、それじゃあ世界は……」
「世界なんてどうでもいい!」
俺は叫んだ。
喉が裂けそうなほどの咆哮。
「世界を救うために、お前を犠牲にする? ふざけるな。俺は、世界を敵に回しても、今ここにいるお前が欲しいんだ!」
その瞬間。
俺の左手首が、高熱を帯びたように熱くなった。
カチ、カチ、カチ、カチ。
秒針が、心臓の早鐘とリンクして動き始める。
第四章 君だけの色彩
「レン、だめ……っ、離して、巻き込まれる!」
マシロが俺を突き飛ばそうとする。
黒い手が彼女の足首を掴み、灰色の泥沼へと引きずり込もうとしていた。
「離すかよ!」
俺は泥にまみれながら、彼女の手を死に物狂いで掴み返した。
爪が食い込む。
血が滲む。
その赤色が、ひどく鮮やかで美しかった。
「俺を見ろ、マシロ!」
「レン……」
「俺は、過去の幻影としての君じゃない。痛みも、苦しみも、理不尽も、全部抱えて、俺の前で泣いている『今の君』を愛してるんだ!」
それは、論理も計算もない、魂からの絶叫だった。
その言葉が放たれた瞬間。
カチリ。
時計の秒針が『12』を指し、完全に一周した。
キィィィィン!
甲高い音と共に、時計のガラスが砕け散った。
中から溢れ出したのは、金色の光。
いや、違う。
青、赤、緑、紫――ありとあらゆる色彩の奔流だ。
「え……?」
マシロを掴んでいた黒い手たちが、光に触れた瞬間に蒸発していく。
灰色の泥沼が、美しい花畑へと塗り替えられていく。
俺の胸の奥底から湧き上がる熱。
それは借り物の感情ではない。
俺自身の内側から生成された、爆発的なエネルギー。
『愛』という名の、世界を書き換えるバグ。
「レン、温かい……」
消えかけていたマシロの身体に、確かな重みと色彩が戻っていく。
半透明だった肌が、血色の良い桜色に染まる。
俺は彼女を強く抱きしめたまま、膝をついた。
涙が止まらない。
熱い雫が頬を伝う感触。
喉の奥が詰まるような愛おしさ。
「これが……感情……」
「うん。おかえり、レン」
マシロが俺の背中に腕を回す。
彼女の鼓動が、俺の鼓動と重なってリズムを刻む。
彼女は消えなかった。
俺が『自分の心』として取り込むことを拒否し、『一人の他者』として愛することを選んだから。
彼女は俺の一部ではなく、独立した命として世界に定着したのだ。
光の奔流が収まると、そこは元の錆びついた屋上だった。
だが、もう灰色の世界ではない。
雨上がりの空には、巨大な虹が架かっている。
街の喧騒、車のクラクション、誰かの笑い声。
そのすべてが、鮮烈な色彩を帯びて目に飛び込んでくる。
手首の時計は、砕け散ってなくなっていた。
もう必要ない。
俺の胸の中には、新しい時計がチクタクと力強く時を刻んでいるのだから。
「ねえ、レン」
マシロがフェンス越しに街を見下ろして言った。
風が彼女の銀髪を揺らす。
「世界って、こんなにうるさくて、眩しかったんだね」
「ああ」
俺は隣に立ち、彼女の手を握った。
柔らかくて、温かい手。
「全くだ。目がチカチカする」
「ふふ、サングラスでも買う?」
「そうだな。……二人でお揃いのやつを」
俺の言葉に、マシロが驚いたように目を丸くし、それから花が咲くように笑った。
俺たちの物語は、ここから始まる。
世界を救った英雄としてではなく、ただの不器用な恋人同士として。
秒針のない時計が動き出した今、二度と戻らない一秒一秒を、積み重ねていくために。
俺は彼女の手を握り返し、初めて心からの言葉を口にした。
「行こう、マシロ」
世界は、痛いほどに美しかった。