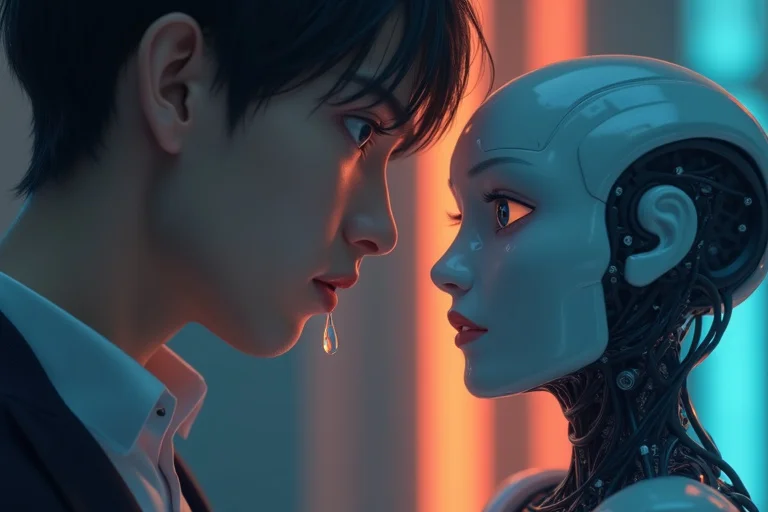第一章 除霊は「ボケ」から
「……つまらん」
その一言は、氷点下のカミソリみたいに俺の心臓をえぐった。
俺、神田ケンジ(26)。職業、売れないピン芸人。
現在、俺の目の前には、空中30センチに浮遊する半透明の老婆がいる。
「あー、あのですねウメさん。今の『布団が吹っ飛んだ』は、あくまでジャブと言いますか、場の空気を温めるための……」
「空気が凍り付いて南極になったわい。さっさと成仏させんか、この三流」
ウメさんは鼻を鳴らした。
いや、霊体に鼻水があるのかは知らんけど。
俺が今やっているのは、とある怪しい派遣バイトだ。
『心霊・お笑い除霊師募集。時給5000円。要・強いメンタル』
この世に未練を残した霊を、笑わせて成仏させる。
バカげた話だが、今の俺には背に腹は代えられない。
舞台に立てば過呼吸になり、客席の冷ややかな視線に殺されかける日々。
借金取りの足音におびえる夜。
そんな俺に回ってきた最初の案件が、この「最強に笑いの沸点が高い幽霊」ウメさんだった。
「そもそも、あんたの顔が気に入らん」
ウメさんが腕を組んで浮いている。
「目が死んだ魚じゃ。もっとこう、生きる覇気がないんか」
「ほっといてくださいよ! これでも芸歴5年目なんです!」
「5年やってそのザマか。親が泣くわ」
グサッ。
痛い。物理攻撃より痛い。
俺はパイプ椅子に崩れ落ちた。
六畳一間のボロアパート。ウメさんの生前の部屋だ。
彼女はここから動こうとしない。
「いいか若造。笑いってのはな、魂の解放じゃ。あんたの芸には、それがない」
「魂の解放……?」
「小手先の技術で笑かそうとするな。腹の底から叫んでみろ」
ウメさんは厳しい。
まるで、昔死んだ俺のばあちゃんみたいだ。
第二章 スベり倒しの特訓
それから一週間、地獄の合宿が始まった。
依頼主である大家さんには「まだ除霊できないのか」と急かされているが、ウメさんが笑わないことにはどうしようもない。
「はい、やり直し!」
「……なんでですか! 今のショートコント『コンビニ』、結構イケてたでしょ!?」
「間が悪い。コンマ2秒遅い。あと声が裏返ってる。不快」
深夜2時。
俺は幽霊相手に、汗だくでツッコミの練習をさせられていた。
「あんた、なんで芸人になった?」
不意にウメさんが尋ねてきた。
俺はペットボトルのぬるいお茶をあおった。
「……子供の頃、ばあちゃん子でさ。俺のばあちゃん、めったに笑わない人だったんだ。でも、俺がテレビの真似して変顔した時だけ、クシャッて笑ったんだよ」
その顔が見たくて、俺は人を笑わせることに夢中になった。
でも、ばあちゃんが死ぬとき、俺はオーディションがあって病院に行けなかった。
『芸人になる』って約束も、まだ果たせていない。
「ふん。どうせ、逃げたんだろ」
ウメさんの言葉が突き刺さる。
「大事な時に、一番大事な人から目を逸らした。その負い目があるから、あんたの芸はどこか他人行儀なんだよ」
図星だった。
俺は舞台の上で、客を見ていない。
『笑わせなきゃ』という焦りだけが空回りして、誰かの心に届く言葉を吐いていなかった。
「……うるさいな、クソババア」
「なんだと?」
「あんただって、未練があるからここにいるんだろ? 何に執着してるんだよ」
ウメさんは少しだけ寂しそうな顔をして、部屋の隅にある仏壇を見つめた。
そこには、一枚の写真が飾られていない。
写真は伏せられていた。
「待ってるんじゃよ」
「誰を?」
「バカな孫を、さ」
第三章 伏せられた写真
翌日、俺は大家さんから衝撃の事実を聞かされた。
「ああ、ウメさんのお孫さん? ……君だよ、神田くん」
「は?」
「依頼主の書類、見てないの? 『依頼主:神田ウメの遺言執行人』。ウメさんが生前、君を探してくれって遺言を残してたんだ」
頭が真っ白になった。
俺は慌ててアパートに戻り、仏壇に伏せられていた写真をひっくり返した。
そこには、泥だらけの野球ユニフォームを着た子供の俺と、厳めしい顔でピースサインをするばあちゃんが写っていた。
「……ウメさんって、ばあちゃんだったのかよ」
部屋の温度がスッと下がる。
背後に、ウメさん――いや、ばあちゃんが立っていた。
「やっと気づいたか、鈍感坊主」
「なんで……なんで名乗らなかったんだよ!」
「名乗ったら、お前、逃げるだろ? 合わせる顔がないって」
ばあちゃんは、全部お見通しだった。
俺が病院に行かなかったことも、売れない芸人を続けていることも、全部。
「あたしゃな、あんたの芸が見たかったんじゃ。テレビに出るって約束、まだ果たしてもらってないからな」
「でも……俺、全然面白くないし……」
「面白いかどうかは、客が決めることじゃ。今は、あたしが客だ」
ばあちゃんがあぐらをかいて、空中に座り直す。
「さあ、やれ。ケンジ。私の未練を断ち切ってみせろ」
俺は震える手で、マイク代わりのテレビリモコンを握った。
逃げるな。
目の前の、たった一人の客を見ろ。
第四章 ラスト・ステージ
深呼吸。
肺いっぱいに、埃っぽい畳の匂いを吸い込む。
「どうもー! 神田ケンジです!」
大声を張り上げた。
いつもみたいな、媚びた声じゃない。腹の底からの声だ。
ネタは、新ネタじゃない。
昔、ばあちゃんに見せるために作った、未発表のコント。
『頑固ババアと気弱な孫』。
「おいババア! また俺のパンツに名前書いただろ!」
「書くさ! 盗まれたらどうする!」
「誰がヨレヨレのボクサーパンツ盗むんだよ!」
俺とばあちゃんの日常をデフォルメした、他愛のないやり取り。
でも、今の俺たちには、それがリアルな対話だった。
ツッコミを入れるたび、涙が溢れてくる。
視界が滲む。
それでも俺は叫び続けた。
「長生きしろよな! 俺が売れるまで、絶対死ぬなよ!」
台本にはないアドリブが出た。
それは、あの時言えなかった言葉。
「……もう死んでるわい、アホ!」
ばあちゃんの鋭いツッコミが飛んできた。
その瞬間。
俺は見た。
ずっと仏頂面だったばあちゃんの顔が、くしゃくしゃに歪んで。
あの時と同じ。
最高の笑顔で、吹き出していた。
「あーっはっはっは! バカだねぇ! ほんっとに、バカな孫だよ!」
部屋中が光に包まれる。
ばあちゃんの体が、粒子になってほどけていく。
「……ケンジ」
光の中で、ばあちゃんが優しく微笑んだ。
「面白かったよ。……合格だ」
最終章 カーテンコール
光が消えると、六畳一間には俺一人だけが残されていた。
静寂。
でも、あの重苦しい寒気はもうない。
床には、伏せられていた写真立てが、今は真っ直ぐに立っていた。
「……ありがとうございました」
俺は誰にもいない部屋に向かって、深く頭を下げた。
数日後。
俺は小さな劇場の舞台に立っていた。
客席はまばらだ。
相変わらず緊張で手は震えている。
でも、客席の一番後ろ。
誰もいないはずの席に、なんとなく、腕を組んで仁王立ちしている気配を感じた。
『間が悪い! 背筋を伸ばせ!』
そんな罵声が聞こえた気がして、俺は思わず吹き出した。
「……何笑ってんだよ」
客が怪訝な顔をする。
俺はマイクを握り直し、ニヤリと笑った。
「いや、ちょっと、一番怖い客が見に来てるもんで」
俺は大きく息を吸い込んだ。
さあ、始めよう。
天国まで届くくらいの、大爆笑を。