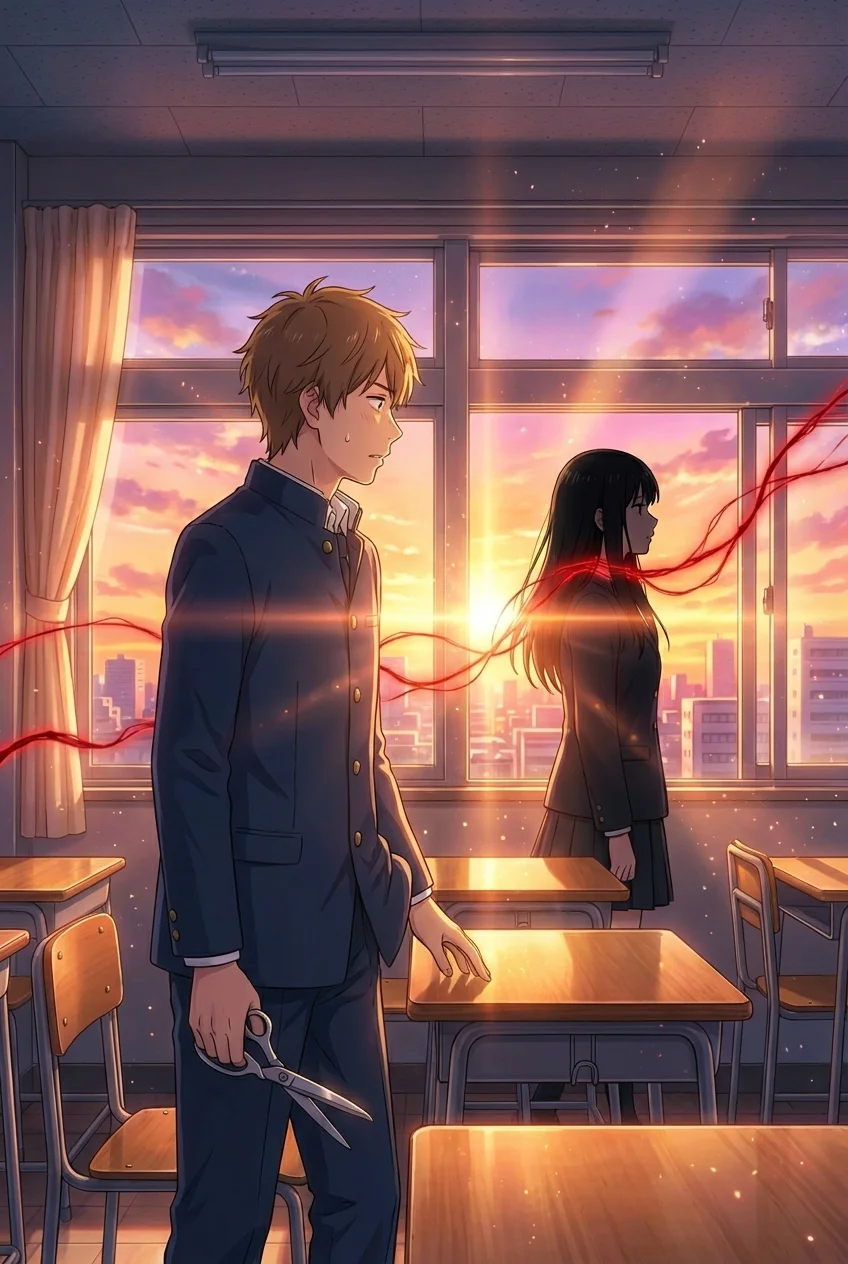止まない雨が、街の輪郭を曖昧に溶かしていた。この街、アステリアでは、三百年前に太陽が雲の向こうに隠れて以来、一度も晴天が訪れたことはない。人々は灰色の空の下、鈍色の傘を差して、湿った石畳の上を黙々と歩き続ける。そんな街の片隅、忘れ去られたような細い路地の奥に、奇妙な建造物があった。鉄錆びたフレームに、無数のガラス板がはめ込まれた巨大な温室。看板すら出ていないその場所は、住人たちの間で「記憶の温室」と呼ばれていた。
「いらっしゃい。雨に濡れてしまったね」
温室の重い扉を押し開けると、湿気と土の匂い、そして言いようのない甘い香りが少女を包み込んだ。温室の中は外の陰鬱さが嘘のように、色彩に溢れていた。天井から吊るされたランタンが、色とりどりに咲き誇る花々を照らし出している。奥から現れたのは、銀髪を後ろで束ね、白いエプロンをつけた青年、レンだった。彼の瞳は、温室に咲くどの花よりも澄んだ青色をしていた。
「……ここに来れば、忘れられるって聞きました」
少女、ミオは震える声で言った。彼女の肩は雨で濡れ、小さな身体は寒さではなく、何らかの恐怖か、あるいは深い悲しみで小刻みに揺れていた。
レンは優しく目を細め、彼女を古びた木製の椅子へと促した。「そうだね。ここは人々の『持て余した記憶』を預かり、花として育てる場所だ。君が手放したいと思う記憶があるのなら、私がそれを土に還し、美しい花へと変えてあげよう」
ミオは俯いたまま、膝の上で拳を握りしめた。「母さんのことです。一ヶ月前に、流行り病で亡くなりました。母さんはいつも笑っていて、私のために毎日パンを焼いてくれて……。でも、今ではその思い出が、棘のように胸に刺さるんです。母さんのことを思い出すたびに、呼吸ができなくなる。夜も眠れない。いっそ、母さんに関するすべての記憶を消してしまいたいんです」
レンは黙って彼女の話を聞いていた。温室の屋根を叩く雨音が、一定のリズムで響いている。彼は棚から小さなガラスの小瓶を取り出し、ミオの前に置いた。
「記憶を消すのは簡単だよ。この小瓶に君の吐息を吹き込めばいい。私がそれを抽出し、花の種にする。一度花が咲いてしまえば、君の頭の中からその記憶は完全に消失する。二度と思い出すことはない。母さんの声も、パンの匂いも、彼女の温もりも。それでいいんだね?」
ミオは一瞬、躊躇した。しかし、胸の奥を掻きむしるような痛みが再び彼女を襲う。「はい……。お願いします」
ミオが小瓶に細い息を吹き込むと、瓶の中が淡い琥珀色の煙で満たされた。レンはそれを丁寧に受け取り、温室の最深部へと運んでいった。ミオもその後を追う。そこには、まだ芽吹いたばかりの苗が並ぶ特別な棚があった。
レンは琥珀色の煙を土に振りかけ、銀色のじょうろで水を差した。すると、見る間に土から緑の芽が伸び、蕾が膨らんでいく。数秒後、そこには見たこともないほど美しい、けれどどこか儚げな青紫色の花が咲き誇った。その花びらは、まるで誰かの微笑みのように優しく波打っていた。
「これが、君の記憶の花だ」
レンが告げると同時に、ミオの脳裏に異変が起きた。母の顔が、霧がかかったように不鮮明になっていく。一緒に歩いた公園の風景も、子守唄のメロディも、指先の感触も。すべてが自分という存在から切り離され、目の前の花へと吸い込まれていく感覚。
「あ……」
ミオは思わず声を漏らした。胸の痛みは、確かに消えつつあった。あんなに苦しかった重圧が消え、心は空っぽの器のように軽くなっていく。だが、それと同時に、自分の一部が永遠に失われていくような、底知れぬ恐怖が足元から這い上がってきた。
レンは静かに言った。「見てごらん。この花びらの脈動を。これは、君のお母さんが君を愛していたという証だ。記憶を捨てるということは、その愛を受け取ったという事実さえも、無かったことにするということなんだよ」
ミオの目から、大粒の涙が溢れ出した。雨音に混じって、彼女の嗚咽が温室に響く。
「消したくない……やっぱり、消したくない!」
彼女は花に手を伸ばした。レンはそれを止めようとはしなかった。ミオがその青紫色の花びらに触れた瞬間、温室の中に柔らかな光が弾けた。吸い込まれていた記憶が、濁流のように彼女の元へと逆流してくる。
不器用な母が焼いた、少し焦げたパンの味。雨の日に二人で入った雨宿りの軒先。転んだ時に抱きしめてくれた腕の強さ。そして、死の直前に母が遺した言葉。「あなたがいてくれて、幸せだった」
記憶は、ただの記録ではない。それは、人が生きてきた証であり、誰かと繋がっていた確かな絆の糸なのだ。痛みがあるのは、それほどまでに深く愛していたから。その痛みを拒絶することは、愛そのものを否定することに他ならない。
しばらくして、ミオは泣き止んだ。彼女の瞳には、先ほどまでの絶望の色はなく、ただ静かな受け入れの光が宿っていた。目の前の花は、彼女が触れた瞬間に光の粒子となって霧散し、彼女の心の中へと戻っていった。
「ごめんなさい、レンさん。私、間違っていました」
「謝る必要はないよ、ミオ。ここは、自分の心と向き合うための場所だからね。記憶は消えなかったけれど、今の君なら、その重さを抱えて歩いていけるはずだ」
レンは彼女に温かいハーブティーを差し出した。それは、雨の匂いに似た、けれどどこか懐かしい香りがした。
「レンさんは、どうしてこの温室を?」
ミオの問いに、レンは少しだけ寂しそうに微笑んだ。「私も昔、大切な記憶を失くしてしまってね。それを探しているうちに、いつの間にか人の記憶を育てる庭師になっていたんだ。失くしたものは二度と戻らないけれど、他の誰かが私と同じ後悔をしないように、こうして手伝いをしている」
ミオが温室を出る頃には、雨はまだ降り続いていた。けれど、彼女の足取りは軽かった。傘を差す手には、母がかつて繋いでくれた手の感触が、確かに残っているような気がした。
温室の中で一人残ったレンは、奥の棚に置かれた、一輪の白い花を見つめていた。それは、どの記憶の花よりも白く、冷たく、そして静かだった。彼が唯一、自分のために育てている「名前も知らない誰か」の記憶。彼は指先でその花びらに触れ、そっと呟いた。
「雨はいつか上がる。……たとえ、この街でなくても」
温室のガラスを叩く雨音は、どこか子守唄のように優しく響き続けていた。記憶の庭師は、今日もまた、誰かの大切な想いを守るために、静かに花に水をやり続ける。