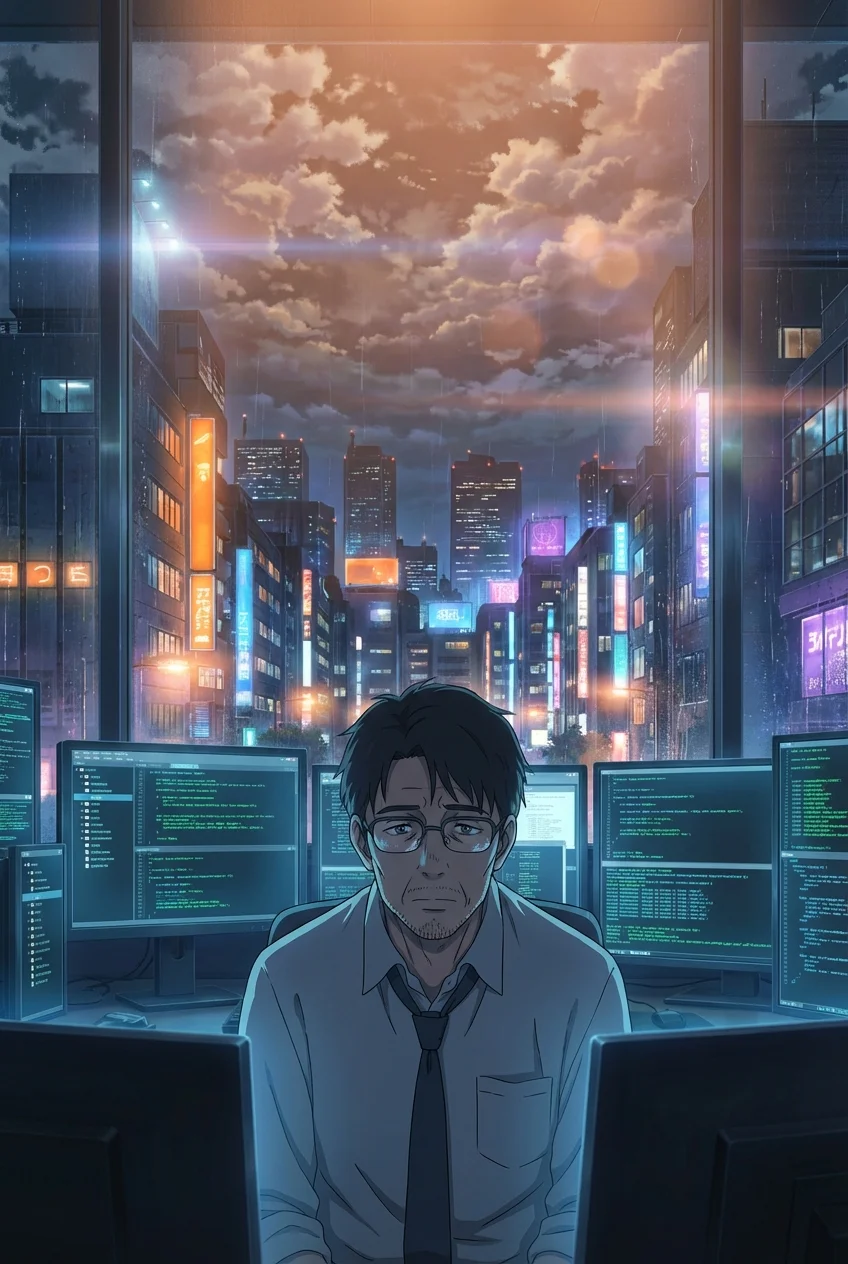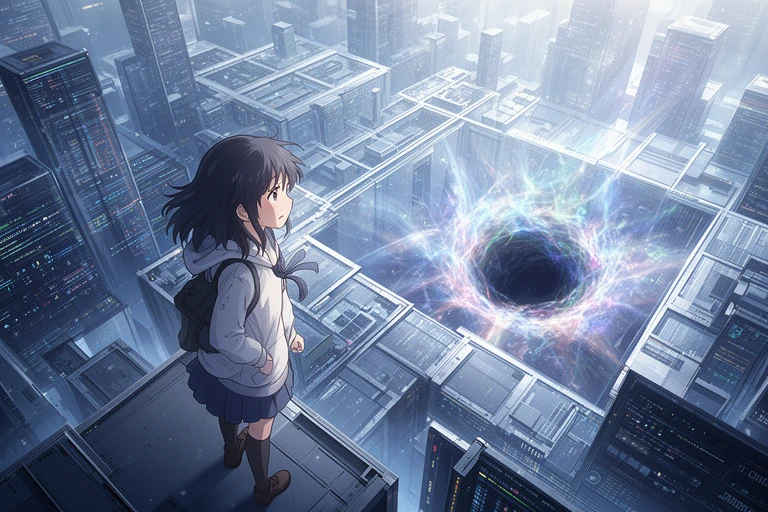第一章 記憶の清掃人
「はい、これで奥様のデータ容量は30%空きました。今夜はぐっすり眠れるはずですよ」
私はタブレット上の数値を指で弾き、顧客の家族に作り笑いを向けた。
目の前のベッドでは、初老の女性が虚ろな目で天井を見つめている。
「ありがとうございます、先生。母も楽になると思います」
息子らしき男が安堵の息を吐く。
私は軽く会釈をして病室を出た。
私の職業は『記憶整理士(メモリー・オーガナイザー)』。
超高齢化社会の日本が叩き出した、認知症ケアの最終回答だ。
脳内に埋め込まれたチップを通じて、ストレス源となるトラウマや、生活に支障をきたす不要な記憶データを削除する。
国はこれを『心の断捨離』と呼び、莫大な補助金をつけて推奨していた。
「次は、402号室の安藤ハナさんです。データ破損が激しく、緊急削除が必要です」
インカムから事務的な音声が響く。
私はため息を一つつき、冷たい廊下を歩き出した。
私はこの仕事が得意だ。
なぜなら、私自身が他人の感情に興味がないからだ。
悲しみも、喜びも、私にとってはただの0と1の羅列に過ぎない。
色褪せた思い出など、容量を食うだけのゴミだ。
そう信じていた。
あの部屋に入るまでは。
第二章 茜色のノイズ
402号室は、消毒液の匂いがやけに濃かった。
ベッドに横たわる安藤ハナは、枯れ木のように痩せ細っていた。
推定年齢85歳。身寄りなし。
「……消さないで」
私が機材をセットしようとすると、彼女のか細い手が私の白衣の袖を掴んだ。
驚くほどの握力だった。
「安藤さん、楽になるためですよ。今の脳内ストレージは限界です。このままでは呼吸中枢にまでエラーが出ます」
私は淡々と説明し、彼女のこめかみに端子を接続した。
視界が切り替わる。
VRゴーグル越しに見る彼女の脳内は、まるでゴミ屋敷だった。
灰色に変色した記憶の欠片が、乱雑に散らばっている。
『夫の暴力』――削除。
『借金の苦しみ』――削除。
『工場の過酷な労働』――削除。
私は手際よく、彼女の人生における「不幸」をゴミ箱へ放り込んでいく。
作業は順調だった。
脳の負荷を示す赤いグラフが、徐々に青へと変わっていく。
だが、一つだけ。
脳の最深部に、真っ赤に点滅する巨大なデータがあった。
ファイル名『Error_404』。
ひどいノイズが走っており、再生すらできない。
容量の6割を占有している、明らかなバグデータだ。
「これが元凶か」
私は削除コマンドを入力した。
その瞬間、アラートが鳴り響く。
『拒絶反応を検知。拒絶反応を検知』
現実世界で、ハナが暴れているのがモニター越しにわかった。
「だめ……! それだけは……あの子だけは……!」
「落ち着いてください! これを消さないとあなたが死ぬんです!」
私は鎮静剤の投与を指示しながら、強制アクセスのコードを打ち込んだ。
なぜこれほど執着する?
中身を確認して、無価値であることを証明してやる。
私は『Error_404』の内部へとダイブした。
最終章 ゴミ箱の中の宝物
ノイズの嵐を抜けると、不意に視界が開けた。
そこは、夕暮れの公園だった。
ジャングルジムの塗装は剥げ、錆びた鉄の匂いがする。
視点は低い。
ハナの視界だ。
目の前には、5歳くらいの男の子が立っていた。
膝を擦りむき、血を滲ませている。
男の子は、泣きじゃくりながら叫んでいた。
「おかあさんなんて、きらいだ! どっかいっちゃえ!」
子供の癇癪。
よくある日常の一コマ。
なぜこれが、死んでまで守りたい記憶なのか。
私はデータを解析しようと、少年の顔をズームした。
心臓が、跳ねた。
少年の右の眉尻にある、三日月形の傷。
それは、私が幼い頃、父の虐待から母を庇おうとして負った傷と同じだった。
「まさか……」
私の母は、私が7歳の時に失踪したはずだ。
父は「お前が悪い子だから捨てられたんだ」と言っていた。
それ以来、私は母を恨み、母の顔を記憶から消し去っていた。
だが、この記憶データには『感情タグ』が付与されていた。
他人の記憶には、その時の所有者の感情がメタデータとして残る。
私は震える手で、そのタグを開いた。
『愛おしい』
『ごめんね』
『愛している』
『生きていて』
音声データが再生される。
それは、男の子の罵声に対する、ハナの心の声だった。
『ごめんね、ケンジ。私がいたら、あの人はもっとあなたを殴る。私が消えることが、あなたを守る唯一の方法なの』
視界が歪む。
ハナは、泣き叫ぶ息子を抱きしめたくても抱きしめられず、拳を握りしめて背を向けていた。
その背中が、どれほど震えていたか。
幼い私には知る由もなかった。
彼女は30年間、この「自分が息子に捨てられる瞬間」を、地獄のような人生の中で唯一の宝物として守り続けていたのだ。
自分が悪者になることで、息子が生きていけるならと。
「……バカげてる」
私の頬を、熱いものが伝った。
VRゴーグルの内側が濡れていく。
「こんな……一番辛い記憶を……なんで……」
『警告。削除を実行しますか?』
無機質なシステム音声が問いかける。
私は迷わず、『保存』のボタンを叩きつけた。
「……エラー解除。当該データは、生命維持に必須と判断」
私は震える声でログを残し、現実世界へと戻った。
ゴーグルを外すと、ハナの呼吸は穏やかになっていた。
痩せ細ったその手は、まだ私の袖を弱々しく掴んでいる。
私はその手を、両手で包み込んだ。
温かかった。
データではない、血の通った温もりがそこにあった。
「ただいま、母さん」
その言葉は、誰に聞かれることもなく、夕暮れの病室に静かに溶けていった。
彼女の記憶は整理された。
だが、私の心の中には、一生消去できない、痛くて愛おしいノイズが刻み込まれたのだった。