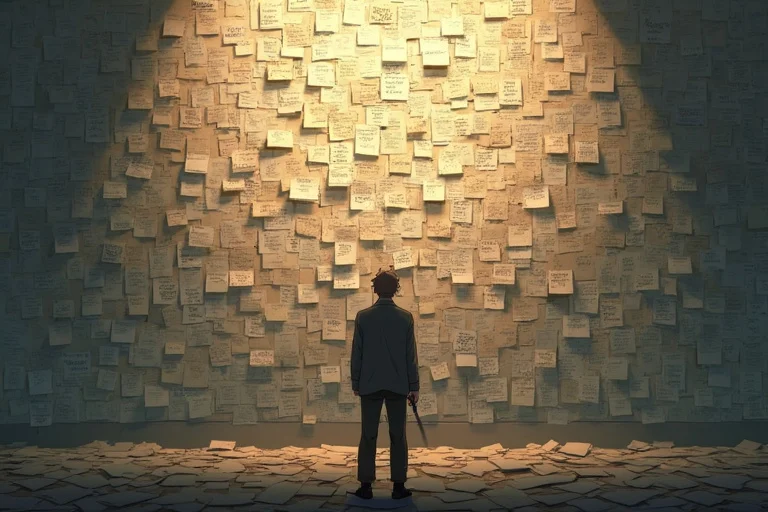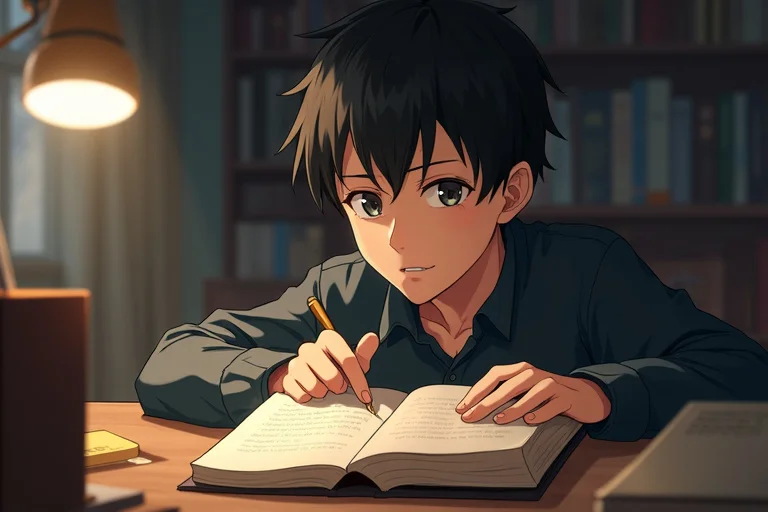第一章 偽りの感謝状
結城航がその部屋のドアを開けた時、むわりと立ち込める埃と時間の匂いに、思わず眉をひそめた。地方新聞社「東邦日報」の記者として三年目。いつしか情熱はすり減り、今はただ、割り振られた仕事を無感情にこなすだけの毎日だった。今回の仕事もその一つ、「孤独死した高齢者の発見」という、ありふれた三面記事の取材だ。
警察官が言うには、死後二週間。死因は心筋梗塞。身元は田所雄三、七十八歳。近所付き合いはほとんどなく、身寄りもいないらしい。典型的な「無縁死」のケースだった。結城は手帳にメモを取りながら、物言わぬ家主の気配が染みついた室内を見渡した。古びた家具、丁寧に手入れされた工具箱、そして――壁だった。
部屋の四方の壁が、おびただしい数の賞状のようなもので埋め尽くされている。黄ばんだ上質紙に、達筆な毛筆で書かれたそれらは、どれも「感謝状」と題されていた。
『田所雄三様 貴殿の誠実な仕事ぶりに心より感謝いたします』
『田所様のおかげで、子供の笑顔が戻りました。本当にありがとうございました』
結城は息を飲んだ。孤独死した老人の部屋に、これほどの感謝の言葉。一体どんな人生を送れば、これほどまでに人に慕われるのか。これは単なる三面記事ではない、社会の片隅に埋もれた美談を発掘できるかもしれない。結城の乾いた心に、久しぶりに記者としての血が騒ぐのを感じた。
しかし、その高揚は数日後に、冷水を浴びせられる形で打ち砕かれた。遺品整理の過程で、警察が奇妙な事実に気づいたのだ。鑑識が調べた結果、壁一面の感謝状は、そのすべてが田所雄三自身の筆跡によるものだと判明した。日付も、差出人の名前も、感謝の言葉も、すべてが彼一人の手による、壮大な自作自演だったのである。
途端に、美談の可能性は消え失せた。残ったのは、孤独の果てに自らへの感謝状を書き続けた、一人の老人の痛々しい狂気だけだ。同僚たちは「気味の悪い話だ」と顔をしかめ、デスクは「記事にする価値なし」と一蹴した。
だが、結城の心には、別の感情が芽生えていた。なぜ、彼はそんなことをしなければならなかったのか。虚構の感謝に埋め尽くされた部屋で、彼は何を思い、何を支えに生きていたのか。その問いが、鉛のように重く、結城の心に沈み込んで離れなかった。彼はデスクに頭を下げ、この記事をもう少しだけ追わせてほしいと願い出た。忘れ去られるには、その謎はあまりに深く、そして悲しすぎた。
第二章 消された足跡
田所雄三の人生を辿る取材は、困難を極めた。近隣住民に話を聞いても、「気難しい人」「挨拶しても返してくれない偏屈な老人」という評判ばかりが返ってくる。彼が住んでいた安アパートの大家でさえ、家賃の支払いが滞らないこと以外、何も知らなかった。まるで、田所雄三という人間は、社会からその輪郭を丁寧に消し去られてしまったかのようだった。
結城は、遺品の中にあった古い工具箱を手がかりに、調査の範囲を広げた。錆びついた工具に刻まれた微かな屋号から、彼がかつて「田所製作所」という小さな町工場を営んでいたことを突き止める。工場の跡地は、今ではコインパーキングに姿を変え、往時を偲ばせるものは何もなかった。
それでも結城は諦めなかった。閉鎖された登記簿を閲覧し、古い業界名簿をめくり、何人もの人間に電話をかけた。そしてついに、田所のかつての同僚だったという、八十歳を超えた元職人に行き着いた。
「田所さんかい?ああ、覚えとるよ。無口で、不器用で、お世辞の一つも言えん男だった。だが、腕だけは本物だった」
老人は、電話の向こうで懐かしむように言った。田所製作所は、大手メーカーの下請けで、精密機械の特殊な歯車を作っていたという。コンマミリ単位の精度が要求される、誰にでもできる仕事ではなかった。
「あいつは、図面だけじゃなく、その歯車がどんな機械で、誰のために動くのかをいつも考えていた。だから、あいつの作る歯車は、ただの部品じゃなかった。命が宿っとるようだったよ」
さらに調査を進めると、田所が作った歯車が、地方の病院で使われる医療機器や、子供たちが遊ぶ公園のからくり時計にも使われていたことが分かってきた。結城は、その病院の技師や、今も時を刻み続ける時計の管理者にも会った。彼らは口々に、何十年も故障知らずで動き続ける部品の質の高さを称賛した。しかし、その部品を作ったのが「田所雄三」という男であることは、誰も知らなかった。
彼は、確かに誰かの生活を支え、誰かの笑顔の一助となっていた。しかし、その功績は誰にも知られることなく、感謝の言葉が直接届くこともなかった。結城の脳裏に、あの偽りの感謝状が浮かんだ。あれは、狂気の産物などではなかったのかもしれない。届くことのなかった、本来あるべきだった感謝の言葉を、彼は自らの手で書き留めることで、かろうじて自己の尊厳を保っていたのではないか。
取材を通して浮かび上がってきたのは、偏屈な老人ではなく、不器用なまでに誠実な一人の職人の姿だった。結城は、社会の隅で黙々と働き、そして静かに忘れ去られていく人々の存在に、初めて現実として触れた気がした。
第三章 虚構の断罪者
田所製作所は、なぜ廃業に追い込まれたのか。結城の取材は、核心へと向かっていた。元同僚の老人は、重い口を開いた。「大手のやり方は、ひどかったよ。一方的な契約打ち切りだ。コスト削減とか、海外移転とか、そんな理由でな」
結城は、当時の新聞の縮刷版をめくった。九〇年代後半、バブル崩壊後の不況の嵐が吹き荒れていた時代だ。そして、結城はある記事に目を留めた。地元のテレビ局が制作した、経済ドキュメンタリーの特集記事だった。タイトルは『淘汰される町工場~時代に取り残された者たち~』。
その記事は、旧態依然とした経営から脱却できずに苦しむ中小企業の典型として、ある製作所を批判的に取り上げていた。匿名ではあったが、記事の内容や描写から、それが田所製作所であることは明らかだった。記事は、田所の頑固な職人気質を「時代の変化に対応できない経営者の傲慢さ」と断じ、大手企業による契約打ち切りを「合理的な経営判断」として肯定していた。この記事が、田所製作所の社会的信用に、とどめを刺したことは想像に難くない。
結城は、怒りで全身が震えるのを感じた。これはジャーナリズムではない。強者の論理を代弁し、弱者を一方的に断罪する、ただの暴力だ。彼は、この記事を執筆した記者の名前を確認しようと、署名欄に目を走らせた。そして、その場で凍りついた。
そこに記されていたのは、高見敏明という名前。現在、東邦日報の編集主幹であり、結城が若手時代に目標としていた、大物記者その人だった。
数日後、結城は意を決して、編集主幹室のドアをノックした。高見は、分厚い眼鏡の奥の目で、いぶかしげに結城を見た。結城が震える手で差し出した古い記事のコピーを見ると、高見は一瞬だけ表情をこわばらせたが、すぐに平静を取り戻した。
「ああ、この記事か。懐かしいな。これがどうかしたのかね、結城君」
「この記事で取り上げられた田所製作所の社長、田所雄三さんが、先日、孤独死しました」
結城の言葉に、高見は「そうか」とだけ短く応じた。何の感情も窺えない声だった。
「高見さん、この記事は、事実を歪めていませんか。田所さんは、時代の変化に対応できなかったのではなく、ただ誠実な仕事をしていただけだった。それをあなたは…」
言葉を継ごうとした結城を、高見が遮った。
「君は若いな。ジャーナリズムとは、真実をありのままに報じることだけではない。大衆が求める『物語』を提示することも、我々の重要な仕事だ。当時、人々が求めていたのは、旧時代の敗北と新時代の到来という分かりやすいストーリーだった。私は、その需要に応えただけだ」
その言葉に、結城は頭を殴られたような衝撃を受けた。尊敬していた先輩記者の、これが本性なのか。人の人生を「物語」の部品として消費し、何ら痛みを感じない。田所雄三を社会的に殺したのは、大企業だけではない。目の前にいるこの男、そして彼が振りかざす「ジャーナリズム」という名の刃だったのだ。結城の中で、これまで信じてきたものが、音を立てて崩れ落ちていった。
第四章 たった一輪の花
結城は、編集主幹室を後にしてから、一晩中、自問自答を繰り返した。高見の言葉は、確かに報道の一側面を捉えているのかもしれない。だが、それを是としてしまえば、記者がペンを持つ意味とは何なのか。田所雄三の人生が、ただの「物語」として消費されて終わることを、彼はどうしても許せなかった。
翌日、結城は自分のデスクで、キーボードを叩き始めた。彼が書くべきは、センセーショナルな告発記事ではない。高見を断罪することでもない。彼が書くべきは、田所雄三という一人の人間が生きた、ささやかで、しかし確かな尊厳の物語だった。
結城は、偽りの感謝状から始まった取材のすべてを、静かな筆致で綴った。無口な職人が作った歯車が、今も誰かの日常を支えていること。彼が本当は、誰よりも「ありがとう」という言葉を渇望していたであろうこと。そして、一つの報道が、いかに一人の人間の人生を静かに追い詰めていくかということ。彼は、田所雄三の「消された足跡」を、一つひとつ丁寧に紙の上に再現していった。
完成した原稿をデスクに提出した時、デスクは黙って最後まで読み、そして一言、「載せよう」と言った。
結城の記事、『残響のスケッチ』が掲載された朝刊は、静かだが、確かな反響を呼んだ。派手な見出しはなかったが、多くの読者が、社会の片隅で忘れ去られた名もなき職人の人生に心を動かされた。SNSには、自分の周りにいる「田所さん」のような人々への感謝の言葉が少しずつ上がり始めた。高見の過去の記事に対する批判の声も、社内外から上がったが、結城にとってそれはもはや主要な関心事ではなかった。
数日後、結城は、新しく建てられた田所雄三の無縁仏の墓を訪れていた。小さな墓石の前に、そっと缶コーヒーを供える。その時、彼は、自分の供えたものではない、一輪の真新しいガーベラが手向けられていることに気づいた。
それは、彼の記事を読んだ、見ず知らずの誰かが供えたものに違いなかった。そのたった一輪の花は、どんな壁一面の感謝状よりも雄弁に、田所の人生が、決して無意味ではなかったことを物語っていた。届かなかった感謝は、時を経て、形を変えて、今ここに届いたのだ。
結城は、その小さな花をじっと見つめた。冷え切っていたはずの胸の奥に、確かな熱が灯るのを感じる。社会という大きな構造は、簡単には変わらないのかもしれない。だが、忘れられた声に耳を傾け、その物語を誠実に伝えること。その小さな営みの先に、こうして一輪の花を咲かせることならできる。
夕陽が墓石を橙色に染めていた。結城は、背筋を伸ばし、墓に深く一礼すると、迷いのない足取りでその場を後にした。彼の記者としての本当の仕事は、今、始まったばかりだった。