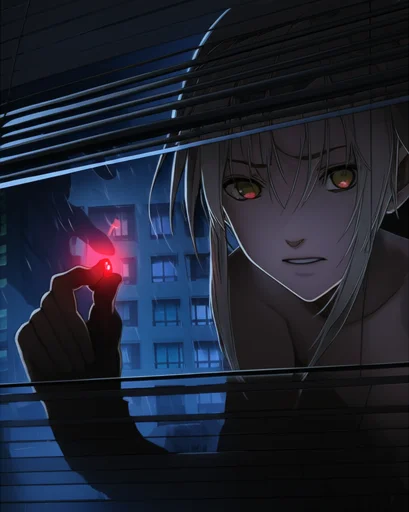第一章 褪せた絵本と見知らぬ訪問者
古書店『揺り籠文庫』の空気は、いつも静かだった。埃と古い紙、そして微かなインクの匂いが混じり合い、時間の流れを緩やかにしている。店主である桐島蒼(きりしま あおい)は、その淀みにも似た静寂を好んでいた。外界の喧騒から身を守る、分厚い繭のように感じられたからだ。
その日も、蒼はカウンターの奥で、古びた事典の修繕をしていた。午後三時を過ぎ、西日が長い影を床に落とす頃、店のドアベルがちりん、と控えめな音を立てた。入ってきたのは、見慣れない老婦人だった。上品なグレーのコートをまとい、その顔には深い皺が、まるで人生の地図のように刻まれている。
「いらっしゃいませ」
蒼の声は、自分でも驚くほど乾いていた。老婦人は店内をゆっくりと見回すと、まっすぐにカウンターへ歩み寄ってきた。その手には、一冊のくたびれた絵本が抱えられている。
「これを……」
老婦人は、その絵本をそっとカウンターの上に置いた。蒼の視線が、その表紙に吸い寄せられる。色褪せた絵。森の中、大きな樫の木の下で、ウサギとリスが寄り添っている。『森のともだち』。そのタイトルを見た瞬間、蒼の心臓が氷の塊に握りつぶされたかのように、冷たく、そして強く痛んだ。
それは、二十年前、蒼が七歳の時に失くした、世界で一番好きだった絵本だった。
「どうして、これを……」
声が震える。老婦人は答えず、コートのポケットから小さな封筒を取り出した。そして、それを絵本の上に重ねる。
「この本の、本当の最後のページを、あなたに」
老婆はそれだけ言うと、穏やかに微笑んだ。その瞳の奥に、計り知れないほどの深い悲しみが揺らめいているように見えた。蒼が何かを言う前に、彼女はくるりと背を向け、来た時と同じように静かに店を出ていった。ドアベルの音が、やけに寂しく響く。
蒼は、震える手で封筒を開けた。中から出てきたのは、一枚の折りたたまれた便箋だった。そこには、インクが滲んだ、古風な万年筆の文字で、たった一行だけ、こう書かれていた。
『――秘密の宝物は、樫の木の根元に』
全身の血が逆流するような感覚に襲われた。その言葉は、蒼と、そしてあの日、忽然と姿を消した親友の陽菜(ひな)だけが知る、秘密の合言葉だった。なぜ。なぜ見ず知らずの老婆が、この言葉を知っている? 封印していたはずの記憶の扉が、軋みながらゆっくりと開き始めていた。二十年前の、あの夏の日の森の匂いと共に。
第二章 罪悪感という名の栞
『森のともだち』は、単なる絵本ではなかった。それは蒼にとって、罪悪感そのものだった。ページをめくるたび、陽菜の屈託のない笑顔が、蝉時雨の喧騒が、そして森の湿った土の匂いが、鮮やかに蘇る。
あの日、蒼と陽菜はいつものように森でかくれんぼをしていた。鬼は蒼だった。百まで数え、目を開けた時、森は不気味なほど静まり返っていた。いくら探しても、陽菜は見つからない。「ひなちゃん!」と叫ぶ声は、木々に吸い込まれて消えていった。やがて日が暮れ、蒼は得体の知れない恐怖に駆られて、一人で森を駆け出した。陽菜を置き去りにして。
以来、陽菜は見つかっていない。警察の捜索も空振りに終わり、彼女は「神隠し」にあったのだと、大人たちは囁いた。だが、蒼は知っていた。自分が陽菜を見捨てたのだと。その罪の意識は、見えない栞のように蒼の人生に挟み込まれ、次のページへ進むことを許さなかった。
『揺り籠文庫』を開いたのも、人との関わりを避け、静かな本の墓守として生きるためだった。しかし、あの老婦人が現れたことで、蒼の築き上げた静寂の壁に、大きな亀裂が入ってしまった。
「秘密の宝物は、樫の木の根元に……」
蒼はその言葉を何度も口ずさむ。それは、かくれんぼの前に二人で交わした約束だった。陽菜が見つけた綺麗な石を、森で一番大きな樫の木の根元に隠しておこう、という他愛のない約束。
老婦人は誰なのか。なぜ、あの合言葉を知っているのか。蒼は、手掛かりを求めて、再び絵本を手に取った。何度も読み聞かせてもらったその物語は、森の動物たちが協力して冬を越す、心温まる話だ。だが、注意深くページを調べていくと、ある異変に気づいた。物語の最後のページ、動物たちが春の訪れを喜ぶ場面の隅に、インクで書かれた小さな記号があったのだ。それは、星の形にも、花の形にも見えた。幼い頃には気づかなかった、小さな落書き。
もしかしたら、他にも何かあるかもしれない。蒼は、藁にもすがる思いで、二十年ぶりに故郷の町の図書館へ向かった。当時の新聞記事を調べれば、何か分かるかもしれない。マイクロフィルムの無機質な光が、蒼の顔を青白く照らす。陽菜の失踪事件を報じる記事はすぐに見つかった。当時の担当刑事の名前が記載されている。「捜査一課、水木警部補」。ありふれた名前だ。だが、その横に添えられた小さな顔写真に、蒼は息を呑んだ。それは、数年前に亡くなった、近所でも評判の好々爺だった水木さんの顔だった。そして、彼の妻こそ、先日店を訪れたあの老婦人に違いなかった。
記憶が繋がっていく。水木夫妻には子供がおらず、蒼や陽菜を孫のように可愛がってくれていた。だが、事件後、夫妻は蒼を避けるように、どこか遠くへ引っ越してしまったのだと思っていた。
なぜ、今になって水木さんの奥さんが? そして、あのメモは何を意味するのか。謎は解けるどころか、さらに深く、暗くなっていく。蒼の胸の中で、罪悪感という名の栞が、より一層重みを増していた。
第三章 本当の最後のページ
数日後、蒼は意を決して、水木夫人の家を訪ねた。古い名簿を頼りに探し当てたその家は、町の中心から少し離れた、静かな住宅街にあった。インターホンを押す指が、微かに震える。
「……はい」
スピーカーから聞こえてきたのは、紛れもなくあの老婦人の声だった。蒼が名乗ると、一瞬の沈黙の後、「お待ちしていました」という静かな声が返ってきた。
招き入れられた居間は、綺麗に片付いていたが、どこか空虚な空気が漂っていた。壁には、穏やかに微笑む水木さんの遺影が飾られている。水木夫人は、蒼の向かいに静かに座ると、ゆっくりと口を開いた。
「主人は、亡くなるまでずっと、あなたのことを気にかけていました」
彼女の話は、蒼の想像を絶するものだった。水木さんは刑事として陽菜の失踪事件を担当したが、それは彼にとっても、生涯忘れられない痛恨の事件となった。そして、あの絵本は、事件後、現場近くで水木さんが見つけたものだったという。
「主人は、いつかあなたに真実を伝えなければならない、とずっと言っていました。でも、そのタイミングが分からなかった。あなたが負うであろう心の傷を思うと、どうしても躊躇してしまったのです」
水木夫人は立ち上がると、書斎から古びた一冊の日記帳を持ってきた。
「これは、主人の日記です。彼があなたに遺した、本当の最後のページ……」
蒼は、震える手で日記帳を受け取った。指定されたページを開くと、そこには、水木さんの几帳面な文字で、二十年前の夏の日の、驚くべき真相が記されていた。
『――陽菜ちゃんの遺体は、森の奥にある古い涸れ井戸の底で発見された。おそらく、かくれんぼの最中に誤って転落したものと思われる。だが、問題はそこではなかった。陽菜ちゃんは、亡くなる間際、井戸の壁に、持っていた石で何かを書き残していた。それは、たった一言。』
蒼は息を止めて、次の行を追った。
『――あおい、にげて』
心臓が鷲掴みにされたような衝撃が走った。涙が、視界を歪ませる。日記は続く。
『当時、森の近くには素行の悪い男が住み着いており、我々もマークしていた。陽菜ちゃんは、その男の姿を見つけ、かくれんぼをしていた蒼ちゃんの身に危険が及ぶと思ったのだろう。だから彼女は、蒼ちゃんを逃がすために、自ら物音を立てて男の注意を引き、その結果、井戸に気づかず転落してしまったのではないか。彼女は、蒼ちゃんを見捨てたのではなく、守ったのだ。
この事実を公表すれば、蒼ちゃんは「自分のせいで親友が死んだ」という、あまりにも過酷な十字架を背負うことになる。私は、まだ七歳の少女にそんな重荷を背負わせることはできなかった。だから、私は真相の一部を胸にしまい、事件を「行方不明」として処理した。いつか、彼女が大人になり、真実を受け止められる強さを持った時に、このことを伝えようと心に決めて。』
蒼は声を上げて泣いていた。見捨てたのではなかった。自分は、陽菜に守られていたのだ。二十年間、蒼を苛んできた罪悪感は、陽菜の深い友情と、一人の刑事の温かい慈悲によって生まれた、巨大な誤解だった。あの秘密の合言葉、『秘密の宝物は、樫の木の根元に』は、水木さんが蒼に真実を伝えるための、最初の鍵だったのだ。
第四章 夜明けの古書店
真実を知った翌日、蒼は二十年ぶりにあの森を訪れた。記憶を頼りに奥へ進むと、かつて涸れ井戸があった場所に辿り着く。そこは、危険だからと埋め立てられ、今では誰が手入れしているのか、色とりどりの小さな花が咲く花壇になっていた。おそらく、水木夫妻が長年、陽菜を弔うために世話をしてきたのだろう。
蒼は、その場に膝をついた。土の匂いと花の甘い香りが、優しく鼻をくすぐる。
「陽菜ちゃん……ごめんね。ありがとう」
声は掠れていたが、それは初めて心の底から言えた言葉だった。罪悪感ではなく、感謝と共に陽菜を思うことができた。風が木々を揺らし、まるで陽菜が「いいんだよ」と囁いてくれているかのように感じられた。
店に戻った蒼は、あの絵本『森のともだち』を、一番日当たりの良い書棚に飾った。色褪せた表紙のウサギとリスが、誇らしげにこちらを見ている。それはもう、罪の象徴ではなかった。陽菜との友情、そして水木さんの優しさ、それら全てを内包した、温かい記憶の塊だった。
数日後、ちりん、とドアベルが鳴った。蒼が顔を上げると、そこに立っていたのは、本を探しに来た若い女性客だった。以前の蒼なら、無愛想に会釈するだけだっただろう。しかし、今の蒼は違った。
「いらっしゃいませ。何かお探しですか?」
その声は、自分でも驚くほど、明るく、そして澄んでいた。蒼の顔には、夜明けの光のような、穏やかで柔らかな微笑みが浮かんでいた。
古いインクの匂いが漂う古書店で、止まっていた時間が、再びゆっくりと動き始める。過去の痛みをインクのように滲ませながらも、その温もりを抱きしめて、蒼は新しいページをめくっていく。人生という名の、まだ誰も知らない物語の、次のページを。