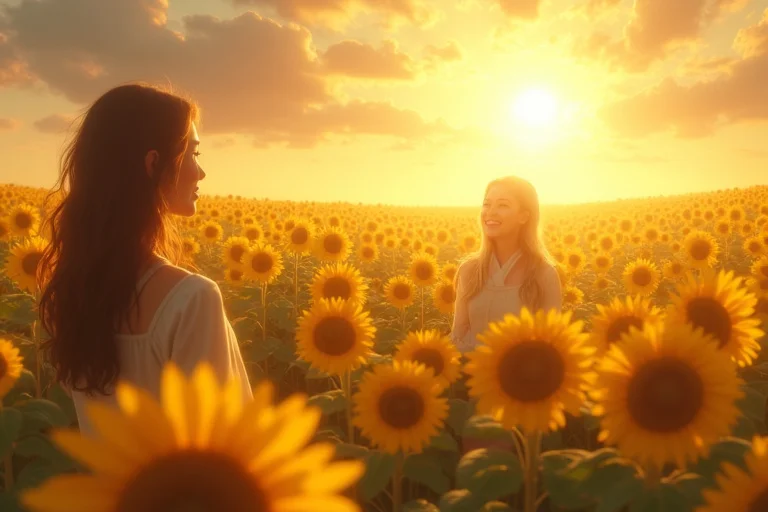第一章 沈黙の古書店
大学を卒業して一年半、僕、相田健太の時間は、澱んだ水のように停滞していた。いくつもの会社の不採用通知は、いつしかクリアファイルの中で地層をなし、社会から拒絶された証明書のようになっていた。希望も、情熱も、就職活動の過程で綺麗に削ぎ落とされ、残ったのは無気力という名の伽藍堂だけだった。
そんなある日の午後、僕はあてもなく街を彷徨っていた。古い商店街の埃っぽいアーケードを抜けた先、蔦の絡まる煉瓦造りの建物の隅に、その店はひっそりと息づいていた。「高林書房」と掠れた金文字で書かれた看板。ショーウィンドウには、日焼けして黄ばんだ古書が、まるで博物館の展示物のように並んでいる。吸い寄せられるように、軋む木製のドアを開けると、カラン、と乾いたベルの音が鳴り、インクと古い紙の匂いが鼻腔をくすぐった。
店内は本の迷宮だった。床から天井まで届く本棚が壁という壁を埋め尽くし、その間にも本の塔がいくつもそびえ立っている。その奥の帳場に、一人の老人が座っていた。銀縁眼鏡の奥の瞳は、分厚い専門書に向けられている。彼が店主の高林さんだった。
「あの、アルバイトの募集を見て……」
僕がか細い声で言うと、高林さんはゆっくりと顔を上げた。深く刻まれた皺が、年輪のように彼の人生を物語っている。彼は僕を値踏みするように数秒見つめた後、ただ黙って顎をしゃくった。採用、ということらしい。あまりの簡潔さに拍子抜けしたが、僕も何かを熱心に語る気力はなかったので、好都合だった。
高林書房での仕事は、奇妙なことの連続だった。店主の高林さんは、とにかく喋らない。「おはようございます」「お疲れ様です」という挨拶に、こくりと頷くだけ。客が来ても「いらっしゃいませ」の一言もない。ただ、じっと客の顔を見つめるのだ。そして、おもむろに立ち上がると、迷いのない足取りで書棚へ向かい、一冊の本を抜き出して、黙ってカウンターに置く。それが、彼の接客のすべてだった。
最初は、ただの偏屈な老人の気まぐれだと思っていた。しかし、彼が選んだ本を受け取った客は、皆どこか満たされたような、あるいは何かから解放されたような表情で店を後にする。そして数日後、その客が再び現れ、「ありがとうございました」と深々と頭を下げていくのだ。菓子折りを持ってくる者さえいた。
失恋で憔悴しきっていた若い女性には、無名の詩人の詩集を。上司との関係に悩み、疲れ果てた顔のサラリーマンには、難解な哲学書を。子育てに自信をなくした主婦には、一冊の古い絵本を。処方箋のように手渡される本と、それを受け取った人々の変化。僕には、その法則性が全く理解できなかった。高林さんの沈黙は、まるで深淵のように、僕のちっぽけな理性を飲み込んでいくのだった。
第二章 栞に挟まれた言葉
アルバイトを始めて一ヶ月が過ぎた頃、僕は高林さんのやり方に、冷めた視線以上のものを向け始めていた。それは、純粋な好奇心だった。なぜ、あの本だったのか。あの言葉が、彼らの心に届いたのか。
仕事の合間を縫って、僕は客が買っていった本をこっそりと読むようになった。高林さんが失恋した女性に渡した詩集には、ありふれた恋の言葉が並んでいるようにしか見えなかった。サラリーマンが受け取った哲学書は、僕にはただただ難解で、眠気を誘うだけだった。
「全然、わからない……」
バックヤードで積まれた古紙の山に寄りかかり、僕はため息をついた。僕には、人の心を救うような言葉を見つけ出す才能もなければ、他人の痛みに寄り添う優しさも欠けている。だから、社会に出ていけないのだ。自己嫌悪が、じわりと胸に広がった。
そんなある日、僕は偶然、高林さんの秘密の一端に触れることになる。返本された一冊の小説を棚に戻そうとした時、あるページに、鉛筆で書かれた小さな星印が付けられていることに気づいたのだ。それは、本の綴じ目に近い、注意しなければ見逃してしまうほど小さな印だった。
『人間は、絶望の淵でこそ、本当に大事なものが何かを見つけ出すのかもしれない』
印がつけられたのは、そんな一文の横だった。僕ははっとした。この本を買っていったのは、確か、事業に失敗してうなだれていた中年の男性だったはずだ。もしかして、高林さんは客の悩みを見抜き、その心に響くであろう「たった一文」を、こうして示していたのではないか。
その仮説を確かめるべく、僕は他の本も注意深く調べてみた。すると、いくつかの本に、同じような小さな星印が見つかった。ある時は励ましの言葉、ある時は痛みに寄り添う言葉、またある時は、視点を変えさせるような問いかけ。それらは決して声高に叫ぶわけではない。だが、深い闇の中にいる人間にとっては、一筋の光となりうる言葉たちだった。
高林さんの沈黙は、無関心ではなかった。それは、言葉の重さを知り尽くした人間だけがたどり着ける、究極のコミュニケーションの形なのかもしれない。彼は、無数の言葉の海の中から、たった一滴の雫を掬い上げ、乾いた心に注いでいたのだ。
その発見以来、僕の中で何かが変わり始めた。高林さんの背中が、以前よりもずっと大きく見えた。そして、この「言の葉の処方箋」の秘密をもっと知りたいと、強く思うようになっていた。
第三章 開かれたページ
季節が秋から冬へと移ろうとしていたある午後、事件は起きた。帳場でいつものように本を読んでいた高林さんが、苦しげに胸を押さえ、椅子から静かに崩れ落ちたのだ。
「高林さん!」
僕の叫び声が、静寂な店内に響き渡った。慌てて駆け寄ると、高林さんは浅い呼吸を繰り返している。震える手で救急車を呼び、僕は担架で運ばれていく彼の姿を、ただ呆然と見送ることしかできなかった。
幸い、命に別状はなかったが、しばらくの入院が必要とのことだった。高林さんの親族から連絡があり、僕は退院までの間、一時的に店を任されることになった。重すぎる責任に、足がすくんだ。僕に、高林さんの代わりなど務まるはずがない。
不安な気持ちで店番をしていた数日後、カラン、と寂しげなベルの音が鳴った。入ってきたのは、四十代くらいの女性だった。その顔は、まるで全ての光を失ったかのように憔悴しきっていた。
「あの……ご主人が、悩みに効く本を選んでくださると聞いて……」
か細い声が、僕の胸を突き刺した。噂を聞きつけ、藁にもすがる思いで来たのだろう。僕は言葉に詰まった。高林さんのように、彼女の心を見透かすことなどできない。何をどう選べばいいのか、皆目見当もつかなかった。
「申し訳ありません、店主は今、入院中で……」
そう言って断ろうとした時、女性の瞳から一筋の涙が零れ落ちた。
「そう、ですか……。息子を、亡くしたんです。半年前、事故で……。もう、どうやって生きていけばいいのか……」
その告白は、あまりにも重かった。僕の陳腐な慰めなど、何の役にも立たないだろう。パニックに陥った頭で、僕は必死に書棚に目を走らせた。悲しみをテーマにした小説? 宗教に関する本? だめだ、何も思いつかない。
その時だった。ふと、高林さんの帳場に、一冊だけぽつんと置かれた本が目に入った。何度も、何度も読み返されたのであろう、表紙は擦り切れ、ページは手垢で黒ずんでいる。それは、クマのぬいぐるみが主人公の、古びた児童書だった。
何気なく手に取り、見返しを開いた瞬間、僕は息を呑んだ。そこには、高林さんのものと思われる、少し震えた文字が記されていた。
『愛する息子、渉へ。父より』
全身に鳥肌が立った。脳裏に、バラバラだったピースが組み合わさっていくような感覚があった。高林さんの深い沈黙。客の痛みに寄り添う、的確な選書。その全てが、一本の線で繋がった。
高林さんもまた、深い喪失を経験した人間だったのだ。彼が客の心を救うことができたのは、彼自身が、言葉によって救われた経験を持っていたからだ。彼の沈黙は、他人の痛みを自分のことのように感じてしまうが故の、雄弁な共感の証だった。彼は、自らの悲しみを乗り越える過程で手に入れた光を、同じように闇の中にいる人々へと、そっと手渡していたのだ。
第四章 僕自身の処方箋
僕は、その手垢に汚れた児童書を、両手でそっと持ち上げた。まるで、大切な宝物を扱うように。そして、目の前の女性に、震える手で差し出した。
「これを……。店主が、ずっと大切にしていた本です」
僕には、どのページに星印がついているか、確かめる余裕はなかった。だが、それでいいと思った。この本は、一文一文ではなく、本そのものが、高林さんの魂の遍歴そのものなのだから。
女性は、驚いたように僕の顔と本を交互に見た後、静かにそれを受け取った。そして、表紙のクマの絵を指でそっと撫でながら、堰を切ったように嗚咽を漏らし始めた。その涙は、絶望の色ではなく、ほんの少しだけ、温かい光を含んでいるように見えた。
数週間後、高林さんは店に戻ってきた。以前より少し痩せたが、その眼光の鋭さは変わらない。僕が店番をしていた間のことを、彼は何も聞かなかった。僕も、あの女性のことや、児童書のことは何も言わなかった。だが、僕たちの間には、言葉を超えた確かな理解と、静かな絆が生まれていた。
高林書房での日々は、僕を根底から変えた。僕はもう、社会から拒絶された無気力な青年ではなかった。自分の足で立ち、自分の言葉を探したい。そう強く思うようになっていた。
アルバイトの最終日、僕は高林さんに辞意を告げた。彼はいつものように、こくりと頷いただけだった。だが、僕が店を出ようとした時、彼は無言で一冊のノートを差し出した。それは、まだ何も書かれていない、真っ白なノートだった。
その意味を、僕はすぐに理解した。
「お前の物語を、お前自身が書くんだ」
沈黙の店主が送ってくれた、最大の餞別だった。
「ありがとうございました」
深々と頭を下げ、僕は高林書房を後にした。商店街の喧騒が、心地よく耳に響く。ポケットの中の真新しいノートの感触を確かめながら、僕は空を見上げた。灰色に見えていた空は、いつの間にか、吸い込まれるような青色をしていた。
僕自身の処方箋は、まだ見つかっていない。だが、それでいい。これから僕が歩む道、出会う人々、そして紡いでいく言葉の中に、その答えはきっとあるはずだ。僕は、確かな一歩を、未来へと踏み出した。