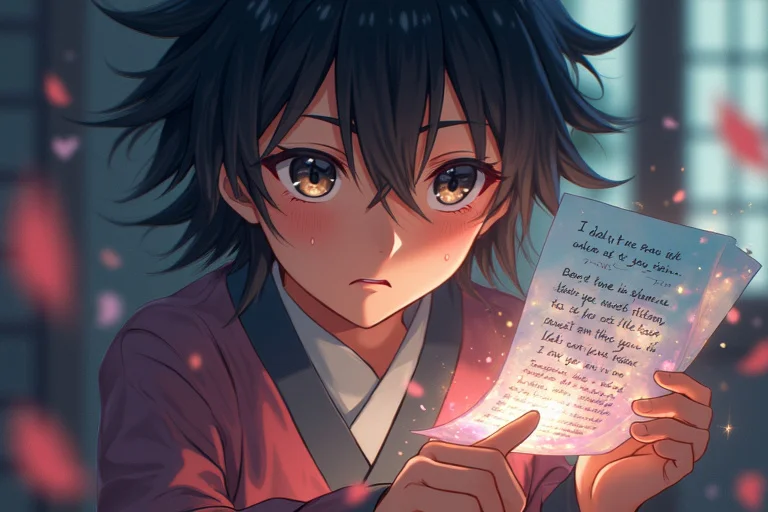第一章 錆びた桜の約束
降りしきる雨が、江戸の夜を墨で塗りつぶしていた。その闇の片隅、打ち捨てられた長屋の一角に、柏木伊織(かしわぎ いおり)の仕事場はあった。かつては藩の剣術指南役として将来を嘱望された身も、今は錆びた刀や折れた槍を修繕して糊口をしのぐ、世捨て人にすぎない。油と鉄の匂いが染みついた薄暗い土間で、伊織は黙々と砥石に水を打っていた。
その時だった。か細い力で戸を叩く音が、雨音に混じって聞こえた。伊織は眉をひそめる。こんな夜更けに訪ねてくる者など、いるはずもなかった。
「……誰だ」
不機嫌を隠さぬ声で応じると、戸の向こうから震えるような少女の声がした。
「あの……お侍様、いらっしゃいますか」
伊織は舌打ちし、立ち上がって荒々しく戸を開けた。そこに立っていたのは、年の頃七つか八つ、濡れそぼった着物を着た一人の少女だった。その小さな手には、古びた布に包まれた何かが大事そうに抱えられている。
「何の用だ。子供の来るところではない」
突き放す伊織の言葉にも、少女は怯まなかった。むしろ、その黒曜石のような瞳でじっと伊織を見据え、懐から震える手でそれを取り出した。錆びついた一本の脇差だった。
「これを……これを、日本一の刀にしてください」
あまりに突拍子もない願いに、伊織は思わず少女の顔と脇差を見比べた。脇差は、柄も鞘もぼろぼろで、刀身は赤錆に覆われ、もはやただの鉄屑にしか見えない。
「馬鹿を言え。こんな鉄屑が名刀になるものか。それに、金はあるのか」
少女は小さく首を横に振った。やはりな、と伊織が戸を閉めようとした瞬間、少女は叫んだ。
「父の、形見なのです! お願いします!」
その必死の眼差しに、伊織の動きが止まる。ふと、脇差の鍔元に彫られた小さな意匠が目に留まった。闇夜の雨に濡れてもなお、そこにはっきりと形を残す、五弁の桜。
伊織の心臓が、どくりと大きく鳴った。その紋様には見覚えがあった。忘れたくとも忘れられない、血と悔恨にまみれた記憶の紋様だった。
「……わかった。預かろう」
自分でも信じられない言葉が、口からこぼれ落ちていた。少女の顔がぱっと輝き、深々と頭を下げる。「千代と申します。ありがとうございます、お侍様」
伊織は少女の名も聞かぬまま脇差を受け取ると、無言で戸を閉めた。手の中に残った、冷たくて重い鉄の塊。それは、伊織が捨てたはずの過去への扉のように、ずしりと彼の心を圧し始めた。
第二章 鈍色の追憶
翌日から、千代は毎日伊織の仕事場にやって来た。何も言わず、土間の隅にちょこんと座り、伊織が脇差を研ぐ姿をじっと見つめている。伊織はそれが煩わしくもあり、同時に、久しく感じたことのない人の温もりに戸惑ってもいた。
脇差の修繕は、困難を極めた。砥石でいくら研いでも、赤錆の下から現れるのは、鈍い光を放つ質の悪い鉄ばかり。刀としての命である刃文(はもん)の気配すら感じられない。
「千代。言ったはずだ。これは名刀にはなり得ない」
ある日の昼下がり、伊織はついに手を止め、少女に告げた。千代は悲しそうに目を伏せたが、すぐに顔を上げた。
「でも、父は言っていました。この刀には魂が宿っているって。腕の立つお侍様なら、その魂を呼び覚ませるはずだって」
千代の父は、腕の良い建具職人だったが、二年前に流行り病で亡くなったという。一人残された千代は、遠縁の家に身を寄せているらしかった。
「お前の父上は、なぜ俺の名を知っていた」
「さあ……。でも、ずっと『柏木伊織というお侍様を探せ』と。父の最期の言葉でした」
その言葉が、伊織の胸に小さな棘のように刺さった。
伊織にも、かつて魂を分かち合った友がいた。同じ藩に仕え、剣の腕を競い合った、水上宗介(みなかみ そうすけ)。宗介は藩随一の刀鍛冶の家系で、自らもまた類稀な才を持つ男だった。彼の打つ刀には、必ずあの小さな桜の紋様が刻まれていた。それは、水上家に代々伝わる証だった。
しかし、八年前、宗介は藩の密命を巡る政争に巻き込まれ、謀反の濡れ衣を着せられた。そして、親友であった伊織自身が、宗介を斬る討手として差し向けられたのだ。雨の降る竹林で対峙したあの日。宗介は抵抗らしい抵抗もせず、静かに伊織の刃を受けた。彼の最期の言葉は、今も伊織の耳から離れない。
「伊織。お前が生きろ。俺の分まで」
友を斬った刀を捨て、藩を抜けた。それ以来、伊織は心を殺し、ただ息をするだけの抜け殻として生きてきた。宗介の記憶は、決して開けてはならない瘡蓋(かさぶた)だった。
だが、この錆びた脇差は、その瘡蓋を容赦なく剥がしていく。なぜ、建具職人が宗介の紋様を知っていたのか。なぜ、俺の名を娘に託したのか。
謎が、伊織を過去の亡霊から引きずり出し、再び現実へと繋ぎ止めようとしていた。
「……もう少し、やってみる」
伊織は誰に言うでもなく呟き、再び砥石を手に取った。その横顔を、千代は安堵したような表情で見つめていた。
第三章 炎のなかの真実
数日が過ぎても、脇差は鈍色のまだった。研磨だけでは駄目だ。伊織は一つの結論に達した。この刀を蘇らせるには、もう一度火に入れ、鍛え直すしかない。それは刀の寿命を縮める危険な賭けだったが、伊織の心を突き動かす何かがあった。
夜を徹して、伊織は仕事場の奥にある小さな炉に火を入れた。ふいごを踏み、炭が真っ赤に燃え盛る。久しく使っていなかった炉の熱気が、伊織の冷え切った身体に染み渡るようだった。彼は祈るような気持ちで、錆びた脇差を炎の中へと差し入れた。
鉄が赤く熱せられ、刀身が柔らかくなっていく。伊織はそれを火床(ほど)に移し、一心不乱に槌を振るい始めた。カン、カン、と澄んだ金属音が夜のしじまに響き渡る。汗が噴き出し、視界が滲む。まるで、八年間の悔恨と無為な日々を、この一振り一振りに叩きつけているかのようだった。
その時、信じられないことが起こった。
槌で打たれた衝撃で、刀身の表面が鱗のように剥がれ落ち始めたのだ。赤錆に覆われた粗悪な鉄の層が、熱と力によって砕け散っていく。そして、その下から現れたのは——。
伊織は息をのんだ。
そこにあったのは、まるで月光をそのまま固めたかのような、青白く澄み渡った鋼の肌だった。夜闇の中でもなお、自ら光を放つかのような幽玄な輝き。これは、かつて宗介の一族だけが製法を知ると言われた伝説の玉鋼、「神鉄(しんてつ)」に違いなかった。
誰かが、この名刀を隠すために、意図的に質の悪い鉄で覆ったのだ。
伊織は震える手で、剥き出しになった刀身を手に取った。そして、茎(なかご)に刻まれた銘を見て、全身の血が逆流するような衝撃に襲われた。
『柏木伊織へ 友、宗介より』
それは、宗介の筆跡だった。友は、自らの死を悟りながら、最後の仕事として、伊織のためにこの守り刀を鍛えていたのだ。しかし、藩の陰謀はあまりに早く、これを伊織に渡す前に、宗介は命を落とした。
では、なぜこれが千代の手に?
伊織の脳裏に、電光石火の如く一つの答えが閃いた。千代の父。彼は建具職人などではなかった。彼は宗介の弟子であり、師の遺志を継いだ刀鍛冶だったのだ。宗介の死後、追っ手から逃れ、身分を偽り、この刀を守り続けてきた。そして、死の床で、最後の希望を娘に託したのだ。「柏木伊織を探せ」と。
千代が持ってきたのは、父の形見ではなかった。八年の時を経て、友から伊織へと届けられた、魂の贈り物だった。
「……宗介」
伊織の口から、嗚咽が漏れた。膝から崩れ落ち、熱い刀身を抱きしめる。頬を伝うのは、汗か涙か、もはや分からなかった。友の温かい心が、八年の時を超えて、今、伊織の凍てついた魂を確かに溶かしていた。
第四章 夜明けの守り刀
伊織は、夜が明けるまで脇差を研ぎ続けた。もはやそれは作業ではなかった。友との対話であり、過去への贖罪であり、未来への誓いだった。夜明けの光が仕事場に差し込む頃、一振りの脇差が完成した。
その刀身は、人を斬るための凶々しい輝きではなく、持ち主の心を静かに映し出すような、深く澄んだ光を宿していた。まるで、夜明けの空そのものを切り取ったかのようだった。
伊織は、訪ねてきた千代を前に正座し、完成した脇差を差し出した。
「千代。これはお前の父上の形見ではない。俺の友が、俺のために遺してくれたものだ。お前の父上は、命がけでこれを守り、お前に託してくれたんだ」
真実を語る伊織の言葉を、千代は黙って聞いていた。やがて、その小さな瞳から、大粒の涙がぽろぽろとこぼれ落ちた。
「父は……最後まで、刀鍛冶でいたかったのですね」
「ああ。立派な男だった」
伊織は脇差を手に取り、ゆっくりと立ち上がると、それを自らの帯に差した。ずしりとした重みが、腰だけでなく、心にも確かな芯を通すようだった。世捨て人、柏木伊織は、もうどこにもいなかった。
「俺が預かる。この刀は、お前の父上と、俺の友の魂そのものだ。俺は、この刀にふさわしい男になる。一生をかけてな」
伊織は千代の手をそっと取った。小さく、温かい手だった。
「行こう」
「どこへ?」
戸を開けると、昇り始めたばかりの朝日が、二人を眩しく照らし出した。江戸の町が、新しい一日の始まりを告げている。伊織は、その光から目を逸らさなかった。
「さあな。だが、お前と一緒なら、どこへ行っても良い道になりそうだ」
伊織は穏やかに微笑んだ。その腰で、暁の光を受けた守り刀が、新しい主の門出を祝うかのように、静かで力強い輝きを放っていた。それは、過去を乗り越え、未来を照らす、希望の光そのものだった。